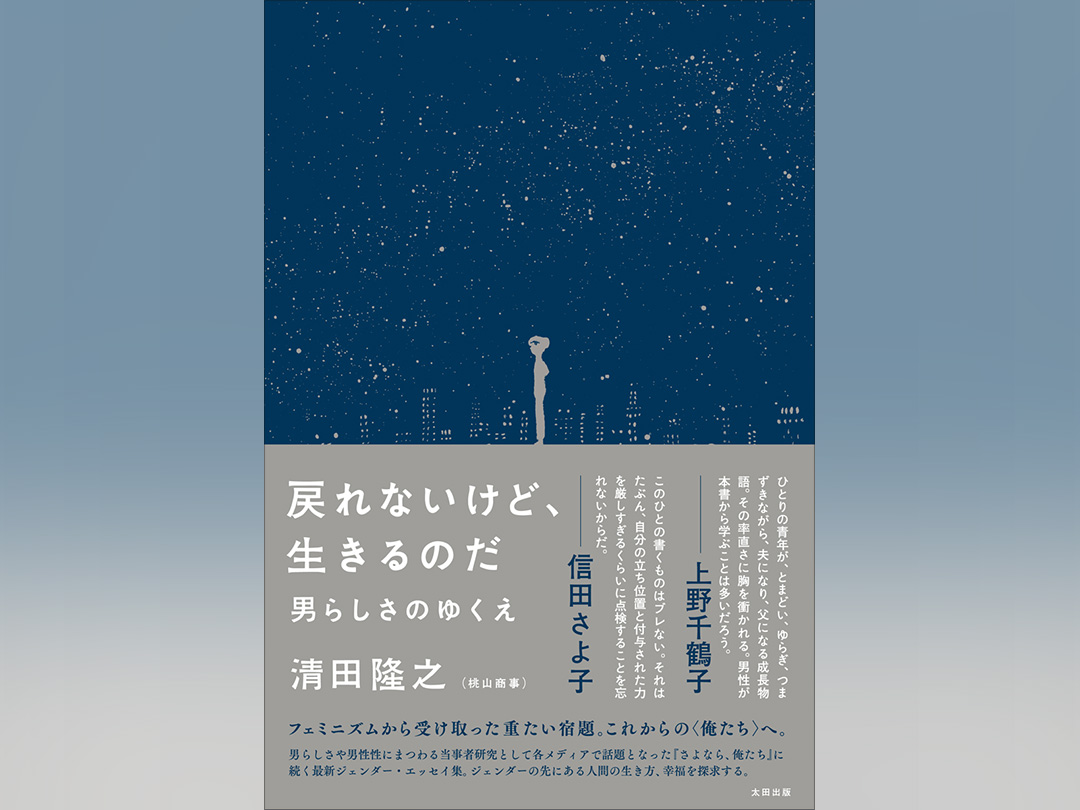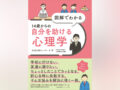現代日本では家父長制的な世界観やミソジニー的なジェンダー感がありとあらゆる場所に浸透しています。特にスマートフォン経由でショート動画にまで侵入し、思春期の男女にも受け継がれてしまっている現状があるのです。
2024年12月24日に太田出版より刊行した、清田隆之著『戻れないけど、生きるのだ 男らしさのゆくえ』では、フェミニズムに向き合い大人の責任について考え、自分の傷や被害もまなざし、新自由主義や家父長制といった構造問題を踏まえながら男性性について探求しています。刊行を記念して、本書の一部を試し読みとして、2回に分けてOHTABOOKSTANDに公開します。
〝ずぼらママ〟による「褒められレシピ」
何もやる気が起きないときに、仕事が行き詰まったときに、変な時間に目が覚めてしまったときに、ふとスマホに手を伸ばしてSNSのアプリを開く。XでもInstagramでも、最近は流れてくるショート動画に目を奪われてしまうことが多い。AIがなんらかのアルゴリズムに基づいてサジェストしてくるそれらのショート動画は、内容は様々だが大体が1分以内の長さで編集のテンポも軽快で、次から次へと眺めていくうちに平気で1時間くらい経ってしまう恐ろしいものだ。
そこでよく見かけるものとして、例えば「ずぼらママ」を自称する女性アカウントのレシピ動画がある。専業主婦の場合も共働きの場合もあるが、基本的にはみんな忙しく暮らしていて、日々の料理をどれだけ効率化していくかという点に重きが置かれている。時短やコスパを追求するそれらの動画では、炊飯器や電子レンジに入れるだけで完成するレシピや、フライパン上で完結する〝ワンパン〞料理、あるいは浸しておくだけで肉や魚がおいしくなる〝魔法の液体〞など、手軽に試せて動画としても映ばえるノウハウが目白押しで、仕事と双子育児に追われる自分にとって参考書のような存在だ。
その一方で、そこで用いられている言葉に引っかかりを感じる瞬間も少なくない。例えば安価で高タンパクの鶏ムネ肉は人気の食材だが、そのレシピのタイトルとして「旦那に褒められたしっとり蒸し鶏」「夫ウケ抜群のワンパン油淋鶏」「息子のご飯が一瞬で消えた鶏の甘辛炒め」みたいな表現がよく用いられているのだ。私も大いに真似させてもらっており、安くて簡単で本当にありがたい。双子たちもモリモリ食べてくれる。だからケチをつけたいわけでは全然ないのだが、手軽でおいしいレシピのタイトルに、なぜそのような言葉が〝あるある〞のように用いられているのか……。おそらくそれは、旦那や息子からの高評価がレシビ動画としての売り文句になるからで、実際にこの系譜は「褒められレシピ」としてひとつのジャンルを形成している。
なんで? どうして? 食ってるだけの旦那と息子、与えられてるポジション高すぎじゃない?そもそも時短やコスパを追求せざるを得ないのは、みんな毎日の仕事や生活で忙しく、また金銭的にもそんなに余裕があるわけではないからだ。そういうなかにあって、できるだけ安く、手軽に、おいしくご飯を作りたいという工夫の結果としてこれらのレシピは存在しているはずだ。炊飯器や電子レンジを上手に利用すれば複数の料理を同時並行で作れるし、ワンパンレシピには洗い物が減るというメリットもある。パサつきがちな鶏ムネ肉をしっとり仕上げてくれる〝魔法の液体〞は、水と塩と砂糖のみで作れるため安価で大変ありがたい。そういう知恵と努力の上に成り立っているレシピに「うまい」とお墨付きを与える旦那と息子は、一体どれだけ偉い立場なのか。
さらにさらにその上に、それを提供する側のママたちがなぜか〝ずぼら〞を自称している……。これはつまり、料理を機械に任せることを、ワンパンですべてを済ませることを、手頃なお肉を裏技で柔らかくすることを、〝手抜き〞や〝サボり〞のような感覚で捉え、「それはちゃんとしたママのやることじゃない」と考えているがゆえのものだろう。単にSNSで受け入れられやすくするための手立てであって、本気でそう思っているわけではないかもしれない。でも、時短や節約のための工夫がなぜ〝ずぼら〞と表現されなければならないのか。こういった見せ方が一定の共感を集めてしまうのはなぜなのか。〝ずぼらママ〞による「褒められレシピ」の背景には、家父長制的な価値観の影響がきっと関係している。
思春期男子にも浸食する〝男磨き界隈〟の世界
ショート動画は蟻地獄だ。あまりに巧妙にできているため、ひとたび足を踏み込むとなかなか抜け出すことができない。見れば見るほどAIにこちらの内なる欲望を読み取られ、「お前はこういうのが好きなんだろ?」という感じで類似動画がどんどん流れてくるようになる。そしてまんまと眺め入ってしまい、ますます流れてくるようになったもののひとつに〝男磨き界隈〞なるジャンルのショート動画がある。
これは筋トレやナンパ、美容に禁欲、読書に自己啓発など、様々なアクションを通じて身体やメンタルの鍛錬を推奨していく一連の動画群で、発信者の男性アカウントは総じてオラついた空気を放っている。今の時代に求められる男らしさはこうだ、だから努力してそれらを身につけ、美女を抱け、金を稼げ、いい車に乗れ_と、そこで発せられるメッセージはいかにもマッチョだ。モテるための行動指南は昔から定番のコンテンツで、出版の世界でも「モテ本」というジャンルが根強い人気を誇っているし、YouTubeでも検索すれば各種のモテテク動画がごろごろ出てくる。だから別段新しい現象というわけではないが、あらゆる言葉が断言口調で、編集のテンポがやたらと速く、極論めいたロジックで見る者の不安を煽り、「お前がモテないのは努力してないからだ」と自己責任論を展開していくようなところには、極めて現代的な何かを感じる。
これらを意識するようになったのは、2024年初頭にXでバズった「メンズコーチ」を名乗る男性アカウントのショート動画がきっかけだった。「スポーツ経験がない男/部活に入った経験がない男/俺ガチで危機感持ったほうがいいと思う/ガチで危機感持ったほうがいい/それこそがお前がどうあがいてもモテない理由だと思う」という言葉で始まるその動画は、著名なインフルエンサーに引用されるなど瞬く間に拡散。そのメッセージは賛否両論を含め大きな話題となり、「厳しいって」というフレーズがネットミームと化すなど、発信者自身もSNS界の有名人となっていった。桃山商事メンバーの佐藤がこうした発信者たちを〝男磨き界隈〞とくくり、Podcast番組で特集を組んだところ、想像以上に大きな反響があって驚いた。とりわけ衝撃的だったのは学校の保健室に勤務しているという女性リスナーさんからのお便りで、そこには思春期まっただなかの男子たちが、一連の動画に強い影響を受けている様子が描かれていた。
ショート動画の目的はアクセス数を伸ばすことで、速いテンポも、語気の強さも、極端なロジックも、再生回数を稼ぐためにPDCAサイクルを回し続けた結果として行き着いたものだろう。数字が収益や知名度に直結する構造である以上、発信者がそれを志向するのも無理はない。しかし、そうして発せられたメッセージが、我々の日常にすいすい入り込んでいることを思うとにわかに恐ろしくなってくる。「金持ちな人生と貧乏な人生、どっちがいい?」「モテて美女を抱きまくるか、モテないまま一生オナニーし続けるか」「色気や清潔感のある男と、臭くて不潔なブサイク、どっちになりたい?」など、〝男磨き界隈〞の動画は極端な二択を提示して不安や欲望を煽り立てる。「女の言うことは聞くな。言いなりになったら一生ATM扱いされるだけ」「牛丼やファストフードばっか食ってるからお前はデブなんだ」「背の低い男は全員キモい。だから絶対に身長は盛れ」など、ミソジニーやルッキズムの色合いも非常に濃い。筋トレも、おしゃれも、自己啓発も、それ自体はなんら悪いことではないはずだ。身体を鍛えることで自信がついたり、読書することで思考がクリアになったりすることは大いにあるし、個々人の幸福を考える上でも大事なものだと思う。しかし、それらがすべて「美女を抱くため」「男同士の競争に勝つため」の努力として打ち出されている点には疑問しかない。
この世は歴然たる競争社会で、そこで勝つためには〝男らしさ〞を磨くことが必須である。トレーニング方法、ナンパ術、男性美容、ファッション指南など、あらゆるノウハウはすでに流通している。それなのに努力しないやつが多すぎる。女は力のある男に惹かれる生き物で、格下と見なされたら一巻の終わり。金と女は勝った者にしか分配されず、敗者はすべて自己責任。それがこの世の仕組みであり、四の五の言っても仕方がない。貧乏でモテない一生を送りたくなかったら、今すぐ行動を起こすべし__。
そんな〝男磨き界隈〞の主張は、悲しいかなこの社会において珍しいものではなく、それどころか受け入れられやすいものですらある。というのも、「強者男性が支配権を有する」という家父長制的な世界観、女性をケアとセックスの役割に押し込めようとするミソジニー的なジェンダー観、能力主義や自己責任論をベースとするネオリベ的意識……など、この社会に蔓延し、多くの男性たちが内面化してしまっている価値観がブレンドして形成されているのが〝男磨き界隈〞のメッセージだからだ。先に紹介した「メンズコーチ」は別の動画で、小さくて細身で家庭的で、仕事をバリバリ頑張っていないような女性が好みのタイプだと語っていた。わざと言ってるのかと思うくらい〝いかにも〞な感じである。こういった価値観をスマホ経由で日常に侵入させてくるのがショート動画の恐ろしいところで、思春期の男子たちに家父長制やミソジニーがしっかり受け継がれてしまっている現実を思うと、なんだか重たい気分になってくる。(本書へつづく)
* * *
清田隆之『戻れないけど、生きるのだ 男らしさのゆくえ』は、全国の書店、書籍通販サイト、電子書籍販売サイトにて発売中です。さらに、刊行を記念した特別記念イベントも続々開催中! 本書詳細とイベント情報は太田出版ウェブサイトをチェックしよう。