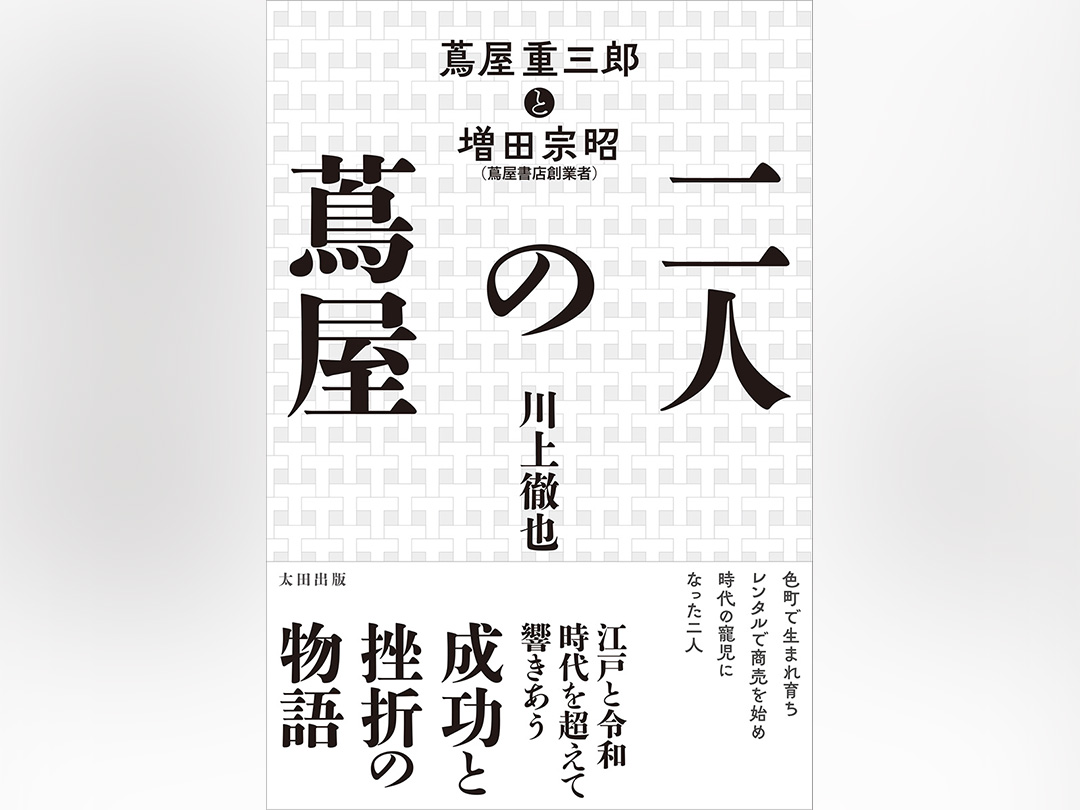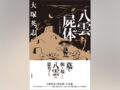色町で生まれ育ち レンタルで商売を始め 時代の寵児になった二人――
江戸と令和 時代を超えて響きあう 成功と挫折の物語
増田宗昭、全国に広がるTSUTAYAフランチャイズ店、SHIBUYA TSUTAYA、代官山 蔦屋書店、武雄図書館等、数々の企画を生み出した蔦屋書店創業者。蔦屋重三郎、喜多川歌麿を育て、山東京伝を世に出し、謎の絵師・東洲斎写楽をわずか十ヶ月で時代の記憶に焼きつけた江戸の名版元。当代きっての「企画マン」であり、「人たらし」であり、「商売人」だった二人の蔦屋の歩みをたどると、驚くほどシンクロする。時代を超えた「二人の蔦屋」の物語を通して、「文化を届けるとはどういうことか」という本質的な問いに対する答えを探る。
2025年9月18日(木)に発売した、川上徹也著『二人の蔦屋 蔦屋重三郎と増田宗昭』の内容を一部公開(第二回)。
枚方の色町で生まれ育つ
初めて増田にインタビューした二週間後、私は大阪府枚方市に向かった。幼い頃のエピソードを色々と聞いたので、祖父が経営していて増田が生まれ育ったという枚方宿桜新地にあった置屋「蔦屋」跡を見学したかったのだ。
枚方市は京都と大阪の中間にあるベッドタウンだ。北河内という地域に属し、「ひらパー」こと「枚方パーク」という遊園地があることで知られている。菊人形が有名で、私も幼い頃、一度だけ母親に連れられて行った覚えがある。
江戸時代の枚方は、江戸日本橋と大坂高麗橋をむすぶ東海道の56番目の宿場町として栄えた。「東海道は五十三次では?」と思った方も多いかもしれない。歌川広重や十返舎一九の作品の影響で江戸日本橋と京三条大橋とをむすぶルートが東海道と思われがちだが、現在においては、滋賀県大津から伏見宿、淀宿、枚方宿、守口宿を通って大坂高麗橋までむすぶのが本来の「東海道」で「五十七次」だったという説が有力である(この区間に限り京街道や大坂街道という呼び名もある)。
「枚方宿」は、淀川を行きかう三十石船の中継港として賑わった。三十石船は30人ほどが乗れる客船で、枚方宿に近づくと「酒くらわんかー 餅くらわんかー」と酒や食事を売りつける小舟が近づいてくる。これが枚方宿名物「くらわんか舟」だ。「くらわんか」とは「食べないか?」を意味する河内弁だ。乱暴な口調が特徴で、「食うこともできないくらい銭を持ってへんのか?」と挑発する意味合いもあり、客との乱暴なかけあいが名物だった。
このように京と大坂を結ぶ交通の要として栄えた枚方宿には、本陣、旅籠、茶店が軒を連ねて大いに賑わい浮世絵にも描かれた。
京阪電車の枚方市駅から枚方公園駅の間にある旧街道沿いを歩く。ところどころに枚方宿の面影がある建物が残っている。地域の人々によって街道の景観をとどめる取り組みが行われているのだ。
この街道のはずれに、増田が生まれ育った色町「桜新地」がかつて存在していた。もともと枚方宿の中心に点在していた妓楼を、1909(明治42)年に、まとめて町はずれに移転したのが始まりだ。移転時には貸座敷20軒・芸妓(芸者)20人余・娼妓(遊女)33人だったという記録が残っている。昭和初期にはさらに多くの店や芸娼妓を抱える色町として栄えたが、昭和33年の【公娼制度廃止】により衰退していく。
現在その地区を歩いても、普通の住宅街で、色町だった痕跡はほとんど見当たらない。
さらに奥に進んでいくと、川沿いに唯一はっきりと「妓楼跡」として認識できる大きな建物が見えてくる。増田の生家だった「蔦屋」跡だ。
増田の祖父は土木作業員から身をおこし、土木建築会社「増田組」を率いていた。増田組が手がけたものには、ひらかたパークの菊人形展のほか、枚方警察署、枚方公設市場などがあった。しかし土木建築は案件のあるなしで売上が上下する。そこで安定収入を得られる副業として営んだのが、桜新地の置屋「蔦屋」だ(当時は合法の商売であった)。
「置屋」というのは芸妓や娼妓が滞在して顔見世などを行う場所で、そこから「揚屋」と呼ばれる店に派遣されていく。送り込み制と呼ばれる関西の色町に多いシステムだ。
一方、江戸の吉原などの遊郭は、自ら娼妓を抱えて同じ店で営業を行う「居稼ぎ制」を採用する店が多かった。
桜新地の「蔦屋」の奥には、広大な敷地にたてられた母屋や奥座敷があり、幼い増田はそこで生活していた。
1951(昭和26)年1月20日生まれの増田は、置屋が廃業される58(昭和33)年まで、まわりに芸妓や娼妓がいるのが日常だったのだ。
「銭湯から帰ってくると、女の人が御腰一枚で上半身裸のまま化粧してるのが目に入ってくる。うちだけやなくて、まわりも置屋ばっかりや。自然と人間の欲やエロスを浴び続けるような環境やった。そやけどそれは決して不快ではなく、これこそが人間の根本にある快楽やないかと、幼いながらに理解してた気がする」
家の中にはいわゆる使用人もたくさんいて、増田は日常的な面倒はお手伝いさんにみてもらっていた。さらに姉と妹にはさまれていたこともあり、中学生になるまで、自分のことを「うち」と呼び、女言葉で喋っていたという。
「それに加えて虚弱体質で体の線も細かったから、小学生の時はいじめられっ子やった。色町のボンボンで『イロボンちゃん』というあだ名をつけられたりもした。家では甘やかされてるけど、外ではいじめられる。その頃の学校での記憶は正直あまりない。無色透明って感じやった」
蔦重、幼い頃に両親と別れ吉原で育つ
一方、蔦屋重三郎(通称:蔦重)は、幼い頃のことはほとんどわかっていない。唯一残っている史料は、狂歌仲間で国学者の石川雅望(宿屋飯盛)が撰した「喜多川柯理墓碣銘」の記述のみだ。
蔦重は、寛延3(1750)年1月7日、丸山重助と広瀬津与の子として、吉原遊郭で生まれた。父は尾張国生まれ、母は江戸生まれ。名前は柯理(「からまる」もしくは「かり」)。幼い頃に両親が離婚したので、喜多川家の養子となる。
ちなみに喜多川家は吉原で引手茶屋(客を客の希望や予算に応じて妓楼を紹介する案内所兼茶屋)を営んでおり、その屋号が「蔦屋」だったことから蔦屋重三郎と名乗るようになった。
以上がすべてだ。父親がどんな職業でなぜ尾張から江戸に来て吉原に住んでいたのか、母親とどうやって出会ったのか、なぜ両親が離婚したのかもわからない。あとは想像するのみだ。
幼い頃に両親が離婚をして、自らの意志とは関係なく養子に出される。両親の事情はわからないが、自分が捨てられたと思ってもおかしくない境遇だ。しかもその場所は、女の股で忘八[*1]たちが食っている吉原遊郭。
おそらく蔦重も、人間の欲やエロスを、日常の風景として、濃密に、否応なく浴びながら育っただろう。
そのなかで、何を感じ、どんな眼を持ったのか──
それを記したものも何ひとつ残っていない。
けれど、のちに彼が手がけた本や絵や作家たちを見ると、その奥底には、吉原という環境で培われた洞察や嗅覚、そして達観した距離感が確かに息づいているようにも思える。
[*1] 忘八…仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌の八つの徳目のすべてを失った者の意から、遊郭に通うこと、遊女屋、またその主人のことをさす
レスリング部に入部 自分の意志力で自分を変える
増田は大阪市内の公立中学に越境で通った。
当時、教育熱心な家では、校区である自宅近くの小中学校に子供を通わせることを避けて、違う校区の公立小中学校に通わせる越境通学はよくあることだった。1968年に越境入学防止対策基本方針が制定される前は、大阪市の小中学校の児童の約10%が越境通学をしていたという調査もある。
増田は越境で通ったその中学で「女言葉でなよなよしてる」ことを指摘され、必死で直すようになった。それまで自然と内股で歩いていたのを意識して外股で歩くようにした。また言葉も意識して男言葉に変えた。
高校は寝屋川市にある私立の同志社香里高校に進んだ。現在は共学になっているが、当時は男子校だった。祖母が「宗昭はそんなに勉強ができる子と違うから、エスカレーターで大学に行けるところへ行かせなさい」と言って授業料を用意してくれたという。
後述するが、その頃の増田家は、地元では名士で、増田自身もボンボンとして甘やかされて育ったが、その内情はけっして経済的に余裕があった訳ではなかった。
入学した増田は一大決心をする。
「このままではあかん。いじめられっ子のままや。そう思って体を鍛えるためにレスリング部に入部した」
虚弱体質でか細い人間が絶対に選ばない一番キツい部活をあえて選んだという。
「しかも一対一の勝負やから誰も助けてくれへん。負けたらメチャメチャみじめや。でもそれくらい追い込まんとあかんと思った。そしたら朝はマラソン、昼はバーベル、放課後はスパーリングという生活が始まった。もうふらふらや。授業中はずっと寝てた。勉強せんでも大学にはそのまま上がれるやろうと思ってた。飯はびっくりするほど食べた。もうとにかく食って鍛えて寝る。それだけやった。そしたらどんどん体が大きくなった。自然と誰からもいじめられないようになった」
レスリングに限らず、学生時代に空手、柔道、ボクシングなど格闘技をやろうと思う人間は大きく2種類にわかれるという。もともとやんちゃで喧嘩が強かった人間と、身体や心にコンプレックスを抱え、そんな自分を変えたいと思う人間だ。
後者だった増田は見事に目的を達した。レスリング部に入った時は当然一番弱かったが、徐々に強くなり、トーナメントのくじ運にも恵まれ大阪府の大会で2位になったこともあるという。
その体験で増田は、「自分の意志力で自分を変えることができる」ことを学んだ。まさに一大転機だった。
バンド活動 海外旅行 洋裁学校
高校ではバンド活動も始めた。中学までのひ弱な少年とは思えないくらいの変貌で、今では言えない「やんちゃな事件簿」も数々あったらしい。
ただし勉強をしなくても大学に上がれるという目論見は外れた。2年生の進路相談で初めて、成績下位の3割は内部進学できないことを知ったのだ。その時、増田の成績は354人中352位だった。
このままではとても同志社大学へ内部進学はできない。それでは祖母に顔向けできないと猛勉強をした。成績はどんどん上がり、最終的には学年4位までなり、無事第一志望の同志社大学経済学部に入学する。
その頃、学園紛争で大学の授業がなかったので、遊びたおしたという。
「母親に、当時流行っていた『いすゞ自動車117クーペ』を買ってもらって、ひたすら遊んでいた。まだ珍しかった海外旅行にも行かせてもらった。最初に行ったのはスウェーデンのストックホルム。どんな国やろ、と思って行ってみたら街がめちゃくちゃ綺麗で驚いた」
同志社大学の「クリーブランドハイム」というフォークバンドにも参加した。大学や関西フォーク連盟などのイベントでは、いつもトリを務める人気バンドだったという。
増田はサイドギターとサイドボーカル。演奏よりも司会や選曲を得意としていて、全員の衣装担当もしていた。増田も他のメンバーもプロを目指して活動していたが、ある新人発掘オーディションをバンドで受けた時、メンバーのひとりだけが審査員に引き抜かれた。
審査員は杉田次郎。杉田は解散していた人気バンド「ジローズ」をそのメンバーと再結成して大ヒット曲「戦争を知らない子供たち」を生む。増田や残されたメンバーは音楽の道をあきらめ、バンドを解散することになった。
同じ頃、増田はライフスタイルプロデューサーの浜野安宏が書いた『ファッション化社会』という本を読んで衝撃を受ける。
「その本の中に『すべての商品がファッション化し、すべての商品がデザイン化される』という一節があったんや。それ読んでこれや! ってなった。つまりこれからの時代の機能だけでなく、商品はデザインで売れるようになるということ」
今となっては当たり前のことかもしれないが、当時は目から鱗だったという。後に増田と浜野は渋谷QFRONTの立ち上げで協業することになる。
元々、ファッションには興味があった。バンドでも衣装担当だったし、ジーンズをストーンウォッシュにして切り繫げたり、ジーンズを加工して鞄を作ったりもしていた。
増田はデザインが一番活かされるのは服だと考えて、その基本を会得しておきたいと大学に籍を置いたまま大阪の上田安子服飾学院(現・上田安子服飾専門学校)に入学した。
その頃の服飾学院はいわゆる洋裁学校で、独身女性の花嫁修業のための場だった。50人のクラスに男性は増田ひとり。女性に交じってレスリングで鍛えたマッチョな男性がひとりいるのは、当初はかなり異様な風景だったという。
そこで増田は、自分の才能を発見する。
「洋裁のプロセスには2種類あって、ひとつ目は図面を描いてから服を作るやり方。これは企画でいうと帰納法的な考え方や。もうひとつは、ボディー(マネキン)に生地をかけていってピンを打って完成形を作って、それを切ったものから後で図面を起こす方法。いわゆる立体裁断。これは企画で言うと演繹法的な考え方やな。自分が持っているのは、まずゴールをイメージしてそこから演繹法的に考えていく才能だとわかった」
服飾学院と大学の卒業の時期が重なっていて、服飾のプロコースに進むか、それとも就職するかの二択を迫られた。周囲の評価も高く、デザイナーになろうかとも思ったが、高田賢三と三宅一生がデビューして活躍するのを見て、とても勝てないとあきらめた。
ただし、ファッションをビジネスとしてやるのであれば、必ず勝機はあるはずと思い、ファッション業界への就職を目指すことにした。
軽井沢ベルコモンズ 残業時間月270時間 サラ金地獄
大学卒業後、増田は「鈴屋」に入社する。
当時「鈴屋」は、『SUZUYA』ブランドで知られ、「三愛」「鈴丹」などとともに婦人服製造販売のリーディングカンパニーだった。服を仕入れて売るという業態から、これまでにない商業施設を展開する業態にシフトチェンジするところで、ファッションで世の中を変えるという野心に溢れていた。浜野の『ファッション化社会』の中でも強く推薦されていたのも志望した動機だ。
当時の増田は、ロン毛でがたいがよく、かなりいかつい感じだったという。そんな見た目で落とされそうになったが、新しい業態を目指すのには異質な人間も必要だろうと採用されたらしい。
上京して最初に住んだのは千駄ヶ谷だった。今でいう裏原宿の外れで千駄ヶ谷小学校の近く。本当は東京で住むなら原宿か青山がいいと思っていた。実際に原宿駅前の不動産屋で部屋探しをすると、希望の場所は家賃が高すぎて新入社員にはとても住めない。駅からは離れているが、頑張れば原宿や青山にも歩いて行けるということで選んだ。1階に大家がいる個人宅の2階で外階段から上がる物件。場所はいいけど、風呂はついてなかったので近所の銭湯・清水湯にかよった。
内定式で鈴屋が新規事業で青山に商業施設を計画中だと知って、近くに住めばそのプロジェクトに参加させてもらえるかもという思惑もあった。その商業施設とは、のちに青山通りと外苑西通りが交わる青山三丁目交差点に建設される「青山ベルコモンズ」だ。
同期のほとんどが婦人服を販売する部署に配属されたが、増田は「青山ベルコモンズ」のプロデュースを担う開発事業部に配属された。住んだ場所のお陰かどうかはわからないが、思惑通りではあった。
「君は新人で何もできないだろうから、立体駐車場の台数設計をしろ」と上司に言われていきなり青山ベルコモンズの駐車場の設計を任される。
当時の鈴屋には商業施設運営の専門家がいなかった。ましてや駐車場の台数設計のやり方を教えてくれる人など誰もいないしノウハウもない。
自分で考えるしかなかった。
机上で計算しても結局はわからない。まずは近隣の様々な商業施設の駐車場でデータを取ることにした。青山ベルコモンズの設計を担当していた黒川紀章建築設計事務所の実務スタッフと、渋谷の商業施設の立体駐車場を訪れた。
そして、駐車してから何秒でターンテーブルを離れるか、買い物後は出庫するまでにどれくらいの時間がかかるかを、すべてストップウオッチで計測した。1人で来る場合と2人4人ではかかる時間も大きく異なる。多くの駐車場で実施して平均値を求めた。
さらに利益を出すために必要な1日あたりの売上から、青山に車で来る人の割合はどれぐらいかを予測し、それを日割りにして分析してみる。もちろんピーク時の混雑も想定しなければならない。
増田は、来店した自動車をさばくにはピークタイムに4つのターンテーブルが必要で、総台数は124台が最適であると計算して、それを会社に報告した。
その報告書は素晴らしく、新人だった増田の評価は一気に高まる。
データを取れば経験がなくても仕事ができるということに増田は気づいた。
翌年、増田は入社2年目で軽井沢の商業施設立ち上げのリーダーに抜擢される。
「軽井沢に土地を持ってるオーナーから鈴屋に有効活用してほしいと依頼があった。それで自分が話を聞きにいって上司に報告したら、いきなりお前が全部やれと言われた。でも法律も建築も収支計算も何も知識がありませんと言ったら、弁護士やデザイナーなどの専門家をスタッフとして用意してくれ、部下として新入社員も2人つけてくれた」
増田は、市場調査、建築基準法、借地借家法などの勉強から始め、工事代金や家賃設定のシミュレーションをひたすらノートに書き記した。商業施設はまずテナントが入ってもらわないと話にならない。入ったら儲かると思えるような賃貸条件を考える必要がある。さらにテナントが儲かるためにはお客さんが来たいと思うような魅力的な施設にする必要がある。そして企画した「新形態のリゾート型ショッピングセンター(軽井沢ベルコモンズ)」は、ほぼ完全な形で採用された。
結局立ち退き交渉からはじまり、投資採算計画、建築デザインなど、「軽井沢ベルコモンズ」のすべての業務に携わることになる。
「一番忙しい時は、床に段ボールひいて。ほとんど会社に泊まってた。残業時間が土日も含め月270時間になって鈴屋の新記録やなと言われた」
増田はそこで「自分が考えたプランどおりに、新しい店舗が作られていく時の興奮と感動」を初めて味わったという。しかも店がオープンすると、マスコミからもお客さんからも非常に高い評価を受け、それが仕事に対する自信と自覚をもたらした。
鈴屋の鈴木義雄社長からは、「一流の店を経験しないと一流のプランニングはできない」と言われ、増田は愚直に実行した。高級寿司や高級フレンチを食べまわり、ディスコに入り浸る日々だったという。特に通っていたのが赤坂の「ビブロス」だった。
「一応リサーチなんやけど全部自腹やったから、当然、会社員の給料で追いつくわけがない。サラ金に手を出したら金利が金利を生んでもう地獄よ。結局、全部返したけど、家族に迷惑をかけてしもた。まあずっとあとに、ディレクTVの失敗で200億借金したことがあるからそれに比べたらたいしたことないけどな。200億借金したことあるか? さすがに落ち込むで」
鹿児島での失敗とかけがえのない出会い
軽井沢ベルコモンズの成功が評判を呼び、その実績を買われて、増田は鹿児島の商業施設の再生プロジェクトを任されることになった。
舞台となったのは、鹿児島市郊外の埋め立て地「与次郎ヶ浜」。この土地を地元の老舗旅館が取得し、かの浜野安宏に企画を依頼して生まれたのが「ぶらぶら」という商業施設だった。白い壁にオレンジ色のかわら屋根。地中海風のデザインで、当時としては斬新かつ洒落た建物だったが、立地の悪さが致命的だった。いくらおしゃれでも、客が来なければ意味がない。施設はすぐに閑散としてしまう。
そこで、オーナーが軽井沢ベルコモンズの成功例を耳にし、鈴屋に「なんとかしてほしい」と再生を依頼してきた。鈴屋の社長は、まず可能性を見極めるため、増田に視察を命じる。
「20代半ばで軽井沢ベルコモンズを成功させたことで、自分は何でもできるという全能感のようなものがあった。当時、尊敬していた浜野さんが手がけてうまくいかなかった案件を、自分なら再生できる気がしていた。またそれができたら浜野さんを超えられると勘違いした。そうして『こうすれば必ず立て直せます』という企画書を書いて提案したら、社長に『じゃあ、お前がやれ』と任された」
増田は、軽井沢で築いた信用とノウハウを総動員し、出店してくれたテナントに声をかけた。結果、約40のテナントをすべて埋め、商業施設は「鹿児島ベルコモンズ」として新たに生まれ変わり、華々しくオープンを迎えた。
しかし、不便な立地は変わっていない。オープン当初は話題を呼んだが、ほどなくして客足は遠のき、施設は再び静まり返った。信じて出店してくれたテナントのオーナーたちからは、怒りと失望がぶつけられた。増田はその責任を引き受け、現地に赴任。管理所長として、もう一度立て直しを図ろうと、1年以上にわたり現場で奮闘を続けた。
「結果としては、完全な失敗だった。そもそも難しい案件だったのに、自分なら成功できると過信してしまった」
結局、思ったような成果は出せないまま、増田は本社に戻ることになった。
増田が鹿児島を離れる前、テナントのオーナーやスタッフらが100人以上集まり慰労会を開いてくれた。プロジェクトの結果は芳しくなかった。それでも、誠実に最後まで向き合った増田の姿勢を、多くの人が評価していたのだろう。
「テナントさんには申し訳なかったけど、鹿児島の失敗もええ勉強になった。スタッフを動かす難しさも身をもって知った。大学で音楽やってたことも、ファッションの勉強をしたのも、軽井沢の成功と鹿児島の失敗も、その後、店舗で婦人服の販売員をしたのも全部ええ勉強になった。そういう過去の経験が、人間としての底辺を広げてくれたからこそ、代官山 蔦屋書店やT-SITEのコンセプトを作り上げることができたと思う」
そしてもうひとつ。鹿児島の地で、増田は人生の大きな出会いを果たす。のちに伴侶となる女性との出会いである。
彼女は、かつて鈴屋に勤めていた元社員だった。退職後、故郷・鹿児島に戻り、縁あって鹿児島ベルコモンズのテナントのひとつで店長を任されていた。鈴屋時代には増田と直接の接点はなかったが、テナントの店長会議などで叱責を受け、もがきながら奮闘する彼の姿を、誰よりも近くで見つめていたひとりだった。やがてふたりは言葉を交わし、心を通わせていく。そして、増田は彼女と結婚する。
それは、再起をかけて挑んだプロジェクトが、思いがけずもたらしてくれた、もうひとつのかけがえのない「成果」と言えるかもしれない。
そしていよいよ、増田が蔦屋になる時を迎える。
筆者について
コピーライター。湘南ストーリーブランディング研究所代表。大阪大学人間科学部卒業後、大手広告代理店勤務を経て独立。数多くの企業の広告制作に携わる。東京コピーライターズクラブ(TCC)新人賞、フジサンケイグループ広告大賞制作者賞、広告電通賞、ACC賞など受賞歴多数。著書は『ストーリーブランディング100の法則』(日本能率協会マネジメントセンター)『キャッチコピー力の基本』(日本実業出版社)、『物を売るバカ』『1行バカ売れ』(いずれも角川新書)、『ザ・殺し文句』(新潮新書)、『高くてもバカ売れ!なんで?』(SB新書)など多数。海外にも6か国20冊以上が翻訳されており、台湾・中国などでベストセラーになっている。