2024年5月から11ヶ月、ヨーロッパとアメリカなど世界各地を対象に、ミュージアム研究者・小森真樹さんが行うフィールドワークをもとにして、ミュージアムの営みについて辿っていく連載「ミュージアムで迷子になる」。
ミュージアムの営みを辿ることは、私たちが生きる社会とその歴史がどのように作られているのかを考えるということです。その中に迷い込むことで、この社会の思いがけない一面を発見していきます。
「キュレーション」という言葉は一時ブームになり、ネット上の記事やコンテンツを選別・整理することを指すようになったが、その流行は日本だけでなく英米でも見られる。ニューヨークのミッドタウンには高級ブテイック「ザ・キュレーテッド・ニューヨーク」があり、ロンドンのヒースロー空港にはレストラン・バーの「キュレーター」がある。
リベラルエリート系新聞ニューヨーク・タイムズのコラム「今や誰もがキュレーター」は、この言葉が“エンパワー”などと並び「意識高い系」な文脈であまりに流行りすぎている、と皮肉めいて紹介している[*1]。
この言葉、そもそもはミュージアムの「キュレーター(学芸員)」が担う仕事のことを指すというのはご承知の通りであるが、同じコラムには、大学のキュレーション学部の教授の発言で、コレクションを調査し管理するのが「キュレーション」であって展覧会を作ることは「エキシビジョン・メーカー」だよね、とかいう発言も載っていて興味深い。その意味をモノの管理をする業務に限るべきだ、というこうした立場は、キュレーション(curation)が元来「世話をする(care)」という意味のラテン語“curare”に由来することから来ているのだろう[*2]。
その逆に、ミュージアムの専門家でも企画演出のことだけを指したりもするし、情報をまとめることを曖昧に指して気軽に使われてもいる。この言葉は、実はけっこう厄介なものなのだ。今回は、厄介な「キュレーション」について考えてみよう。
舞台と語りをキュレーションする
メニューや商品など情報キュレーションの意味へと転用される元になったのは、ミュージアムにおける展覧会制作のプロセスや業務を指す用法だ。丁寧に言えば、展示物やパネルなどの「モノ」や展覧会場や野外やバーチャル空間などの「場所」を、展示のストーリーで語られる歴史やテーマなどの「言説」と関係づけることを、「コンセプト提案」「作家・展示物の選定」や「展示室での展示構成」などを含む一営みによって行なうことである。このように説明できるだろう。
本稿では、この意味における「キュレーション」について芸術祭を取り上げながら考えていきたい。
ミュージアムではキュレーターや学芸員と呼ばれるが、芸術祭の場合にはディレクター(芸術監督)という役職で呼ばれることもある。彼らは広い領域で強い影響力をもつため、作家や作品を利用し権力を振りかざす専制君主になることもあれば、様々な改善運動をおこない、新たな価値観をもたらす改革者にもなりうる存在だ。モノの世話だけではなく、展覧会の「舞台」や「語り」の“お世話をしている”と言えるかもしれない。
自己批判する芸術祭・現代美術
世界最古かつ現在も権威を持つヴェネツィア・ビエンナーレは、「美術のオリンピック」として知られる。国民国家別に展示して競い合うからだ。アートが代理戦争を行なうような状況で競争が激化していくなか、現代美術は国際文化外交へと組み込まれていった。「国民国家」という枠組に固執するならこの成り行きは必然だったと言える。
その開始以来、国民国家構造とビエンナーレの蜜月な関係は、①ビエンナーレの起こり、②万博モデルから美術運動の見本市へ、③第二次大戦下の急進化と中断、④再開と冷戦構造での文化外交という経緯で展開していった(過去記事「アートが代わりに戦争する 「美術のオリンピック」ヴェネツィア・ビエンナーレの歴史をたどる」)。
こうした「国家代表型展示」のしくみは、ひとりのキュレーターが決めたわけではないのだが、ヴェネツィア・ビエンナーレ独特の「キュレーション」のようにも見えてくる。政権強化などプロパガンダ的な手段へと容易に通じかねない国民国家的な枠組みに依拠し続けることに対して常に批判が向けられてきたが、ヴェネツィア・ビエンナーレはそれに対して、組織改革やキュレーションで応答してきた。
以下では、この改革期を⑤「『自己批判』とキュレーション」と位置づけ、改革の歴史を辿りながら、国民国家モデルをいかにかえりみてきたのかをみていきたい。改革的なキュレーションの試みにおいては、そのしくみや舞台設定に対しては「属性」面で、またテーマやコンセプトなどの語りに対しては「物語」面で打開策が提案されてきた。言いかえれば、ヴェネツィア・ビエンナーレは量的・質的アプローチの両面から改革にアプローチしてきたのである。
芸術祭のあり方について“ケア”をしてきた、ヴェネツィア・ビエンナーレの「かえりみるキュレーション」について具体例を見ていこう。
組織運営をめぐる対抗運動と改革
芸術祭改革には社会運動が貢献した。第二次世界大戦後、敗戦国の民主主義化を目指したアメリカの支援も手伝いイタリア社会は産業化し安定に向かったが、1968年のパリ五月革命を契機として権力構造を担う体制に対抗する学生運動が世界中へと拡大するなかで、ヴェネツィア・ビエンナーレへの運営に対する学生の抗議も拡大していった。
ビエンナーレのキュレーションは美術市場と並走した。たとえば1942年から68年まではビエンナーレ運営組織が各国の「出展」者に10%の手数料を課し、展覧会で作品の販売が行われた[*3]。つまり、彼らは各国からの「出店」者であり、この時期ビエンナーレは、実質的に見本市――アートフェアと同様の存在――であった。
ビエンナーレは美術市場における価値づけにも影響を与え、権力維持強化の手段となり腐敗を生んでいるものとして、大賞を決める制度へも批判が向けられた。69年以降懸賞は廃止されたが、それは86年までの一時的なものにとどまった。
学生運動は、自治体だけでなく、ローカルの様々な部門の組織代表、各種業種の組合などの構成員をふくめた「より民主的な」理事会へと再編することを求め、73年には新体制のビエンナーレ組織委員会が作られるにいたった。

改革するキュレーション:「属性」と「物語」
こうした組織運営をめぐる様々な改革を求める対抗運動とは別の水準でおこなわれたのが、キュレーションをめぐる改革である。ここではヴェネツィア・ビエンナーレに見られるその方法を、「属性」と「物語」と二つに分けて考えてみよう。
1)「属性」を拡げる量的アプローチ:若手に雇用機会を“開く”アペルト
ヴェネツィア・ビエンナーレの歴史における大きな事件に、1980年の新人枠「アペルト(apert)」の導入がある。「開かれた」を意味するイタリア語(英語:open)で名づけられこの制度は、のちには芸術監督も務めキュレーターとして名高い批評家のハラルド・ゼーマン、及び、同じく批評家のアキッレ・オリーヴァの二人が発案したものだ。
その意義は経験の浅い世代への登竜門を提供したことである。若手に主眼におくカテゴリーをつくったことで、これまではすでに評価の定まったベテランアーティストを中心にしてきた選定が開かれたものとなった。
大きなビエンナーレでの活躍は、美術館での展示やコレクション買上の機会、美術市場での高額化や販売促進などへとつながる。つまるところ、アペルトは「若年層・非ベテラン層への雇用機会への拡大(開放)」であった。いっぽうで、それは言うまでもなく懸賞制度と同じく権力行使の手段にもなる。また重要なのは、アペルトは常設のパビリオンをもたない国籍のアーティストへの機会提供という役割も果たしてきた。
ディレクターの多様性が選択眼を開く
人種・ジェンダー・言語などにおいて多様な背景をもつディレクターの起用は、ビエンナーレの企画自体の多様化へとつながる。言語圏や文化圏が異なり、活動拠点・範囲や思考の体系が違う人々が作家を選んだり、アイディアをもたらすからだ。ヴェネツィア・ビエンナーレのこうした方針が色濃くなるのは1999年のことである。
先立って1995年のビエンナーレ百周年記念第46回には、フランス出身の著名なキュレーター、ジャン・クレールが初の非イタリア人ディレクターとして選ばれた。99年以降は、ディレクターに非イタリア人を積極的に指名することで多様化を謳うようになる。2001年、03年には先に挙げたスイス出身のハロルド・ゼーマンが務め、05年以降を挙げれば、スペインのローザ・マルティネスとマリア・デ・コラール、アメリカのロバート・ストー、スウェーデンのダニエル・ビルンバウム、スイスのバイス・クリガーと続いていく[*4]。
多様化路線への移行を象徴するのは、この頃のアペルトの扱いである。95年のジャン・クレールの回でアペルトは一度廃止されている。それをゼーマンが99年、その復活を「ダッペルトゥット(dAPERTuttO)」という題でテーマ自体に打ち立てた。「あらゆるところに(英語:everywhere)」を意味するイタリア語 dappertuttoをもじった企画名には、「アペルト(開かれ)」が含まれている[*5]。
ディレクターを脱植民地化し、脱家父長制化する
だが、彼らの出身国は非イタリアであるがすべて欧米の国々であることにも気が付くだろう。さらに、彼らは皆、非ラテン系白人であり、英語圏でよく名の通った著名な評論家・研究者である。同様に、この時期のイタリアからの起用も、1997年のジェルマーノ・チェラント、2003年のフランチェスコ・ボナミ、13年のマッシミリアーノ・ギオーニ、22年のチェチリア・アレマーニと、ニューヨーク拠点の者も多く英語圏を中心にモダンアートのグローバルな美術界で活躍する立場にあった。要するに、歴史的にみて支配的な立場の属性を持つものである。
この意味で、2015年の第56回にナイジェリア出身のオクウィ・エンヴェゾーが選ばれたことが、その属性という点でも美術界を超えて大きな話題となった[*6]。黒人男性である彼は、ビエンナーレ初のアフリカ生まれのキュレーターだ。1998〜2002年のドイツの芸術祭ドクメンタ11でも非ヨーロッパ出身の初の芸術監督となった。他方で、18歳からブロンクスに移りアメリカで教育を受けており、流暢なアメリカ英語を完璧に操ることができ――アクセントも少しだけ感じられる程度で――「西洋」の「グローバル」な美術界で活躍を続けていた人物である点も押さえておきたい。
ジェンダーに目を配ると、2005年のローザ・マルティネスとマリア・デ・コラールはヴェネツィア・ビエンナーレ史上初の女性監督であった。2013年のバイス・クリガー、17年のクリスティン・マセル、22年のチェチリア・アレマーニと近年続く。
今年の24年は進歩姿勢が象徴的だ。選出されたブラジルのサンパウロ美術館アシス・シャトーブリアンのアドリアーノ・ペドロサは、ビエンナーレ史上において初のラテンアメリカ出身であり、クィアを公表している初めての芸術監督である。
ディレクターの属性の多様化が90年代に始まったように、背景には多文化主義という社会の潮流があり、「国民国家」の枠組みへの自己批判へと通じている。国籍、言語、民族・人種、女性や性的マイノリティなどジェンダー、障碍の有無など身体など、さまざまな「属性」に注目して導入し、多様化を通じて改革に実行力を持たせられる可能性はあるチャンネルではある。こうした属性へのアクションは単なるうわべだという批判は絶えず起こるが、属性へのアプローチから、芸術祭を脱植民地化(decoloniztion)し、脱家父長制化(depatriarchization)することはできるのだろうか。
芸術祭のアファーマティブアクション
ディレクターの視座の多様化は、選ぶプロセスを通して美術展を構成するアーティストの多様化へと結実するが、それをはっきりコンセプトとして打ち出した例を取りあげてみよう。
2019年第58回の際、芸術監督のラルフ・ルゴフは、ジェンダー不平等と不均衡に対するアクションを掲げ、メイン展示部門で登録されるアーティスト81名中40名を女性としたのである。この年は日本のあいちトリエンナーレでも同様に、「男女」を数の上で同数とするコンセプトが企画進行中に決まっている。雇用や学業の機会均等のためのアファーマティブアクションとしても知られる方法であるが、ディレクターという立場はこうした方法で構造を制御する力をもっているのだ。
こうした「男/女」という二分的な(バイナリー)分け方には、その他のカテゴリーが考慮されないこと、カテゴリー化作用自体が含む課題――たとえば、黒人女性という二重に差別されるインターセクショナルな問題、ノンバイナリーやアセクシャルなどカテゴリーの基準自体を問う立場――についてはいったん傍に置かれることになる。
ただし、こうしたコンセプトをわざわざ打ち出すということは、進歩的な思想と相性がよい現代美術や芸術祭という文脈であっても、これまで十分に対象とされてこなかったということであるし、ゆえに、そのなかにあって「女性」という枠組みで生きるアーティストらの人々が未だ窮状に置かれていることを意味する。ここに対するまさに「ケア=手あて」としてのアクションである。
ディレクターであれアーティストであれ、それは市場における雇用機会へのアプローチである。繰り返しになるが、しかしそれは、ある意味ではカテゴリー・属性の枠組みに依存している段階でもある。キュレーションにおけるこうしたアクションの段階自体もまた、社会の認識現状を映す鏡である。
2)「物語」を提案する質的アプローチ:テーマで意味を与える
構成比からこうした様々な「属性」に対して取り組むキュレーションのアプローチは、いわば“量的な”アプローチである。それに対して、キュレーターや芸術監督が企画趣旨にコンセプトと言葉を駆使しておこなうキュレーションの“質的”アプローチもある。
キュレーターは芸術祭・展覧会を通して、世界の趨勢や時世を読み、ちょっと先の未来への想像力を企画内で見せていく。「物語」によって新たな価値観をもたらすことを目指している。
全体を統一するテーマの明示を以てそれを判断するならば、ヴェネツィア・ビエンナーレにおいてこの意味での質的なキュレーションが明確化されたのは、2007年のことと意外に歴史が浅い。その初回に「現在形で記す『芸術』(Art in the Present Tense)」が副題に掲げられているのは宣言的である。
以下に挙げたのはそれ以後のコンセプト一覧である[*7]。
〔ヴェネツィア・ビエンナーレコンセプト一覧〕
“Think with the Senses, Feel with the Mind. Art in the Present Tense.” (52nd )
“Making Worlds” (53rd)
“ILLUMInations” (54th )
“The Encyclopedic Palace” (55th)
“All the World’s Futures” (56th)
“Viva Arte Viva” (57th )
“May You Live in Interesting Times” (58th)
“The Milk of Dreams” (59th)
“Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere”
「この“ある意味で”面白い時代を私たちは生きてゆけますように」
2019年、芸術監督ラルフ・ルゴフが掲げたキャッチフレーズは、May You Live in Interesting Timesであった。少しだけ意訳するなら、「この“ある意味で”面白い時代を私たちは生きてゆけますように」。このような意味だと解釈できる。この言い回しは、中国の呪いの言葉――と、まことしやかに知られる――表現である。“ ”に示してみたように、ここにあるのはアイロニーである。「平和」や「平穏」というun-interestingな時代ではないという含意があきらかに込められている。

ルゴフのステートメントにはこうある。「フェイクニュースやオルタナティブ・ファクトがインターネットを中心に普及し、政治的言説やその拠り所となる信頼が蝕まれていく現在、立ち止まれるときに立ち止まり、自分たちの使命を考え直すべきではないだろうか」。パンデミック前の世界、「戦争」が世界の各国でリアリティをもって迫り出す前の時代に語られるのは、ドナルド・トランプやブレグジットに代表されるポピュリズムやポスト真実の不安であった。つまり、プレ・パンデミックに掲げられたのは、「コミュニケーション」の課題をアートで解決することであった。
彼はこう続ける。「アートが政治の領域においてその力を発揮することはない」ものの、「アートは間接的に“面白い時代”の生き方や考え方の指針になりうる」。アイロニーの復権のように、その物語を読む、生きるリテラシーを発揮することがアートには可能であるし、それを解決策のように語ることも可能であるかのようだ。
2019年の回でルゴフは、ひとつのテーマ自体を掲げるよりも、作品をつくること自体や、観客に快楽や批判的思考をもたらすというアートの社会的役割を強調したいと述べている。
そして、作品の意味は基本的にはモノではなく、3種類の対話に宿るという考え――アーティストと作品との対話、作品と観客との対話、そして、観客同士で交わされる対話であるという。つまり、観客が作品を通じた経験でものの見方を更新し、その後の日常に向き合うこと、これを展覧会の目的、アートの本懐とキュレーションで枠づけている。
コミュニケーションの問題の対象化、アートはあくまで社会の道具で社会のインフラになりうるという考え方自体は、ソーシャルメディアでまともな議論が成立しにくくなり、不健全な対話の問題が先鋭化した現在もいっそう重要な視座になっている。19年当時はまさにあいちトリエンナーレで「表現の不自由展・その後」への攻撃をめぐる問題が起こっていた折だ。
社会の「コミュニケーション」を歴史の「構造」と共に考える
しかし一方で、表現・芸術を通じたコミュニケーションが見落としていたのは、だれが見過ごされてきたのかという問いではなかっただろうか。社会の〈コミュニケーション〉は、不均衡を生む基盤となる〈構造〉と同時に見なくてはならない[*8]。上で紹介したように、ルゴフは“アファーマティブアクション”という量的なアプローチでこの不足をケアしたのだろう。
今回2024年のビエンナーレで、初のクィア、ラテンアメリカ出身の芸術監督となったアドリアーノ・ペドロサが掲げたのは、「ストラニエリ・オブンケ/フォリナーズ・エブリウェア Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere」というテーマだ[*9]。「外国人はどこにでもいる」という意味のこの言葉は、2000年代初頭イタリアで人種差別と外国人嫌悪と闘ったトリノのグループ名から取られている。つまるところ「外国人」とは――言語であり民族であり国籍であり公衆衛生でありセキュリティであり経済利権であるところの――自己存立を危ぶむ「敵」に貼られるレッテルである。
パンデミックでウイルスを闖入させる“やつら”、ウクライナとロシアと関係諸国で生きている“やつら”、パレスチナ・ガザ地区やイスラエルや合衆国のキャンパスでも声高に叫ばれる“やつら”。「外国人はどこにでもいる」――ヴェネツィアの街中に掲げられることでこの言葉は、ローマ帝国時代の難民が住み、国際交易で栄え、ナポレオンとオーストリアに占領され、そしてイタリア屈指の国際観光都市というこの街の歴史とも接続される。この言葉はポスターにはイタリア語と英語で併記され、展示では各国言語で表記されている。「外国人」とは誰にとってのものなのかという相対性が強調される。
クィアな“やつら”はどこにでもいる。キュレーションは、キュレーターのペドロサ自身のもつ属性へも通じていく。「外国人」は「アウトサイダー」の隠喩と言ってよいのだろう[*10]。「彼らと私たち」の違いと格差を言葉にする危険性についてペドロサは示唆しているが、このことが「国民国家」の枠組みに立った線引きの言葉で表現されていることは、その歴史をかえりみたとき、ヴェネツィアの街、そして、ヴェネツィア・ビエンナーレにふさわしい。
これは、「外なる存在」は誰がどう決めているのか? という、境界と属性が生み出す序列の問題を問うている。それはヴェネツィアを飲み込んだ国民国家の制度のなかに、そして我々の心の中に「どこにでも」いる、歴史がつくり出した〈構造〉である。〈コミュニケーション〉はその構造を見てこそ真に成立する。

〈キュレトリアルなるもの〉でかえりみる
キャッチフレーズ的に掲げられるコンセプトが、選定され注意深く配置されたアート作品の意味を複層的に広げていく。そして同時に、コンセプトはそれらを選ぶ指針にもなる。こうした往還関係が機能するのなら、そのキュレーションは秀逸なものである。「物語」をつくるキュレーションの質的側面はこのように機能するのである。
キュレーターのマリア・リンドは、キュレーターの力関係が一方向的でなく、双方向的かつネットワーク型である新たなキュレーションの視座に、〈キュレトリアルなるもの(the curatorial)〉という名を与えている[*11]。
この意味においてキュレーションは、アーティストや作品に対して意味を与える行為のことのみを意味しない。展覧会・ビエンナーレやその土地の歴史や社会制度、建築や都市といった空間設計――さらに気候や災害なども変数に入れてもよいだろう――などを相互に関係づけるシステムとして捉えられる。「キュレーション/キュレーター」「アート/アーティスト」はその変数の一つである。こうした視座である。
リンドのこの概念は、シャンタル・ムフの「政治的なもの(the political)」にならったものだ[*12]。すなわち、集合意思に表向きあらわれる「融和」や「合意」「一致」という結果に着目するのではなく、合意するにせよしないにせよ決定される前に存在していた摩擦や対立や没交渉など「闘争」的なコミュニケーションの動的な部分にこそ着目すべきだ。このような見方をとっている[*13]。
つまり、プロセスを隠す暴力を棄てさろうと志向し、展覧会をめぐる場の力学に意識的なのである。キュレーター自身を常に介入と変化をもたらす触媒であるとみなし、その役割について自省的にキュレーションする。これが〈キュレトリアルなるもの〉の実践なのである。
2019年と2024年のヴェネツィア・ビエンナーレのキュレーションを較べれば、その焦点が転換したと気がつく。対話不全という「コミュニケーション」から、各層のステークホルダーが発揮しうる力(エージェンシー)はその場の歴史に決定づけられたものだという「構造」へと焦点が展開していったのである。
そうそう、「キュレーション」の語源の話で、ひとつ忘れていたことを思い出した。同じラテン語のcurareは、「治すcure」という言葉も生んだのだとか[*14]。「キュレトリアルなるもの」によって、かえりみる「治療」の道半ばにあるヴェネツィア・ビエンナーレを象徴するかのようだ。
[*1] Lou Stoppard, “Everyone’s a Curator Now: When everything is “curated,” what does the word even mean?” New York Times (March 3, 2020)
[*2] “curate,” Online Etymology Dictionary.
[*3] Adam, Georgina, “Trading places”.Financial Times (June 6, 2009).
[*4] ヴェネツィア・ビエンナーレ公式サイト “BIENNALE ARTE / HISTORY”
[*5] 「1999 / DAPERTUTTO」 ヴェネツィア・ビエンナーレ公式サイト。「ダッペルトゥット」についてはGoogleArt&Cultureをつかったウェブ展示版がここ公開されている。
[*6] たとえば、『ザ・ガーディアン』など大手一般新聞だけでなく、アクティヴィズム系ジャーナリズムの『デモクラシー・ナウ!』なども報じている。2019年の死後の記事には、エンヴェゾーの功績がまとめられておりディレクター時のヴェネツィア・ビエンナーレでのインタビュー動画を含む。
[*7] 複数形や大文字表記などの活用で、多義的な意味を与えようとするキャッチフレーズ的なタイトルの数々は日本語訳が難しいが、以下のように訳を与えてみたので参考にされたい。
〈センスで考え、マインドで感じる 現在形で記す「芸術」〉“Think with the Senses, Feel with the Mind. Art in the Present Tense.” (52nd )/〈複数形の世界をつくる〉“Making Worlds” (53rd)/〈照らす(たくさんの国を)〉“ILLUMInations” (54th )〈百科事典の宮殿〉“The Encyclopedic Palace” (55th)/〈全世界の未来〉“All the World’s Futures” (56th)/〈芸術万歳〉“Viva Arte Viva” (57th )/〈この“ある意味で”面白い時代を私たちは生きてゆけますように〉“May You Live in Interesting Times” (58th)/〈夢のミルク〉“The Milk of Dreams” (59th)/〈ストラニエリ・オブンケ/フォリナーズ・エブリウェア〉“Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere”
[*8] 『楽しい政治――「つくられた歴史」と「つくる現場」から現代を知る』講談社、2024年(近刊)
[*9] 公式パンフレットはここから利用可能。
[*10] ペドロサは、テーマ全体を「外国人」で代表させつつ、以下「外国人(The Foreign)」「よそ者(The Distant)」「アウトサイダー(The Outsider)」「クィア(The Queer)」という四つのカテゴリーで構成されると並べている。「Introduction by ADRIANO PEDROSA / Curator of the 60th International Art Exhibition」ヴェネツィア・ビエンナーレ公式サイト
[*11] Maria Lind, “The Curatorial,” Artforum (October, 2009).
[*12] Chantal Mouffe, On the Political (Routledge, 2005).
[*13] この用語は、美術界の潮流という文脈の上で用いられている。たとえば2006年にロンドンのゴールドスミスカレッジにはキュレーションの理論と実践をつなぐ志向を持つ博士課程プログラム「キュラトリアル/ナレッジ」が創設されたが、ジャン=ポール・マルティノンらがつけたプログラム名に掲げられた「キュレトリアルなるもの」という言葉は、展示企画者は強い主体性をもつものの、創造的であることでより民主的な展覧会のあり方を探究するという志向性をもちながら、キュレーション概念を再定義しようとしたものである。彼らは「展覧会やその他の展示の方法に関係する専門的な実践群」という一般的なキュレーション概念に対して、キュレトリアルとは、「イベントの演出から実際に起こるイベントそのもの――エンアクトメント、ドラマ化、パフォーマンス――への転換を強調すること」という動的な概念であると、演劇的なメタファーで説明している。Jean-Paul Martinon and Irit Rogoff,”Preface,” Jean-Paul Martinon ed.,The Curatorial: A Philosophy of Curating (London: Bloomsbury, 2013), p.ix.
[*14] “cure,” Online Etymology Dictionary.
【お知らせ】
当連載を収録した書籍『歴史修正ミュージアム』が待望の書籍化! 全国書店やAmazonなどの通販サイトで、2025年9月29日(月)より発売いたします。
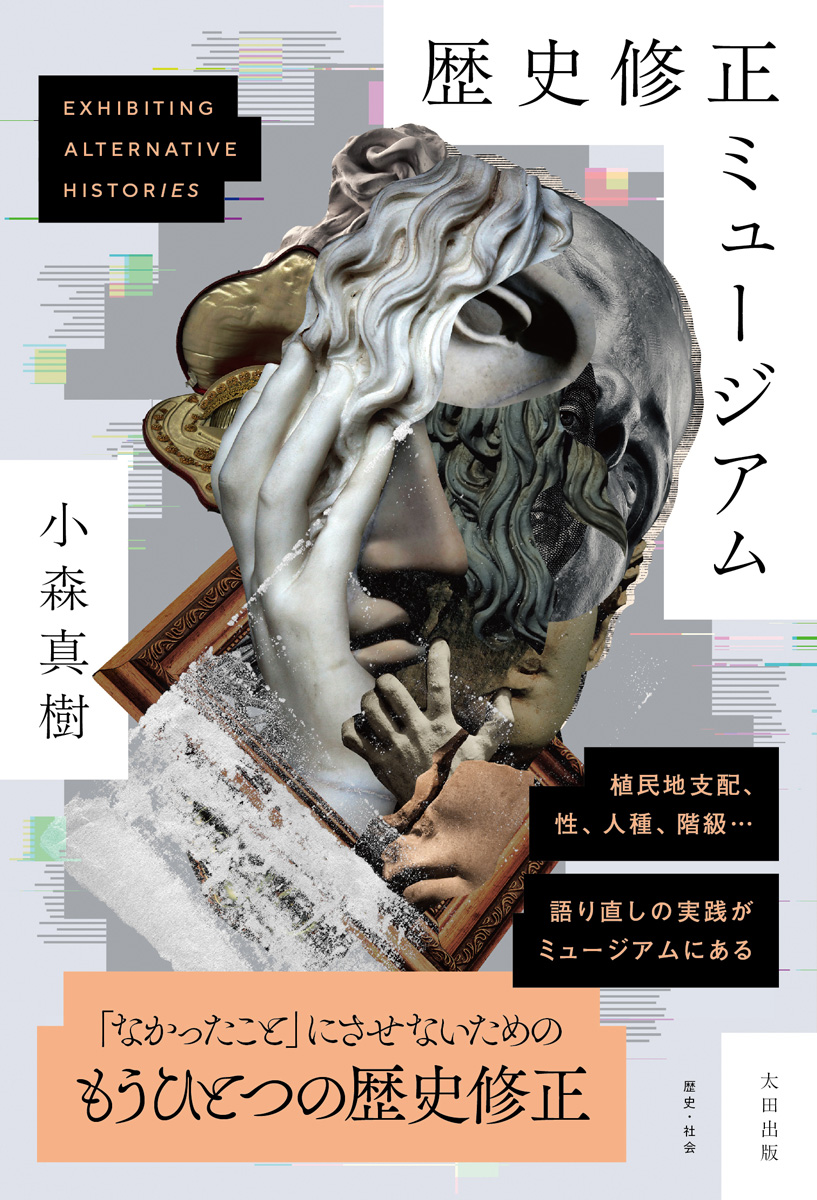
筆者について
こもり・まさき 1982年岡山生まれ。武蔵大学人文学部准教授、立教大学アメリカ研究所所員、ウェルカムコレクション(ロンドン)及びテンプル大学歴史学部(フィラデルフィア)客員研究員。専門はアメリカ文化研究、ミュージアム研究。美術・映画批評、雑誌・展覧会・オルタナティブスペースなどの企画にも携わる。著書に、『楽しい政治』(講談社、近刊)、「『パブリック』ミュージアムから歴史を裏返す、美術品をポチって戦争の記憶に参加する──藤井光〈日本の戦争画〉展にみる『再演』と『販売』」(artscape、2024)、「ミュージアムで『キャンセルカルチャー』は起こったのか?」(『人文学会雑誌』武蔵大学人文学部、2024)、「共時間とコモンズ」(『広告』博報堂、2023)、「美術館の近代を〈遊び〉で逆なでする」(『あいちトリエンナーレ2019 ラーニング記録集』)。企画に、『かじこ|旅する場所の108日の記録』(2010)、「美大じゃない大学で美術展をつくる vol.1|藤井光〈日本の戦争美術 1946〉展を再演する」(2024)、ウェブマガジン〈-oid〉(2022-)など。連載「包摂するミュージアム」(しんぶん赤旗)も併せてどうぞ。https://masakikomori.com

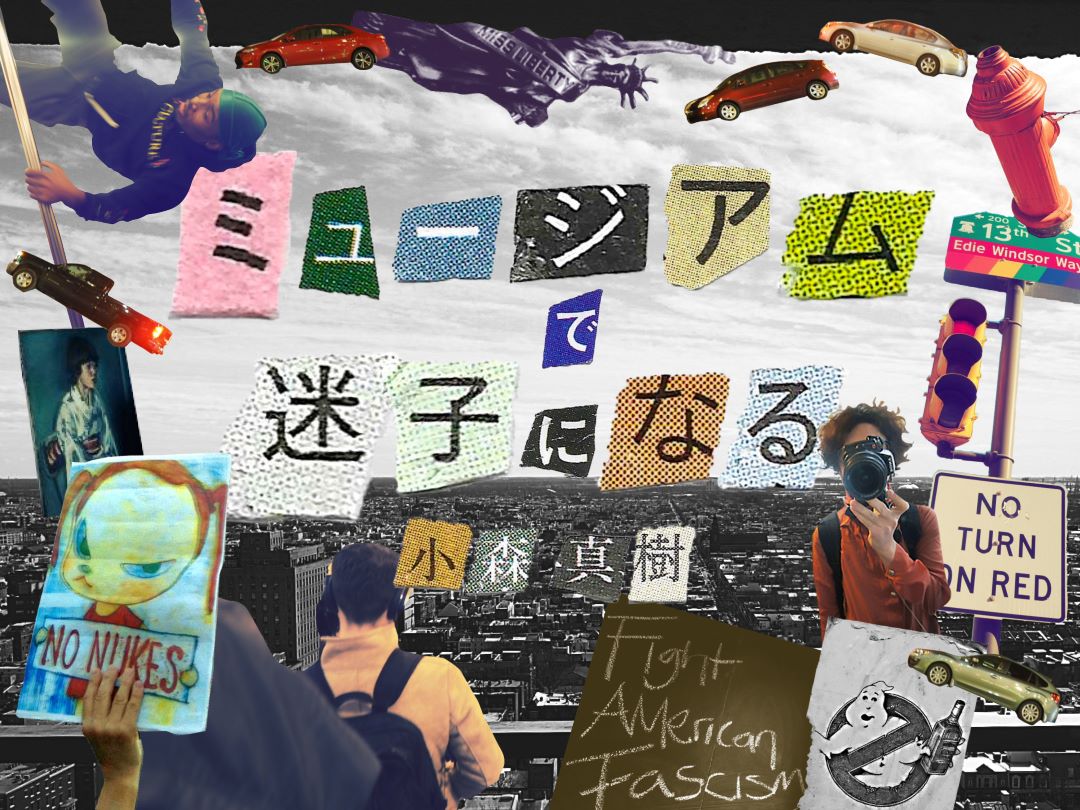

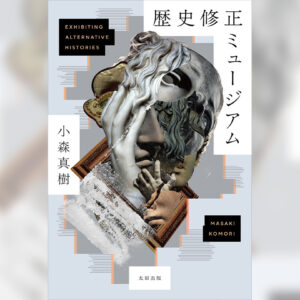

![アートの入り口 美しいもの、世界の歩き方[ヨーロッパ編]](https://m.media-amazon.com/images/I/41NkPjv70ZL._SL160_.jpg)

