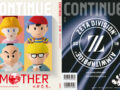20年ぶりに奄美大島に行った。加計呂麻島がすぐそこにあったのにそのときは行くことができなかった。好きでよく読んでいた小説家の島尾敏雄が第二次大戦末期に特攻部隊の隊長として配属されていた場所だった。そこがどんな場所なのか見てみたかった。そう思いながらあっというまに20年以上が過ぎてしまうから驚く。しかし20年も経つとふと、そこへ行く機会が巡って来たりもする。
「あともう少しで加計呂麻島まで行けたのにな」と思いながら引き返していた
私が20代前半だったときのことだから、今から20年以上前になるのだが、奄美大島に行ったことがある。その頃よく遊んでいた音楽仲間に、親戚が奄美大島に住んでいるという人がいて、その親戚の家に自由に泊まっていいという。
ということは、親戚はすでに奄美大島にいなかったのか、島にはいたけど生活の拠点は他にあって、その家は半ば空き家のようになっていたのか、とにかく、好きなように使っていい一軒家が奄美大島にあるというのだ。
私の友人が奄美大島のその家に泊まりに行く、何か目的があるでもなく、1週間ほど、ただそこにのんびりしに行くという。その当時、私は東京に住んでいたのだが、東京から奄美大島までの交通費と、向こうで使う最低限のお金さえあればなんとかなると友人は言う。
奄美大島がどんな場所かもよく知らなかったが、宿泊費を気にせず、自由にいられる場所があるというその条件が楽しげに思えて、私も一緒に行くことにした。奄美大島の人を親戚に持つ友人と私と、もうひとり、別の友人も加わって、合計3人で行くことになった。
私以外のふたりは、私より少し年下で、音楽好きの穏やかな人で、一緒にいて気楽だった。多少のことがあっても苛立ったりせず、その場その場をそれはそれで楽しもうという姿勢が共通していた。東京から飛行機で鹿児島へ、鹿児島で乗り換えて奄美空港、南北に長い奄美大島の北東端にある空港に降り立った。夏だった。
空港近くでレンタカーを借りて、その車が私たちの生活の足となった。私たちが過ごした家は、今思えば奄美空港からそれほど離れてはいない。空港から南へ少し行った龍郷町(たつごうちょう)あたりにあったと思う。おぼろげな記憶によると宿泊地の近くには売店などはなく、何か買うのなら「ビッグツー」という名の大きなホームセンターに行くのがいちばん手っ取り早かった。歩いて行くのは大変な距離だったが、車に乗れば15分か20分ほどで着いた。
ビッグツーで野菜や肉を大量に買い、とにかく毎日、庭先に用意した焼き台で、焼いて食べる。味付けは焼肉のタレか塩こしょう。美味しくて、昼も夜もそれでよかった。
そんな最低限の食生活でも、買い出しのために車は欠かせないのだったが、その車は私が運転した。単純に、3人のなかで免許証を持っているのが私だけだったのだ。そもそも、免許を持っていたから私が呼ばれたのだと思う。
私は運転免許を取得したが、あとにも先にも、その奄美大島にいたときしか運転していない。反射神経も鈍く、判断力にも欠けていて、最初から車を運転するのが怖かった。あのときだけ、仕方ないから運転した。
奄美大島には1週間ぐらいいただろうか。私はできるだけ運転したくなかったので、泊まっている家の近くにある砂浜まで歩いてシュノーケリングをしたり、日が沈むのを見てぼーっとしたり、夜になればまた海まで歩いて星を見てと、その繰り返しだった。
シュノーケリングをすれば色とりどりの魚が間近に見え、夜は流れ星がビュンビュンと流れた。「よし、あとひとつ流れ星が流れたら帰ろうか」と友人が言った、あんな素敵なセリフはそうそう聞かない。そんなことをしながら酒を飲んで、3人でどうでもいい話をして、野菜と肉を焼いて食べて、時間が過ぎていく。
とはいえ、せっかく奄美大島まで来たのだから何か観光らしいことをと、思わないでもなかった。それは私以外のふたりも同じで、なんせ1週間近くの滞在期間があるのだから、そのなかで1日ぐらいはどこか遠くまで行ってみようという話になった。運転距離が伸びるのは私の本意ではなかったが、島での数日のなかで少しは運転に慣れた気がして、挑戦してみてもいいかと思った。
それで、島の南へ車で1時間ほど走ったあたりにあるマングローブの原生林まで行くことにした。カヌーに乗り、原生林のなかに流れる川を回遊するツアーがあって、観光スポットになっている。冒険気分で、それはそれでいい思い出になった。
これは完全に私の記憶違いで、その原生林まで行ったら、さらにもう少し進めば、奄美大島の南に横たわるようにある加計呂麻島(かけろまじま)へ行くフェリーに乗れたはずだった。実際は原生林からさらに30分は車を走らせなければフェリー乗り場までは行けない。が、とにかく、そのときの私は「あともう少しで加計呂麻島まで行けたのにな」と思いながら、そのときは宿泊地のほうに引き返した。
加計呂麻島は、好きでよく読んでいた小説家の島尾敏雄が、第二次大戦末期に、「震洋(しんよう)」という、魚雷を積んで敵艦に突撃する特攻部隊の隊長として配属されていた場所だった。そこがどんな場所なのか、見てみたかった。
そう思いながら、あっというまに20年以上が過ぎてしまうから驚く。そして、また驚くことに、20年も経つと、ふと、そこへ行く機会が巡って来たりもする。2025年の7月、46歳になっている私は、再び奄美大島に行くことになった。
理由もわからぬままに引き延ばされまた当たり前のように次の朝が来た
奄美大島で黒糖焼酎を作っている酒蔵を取材したり、地元でコミュニティFMを運営している方を取材したりと、仕事の用事で行くことになったので、自分の自由になる時間はそれほどなかったのだが、それも取材の一環として、加計呂麻島にも一泊できることになった。しかも、加計呂麻島出身で今は奄美大島の中心街・名瀬でお仕事されているT氏が、車に乗せて案内してくれるという。
朝、前夜宿泊した名瀬のホテルからT氏の車に乗って出発する。うねるようにして奄美大島の北から南へと延びる国道58号を車が走り、私が20年以上前に怯えながら車でやってきたマングローブの原生林の脇をあっというまに超えていった。

名瀬の街から1時間ちょっとで奄美大島の南端の古仁屋という街に着く。古仁屋の港から加計呂麻島へは町営の大きなフェリーでも行けるし、海上タクシーと呼ばれる、小さな船に乗って行くこともできる(海上タクシーのほうだと、島のあちこちにある小さな港まで行けるようだった)。
私たちは町営の「フェリーかけろま」に乗り、古仁屋港から加計呂麻島の瀬相港まで行く。出航から20分ほどで到着。

早速、T氏の車に乗っての加計呂麻島めぐりがスタートする。車は山道を行く。というか、加計呂麻島をT氏の車で移動しながら思ったのだが、加計呂麻島はずっと山だ。山と、その山の麓の森があって、陸と海との少しの狭間に複雑な形の海岸線がある。20年ちょっと前の私は「加計呂麻島にも行きたかったな」と思いつつ果たせなかったが、もしあのときに勢いで島まで上陸したとして、こんな険しい山道を運転できたとは到底思えない。
T氏は車はすいすいと行く。これでも山を切り拓いて道路が通って格段に便利になった。昔は、山に隔てられた集落と集落のあいだにはほとんど交流がなかったほどだという。T氏は74歳なのだが、子どもの頃は山のなかのけもの道を裸足で片道1時間半ほど歩いて学校へ通ったそうだ。
映画『男はつらいよ』シリーズの最終作『寅次郎紅の花』は、加計呂麻島をロケ地に撮影された(阪神淡路大震災の発生からまもない頃の神戸の長田の街も出てくるし、岡山の津山も出てくる、寅さんの地元である葛飾の柴又ももちろん出てくるのだが)。その映画の印象的なロケ地が、加計呂麻島に点在していて、T氏はそんな場所へも立ち寄ってくれた。私はその時点では『寅次郎紅の花』を見たことがなく、「へー!」としか言えなかったが、大阪に戻ってからサブスクで配信でその映画を見て、加計呂麻島でもっとじっくりロケ地を見ておけばよかったと思っている。
ロケ地のひとつ、樹齢700年と言われる「於斉のガジュマル」の前で写真を撮ったあと、そこからまた10分ほど車に乗り、東西に長い加計呂麻島のちょうどなかほどにある呑之浦(のみのうら)という集落へ向かった。そこに「島尾敏雄文学碑公園」という公園があり、島尾敏雄文学碑が建っている。

私は、今回、奄美大島に向かう飛行機や空港に向かう電車の中で、島尾敏雄の『出発は遂に訪れず』という短編集を久々に読み返した。表題作の『出発は遂に訪れず』は、島尾敏雄が終戦の数日前から呑之浦で出動命令を待ちながら過ごした日々のことが綴られている。最終的には島尾敏雄が指揮した隊員たちは出動せぬまま、終戦を迎え、生き延びる。私はそうと知っているからこんなふうに「最終的には」なんて簡単に書けるが、島尾敏雄も隊員たちも死ぬつもりでここにいた。
震洋艇はひとり乗りの小型のボートで、船首に約230㎏の炸薬を搭載している。攻撃目標に体当たりして自爆するための船である。同じような特攻艇に、人間魚雷とも呼ばれる「回天(かいてん)」という潜水艇もある。
震洋艇は1944年以降量産され、日本各地、香港や台湾、フィリピンやマレーシアにも震洋の部隊があったようだ。島尾敏雄は第十八震洋隊の隊長として、183名の部下を率いて、この加計呂麻島の呑之浦に駐屯していた。1945年8月13日、一度は出撃命令を受けるも、攻撃目標となる敵艦がその時は現れず、待機したまま8月14日を過ごし、15日の正午に終戦を知らされる。
『出発は遂に訪れず』には、その宙吊りに去れたような時間のことがこんなふうに書かれている。
太陽が容赦なくのぼり出すと、もう引きもどすことはできず、遂行できずに夜を明かした悔いの思いが、からだにみなぎり、狂暴な気持に傾いてとどめられない。でも爆発させることがためらわれ、内側におさえこむと、無性に眠くなった。私たちは発進しなければほかに使いみちのない未熟な兵員にすぎない。
死を前提としてここに来て、死を覚悟し、死ぬために発進していくことが自分たちに課された最大かつ唯一の使命なのだった。それが理由もわからぬままに引き延ばされ、また当たり前のように次の朝が来た。
木々の生い茂る公園の奥に、文学碑がひっそりとあった。磨かれた石の、中央が丸くくり抜かれている。その碑に向かって右に「島尾敏雄文学碑」と刻まれた石が、左には島尾敏雄に見出された作家・小川国夫の言葉が刻まれた石が置かれている。

島尾さん、あなたの声は 小川国夫
あなたはおだやかな人でした。微笑しながらユーモアをまじえ、相手の立場をわかろうと心づかいしてくれました。あまりにたんたんと話すので私は忘れそうでした、あなたがかつて過酷な大渦に投げこまれた人で、今もその大渦が身内で動いていることを。だから、あなたと会ったあとで、私はあなたのいくつかの小説を読みかえしてみたこともあります。ひきつけられ夢中になり、しばらく文字を追っておりますと、あなたの体験が私の体験になるかのようでした。内容は広々として自然でありながら、奇怪で胸をしめつけられるところもありました。しかし読み終わって残ったのはあの物静かな語り口でした。身をさいなむどんなことも平気と人に思わせるような、あなたの声でした。
死ぬはずだったのに生き残った自分の存在を何度も何度も疑いながら生きた
そして、文学碑の周囲を取り囲むように『出孤島記』『はまべのうた』など、島尾敏雄の小説から抜き出された文章が刻まれた小さな碑が配置され、そのなかには『出発は遂に訪れず』の一節を夫人・島尾ミホが書き写したその筆跡そのままに刻んだ石もあった。
文学碑のある場所のさらに奥、少し高台になった場所にあるのは墓石で、「島尾敏雄・ミホ・マヤ この地に眠る」と刻まれている。島尾敏雄の墓は福島の南相馬にあるそうだが、島尾敏雄、島尾ミホ夫妻、そして娘の島尾マヤの遺骨は、分骨され、ここにも納められている。
手を合わせたものの、どう思っていいかわからない。私は島尾敏雄の文章も、妻の島尾ミホの文章も好きなので「ありがとうございます」とだけ、頭の中で言った。
文学碑とお墓のあるあたりから、海辺に出て少し北へ歩くと、第十八震洋隊の基地の跡地がある。小山の山肌に掘られた壕に、震洋艇のレプリカが収められている。このレプリカは、島尾敏雄原作の『死の棘』という1990年公開の映画が加計呂麻島を舞台に撮影される際に制作され、そのまま今も残っているものらしい。

壕(ごう)の奥は暗くてよく見えないが、小さなボートだ。言葉は悪いが、決して重厚なものには見えない。それはレプリカだからではないようで、実戦用の震洋艇は、ベニヤ板で作られていたという。そんなものに爆薬だけ重量の限界までのせて、人ごと突っ込ませる作戦。本当に馬鹿馬鹿しくて、見ていて悲しくなってくる。
その壕を見て、うしろを振り返ったら海だ。山の裾にねじ込まれたような、奥まった入江の静かな水面。青い水面の向こうの山の緑は輝くようで、遠くから鳥の声が聴こえる。こんな場所で、命令さえ下ればいつでも死にに行く時間を生きて、また、そこから、急に解放される。

『出発は遂に訪れず』のなかで、8月15日、主人公である隊長は呼び出されて“防備隊”という場所に向かい、そこで終戦を告げられる。
正午の放送は雑音が多くてよくききとれずに終わった。雑音を縫って高く低く耳なれぬやわらかな声音がいっそう架空な気持ちに誘った。そのあと司令官があらためて日本が無条件降伏を受け入れたことを伝えた。
と、それだけで「はい、終わり」となるわけでもなく、特攻参謀に呼ばれ、こう告げられる。
「司令官の達しで分ったと思うが、今のところ単に戦闘を中止した状態ということだな。だからもし敵が不法に近接したときは突撃しなければならない場合の起こってくることも充分考えておかなくちゃいけない。君のところの特攻艇だが、御苦労だけれど即時待機の態勢を解いてもらっては困るんだ。こちらから指示するまで、今のままで待機していてほしい。ただし信管は抜いておいてほしいな」
そのあとに会った予備士官にはこう言われる。
「キサマは特攻艇をもっているからうらやましい」
返事ができないでいると、
「何かたくらんでいるといううわさだぞ。やるのか」
と重ねて言ったので私は返事をした。
「何もたくらんでなぞいないよ。オレのところは拳銃もないんだ。二百三十キログラムの炸薬だけだ。でも何もしないよ」
と、つまりは終戦の知らせを受けたうえで、このまま引き下がるわけにはいかないと、名誉の(?)特攻を暗に勧められすらするのだ。
しかし、その後、隊長は、隊員たちを冷静になだめる。隊員のなかには荒ぶる気持ちを隠さない者もいるし、任が解かれたことで急に隊長に対して反意を表す者もいる。死ねなかったあとの日々が、悪い夢のようにそれからも生ぬるく続いていく。
死ぬはずだったのに生き残った自分の存在を、何度も何度も疑いながら、島尾敏雄はその後も生きたと思う。69歳まで生きて、たくさんの小説を書いた。その人生はずっと、この場所で過ごした時間から完全に離れることはなかっただろうと思う。それがどれだけ重たく、苦しいものだったが、私は想像することもできない。ただ、鮮烈な呑之浦の海と山の景色を見て、きっと島の風景は昔とはだいぶ違うのだろうけど、この夢のように静かな美しさを、島尾敏雄が確かにこの場所で感じていたことが、私にはわかった。
* * *
スズキナオ『今日までやらずに生きてきた』は毎月第2木曜日公開。次回第16回は9月11日(木)17時配信予定
筆者について
1979年東京生まれ、大阪在住のフリーライター。WEBサイト『デイリーポータルZ』を中心に執筆中。著書に『深夜高速バスに100回ぐらい乗ってわかったこと』、『遅く起きた日曜日にいつもの自分じゃないほうを選ぶ』、『思い出せない思い出たちが僕らを家族にしてくれる』、『「それから」の大阪』など。パリッコとの共著に『ご自由にお持ちくださいを見つけるまで家に帰れない一日』、『椅子さえあればどこでも酒場 チェアリング入門』、『“よむ”お酒』、『酒の穴』などがある。