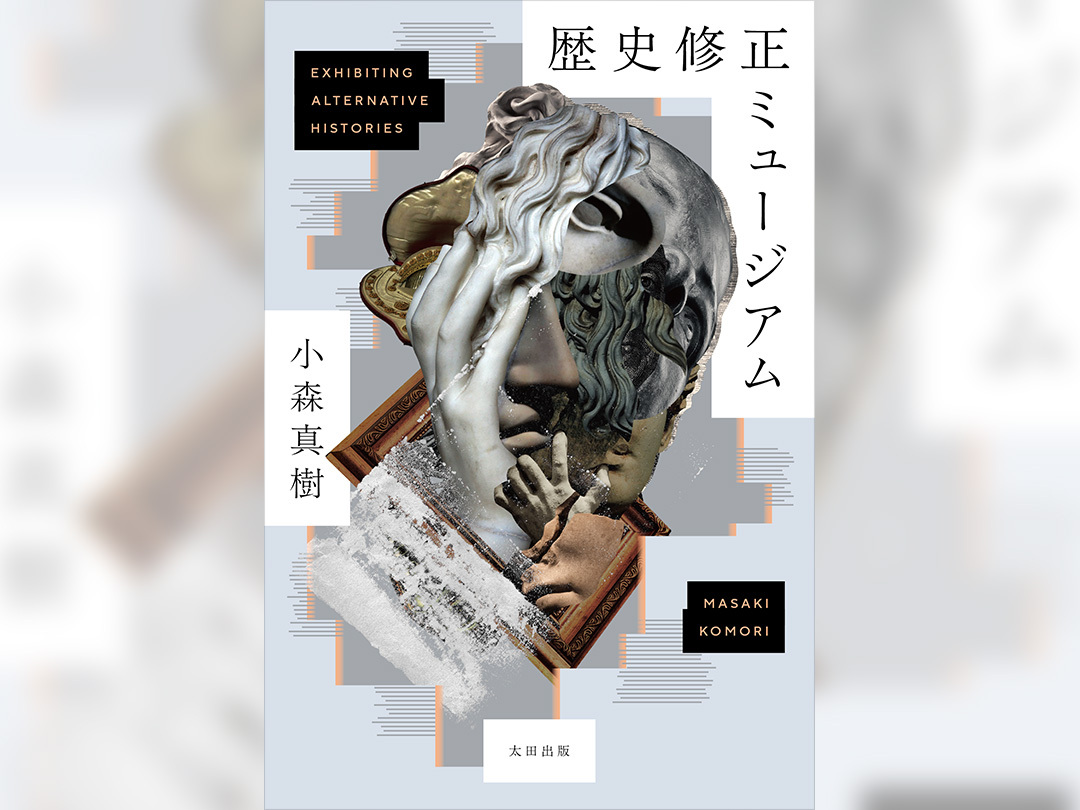戦争責任の軽視、植民地支配の正当化、マイノリティへの差別の否認──都合の悪い過去を次々と書き換え、「なかったこと」にしようとする歴史修正が世界中で行われる中で、私たちはどのように歴史に向かい、語り直せばよいのか。
ミュージアム研究者・小森真樹さんによるフィールドワークをもとにしたOHTABOOKSTANDの連載「ミュージアムで迷子になる」が、9月29日に『歴史修正ミュージアム』として刊行することが決まりました。刊行に先んじて本書から「はじめに」を試し読みとして掲載いたします(※刊行時には一部修正が入る可能性があります)。
はじめに
この本は330日間の旅をしながら書かれた。ミュージアム研究者である筆者が、1年間の研究休暇の期間に45都市のミュージアムで行ったフィールドワークの成果である。記録を見返すと、300以上の展示を訪れているようだから、その間ほとんどの時間をミュージアムで思いをめぐらせたことになる。
拠点としたのは、イギリス・ロンドンとアメリカ合衆国・フィラデルフィア。それぞれミュージアムや大学など研究機関を利用しつつフィールドワークの成果を文献調査で補完しながら、本書に収めた23本のエッセイをしたためた。
訪れたミュージアムは多種多様だ。ロンドン・ナショナル・ギャラリーのような巨大国立美術館からヴェネツィアなどの国際美術展、エンタメ系科学博物館や子供博物館、人体展示の医学博物館に元万博会場の人類学博物館、オクラホマの奥地にある先住民の部族博物館や、アムステルダムなど大都市の片隅にある小さな私設展示室から、トラックで巡回する移動博物館に、マンハッタンの裏路地に潜む無人美術館まで。各地で展示を観察しながら、もやもやと頭に浮かびはじめたのは、次のような問いである――今日のミュージアムが果たしているのは、単なる“文化の保存や展示”ではなく、むしろ“語られてこなかった歴史の修正”なのではないか?
忍び寄る“修正”―排外主義と陰謀論
旅の期間は、2024年5月から翌年の3月まで。まずはロンドンに居を構えて6か月ほど欧州の各都市を観察した。暮らしながら実感していたのは、穏やかで多文化的な日常の裏側で、ときおりひょいと顔をのぞかせる排外主義や陰謀論的な言説の気配だった。
6月のイギリス国政総選挙では、右派ポピュリスト政党のリフォームUK――その名は「イギリスの再生」という意味だ――が躍進した。反移民、反多文化、反気候政策といった文化戦線を減税と併せて訴えるポピュリズム戦略をとる彼らは、EU離脱を唱えるブレグジット党とナショナリズム極右政党の流れを汲む。21年には人びとが辟易していたコロナ禍のロックダウンに反対し、以後「生活費危機」と呼ばれるほどの急速な物価高騰に陥ったイギリスで、階級を超えて大衆の支持を得た。
彼らは表向きは穏健を装うが、その言動の陰には排外主義や陰謀論が見られる。党首ナイジェル・ファラージは、土地の相続税基準引き下げに抗議する農家たちのデモに現れ、「農地が移民のために接収されている」という根拠の薄い主張を繰り返した。これは「大いなる置き換え説」と呼ばれる陰謀論のバージョンだ。すなわち、進歩的な移民政策は他の人種や国籍の人びとが既得権を奪うための策略であるという、白人至上主義的な語りの常套句にほかならない。いわゆる「逆差別」という、歴史的・構造的な差別の文脈を無視した反動的なレトリックだが、ここではさらに巨大な陰謀という物語になっている。農場でトラクターの前に立ったファラージは、使い込んだレザージャケットとハンチング帽で大衆の装いを演出していた。
排外主義や陰謀論は最悪の形でも現れていた。8月に起こったサウスポートで3名の少女が刺殺される事件をきっかけに、イングランドと北アイルランドの各地で極右による反移民抗議と暴動が発生した。引き金となったのは、加害者がイスラム教徒の亡命希望者であるという虚偽情報だった。極右グループが広めたこのデマは、ムスリム嫌悪や人種差別、反移民感情を煽り、結果的に2000名以上の逮捕者を出す記録的なヘイト犯罪へと発展した。
ここで見えてくるのは、社会が多様性や包摂へと進もうとするたびに、それを“失われたもの”や“奪われたもの”として受け止める反発の欲望である。進歩的に“書き換え”られていく社会に対して、過去を取り戻そうとするもうひとつの“修正”の反動。
この衝動は、必ずしも事実や根拠に基づくとは限らない。むしろ、情動や被害感情に根ざしたものであり、自らに都合の良い物語を、“歴史”や“社会のあり方”そのものを書き換えようとする。
こうした修正は、排外主義や陰謀論と結びつきながら、静かに、しかし確実に社会の中に浸透している。しかもその過程は、可視化されにくい。
それこそが、この動きの脅威であり、同時に、本書が問題提起する“修正”という概念をめぐる対立の出発点でもある。
知性と権威を疑う欲望
進歩的に多様に変わっていく社会。そのように、“修正”された社会をさらに“書き換える”かのように、自らの物語を主張しはじめた人びとがいる。さらにそれは、従来の歴史叙述や文化的蓄積に疑義を差し挟むことで、主流の語りそのものに異議を申し立てる大きなうねりへと深化している。
11月初頭にアメリカのフィラデルフィアに越してからは、こうした空気をより鮮明に感じることとなった。アメリカ大統領選挙の直前である。アメリカ研究者でもある筆者にとって、大統領選とその後選ばれた新大統領で沸き立つアメリカ社会でフィールドワークを行うことは、今回の旅の大きな目的のひとつだった。選挙集会や就任式で熱狂するトランプ支持者たちの間に混じり、氷点下20度近い首都ワシントンやラストベルトの郊外でともに時間を過ごす中で、彼らの語る“真実”に耳を傾けた。飲み、食べ、楽しく談笑し、ときにあからさまな差別や罵倒の言葉を浴びながら彼らの信じる陰謀論や政治不信、“奪われている”という剥奪感や、“奪った”ものたちへの怒りを聞いた。
彼らの多くが信じるものに、ナショナリズムがある。それはグローバリズムに対する反動でもある。その一部は白人至上主義とも合流して「白人ナショナリズム」の形をとっている。そこにあるのは、ワシントンで政治を執るエリートがまとう権威に対する深い不信感であり、反動だ。この点において、彼らの“右傾化”とは、必ずしも現行の政治や国家体制を保守するということを意味しない。現体制や秩序を“乗っ取られたもの”として憎み、それゆえ“取り戻す”べき対象とする。愛するがゆえに“壊し作り替えたい”という逆説的な欲望に駆動されたねじれた反動である。就任式の日、大統領によって極右団体プラウドボーイズらが恩赦されたが、彼らが2021年の1月6日に議事堂襲撃を起こしたのはこうした歪んだ国家(ネーション)との距離感である。
彼らが信じる陰謀説に、既存の政府がエスタブリッシュメントが牛耳る「闇の政府(ディープステイト)」に操作されているというストーリーがある。Qアノンなどの運動で知られるそれらはときに、民主党政治家が幼児性愛カルトの一味で夜な夜な生き血をすする儀式を行なっていたり、トカゲ人間が権力者に化けていたりしているという荒唐無稽としか言いようのない領域にまで達しているが、こうした陰謀論者の心性を支えているのは、エリートが司る“知性”そして“専門性”への積極的な疑いと反動である。こうした反知性主義のアメリカ的伝統は長く、一部の特権階級による支配を拒絶することで欧州の王政から共和性へと移行する流れで生まれた、一般大衆による社会の支配――すなわち語源通りにデモクラシー――や、ポピュリズムの知的伝統へと通じている。
この“知性”や“権威”への不信や反感は、学問や歴史そのものに対する懐疑へと波及する。ひとたびその閾値を超えてしまえば、“主流の歴史”は操作されているという言説が前提となり、どのような反論も“体制側の弁明”としか聞こえなくなる。こうして、修正された歴史をさらに書き換えようとするまた別の修正主義が生まれていく。
これは単なる歴史観の違いではない。歴史に向き合う態度そのものの分断である。つまり、感情に訴える物語としての“修正=書き換え”が、知的誠実さに根ざした“修正=問い直し”と拮抗する時代に私たちが生きていることを意味している。
だが、そうした声に触れることができたのは、選挙という「政治の季節」ならではのことだった。選挙が終わると、その熱はあっという間に日常に溶け込んでいった。それは、なくなったわけではない。ただ、見えにくくなっただけなのだ。
報道で知る「アメリカ」では、毎日のようにトランプの発表が世間を仰天させ、目まぐるしい日々が続いていたが、少なくとも日常の暮らしは凪いでいた。政治的でリベラルな大都市フィラデルフィアでもそうだったし、ましてやオクラホマやカリフォルニアの郊外の小さな街では、そうした空気は違和感を覚えるほど透明だった。
文化戦争としての“歴史”
2025年1月、再選を果たしたトランプ大統領は就任初日から、矢継ぎ早に大統領令に署名した。なかでも注目を集めたのは、いわゆる「DEI政策」の全面的撤廃である。多様性(Diversity)、公正性(Equity)、包摂性(Inclusion)という考え方に基づいた人事・教育・展示施策は、連邦政府機関はもちろん、スミソニアン博物館や州立大学に至るまで、次々と否定・停止され、進歩的な学芸員らが解雇されていった。
こうした動きは8月現在まで続いており、書類未記載の移民、LGBTQなど標的と定めた政敵を攻撃するトランプ政権のニュースで世の中が翻弄されている。トランプの行う反動的修正とは、支持者への利益誘導なのである。
3月27日に出された「アメリカの歴史に真実と正常さを取り戻す大統領令」の冒頭には、こう書かれている。
過去10年間、アメリカ国民は、客観的な事実を真実ではなくイデオロギーに駆り立てられた歪んだ物語で置き換える、組織的で広範な歴史書き替えの運動を目の当たりにしてきた。この修正主義運動は、アメリカ合衆国の目覚ましい功績を貶めるため、その建国の原則と歴史で達成された画期的な出来事を否定的な光で照らし出そうとしている。この歴史修正の下で、我が国の自由、個人の権利、人間の幸福を推進してきた比類ない遺産は、本質的に人種差別的、性差別的、抑圧的、または根本的に欠陥のあるものとして再構築されてしまった。歴史を書き換える広範な努力は、団結や共有される過去についての深い理解を育むのではなく、むしろ社会の分断を深刻化し、国家の恥の意識を助長し、アメリカが成し遂げた進歩と、世界中の人々をいまもなお鼓舞し続ける理想を無視している。(強調は引用者による)
驚くべきことに、ホワイトハウスの正式見解によれば「本質的に人種差別的、性差別的、抑圧的」なのは、むしろDEI政策やスミソニアンの展示内容の側だとされている。この文言のロジックを用いた批判は、トランプ政権が進め、支持者たちが信じる“歴史修正”にそのまま当てはまるものだろう。
この対称性は、現代の「文化戦争(culture war)」の本質を浮き彫りにしている。それは単に言論の応酬ではなく、過去の語りをめぐる物語の主導権を争う闘争である。どの歴史を記録し、どの声に正統性を与えるのか。記憶の制度をめぐって、ふたつの“修正”が激しく対立している。
日本の右派運動の文脈では「歴史戦」という言葉で語られてきたように、歴史認識の問題はしばしば、意図的に構築された世界観に依拠する情報戦のかたちをとる。そこでは異なる“世界線”を創出することを目指し、「両論併記」や「どっちもどっち」といった相対主義がしばしば援用される。だが、こうした構造は、根拠や証拠がない言説にとってこそ有利に働くことになる。“対話”や“論証”そのものが前提とされない場においては、最も突拍子もない言説を主張しようと企てる者こそが優位に立つのである。また、大統領令には「国家の恥」と論難するロジックも見られるが、これは日本の右派論壇が好んで使う「自虐史観」言説に当たる。このように、トランプが採る言説は、右派の言論活動において典型的な言論戦術なのである。
トランプ政権を支持するのは、聖書にある物語を社会に実現しようとするキリスト教福音派、ワシントンを掌握するエリートに反する労働者層、技術万能主義を社会設計に援用するテクノリバタリアンや、白人純血思想を希求する白人ナショナリストなど、それぞれの主張は対立し矛盾もする属性も動機も異なる人びとだ。だが、彼らを貫いているのは、“修正された主流の物語”への深い懐疑と不信である。
とりわけQアノンに代表される陰謀論的運動は、史実やファクトといった知の共有地盤そのものを疑う。学校教育も科学もマス・メディアもソーシャル・メディアも、そしてミュージアムも、すべてが抽象的な“敵”による情報統制だという前提のもとでは、事実を問い直す行為そのものが、敵対的なプロパガンダとみなされる。
こうして現在、“修正された事実をさらに書き換える運動”と、“語られなかった過去を正当に修正しようとする営み”とが、歴史の場をめぐって真っ向から衝突しているのである。「オルタナティブ・ファクト(もうひとつの事実)」や「ポスト・トゥルース(真実以降)」といった言葉はその一断面だ。
歴史を「修正する」のは悪いこと?
こうした「文化戦争」のただ中で、そもそも“歴史を修正する”こと自体が、悪であるかのようにみなされてしまっている。
たしかに、「歴史修正主義(historical revisionism)」という言葉は、過去の加害を否定し、植民地主義や戦争責任を矮小化する行為と結びついて批判的に語られることが多い。ホロコースト否定論や従軍慰安婦問題への反発など、いわゆる「歴史否定論(denialism/negationism)」と同義に用いられることも少なくない。
けれども、修正という行為そのものが問題なのではない。本来、“歴史を修正する”という行為そのものは、学問の根幹にあるべき営みである。新たな史料や証言が発見され、視点が拡張されるたびに、歴史はより多層的なものとして描き直されていく。そのような修正こそが、真に誠実な歴史実践である。
同時にそれは、支配的な歴史記述に対して異議を申し立て、排除された声や視点を取り戻すための、極めて倫理的な知的・政治的実践でもありうる。むしろ、誠実で批判的な歴史研究とは、そのような修正によってこそ成り立っているはずなのだ。
だとすれば、いま求められているのは、事実や証拠に即しつつも、抑圧されてきた経験に光を当てるような、“誠実な修正”の技法ではないだろうか。歴史とは、過去にあったことの“ありのままの記録”ではなく、現在の視点からその過去をどのように“語り直すか”という営みである。その語り直しの手つきをめぐって、いま、真っ向から対立が起きているのだから。
ゆえに、わたしたちは“修正する”という行為についてもう一度捉えなおさなければならない。いわば、修正観の“修正”である。誰が、どの立場から、何のために修正するのか――その問いを避けることなく引き受けることが、いま切実に求められている。
知的抵抗の場としてのミュージアム
では、誠実で批判的な“修正”は、どこで、いかにして実践されうるのか。
本書が提案するのは、そのような歴史修正の可能性を、ミュージアムという知的実践の現場に見出すことである。
旅を通じて感じたのは、排外主義や陰謀論に支えられた根拠のない“不誠実な修正”が、情動や憎悪を燃料にして広がる一方で、まったく異なる方向を向いた“もうひとつの修正”が、ミュージアムを通じて静かに実践されているということである。それは事実に依拠し、異なる声をすくい上げ、複雑な社会の記憶を編み直そうとする、知的で開かれた修正の営みである。
ミュージアムは、歴史と記憶を視覚化する場である。そこでは、支配的な語りに対して異議を唱える多様な視点が、展示というかたちで提示される。ミュージアムとは単なる保存と展示の施設ではない。そこは、過去の出来事を「誰が」「どのように」語るのかを問い直す、知的抵抗の場=フォーラム(対話空間)なのだ。
歴史博物館、美術館、科学博物館や医学博物館、あるいは子供博物館や移動式展示など、ジャンルや規模にかかわらず、今日のミュージアムは、次のような力を備えつつあるように見える。
・歴史と具体的に向き合い、様々な立場や声を尊重する多声性
・見えにくい社会の緊張や葛藤を問題提起する批判的可視化性
・公共の意見や価値観、知見を具体的に提示して意見を交わす対話性
・多様な人びとが参加可能なオープンな空間である参与開放性
・社会の外部――観光客や移民、マイノリティ――へ開かれる越境性
こうした特性を持つミュージアムは、文化戦争の時代にあって、信頼できる“歴史の修正”のための装置でありつづけようとしている。そしてそれは、いままさに危機に瀕している、“真実をめぐる語り”の土台そのものを支える場なのである。
「歴史修正ミュージアム」へようこそ
情動と陰謀によって過去を書き換える根拠なき不誠実な修正とは異なり、誠実な歴史の修正とはいかなるものであり得るのか。
本書『歴史修正ミュージアム』は、こうした知的抵抗の現場としてのミュージアムをめぐる書物である。具体的な展示やその方法を通して、歴史を修正するための創造的なアプローチの可能性を探っていく。
ミュージアムの変容は、制度によって固定された語りの構造そのものを揺るがし、語る権利と暴力の構造を可視化しながら、歴史を語る力学を再編していく。過去の過ちを少しずつ更新し、語られてこなかった声を掘り起こし、これまで見えなかった構造を可視化すること――修正とは、むしろ正当な「批評的再構成」なのである。
本書が掲げる「歴史修正ミュージアム」とは、こうした「物語=歴史」的対抗の場を指す。国の歴史、人種と差別の構造、性の語られ方、階級の記憶、そして展示を支える制度そのもの。これらを対象に、歴史の修正はどのようにして可能なのかを、ミュージアムの現場から問い直していくこと。そして、「歴史修正」という言葉そのものを取り戻すことが本書の目指すところである。
第一章「国史の書き方を修正する」では、国家が自らを語る制度装置としての展示空間に注目する。ロンドンのナショナル・ギャラリーやフィラデルフィア美術館、ヴェネツィア・ビエンナーレといった制度的な展示が、“国民国家”の自己表象をいかに視覚化し、その正統性を構築してきたかを分析する。その上で、展示の再編成や自己批判的なキュレーションによって、“国家の物語”がどう修正されうるのかに目を向ける。
第二章「人種差別の歴史を修正する」では、帝国主義や植民地主義とミュージアムの結託を問う。地球規模で展開された帝国主義において、奴隷貿易と植民地主義という人種差別のシステムは経済的拡張主義を支える柱であった。そして、富と文化の収奪の装置として、ミュージアムはその構造を支えてきた。資本主義の揺籃となったかつての大英帝国に目を向け、コレクションの返還、展示物語の再編、そして人びとを巻き込む対話を通じてミュージアムの脱植民地化を進める各館の動向を追う。展示室の片隅にいた“見られる側”の人びとが、いまやキュレーションの共同制作者として登場する現場では、“歴史を語る主体”そのものが転換しつつある。
第三章「性の規範を修正する」は、ジェンダー、クィア、セクシュアリティといった、語られにくかった身体や欲望の記憶に、展示の言葉を与える実践に焦点を当てる。ブラック・クィア・アーカイブは、アートによって史料館を開くという方法で、不可視化されていた性へのアクセスを促す。アムステルダムで合法化された売春の博物館は、ツーリズムと性産業の倫理を問いかける。性という“語りにくいもの”を語る技術もまた、着実に修正されつつある。ヴァギナ博物館は、女性器というタブー視された身近な存在を、ユーモアに溢れた戦略で開くフェミニスト・ミュージアムの実践だ。
第四章「階級を修正する」では、労働者階級の視点から、ミュージアムの制度的偏りを考える。可視化されるべきはエリートの成功譚ではなく、社会の大部分を占める“普通の人びと”の生活史であるという前提が歴史認識を改変する。マンチェスターにある図書館と博物館は、この街を基礎づけた“一般人”による抵抗の歴史に光を当てている。ミュージアムのない地域や階級へ自ら赴く移動美術館の試みは、その制度的限界に挑戦するミュージアムの社会包摂の新たなステージだ。フィラデルフィア美術館をめぐるロッキー像論争は、文化資本と階級の関係を問い直す。展示の階級偏差、文化へのアクセスの不均衡、表象のヒエラルキーに対して、“誰の歴史が語られるべきか”が問われる。
第五章では「みんなで修正する」と題し、公共性そのものを問い直す活動――マンチェスター博物館と美術館や、ヤングⅤ&Aに見られる制度の刷新――を取り上げる。ここでは、展示を見るという受動的行為から、展示を「つくる」「使う」「開く」という能動的プロセスへと、ミュージアムが移行する過程が描かれている。
こうして見えてくるのは、「誰が語るか」だけでなく、「どのように語るか」、そして「どこで語るか」という、ミュージアムという場を根本から揺さぶる問いだ。展示の構造自体を再構成することで、語り直す権利は再配分される。それが、修正という営みのもつ批評的な可能性である。
「ミュージアムとはテンプル(神殿)かフォーラム(対話の広場)か?」――半世紀以上前にダンカン・キャメロンが提示した問いである。彼は言った。「文化の機会の平等を実現するために、美術館は改革されなくてはならない」[注1]。神殿のように崇める場から、参加し、語り合い、批判と対話の中で未来の歴史を共に編む場へ――修正とは、まさにそのための契機なのである。
いま、わたしたちは“修正”という営みをめぐって、ふたつの力学を目の前にしている。
ひとつは、変わりゆく社会や制度、それに基づく新たな歴史の語りに不満を抱える人びとが、情動や陰謀、不寛容な信念に駆られて、進歩や包摂の成果を“書き換える”動きだ。人権、多様性、公平性といった理念を敵視し、歴史の修正を武器に変えていく。“修正=攻撃”へと反転させる力である。
そしてもうひとつは、黙殺された声をすくい上げ、抑圧の構造を可視化し、語りの制度を問い直すための“誠実な修正”の力である。これは、批判と対話、連帯と再構成によって歴史を組み替えようとする力だ。ミュージアムは、この後者の営みの立役者となっている。ここでは、“語ること”へのアクセス自体が問い直される。語りによる“修正”は、暴力ではなく包摂的なケアである。
「歴史を修正する」とは、過去を好き勝手に書き換えることではない。誰の声も記録されないまま消えていくことのないよう、言論の構造を見渡しながら均衡をとることである。すなわち、語り直す権利を再分配することだ。具体的な空間にそれらを可視化し、誰しも参加可能な状態に置くこと。そうしたミュージアムの政治性と公共性に支えられた修正の営みこそが、本書の提案する「歴史修正ミュージアム」の核心である。
さあ、ミュージアムから「歴史を修正する」旅をはじめよう。
[注1] Duncan Cameron, “The Museum, a Temple or the Forum,” Curator: The Museum Journal, 14, 1971, p.23.
小森真樹『歴史修正ミュージアム』
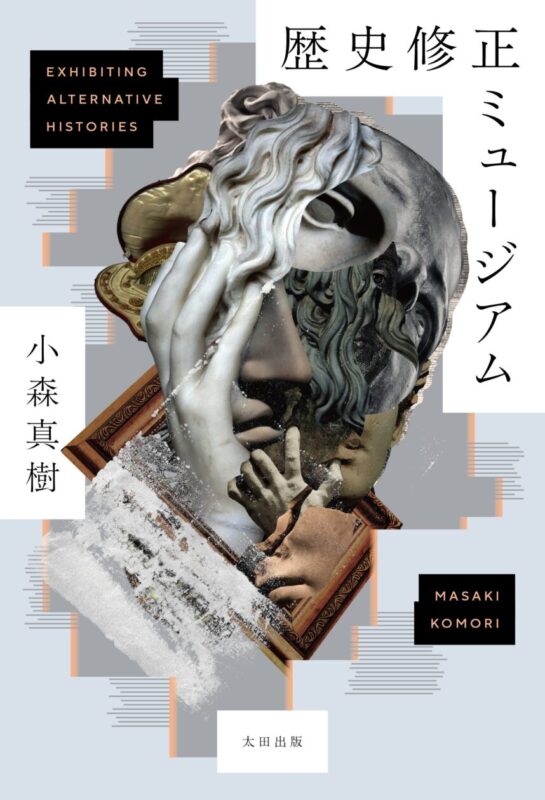
戦争責任の軽視、植民地支配の正当化、マイノリティへの差別の否認──。
いま、都合の悪い過去を次々と書き換える「歴史修正」が世界中で行われている。
だが、歴史を修正することは、本当に「悪」なのだろうか?
本書が注目するのは、支配的な歴史の語りに異議を唱え、語られなかった人びとの声を、展示というかたちで「修正」しようとする、欧米各地のミュージアムの実践である。
「顔」の展示から国史の語りを問い直すナショナル・ポートレート・ギャラリー
差別的表現に注釈を加え、歴史の読み直しを促すテート・ブリテン美術館
そして、フィラデルフィア美術館の前に「戻ってきた」ロッキー像が語る、階級の対立と融合
そこにあるのは、陰謀論でも過去の否定でもない。
蓄積された知見を反省的に継承しながら、現在へとつながる過去を語りなおす、誠実で批評的な「歴史修正」の試みだ。
ミュージアム研究者・小森真樹が、約1年をかけて訪ね歩いた欧米各地のミュージアムの実践から、
私たちの、歴史を語る権利と可能性を考える。
全国の書店、書籍通販サイトで予約受付中!
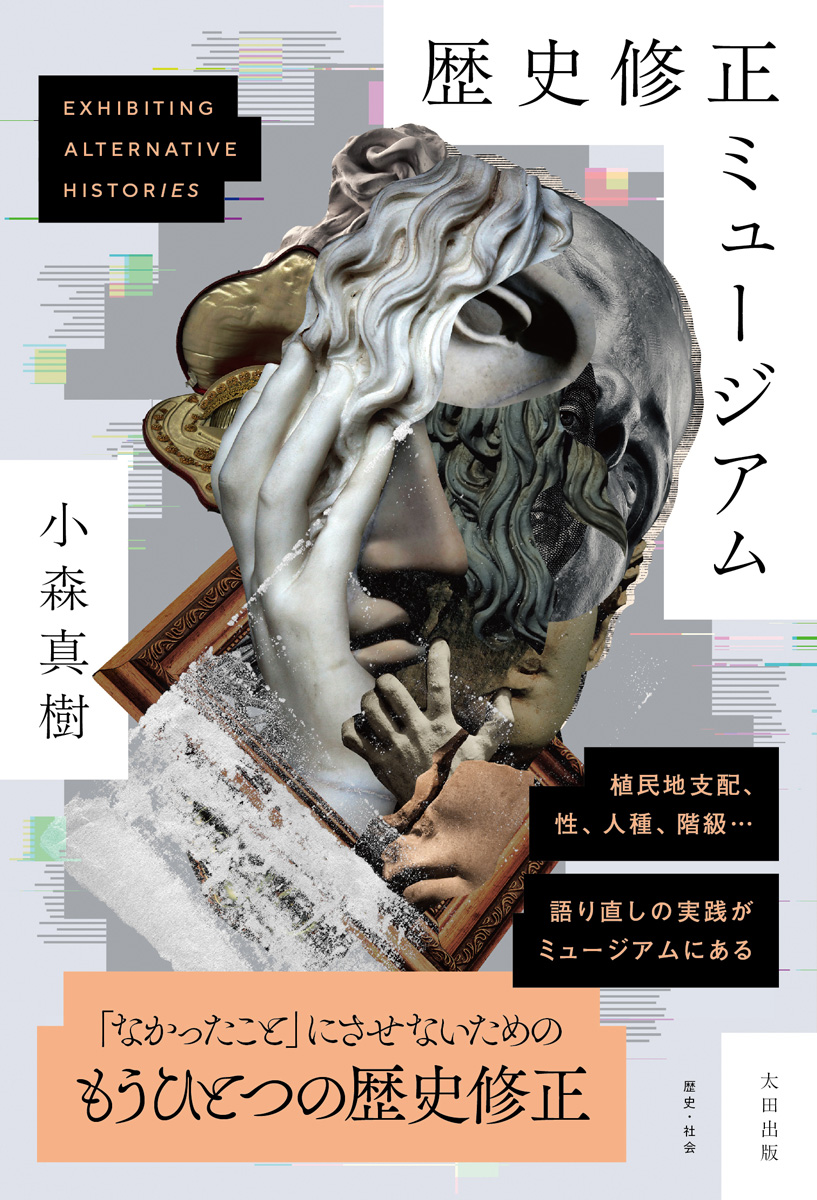
筆者について
こもり・まさき 1982年岡山生まれ。武蔵大学人文学部准教授、立教大学アメリカ研究所所員、ウェルカムコレクション(ロンドン)及びテンプル大学歴史学部(フィラデルフィア)客員研究員。専門はアメリカ文化研究、ミュージアム研究。美術・映画批評、雑誌・展覧会・オルタナティブスペースなどの企画にも携わる。著書に、『楽しい政治』(講談社、近刊)、「『パブリック』ミュージアムから歴史を裏返す、美術品をポチって戦争の記憶に参加する──藤井光〈日本の戦争画〉展にみる『再演』と『販売』」(artscape、2024)、「ミュージアムで『キャンセルカルチャー』は起こったのか?」(『人文学会雑誌』武蔵大学人文学部、2024)、「共時間とコモンズ」(『広告』博報堂、2023)、「美術館の近代を〈遊び〉で逆なでする」(『あいちトリエンナーレ2019 ラーニング記録集』)。企画に、『かじこ|旅する場所の108日の記録』(2010)、「美大じゃない大学で美術展をつくる vol.1|藤井光〈日本の戦争美術 1946〉展を再演する」(2024)、ウェブマガジン〈-oid〉(2022-)など。連載「包摂するミュージアム」(しんぶん赤旗)も併せてどうぞ。https://masakikomori.com