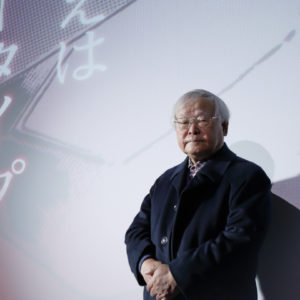2022年6月3日(金)に公開を控えた、映画『機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島』。本作の監督で漫画家・アニメーターの安彦良和がこれまでに手掛けてきた「全仕事」を、30時間を超えるロングインタビューで語り下ろした『安彦良和 マイ・バック・ページズ』(2020年11月発売)。ここでは、安彦良和作品のファン、そして最新作の公開を待つ方々にとっても永久保存版となる本書の中から、映画がもっと楽しみになるエピソードをご紹介します。第2回は、『機動戦士ガンダム』誕生に迫るエピソードの後編。新たな立場で臨んだアニメ制作の現場で、安彦良和が抱いた思いとは――。これを読んで、安彦良和の軌跡を共に辿りましょう。
自ら望んだ「アニメーションディレクター」という立場、画作りに込めた思い
安彦自身は、これまでの作品では、作画監督やキャラクターデザインという画作りの中心となりながら、絵コンテ、演出、脚本というポジションも経験済みであり、単なる作画するだけのアニメーターに比べると、クリエイティブに幅広く活躍できる状況にあった。
そこで、安彦が『機動戦士ガンダム』に関わるにあたって希望したのは、画作りの総合的な役割を担う役職である「アニメーションディレクター」だった。これは、作画する人間として、監督や演出の言うことをだけを聞いて原画を描いたり、チェックしたりするだけのポジションではなく、作画を統括する側として作品のクオリティ全体に口を挟めるという役割だった。

『ガンダム』では、最初に作画監督だけってことだったらやらないという意思表示をしたんだよね。これまで、演出だってやってきたし、『ヤマト』では文芸設定もやっていたので、作画の直し作業だけならもうやらないと、生意気にも公言していてね。でも、実際に画は描くわけだから、その仕事を何と呼ぶかというところで、「アニメーションディレクター」って呼ぼうと。
アニメーションディレクターというのは別に俺が初めて言ったわけじゃないと思うけど。劇場版『宇宙戦艦ヤマト』の立ち上げの時にテレビシリーズの演出をやっていた石黒昇さんの扱いが問題になって。劇場版は東映との仕事だし、新たに映画監督の舛田利雄さんも関わられる。その頃、もう松本零士さんと西崎義展の仲はかなり悪くなってきていて、西崎は「(東映の)勝間田具治もいるし石黒は松本派だから要らない」って言うわけですよ。それで俺が「石黒さんは作画のわかる人で、テレビシリーズが上手くいったのは石黒さんがいたおかげでもあるんだから絶対要ります」って言った。そうしたら西崎が「作画監督も決まっているし、石黒には何をさせるんだ?」と言うんだよね。それで思いつきで「アニメーションディレクター」でどうですかって言った。将棋で言う「飛車角」みたいな立場で、いろいろと口が出せたり、手が出せたりするという立場として「アニメーションディレクター」という立場にしてほしいと言ったんだよね。
だから、『ガンダム』でも、もうちょっと作品的に踏み込んで関わることができる「アニメーションディレクター」というポジションを希望した。
作画監督でも作品に対して意見を言えないわけじゃないんだけど、もっと発言権を保障されてほしいと思っていたから。もちろん、絵の直しや画作りを率先してやりつつ、そういう越権行為も許されたいという思いがあったからね。
アニメ業界では、監督のことをチーフディレクターって言ったりしているんだよね。アニメーションディレクターというのは、チーフディレクターの下のちょっとユーティリティープレイヤーというイメージという感じだったね。ただ、実際に制作が始まったらそれどころじゃなくて。シナリオとしてできてくる話はどれもすごく面白いから、これは俺の出る幕じゃないということで、結果的には絵の責任だけを負うことにしようということになっていった。
アニメーションディレクターとしては、ごく初期の頃にちょっとだけ口を出した。制作に入った直後に、富野氏が5話までのシノプシスのようなものを上げてきてね。あの人はテンポがとても早いというか、詰め込み主義なので、ガルマが死ぬところまでがわずか5話で描かれていて。それは、読んでみると中身がギュウギュウに入っていて、わけがわからなかったんだよね。だから、「これはちょっと詰め込みすぎなんじゃないか?」と言って、「尺はこの倍はほしい」と意見を言った。その頃の富野氏は結構話を聞いてくれたので、それが実際には10話分になる。覚えているのはそれくらいかな。あとはできてくるシナリオや設定に「いいね!」って言ってばかりいる煽り役で、「今度のコンテは面白い!」「こういうシーンは大好きだからもっとやりたい」という感じだったね。
こうして、『機動戦士ガンダム』は企画やスタッフの陣容なども固まり、制作に入っていくことになる。そして、時間がない中で、細部まで練り込まれていった『機動戦士ガンダム』の物語は、以下のように始まる。
人類が増えすぎた人口をスペースコロニーへと移住させ、宇宙が新たな生活の場となる宇宙移民を始めて半世紀以上がすぎた宇宙世紀0079年。地球から最も遠いスペースコロニー群であるサイド3は、地球連邦からの独立を宣言。地球連邦政府に対して宣戦布告し、後に“一年戦争”と呼ばれる独立戦争が勃発した。
ジオン公国軍は、“一年戦争”の緒戦に密かに開発を進めていた人型機動兵器である<モビルスーツ>を投入。戦力差に劣る地球連邦軍に勝利し、地球への侵攻を開始する。しかし、戦争は膠着状態へと突入してしまう。
そんな状況の中、地球連邦軍はジオン公国軍に対抗するためのモビルスーツの開発を進め、新造コロニーであるサイド7で最終テストを行っていた。そうした地球連邦軍の動きを追っていたシャア・アズナブル少佐は、地球連邦軍の新造艦がサイド7へ入港するのを確認。部下たちをコロニー内に潜入させる。そこで戦闘に巻き込まれた少年、アムロ・レイは新型モビルスーツ<ガンダム>のマニュアルを偶然手にし、ジオン公国軍のザクを撃退。これをきっかけに、強襲揚陸艦ホワイトベースに乗り込んだアムロたちは、ジオン公国軍の攻撃を退けながら、戦火の中、地球へと向かうことになる。
物語は、見せ場となるモビルスーツの戦闘シーン以上に、戦争の中に置かれたさまざまな人々の出会いを通し、アムロとその仲間たちの成長や葛藤が描かれていくことになる。
こうした、これまでの子供向けのロボットアニメとは一線を画する、ロボットを兵器として扱う作品として作業が進む中で、安彦はアニメーションディレクターと兼任する形で、劇中に登場するキャラクターたちのデザインも担当。人類同士の戦争を背景に描く物語における、キャラクターの外見的な特徴で重要な「衣装」に関しても、これまでとは違う方向を模索することになる。
それまでの作品で描かれてきたような、ピッタリフィットのボディスーツを着て、未来的でツヤツヤしたような印象ではないなとは思ったんだよね。よくわからないアンテナなんかがついたヒーローコスチュームはやめようという意識はあった。だから、軍服も詰め襟にして実際に存在するような雰囲気にしようとはしている。そう言いながらも、ヘルメットに角とかつけているけどね。あれもやはり妥協のひとつではあったんだよね。
ただ、当時のそれまでの作品が築き上げてきた「流れ」の痕跡は残さないといけないので、マントをつけたりして「一応ついています」っていうね。後から見ると、「なんでこんなところに角やトゲがあるんだろう」って思ったりもするんだけど、でも、それは今となっては仕方がない。シャアだけなぜ尖っているのかと言えば、「こいつは敵側のヒーローなので、何か尖ったものがなくちゃいけない」という感じでしかないんだけど、そうしたデザインの仕方も、やはり過渡期だからこそだね。
一方で、安彦はアニメーションディレクターという立場から、劇中に登場するロボット兵器=モビルスーツのデザインにも関わる。デザインの方向性を模索する中で、『宇宙の戦士』のパワードスーツのデザインをモチーフに、ガンキャノンのラフデザインを描き、それがデザインの方向性を変える大きな指針となったのは有名な話だ。そして、デザインを詰めていく中で、いくつかの提案を行っている。
最初に提案したパワードスーツ的なデザインだけではダメだというので、大河原さんが、決定稿に近いああいう形にまとめてくれた。
それから、これもよく言っていることなんだけど、ガンダムに関しては色でもちょっと抵抗したんだよね。当時の日本サンライズには悪しき伝統みたいなものができていて、「色はこんな感じでしょ?」って頼んでもいないのに、企画室の方で勝手に作っちゃう。「今までにないものを作る」って言っているのに、何をやっているんだという感じだったね。
その色味は、『マジンガーZ』の延長というか、『ザンボット3』や『ダイターン3』と同じような白、紺、赤ですよ。まさに「例によって」という感じで。「それじゃない」って言ったら、「こういう色味じゃないと当たらない」とも言われた。だから冗談じゃないと思ったね。
そうした言い合いをした後、「白と赤と青を使うのは決まりだから」と言われたので、たまたま家にセル画用の絵の具を1セットもらっていたから、それを使って自分で色を塗ってみた。青色は、紺じゃない青で、むしろスカイブルーに近い色を使って面積を小さくして、圧倒的に白の比率を大きく取ってみたんだよね。そこに、黄色と赤を申し訳程度に入れるような感じにして、「言われた色はちゃんと入っているぞ」と仕上げたら、富野氏が「見事だね」って認めてくれて。それで決まり。ちなみに、ガンダムのデザイン面に関しては、最初は顔に「口」があって。声を出したりしない設定なのに口があるのはおかしいから、マスクをつけてみてはどうかと提案して。マスクのデザインだけは俺の仕事ですよ。あとは全部大河原さんが作り上げてくれた。
モビルスーツ、衣装のデザインなどは、新たなチャレンジに相応しい方向性が模索され、それまでの作品に比べると「地に足のついた」と表現するに相応しい方向へと進んでいった。そうした、まさに「新しい」と感じる画作りに関して、安彦は作業をしながらどのような感想を持っていたのだろうか?
ヒーローが出てきて戦うという話ではないというのは、富野氏のプランがそうだったんだよね。人物設定にも徹底していたし。主人公は美少年ではないし、国籍も日本人じゃないとか、当時としてはタブーだったことをいろいろやっている。でも、姑息だったのは制作局から「主人公は日本人じゃないの?」って突っ込まれたら逃げられるように、ちゃんと漢字をあてられるようにして、「日系二世です」と言えるようにしていた。それだけ、当時は外圧も強かったということだけど。
あの頃は、子供番組ならば主人公を日本人にした方が安全というか、それしか考えられなかったんじゃないかな? カタカナ名の主人公なんて、とにかくあり得ないというのが風潮だった。でも、特にテレビ局側との押し問答もなくて済んで。そういう意味では、思ったよりもハードルは低かったね。色の問題もそうだけど、作り手側の取り越し苦労や考えすぎ、頭が古いまま止まっていたということもあるんじゃないかと。「テレビ局がうるさい」とか言いながら、実際は自分たちの内部規制や先入観の方が強かったということだね。
* * *
本書『安彦良和 マイ・バック・ページズ』では、アニメ『機動戦士ガンダム』のほか、『クラッシャージョウ』『巨神ゴーグ』『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』、漫画『アリオン』『虹色のトロツキー』『天の血脈』『乾と巽-ザバイカル戦記-』などの作品についてのインタビューや、単行本発収録となる漫画『南蛮西遊記序章』(オールカラー24ページ)も収録。安彦良和の「マイ・バック・ページズ=歩んできた長き道のり」、その軌跡のすべてが詰まった一冊。書籍・電子書籍ともに好評発売中です。
また、ゲーム&カルチャー誌『CONTINUE』では、『安彦良和 マイ・バック・ページズ』が特別編として復活! Vol.76から全3回の予定で、待望の監督最新作となる映画『機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島』の公開を控える安彦良和氏に再びロングインタビューを敢行。こちらも併せてチェックしてみてください。
筆者について
1947年生まれ。北海道出身。1970年からアニメーターとして活躍。『宇宙戦艦ヤマト』(74年)、『勇者ライディーン』(76年)、『無敵超人ザンボット3』(77年)などに関わる。『機動戦士ガンダム』(79年)では、アニメーションディレクターとキャラクターデザインを担当し、画作りの中心として活躍。劇場用アニメ『クラッシャージョウ』(83年)で監督デビューする。その後89年から専業漫画家として活動を開始し、『ナムジ』『神武』などの日本の古代史や神話をベースにした作品から、『虹色のトロツキー』『王道の狗』など日本の近代史をもとにしたものなど、歴史を題材にした作品を多く手掛けている。2001年から『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』の連載をスタート。10年にわたる連載終了後、アニメ化。現在『月刊アフタヌーン』にて『乾と巽-ザバイカル戦記-』を連載中。2022年6月には待望の監督作『機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島』が公開された。
1971年生まれ。茨城県出身。アニメ、映画、特撮、ホビー、ミリタリーなどのジャンルで活動中のフリーライター・編集者。アニメ作品のパッケージ用ブックレット、映画パンフレット、ムック本などの執筆や編集・構成。雑誌などで、映画レビューや映画解説、模型解説、インタビュー記事などを手掛けている。著書に『マスターグレード ガンプラのイズム』(太田出版)、『機動戦士ガンダムの演説から学ぶ人心掌握術』(集英社・共著)、『不肖・秋山優花里の戦車映画講座』(廣済堂出版・共著)などがある。