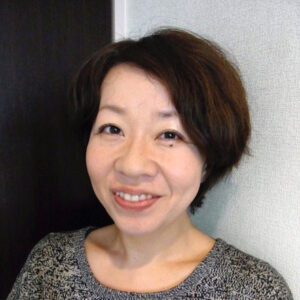日本の女性と家族、仕事と恋愛、幸せのかたちを描いてきたNHK「連続テレビ小説」(通称「朝ドラ」)。1961年度の誕生からこれまで、お茶の間の朝を彩ってきた数々の作品が、愛され、語られ、続いてきたのには理由がある。はたして「朝ドラっぽい」とは何なのか?
『大切なことはみんな朝ドラが教えてくれた』(太田出版刊)では、エンタメライターで「朝ドラコラム」の著者・田幸和歌子が、制作者のインタビューも踏まえて朝ドラの魅力に迫っています。
ここでは、その一部を特別に紹介していきます。(第4回目/全6回)
朝ドラといえば、会社や学校に行く前、家事の前などに、家族が揃って朝ごはんを食べながら、「家族」を観るもの。朝の習慣であり、家族で過ごした時間の「共通の記憶」でもある。
「今日は大阪で最後のカメラテストがあると聞いてたので、(ヒロイン決定を聞いて)驚いてパニック状態になりました。お父さんやお母さんはもちろん、おばあちゃんたちに知らせたい!」
これは、朝ドラオーディション「三度目の正直」にして、ヒロインの座をつかんだ2012年10月からの作品『純と愛』主演女優・夏菜のコメント。朝ドラでは、ヒロイン決定時にこうした「家族」の話をする人が実に多い。
そんな「朝ドラの家族」って、いったいどんなものだろうか。
朝ドラでは、『梅ちゃん先生』(2012年)などに見るように、「ちゃぶ台」を囲んで家族みんなが食事をするシーンが定番となっている。時代によって様々に変化しているものの、朝ドラの原型は「ホームドラマ」と言われる。
研究ノート「テレビ文化と女性―初期のNHK連続テレビ小説の形式転換と女性視者との関係」(黄馨儀/Gender and sexuality:journal of Center for Gender Studies, ICU 2010年3月31日収録)において、こんな指摘を見ることができる。
ホームドラマ(home drama)は、日本の独特な放送形態と見られているが、その誕生については主に2つの要因が挙げられる。1つ目の要因は、アメリカの番組の影響である。1950年代、テレビの製作技術や番組のノウハウは未熟であった。テレビの普及に追い付かないほど番組の需要があり、一時はアメリカから番組を大量に輸入した。このように日本のテレビの初期放送史から考察すると、アメリカの「シチュエーション・コメディ」と「ソープオペラ」がホームドラマの原型として捉えられる。
「テレビ文化と女性―初期のNHK連続テレビ小説の形式転換と女性視者との関係」(黄馨儀/Gender and sexuality:journal of Center for Gender Studies, ICU 2010年3月31日収録)
2つ目の要因は、映画のジャンルの中での<ホームドラマ>に遡ることができる。
また、同論文で指摘されているのは、映像メディアのジャンルにおいて「家族もの」を最初に扱ったのは映画であり、母性愛をテーマにする「母もの」の日本映画は1920年代のアメリカから輸入されたものがきっかけとなって製作されたということ。「家族もの」は母もの・父ものからホームドラマへ、という流れがあり、女性の観客を想定して形成されたということ。家族関係の愛をテーマとした物語で、アメリカから輸入されたもののなかで、「父もの」はあまり日本では定着しなかったということなどが挙げられる。
「男性不在」のなか、苦しい時代をたくましく生きる女性たち
思えば、朝ドラにおいても、『おはなはん』(1966年)に始まる「女性の一代記もの」では、父や夫と戦争で死別する「男性不在」の状況の中、苦しい時代を女性がたくましく生きる作品が多く見られる。
そして、80年代には『澪つくし』(1985年)に見るように、「家父長制度」に縛られる女性が多く描かれ、そこからの「父親、夫の不在」を経て成長・自立していく女性主人公が登場している。
『純ちゃんの応援歌』(1988年)に至っては、和歌山に疎開し、父の復員を待つヒロイン・純子(山口智子)が、孤児の少年を連れて満州から帰国した父と再会し、父が病気によって急死した後に、少年を養子に迎え入れる。さらに、兵庫に移り、甲子園球場近くで旅館を開いて、「球児の母」と呼ばれるに至るまでを描いていた。
『主婦と生活』(1988年10月号)の「テレビそこが知りたい」には、こんな記述がある。
ヒロイン・小野純子は戦後の名もない庶民の一人。“立身出世”をするわけではありませんが、見る側にとってはそれだけ身近な存在として感じられます。家族意識が薄らぐ現代、貧しくとも固い絆で結ばれた温かな家族愛を多くの人に訴えようというのが今シリーズ最大の狙いです。
『主婦と生活』(1988年10月号)
戦後の苦境を乗り越えていく中で、女性は「ひとりの女性」としてではなく、「母」として、子どもとの関係性の中で献身的な愛を注ぐことで輝きを放っていたようだ。
『青春家族』から始まる「家族崩壊」と再生の物語
だが、そんな「母」としての生き方の価値観を大きく変え、家族像も大きく変えた作品が、『青春家族』(1989年)だ。
『週刊文春』(1989年8月10日号)の「THIS WEEK’S VIEWER テレビ評 見もの聞きもの」では、映画評論家・白井佳夫が次のような記述をしている。
今までのこの時間枠のテレビ小説ドラマは、どれもたいてい、第二次大戦頃から現在までの日本人一家族の、苦闘の歴史のなかでの一体感の保持を讃美して描いたようなものが多かった。要するに、レトロなヒューマニズムドラマが、とても多かったのである。(中略)
『週刊文春』(1989年8月10日号)
ところが、井沢満のオリジナル・シナリオによる「青春家族」は、リッチで平和な、飽食時代の現代日本の、典型的な中流の一家族のドラマを、今日ただ今から近未来に向かって、ホームドラマとして爽やかに、いわば現在進行形で描いていこうとしているのが、とてもいい。それも、家族一人一人がそれぞれの仕事や生活をもっていて、別れ別れになって生きていきつつも、なおかつ新しい形での一体感を、どう作っていこうとしているのか、を描くドラマとして。
また、『調査情報』(1989年8月号)では、「TVドラマ時評」において放送評論家・松尾羊一が次のような記述をしている。
たぶん、これは新しいタイプの家族解体、家庭崩壊の劇なのかもしれない。それは従来もしばしばドラマの主題となり、その悲劇性を訴えた作品は多く存在した。しかし、ここでは悲劇としてとらえることをしない。「家族」とは人間の成長と同じで、ライフ・ステージに応じて貌かたちを変える。阿川家では、家族の枠組からはずれた「場」を求めはじめている。
『調査情報』(1989年8月号)
『青春家族』の家族のコワれ方は、衝撃的だった。結婚式という土壇場で娘がやめるところから幕開きとなり、親の反対を押し切って学生結婚した両親(いしだあゆみ、橋爪功)は「結婚してすぐ娘が生まれ」「水入らずの生活が3カ月もなかった」という設定。「無償の愛」といったものよりも、我が子のこともひとりの人間として冷静に見ているところがあったが、息子(稲垣吾郎)が暴力沙汰で警察につかまったことを機に、「父親」の必要性を感じるというシーンも印象深い。
『青春家族』によって「家族の崩壊」が描かれた後には、現在に至るまで様々な家族の崩壊と再生物語が登場した。「他人から家族になっていくケース」や「崩壊から始まり、再生へ向かって努力していく」姿を描くパターンも多数ある。
たとえば、『京、ふたり』(1990年)では、幼い頃離婚して自立の道を歩んでいた母(山本陽子)と、老舗漬物屋の跡取り娘(畠田理恵)が18年ぶりに再会し、家族の絆を築いていく。
『おんなは度胸』(1992年)の場合は、温泉ブームに乗り遅れた旅館に後妻として嫁いだ女性(泉ピン子)が、義理の娘(桜井幸子)とともに旅館を支えようと奮闘し、「家族」になっていく。
『オードリー』(2000年)の場合は、「産みの親」と「育ての親」というふたりの母とアメリカ育ちの父が登場し、複雑な家族のあり方の中でヒロインが翻弄されつつも、映画作りという夢にむかって生きていく。
『こころ』(2003年)では、ヒロイン・こころ(中越典子)がふたりの子持ちの医師(仲村トオル)と結婚するものの、夫が不慮の遭難事故で命を落としてしまったことから、血のつながらないふたりの子の「母」として暮らし、やがて花火職人(玉木宏)に惹かれていく。血のつながらない連れ子を間にはさんでの「家族」の成立が大きなテーマとなっていた。
『ファイト』(2005年)では、一家離散・不登校からの家族の再生が描かれ、また、『風のハルカ』(2005年)では、父子家庭で育ったヒロイン(村川絵梨)が、離婚して離れて暮らす母の住む街にいくことから、バラバラだった家族に「絆」が生まれていくのだった。
また、『芋たこなんきん』でヒロイン(藤山直美)が結婚した相手・開業医の「かもかのオッチャン」(國村隼)はバツイチで、5人の子持ち。しかも、両親や兄弟とも同居する10人の大所帯で、オマケに、毎日のように近所の患者たちが押し寄せるという、てんやわんやの「大家族」ぶりが描かれていた。
そして、『瞳』(2008年)では「里親」をしている祖父のもとに孫・瞳(榮倉奈々)がとびこむことで、不仲だった祖父と母、離婚した父などが結びついて「家族」になっていく。
『だんだん』(2008年)では、互いの存在を知らずに離ればなれで育った双子姉妹(三倉茉奈・佳奈)が偶然巡り合ってしまったことから、物語が始まる。
『つばさ』(2009年)では、自由奔放で家を出ていってしまった母のかわりに、主婦業をしてきた娘・つばさ(多部未華子)が、家にふらりと舞い戻った母がいがみ合いつつも、壊れた家族の絆を取り戻そうと努力していく。
また、『てっぱん』(2010年)では、自分が養子であることを知ってしまったヒロイン(瀧本美織)と、育ての父母と、家を飛び出して子どもを産み、亡くなってしまった娘(ヒロインの実母)への思いを抱えている祖母(富司純子)とが、新しい家族のかたちを築いていくのだった。

* * *
※この続きは、本書『大切なことはみんな朝ドラが教えてくれた』(田幸和歌子・著)にてお読みいただけます。
※本書では、他にも最高視聴率62.9%の”お化け番組”『おしん』の大ブームや、『ゲゲゲの女房』で挑んだ大変革、朝ドラの「職業」の変遷、新人女優の”登竜門”ヒロインオーディションについてなどを朝ドラの人気を紐解くエピソードを多数収録しています。『大切なことはみんな朝ドラが教えてくれた』(田幸和歌子・著)は、各書店・電子書籍配信先にて大好評発売中です!
筆者について
たこう・わかこ 1973年長野県生まれ。出版社、広告制作会社を経て、フリーランスのライターに。『日経XWoman ARIA』『通販生活web』でのテレビコラム連載のほか、web媒体などでのドラマコラム・レビュー執筆や、週刊誌・月刊誌での著名人インタビュー多数。エンタメ分野のYahoo!ニュース個人オーサー、公式コメンテーター。
かり・すまこ。福岡県出身。1994年に『SWAYIN' IN THE AIR』(「蘭丸」/太田出版)にてデビュー。BLから青年誌、女性誌まで幅広く活躍し、読者の熱い支持を集め続けている。2006年に『ファミリーレストラン』(太田出版)が映像化。2020年、『あした死ぬには、』が第23回文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞を受賞。『幾百星霜』(太田出版)、『どいつもこいつも』(白泉社)、『感覚・ソーダファウンテン』(講談社)、『うそつきあくま』(祥伝社)、『ロジックツリー』(新書館)など、著書多数。