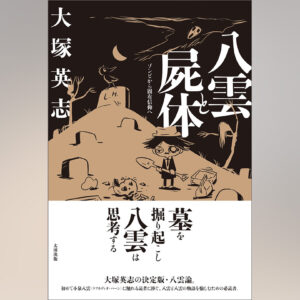『先祖の話』~検証
まず『先祖の話』の「自序」から見ていく。同書は既に東京への空襲下と重なり合う形で書かれた。しかし、「自序」だけは戦後の筆だ。柳田は戦時下を「このたびの超非常時局」とまず形容詞し、こう続ける。
かつては常人が口にすることをさえ畏れていた死後の世界、霊魂はあるかないかの疑問、さては生者のこれに対する心の奥の感じと考え方等々、おおよそ国民の意思と愛情とを、縦に百代にわたって繋ぎ合せていた糸筋のようなものが、突如としてすべて人生の表層に顕われ来たったのを、じっと見守っていた人もこの読者の間には多いのである。私はそれがこの書に対する関心の端緒となることを、心ひそかに期待している。故人はかくのごとく先祖というものを解していた。またかくのごとく家の未来というものを思念していたということは、伏して今後もまた引き続いて、そういう物の見方をなさいという、勧告でないことは言うにも及ぶまい。
(柳田國男『先祖の話』筑摩書房、1941)
柳田はここで二つのことを言っている。
一つは「超非常時局」つまり戦争による否応のない死者への関心が、これまで「死後の世界」「霊魂の有無」をめぐる「国民」に面々と連なってきた系譜を「人生観の表層」に浮上させたのだということ。つまり戦争による「古層」の復興である。
そして二つめは「固有信仰」が「先祖というもの」の解し方であるとする点。つまり死生観が祖霊と結びつくという主張である。
それを柳田は「家の未来」への「思念」とするが、しかし「超非常時局」とそれを終えた現在では実は「未来」の意味が大きく変わってくるはずだ。
そもそも『先祖の話』本文では、「未来」は生まれ変わった来世である。
『先祖の話』は最終節で唐突に「先祖」を祀る者が戦死することで祭祀不在の霊が出現することへの危惧を語り、直系でない「先祖」の継承と「国難に身を捧げた」、つまり軍人の死者を「初祖とした家」の創出を期待し、それがこの国の「固有の死生観」を復興させ得るとする。それが同書の主張のように捉えられるが、実際にはこの本の結論はその前にないか。新たな祖先の祀り方はいわば「提言」であるから結論はそれ以前にあるはずだ。
それはその直前の「七生報国」と題した節である。
そこでは、その死生観、つまり「固有信仰」はでこう示される。
人生は時あって四苦八苦のちまたであるけれども、それを畏れて我々が皆他の世界に往ってしまっては、次の明朗なる社会を期するの途はないのである。我々がこれを乗り越えていつまでも、生まれ直して来ようと念ずるのは正しいと思う。しかも先祖代々くりかえして、同じ一つの国に奉仕し得られるものと、信ずることのできたというのは、特に我々にとっては幸福なことであった。
(同)
つまり人々が繰り返し生まれ代わり生を受けて、幾度も「一つの国に奉仕」することを信じるのが「七生報国」であるとする。「次の明瞭なる社会を期する」という言い方に「戦後」が暗示されていると読むことも可能だが、それは「教育勅語」も良いことが書いてあると、歴史の文脈を無視して評価する愚と重なりはしないか。
やはり『先祖の話』は「七生報国」の肯定という世界線に接続する「固有信仰」を政治的につくり出していく「伝統の創造」なのだ、と厳しく思うべきでないか。
今少し同書での「固有信仰論」の詳細は見ていこう。
『先祖の話』における「固有信仰」は以下のように要約される。
第一には死してもこの国の中に、霊は留まって遠くへは行かぬと思ったこと、第二には顕幽二界の交通が繁く、単に春秋の定期の祭だけでなしに、いずれか一方のみの心ざしによって、招き招かるることがさまで困難でないように思っていたこと、第三には生人の今わの時の念願が、死後には必ず達成するものと思っていたことで、これによって子孫のためにいろいろの計画を立てたのみか、さらにふたたび三たび生まれ代って、同じ事業を続けられるもののごとく、思った者の多かったというのが第四である。
(同)
「昔話」論における物語要素的意味合いから、一気に、先祖をめぐる魂のエコ・サイクル仮説に固有信仰論は変質するのだ。そこでは死者は天国なり地獄なりに行くのではなく「この国」、より限定的には「ムラ」に留まり、そして定期的に先祖として帰還するだけではなく、生まれ変わって生を受け同じ「国」なり共同体に奉仕するとされる。この祖霊の居場所はより具体的に鎮守の森や山の高所にイメージされ、かつ、ムラを定期的に訪れるというニュアンスが祖霊を山の神と結びつける議論によってその山と里の復住という属性が付与されたものだ。
山ノ神ト田ノ神トハ同ジ神ナリト云ウ信仰ハ、弘ク全国ニ分布スル所ノモノナルガ、伊賀ナドニテハ秋ノ収穫ガ終リテ後、田ノ神山ニ入リテ山ノ神ト為り、正月七日ノ日ヨリ山神ハ再ビ里ニ降リテ田ノ神トナルト云ウ。
(柳田國男『山島民譚集』1914)
このように田の神と山の神の往還論は『山島民譚集』(1914)にも見られたものだ。こういう山神の属性を祖霊に実装し「固有信仰論」が成立する。だが「山の神」を祖霊と完全に同一視できるかには疑念もあるし、研究者による批判もある。
しかし、この「生まれ変わり」「山と里の住復」に加えて柳田の固有信仰論で重要なのは以下の属性である。
つまりは一定の年月を過ぎると、祖霊は個性を棄てて融合して一体になるものと認められていたのである。
(柳田國男『先祖の話』筑摩書房、1941)
この「祖霊」が「個性」を捨てた後の姿であるというイメージは仏教における「弔い上げ」で死者の個別の供養から「先祖」としてまとめて供養されることの言い換えのように思えるが、果たしてそうか。この魂における個の消滅論こそが明治期の外国人による日本文化論の共通の基調であることは注意が必要だ。
霊魂に関する西洋の旧思想と、東洋の思想との大きな相違は、つまり、仏教には、われわれが伝統的に考えているような霊魂というもの──ひとりでぼーっと煙のように出てくる、あのふわりふわりした人間のたましい、つまり幽霊というものがないことである。東洋の「我(エゴ―)」というやつは、これは個ではないのだ。また、神霊派の霊魂のような、数のきまった複合体でもないのだ。仏教でいう「我(エゴ―)」とは、じつに、想像もできないような複雑怪奇な統計と合成による数、──前世に生きていた百千万億の人たちについて、仏教がはじめて考えだした思想を凝成した、無量百千万億載阿僧祇という数なのである。
(小泉八雲「前世の概念」)
八雲が明治期に来日した当初の彼の日本文化論の一説である。
ここで八雲は東洋の「我」は前世の人々の魂が綿々と続く一種の合成物だとだとする。それを最終的には「遺伝」で説明するのだが、この議論の前提にあるのが以下の言説である。
もしわれわれが地球の温帯の地域に、その南端と北端が一定の等温線で区切られる一連の地帯を取り上げてみると、その温帯幅の半分ほどの比較的狭い帯状の地域に、過去および現在における名だたる国がほとんど入ってしまう。この地帯をよく調べ、その中の各々異なる地域を一つずつ比較して行くと、驚くべき事実が分かるであろう。この地帯に住んでいる民族は西に行くにつれて次第に個性的になって行く。(中略)同様に、自己を知覚する度合は、太陽の沈む方角を追って行けば行くほど、強まり、夜明けの方角に進めば進むほど、次第に弱くなって行く。アメリカ・ヨーロッパ・中近東・インド・日本の各民族はこの順番に従って次第に没個性的になっている。われわれはこの物指しの一番手前の端に立っており、極東の民族は一番向うの端に位置する。われわれにとって「自我」が、心の本質を形作る魂とすれば、極東の民族の魂は「没個性」と言ってよいかもしれない。
(パーシヴァル・ローエル著/川西瑛子訳『極東の魂』公論社、1977)
1888年に書かれた訪人外国人による日本人論の一つである。ローエルは、火星の運河を「発見」したことで知られる人物だが日本人は進化論的に劣性であるが故に「個我」が脆弱だと言っている。「個我」が脆弱だということはそれが集合的であるということにつながる。つまりハーンの言う「東洋の我」は仏教の誤読とではなくローエルの議論をこそ踏まえている。
こういったローエル式の「個人」と集合霊をめぐる枠組みは戦時下の以下の言説にも継承されている。復興している、というべきなのか。
個我としての人間は、有限なるが故に死を免れぬが、「ひ」そのものは悠久無限の宇宙生命であって、家族生命並びに民族生命として不滅に流動して行く。近代人は、個我のみに執着した結果、個人の生命の拠って出ずる「ひ」の宇宙生命と感応し得る宗教的情操を喪ってしまったのである。故に宗教界新秩序建設の根本問題は、浅薄なる実証的合理主義を打破して、人類を再び神人合一の崇き宗教的境地に帰入せしむることでなければならない。
(藤沢親雄『国家学原理』三省堂出版、1944)
柳田の元側近でムー大陸説の藤沢の発言であるが、これは『先祖の話』とパラレルに空襲下書かれた丸山敏雄の『神国』における引用部分である。だからこの引用が以下の隣りにあることにさらなる留意も必要だろう。
このように、日本人の生も死も、天皇国家に尽すことを本義としているから、単に生を享楽し、安楽往生を願うのとは筋道が違うのである。ここに日本人は個人主義による生死観とは全く離れて、日本の命の中に生れ変り死に変りしつつあるのである。個人としての生死そのものの価値ではなくして、日本の命のための生死こそ、日本大の価値を持つのである。
(大倉邦彦『産霊の産業』大日本産業報国会、1942)
大倉は実業界出身だが1937年、東洋大学学長となる人物である。その就任理由は戦時下の言論界の「革新」思想である超国家主義陣営に「はなはだ好評であった」とされる。「個我」が「個人」、「先祖」が「日本の命の中」に置き換わっているが、この二つを丸山が引用している点からも丸山の『神国』がいわばもう一つの『先祖の話』、あるいは「固有信仰」論であることが見えてくる。
事実、『先祖の話』にはあからさまにこうある。
ともかくもこれがおおよそ好い頃合いの区切りと認められ、それから後は人間の私多き個身を棄て去って、先祖という一つの力強い霊体に融け込み、自由に家のためまた国の公けのために、活躍し得るものともとは考えていた。それが氏神信仰の基底であった。
(柳田國男『先祖の話』筑摩書房、1941)
「私多き個身」を捨て「先祖」に融合し「公」に奉ずることが「氏神信仰」であり、続く一行ではそれは「民俗固有の観念」という。つまり「固有信仰」である。こうして柳田と同時代の言説を並べてみれば丸山の「魂」をめぐる言説が柳田と同じ収斂先に向かっていることがわかる。
だから丸山が感銘を受けた『先祖の話』よりも早く刊行された柳田の『神道と民俗学』にもこうあるのだ。
国の共同の問題を解決するに先だって何よりもありがたいことは、一国の秩序に服し、各自の区処に就き、皇家の安泰のために働こうとした点であります。具体的にいうと神御自身の御分限をお認めなされ、より大いなる神々の御威徳によって、さらに万民をもっと高い幸福へ進ませようとせられる点であります。神となって後もなお朝廷に忠誠であったことであります。こういうことが果して我々の霊の、死してなお永遠にこの邦に安住する姿を信ぜず、それが一団の清い力に融合して、未来に光被するということを信じない者に、なし得られることでありましょうか。
(柳田國男『神道と民俗学』明世堂、1943)
柳田は、先祖は「神」になっても「国の共同の問題」を解決しようとし、死者は「一団の清い力」に「融合」するという。
ここに柄谷は「死者」との「アソシエーション」を見るのかもしれない。
その善意はわからなくないが、柳田の「先祖」観はやはり死者の「協働」である。
近衛新体制の基本思想は協働主義であり、行き過ぎた個人主義を排し、一人一人が公や社会の構築に集合的に参加する、いわば参加型ファシズムである。つまり滅私奉公のマルクス主義的言い換えである。死者が先祖に統合されそして生まれ変わりその大いなる社会を構築するのが既に見たように「七生報国」であり、死者の「協働」としての先祖と、さらには生者との「協働」でもある。
このように『先祖の話』はつまりは「魂の協働主義」の書である。
そういう「魂の協働主義」思想としての固有信仰論が丸山や藤沢や同時代の人々の「協働」によってなされ、柳田もまたその参画者だった。それが『先祖の話』である。しかしこのような協働は柳田が強いられたわけでなく、国策の圧力や偽史思想家の接近を許しつつも流されたとまでは言い難い柳田が、最後に自ら自発的に書き始めたものである。しかし、協働主義とは「上意下達」ではなく「下意上達」、つまり自発的な参与が肝であり、近衛文麿は「心ヨリノ参与」つまりは国民の「心」の「協働」を求めたのである。それの「協働」を死者に及ぼしたところに『先祖の話』の本質がある。
だから田部が『神国日本』の読みを以下のように求めたことも「協働」の一つに過ぎない。
田部は八雲が「日本民族固有の宗教」つまり「固有信仰」をこう記す。
日本人はこれに反して、もっと精神的な考へ方、心霊を重んずる考え方をする。肉体は死しても霊魂は超自然的な力を得て、その生前に於けると同じく死後に於ても、我々と共にあって、この国土を護り子孫のためを思い、我々の日常生活にも参与する。
(田部隆次「解説」『神国日本』)
これはいうまでもなく、『先祖の話』の収斂していく先でもある。「先祖」となった霊魂が「日常」に「参与」するという言い回しはこの「固有信仰」論が近衛新体制の「日常」の更新、「心」の「参与」に正確に沿っているとわかる。
さきほどこれらハーンを含めた明治期の外国人論の延長なりその蓄積が前提である可能性を示唆したが、その点で柳田が穂積陣重の名を出して「日本人が最も先祖の祭を重んずる民俗」であったと記したことでそれも結果的に裏付けられる。穂積は1881年日本で初めての法学博士号の授与であるが、社会進化論のハーバード・スペンサーの影響を受けつつ、日本の祖先信仰とキリスト教的世界像を前提とする西欧の法体系の接合を図った人物だ。
スペンサーの著作は明治期の帝大の教科書として多領域で採用されただけでなく、八雲にせよ、ローレルにしろ、皆この時代の知識人はスペンサーの影響下にある。
穂積は『祖先崇拝と日本の法律』なる書を上梓したが、これはローマで1899年に行われた「祖先崇拝」についての講演が元だとされる。穂積は自らの発言が祖先祀祭者の信仰告白と受け止められたと記すが、柳田が日本人が先祖の祭を重んじると「汎く海外の諸国」に知られていると記したのはこのことを指す。穂積の議論は「祖先の霊は霊魂不滅の信念の所産」と書くが、祭祀のもっぱら外形、制度に終止するが、その祖先祭祀論が天皇制のためのものであることを隠さない。他方で八雲の『神国日本』(もちろん日本語訳以降の英文)を引用しキリスト教の流入によって祖先祭祀が阻害されていることを批判するが、それは最終的には「外来思想」に対する「固有信仰」論に発展しうるものだ。
こういったぼくの見解に対し、柳田の父やあるいは短歌の師を介した「国学的教養」を柳田に強く見出し『先祖の話』への反映を重視する立場もあるが、ハーンが平田篤胤「勝五郎再生記」を様々な「生まれ変わり」のフォークロアとともに海外に発信したように、それらは「西欧」の言説で一度加工されたものであり、柳田の「幽冥談」もまた西洋の文脈で語り直された日本である。この「国学」的なものの西洋による語り直しは看過すべきではない。
八雲『神国日本』と柳田『先祖の話』に違いがあるとすれば、八雲は靖国神社に戦死者が祀られる「協働」を日本人の霊魂感の反映として無邪気に評価したが、柳田は「七生報国」と結び付け死者の協働主義ともいうべき死後までもの動員を語っている点にある。
なるほど、幕末の国学者・岡熊臣の以下の如き「死後安心」論と『先祖の話』の「固有信仰」論と相似はする。
われ人現世に生れ出でて、それぞれの産業をなし、世をわたるもの、其の身の分の品位につけて、子孫の永昌を思い、君父の幸福を願ひなどせんものは、たとえ死すとも、かならず霊魂をたしかに此の世に残し留め置きて、永くとこしえに、神の朝府に仕う奉り居て、殊更に我が天皇尊の大御為、わが子孫の為に、守幸をなさんものと、平生おこたらず心がけ居るべき。
(岡熊臣『幽路乃葉の段』)
だが幕末の「死後安心」論との類似はあっても、累々と扉が積み重なり死が国家によってもたらされる中で書かれた『先祖の話』は「家の存続」を渇望する柳田個人にとって必要だったかもしれないが、「七生報国」の協働主義的言い換えであり、その心情は明らかにここではないどこか「死後」を生々描くロマン主義である。
最後には先祖の新たな祀り方を提案してみせるが、それが、養子・春洋を戦地に赴かせて死なせてしまった折口信夫に「死後安心論」として響いたとも思えないのである。その意味で『先祖の話』はロマン主義にもっていかれた空襲下の柳田の国策との悪しき野合であり、「魂」の協働主義としての柳田「固有信仰」論は創られた伝統に他ならない。
※註)柳田國男の『炭焼日記』でもう一点気になったのが1944年6月、つまり『先祖の話』を脱稿したすぐ後に刊行された『黒百合姫物語』である。同書は、郷土史家の藤原相之助が刊行の10年近く前の1934年に柳田に託した黒百合姫の祭文の資料に、筑土鈴寛らの文章と、さらには柳田のやや長文の論考「山臥と語り物」を加えたものだ。この柳田の文章だけは「底本」などで読めるが改めて原本を確認しようと思っているうちに本稿を書き終えてしまったので付記の形で記すが、この『黒百合姫物語』が気になったのは刊行後、来訪者に盛んに配った様子が記されているからだ。どうやら柳田の私家版らしく言霊書房の刊行とあるが300部の印刷費を柳田が負担し、うち200冊を柳田が配布用としたらしい。文庫サイズの冊子でもあり人に配りやすいという事情がわかるがしかしこの書の巻頭に折口の以下の如き詩があるのだ。
母が子の 父やいづこ
都べの 人のおくりし
ふりつづみ ふりつつ行かば
汝が父や 汝を出で見む。羽黒山 行き行きつつ見れば
(折口信夫「母の乳汁」柳田國男編『黒百合姫物語』言霊書房、1944)
月の山 そこに立ちたり。
ちちのみの 父やとよべば、
谷々の こだまこたえて
湯殿山 雲にこもれり。
これは折口の中でもかなり異様な詩である。
折口が自分を実母の不義の子と懐疑する来歴否認者であることは昔、『「捨て子たち」の民俗学』で問題としたが、それがねじれて一方では「妣の国」という母性的他界を国文学上の仮説とする一方、私生活では「母」を介さない父子関係、つまり同性愛を弟子たちに求めたとされる。この詩は一方では、「母の乳汁」というその母性への渇望があからさまなこの詩は、その一方で「母が子の父」つまり春洋に対する折口を主題とし、「ちゝのみの父」とも語る。春洋を出奔させた壮絶な悔いが読み取れる。
それがさらに柳田の論文によって閉じられる書物が『黒百合姫物語』なのだがこの論文も「語り物論」の体を装いつつも最後にこのように第二の主題を語り出す。
第二の疑問は今一段と大膽なもので、ちとやそっとの説明では共鳴する人も得られまいが、私は実は今、我々日本人の死んでから行く先の、高く秀でた山の頂であったことが、月山鳥海を始めとし、多くの名山の信仰の起原では無いかと思い、それが少しづつ、此方面から、明らかになって来はすまいかということを問題にして居るのである。この点にかけては仏教の浸染は物凄いばかりで、よくよく外来宗教を軽しめて居る日本人でも、もう古来国民固有の死後観のあったことを忘れて、死ねば天国へ行くだの、高天原へ行くだのということを口にする。そんな証拠は一つも残って居ないのみか、一方にはまだ幸いに書冊の教育を受けなかった人々の間には、古い考へ方が幽かながら伝わって居るのである。
(柳田國男「山臥と語り物」、柳田國男編『黒百合姫物語』言霊書房、1944)
つまり『先祖の話』に連なる「固有信仰」論であり、論文においては山を死者の魂の帰還先として位置づけようとするものだ。それが資料を10年放置しての刊行の動機であるとわかる。
注意したいのは日中戦争の年、柳田は同じ「山臥」を題に掲げつつ、ひどく婉曲にこう記したことは前の文章で触れたが再度囲繞しておく。
以前我々が山立の気風として、は山臥行者の長所短所として、あれほど注視し批判した正直・潔癖・剛氣・片意地・執着・負けぎらひ・復讐心その他、相手に忌み嫌はれ畏れ憚られ、文芸には許多の伝奇を供し、凡人生涯にはさまざまの波乱を惹起した幾つともない特色は、今や悉く解消して虚無にきしたのであろうか。或は環境に応じ形態を改めて、依然として社会の一角を占取し、この今日の日本的なるものを、撹乱せずんば止まるまじとして居るのであろうか。
(柳田國男「山立と山臥」柳田國男編『山村生活の研究』民間伝承の会、1937)
南京虐殺に先立ち「山立」「山臥行者」の暴力性を含む気質(古層)が、「日本的なるもの」(ナショナリズム)へのリスクとなることを危惧しえた柳田が、しかし、この新しい山臥論をこう閉じるのだ。
「死ねばどこへ行くと思って居たか」。斯ういう方面からも今一度、尋ねて見る機会は無いものかどうか。この問題に向って現実の関心を抱く者は、今日の時代としては決して我々垂老の翁だけでは無いのである。極楽は十萬億土、あそこへ行ってしまってはもう七生報國は出来ないからである。
(柳田國男「山臥と語り物」、柳田國男編『黒百合姫物語』言霊書房、1944)
七生のために死者は山へこそ還らねば困るというのである。やはり柳田の関心がこの時、「七生報国」を彼の学問で合理化することだったとわかる。
* * *
本連載は不定期連載です。
この続きは、次回の更新を楽しみにお待ちください。
筆者について
おおつか・えいじ。国際日本文化研究センター教授。まんが原作者。
著書に『手塚治虫と戦時下メディア理論 文化工作・記録映画・機械芸術』(星海社、2018年)、『大政翼賛会のメディアミックス『翼賛一家』と参加するファシズム』(平凡社、2018年)、『大東亜共栄圏のクールジャパン「協働」する文化工作』(集英社新書、2022年)、『「暮し」のファシズム ――戦争は「新しい生活様式」の顔をしてやってきた』(筑摩選書、2021年)、『シン・論 おたくとアヴァンギャルド』(太田出版、2022年)、『木島日記 うつろ舟』『北神伝綺』『北神伝綺 妹の力』(いずれも星海社、2022年)など。
現在の研究テーマは戦時下のメディア理論と文化工作。