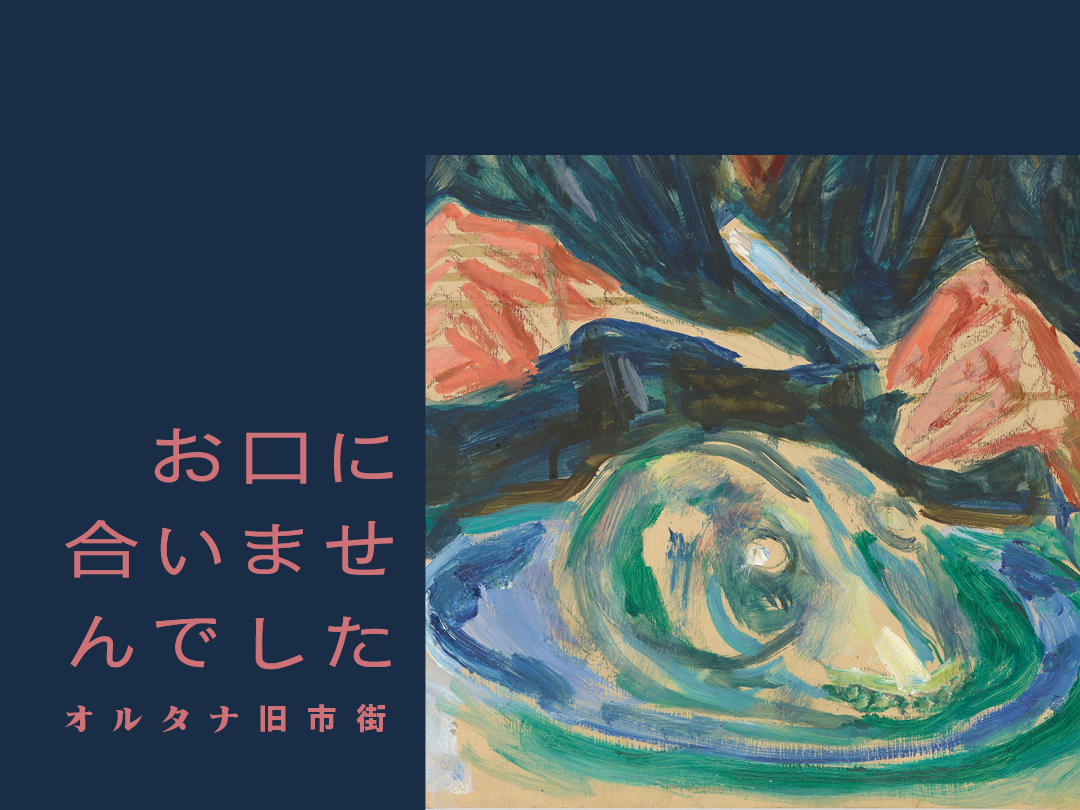ゴーストレストランのスープ、やる気のない食堂のうどん、某家具チェーンの人工肉……。お口に合わなかった食事の記憶から都市生活のままならなさを描く、オルタナ旧市街の大好評短編連載『お口に合いませんでした』。
今週16日(木)にいよいよ連載最終回を迎えるにあたり、今回は特別編としてOHTABOOKSTAND編集部員の「お口に合いませんでした」なエピソードを集めてみました。最新話が配信されるたびに社内で「不味いエピソード」を競い合ってきた編集部員たちの、気持ちがこもった5本の寄稿です。
パフェや紅茶がまずいわけがない(編集部・藤澤)
友人の結婚式に出席するため、人生で初めて福岡に行きました。ホテルに着くと、一緒に来ていた友人がしばらく仕事をすると言うので、Google Mapを検索。近所に⭐4.6の古民家を改造した風のカフェがあるのを発見。時間を潰すことに。
中に入ると店主がひとつひとつ丁寧に集めたのであろう、かわいらしいアンティーク家具の数々。お客さんで賑わう店内。テイクアウトの焼き菓子のレジにも人が並んでいます。運良く一つだけ空いていた席に通されました。これは期待ができる。
メニューを開くと季節限定いちごのパフェが目に入りました。私は無類のパフェ好きです。迷わず注文。飲み物は少し珍しい紅茶のラテを頼みました。
しずしずと運ばれてきたパフェはなんともかわいらしい見た目。店内の小ぶりなアンティークの雰囲気にぴったりの、まるでシルバニアファミリーの世界から飛び出してきたようなメルヘンな盛り付け。写真を撮って、いただきます。
ひとくち口に運ぶと、いつもならパフェで感じられる多幸感がまったくありません。甘さ控えめの生クリームは脂っぽく、乳臭い。もったりとした脂肪分に対して、さっぱりとしたいちごは圧倒的に数が少なく、いちごの味がまるでしない。中に入っているレモン味のシフォンケーキはもっさもさのパサパサ。生クリームと混ざり合うこともなく分離しています。乳臭いもっさりもさもさの中に酸味。パフェ全体が腐っているように感じられます。
眉間に皺を寄せたまま口の中を洗い流そうと紅茶ラテに口をつけると、紅茶の苦味が薄いため、これまた泡立てられた牛乳の乳臭さをダイレクトにくらいます。しかし紅茶はミルクティーには合わないのだが、良い茶葉を使っているようで、華やかなお花のような香りがします。お花、乳臭い、お花、乳臭い。完全に分離した香りと触感がダイレクトに鼻腔を支配します。
いやそんなはずはない。おかしい。パフェや紅茶がまずいなんて、そんなことあるわけない。でももうスプーンを持つ手が止まってしまい、身体がこれ以上口に運ぶことを拒否しています。すると、後ろの席に座っていた、同じパフェを注文していた若い女性二人組がぼそっと「これ見た目だけだね」。
3分の2以上残して席を立ちました。
次の日、お口直しにロイホのパフェを食べました。ロイホは私を裏切りません。
K子の絶望スパゲッティ(編集部・杉山)
大学入学時のこと。母は、芸術学部デザイン学科に進学した私のことを思ってか、ファションデザイナーである母の姉・K子の家に居候することを私に提案した。東北の片田舎で育った私は、K子の家(千葉)から神奈川のキャンパスまで片道2時間半もかかることは知らずに同意。毎日課題に追われ、何よりも大好きな睡眠時間よりも、電車に乗っている時間のほうが長い、かなり忙しい大学生活を送っていた。
そんな私をみてか、K子が原宿へ誘ってくれたことがある。当時はゴスかゴスロリかパンクファッションだった私。今思えば、例の有名な橋とかも見せたかったんだと思う。思っていたよりも入り組んだ道を歩き、ウインドウショッピング(※K子は姪の私に服を買ってはくれない)を楽しんでいるとさすがにお腹が空き、連れて行かれるまま、行き止まりにあったイタリアンへ。目に飛び込んできた謎のメニュー「絶望スパゲッティ」をオーダーした(※本当にこの名前でメニューにありました)。
「なにが絶望なんだろう」とワクワクして待っていると、ブラックオリーブをふんだんに使ったパスタが登場。思っていたよりも見た目が美味しそうで、逆にがっかり(?)しつつ、安心して口に運んだ。 ……ちょっと、すっぱい。あと、かなり脂っこいし、食感も……なんだかツナみたいなもっさり感? そんなことよりも、なぜか、ぬるい。味はともかく、ぬるさのせいでけっこう、美味しくない……。
コンセプト重視の料理はこんなものなのかなあと、なんとか完食はして退店。すぐにお腹が痛くなってしまい、その後はまっすぐ帰った記憶がある。 もう20年以上も前の出来事でしたが、このあと、宗教勧誘や金銭問題などで振り回され、K子に対して「絶望」することになる筆者でした。母はすでに、K子との縁切り宣言を何度もしている。
喫茶店の水は人間の業を肯定する(編集部・脇)
私は2年前、「喫茶店の水はまずいけどかわいい」というZINEを作った。どのようにまずいかといえば、カルキ臭かったり、夏の暑い日に常温だったり、見るからにコップの衛生面が心配になったり、明確な原因はわからないが一口飲んでこれ以上体に入れたらダメだと思ったり、千差万別。水は「出しておけばよい」、というようなやる気のない喫茶店が愛おしかった。水だけでなく、喫茶店の看板メニューとも言えるコーヒーまでもやる気が感じられない店だって、日本にはまだまだ存在する。そういう店に出会うたびに興奮していた。心地いい不快。笑顔で受け入れたくなる不快感。
いま、あらゆるコーヒーチェーンが(そしてコンビニまでもが)、より美味しいコーヒーの味を追求し、しのぎを削っている。たしかにどれも美味しい。しかしあなたはそれでいいのだろうか。そんな美味しいものばかり飲んで、何か大切なものを見失ってはいないだろうか。いまこそ、あの怪しげな常連の高齢者しかいない喫茶店に入店するときである。自ら不快感を受け取りに行く、そんな日があってもよい。喫茶店の「ださしなさ」や「まずさ」を受け入れるとき、(立川)談志の言う「人間の業の肯定」とはこういうことなのかなと思いを馳せたりするのだ。
理想的なコーヒーの探求(編集部・金子)
一年以上前からロースターで仕入れた浅炒りのコーヒーを淹れている。かつて好んでいた苦くて酸っぱいコーヒーにはすっかり魅かれなくなり、コンビニやチェーン店で買うことはもうほとんどなくなった。
スケールで豆の重さを測り、挽き目を少し粗めにしてミルで挽く。ケトルの温度を調整してお湯を沸かす。準備ができたらお湯を注いで1分弱ほど蒸らす。それから複数回にわけてゆっくりとお湯を注ぐ。微細な変化に気が付けるほど敏感な舌は持ち合わせていないものの、次第に安定した味を作り出せるようになってきた。
ゴールデンウイーク中にいつも通り小さなベランダで淹れたてのアイスコーヒーを飲んでいると突然、もしかしたら僕はコーヒーが好きではないのかもしれないという疑念が浮かび上がってきた。
淹れるたびに改善点を探しながら飲む。自分にとっての理想のコーヒーの輪郭はまだ見えない。でも少なくとも「これじゃない」はわかる。雑味が入っている。苦みを感じる。フルーティーなフレーバーが弱い。酸味がある。まるでコーヒーの特徴をそぎ落とそうとしているではないか。
決してまずくはない。でもコーヒーそのものが僕のお口に合わない可能性がある。思い過ごしもあり得る。飲み続ければお口が変わってくるかもしれない。おそらく、もうしばらく飲み続けないとわからない。
唐揚げステーション(編集部・山本)
片道2時間かけて通っていた田舎の高校の周辺にはコンビニもなく、野球部で練習漬けの日々を送っていた私たちは常に腹が減っていた。唯一のオアシスは、学校の正門の目の前にある売店「レオン(仮名)」。何十年も前から70代のおばあさんがひとりで切り盛りしていて、夏になると駅前のスーパーで売っている100円のミカンの缶詰を凍らせて「みかんアイス」として300円で売っているなど、いい加減な店だった。
少ない小遣いで腹を満たしたい野球部員たちのお気に入りは一個80円の唐揚げだった。10円玉くらいの鶏肉にソフトボール大くらいの衣がついていて、肉と衣の比率が逆転したようなベトベトの唐揚げ。決しておいしくはないが、とりあえず腹が膨れるので練習後のエネルギー源として私たちは重宝していたのだ。
2年生の秋、われわれ野球部は地区予選を勝ち抜き、県大会出場を決めた。そして地区予選の翌日、いつものとおり5〜6人の部員と「レオン」に立ち寄ると、そのニュースを知ったおばあさんが「おめでとう!がんばったねえ」と満面の笑顔で迎えてくれた。用意されていたのは、山盛りの唐揚げ。20個はあったと思う。ご厚意に甘えて全員で唐揚げにかぶりついた。1個でも胃もたれする唐揚げをひとり3〜4個は食べたせいだろう、帰り道は全員が無言。駅のトイレに駆け込む者もいた。「俺、一生唐揚げ食わねえ」という友人の言葉が忘れられない。その言葉どおり、私たちはその後しばらく唐揚げを食べなかった。
余談だが、現在放送中の某民放ニュース帯番組で司会を務める男性アナウンサーは同じ高校の卒業生で、在学中は毎日レオンの唐揚げを食べていた、という噂があった(レオンの壁にはそのアナウンサーの写真と「レオン、最高!」と書かれたサイン入り色紙が飾ってあったので信憑性は高い)。私は夜のニュースでそのアナウンサーの柔和な笑顔を観るたびに、ベトベトの唐揚げを思い出している。
オルタナ旧市街『お口に合いませんでした』最終回は5/16(木)配信です
※当サイトOHTABOOKSTANDに掲載の「関連商品」は、関連書籍および編集部おすすめのアイテムです。このほかの欄に表示される広告は自動表示につき、編集部が評価して表示するものではありません。