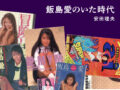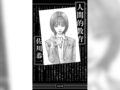今日までやらずに生きてきた。一本の桜を目指して出掛けるような花見を、私はこれまでしたことがなかった。私が住む大阪から気軽に行ける場所はないか。奈良県の北東にある宇陀市に「又兵衛桜」という名木がある。満開状態は少し過ぎたようだが、まだ咲いているようだ。「これだ!」と思ったとき、私はまだ布団の中でゴロゴロしながらスマホを触っていたのだが、すぐ起きて支度を始めた。
桜を見に行くために家を出る、積極的な花見
2025年の春は桜をよく見た気がする。人と集まって花見をすることはほぼなかった(この連載の前回に書いたモルックの後のお花見ぐらいだった)のだが、近所の桜並木の脇を少し歩いたり、出かけた先で思いがけず満開の桜に出くわしたりした。
そうやって日常的に桜を見ることができたからか、いつもなら「ああ、もうすぐ桜が散ってしまう。お花見しなくては」と、謎の焦りを感じるところ、気持ちに余裕があった。「そろそろ散り際だろうけど、今年はもう何度も見られたし、まあ、いいか」という感じ。

……そうだったのだが、そういう、出かけた先で桜を見るような、いわば受け身の花見ではなく、桜の木の下にシートを敷いて何人かで宴会をするようなザ・花見でもなく、一本の桜を目指して出掛けるような花見を、私はこれまでしたことがなかったなと思った。桜を見に行くために家を出る、積極的な花見。
もう何年も前だが、『日本の絶景お花見スポットベスト50』みたいな感じの、コンビニで販売されるムック本の制作に関わったことがあった。関わったといっても、ああいうムックは綺麗な写真がメインのようなところがあって、私はそのスポットに関する基礎的な情報を調べて短い文章にまとめるという仕事をしただけだった。とはいえ、そんな仕事をしたから、日本各地の桜の名所と呼ばれるような場所について、ほんの少し、知ることにはなった。人が集まるような名所は日本のあちこちにあるわけだが、私が好きだなと思ったのは、桜の木がたくさん並んで、ぶわーっとなっていて見事、というような場所より、樹齢数百年とかで、昔からその土地の人に守られて咲き続けてきたような一本の名木のほうだった。
今、この原稿を書きながら検索してみると、たとえば福島県田村郡にある「三春滝桜」は樹齢1000年以上の、まさに滝のように花を咲かせる大樹らしい。山梨県北杜市にある「山高神代桜」という木も有名で、ムック本を作ったときにもそれについて調べた記憶がある。樹齢2000年と推定されるそう。そういう、一本の桜単体が名物になっているような、そういう桜を見てみたいと、急に思ったことが、先日あった。
私が住む大阪から気軽に行ける場所はないかと探してみたところ、奈良県の北東にある宇陀市に「又兵衛桜」という名木があるという。後藤又兵衛という武将の屋敷跡に咲いていることからその呼び名がついた、樹齢300年の木らしい。SNS上でその桜の名を調べてみると、満開状態は少し過ぎたようだが、まだ咲いているようだ。「これだ!」と思ったとき、私はまだ布団の中でゴロゴロしながらスマホを触っていたのだが、すぐ起きて支度を始めた。
歩きながら、少し緊張してくる。少し怖い気さえする。
家の最寄り駅から1時間ほど電車に乗って近鉄桜井駅まで行き、そこからバスに乗ると桜の木の近くまで行けるらしい。昼近くにようやく家を出て、13時過ぎには桜井駅に着いた。今日行くと決めてもうこの時間にここまで来ているのだから、上出来なほうじゃないかと思った。

駅前のロータリーで大宇陀行きのバスを待つ。桜井駅には20年近くも前、一度来たことがあった。20代の半ば、みうらじゅんといとうせいこうの『見仏記』シリーズが好きになって、その真似をして仏像めぐりをよくしていた。桜井駅の近くには聖林寺という、国宝の十一面観音像が祀られているお寺があって、そこに行ったのだ。
当時は東京で暮らしていて、お金に余裕もなかった(今もだが)はずなのに、電車に乗って奈良の桜井まで来て、おそらくここからバスに乗って行ったのだろう。その日の記憶はもう遠く、十一面観音像と対峙したときの静かな気持ちだけが、かすかに残っている。そうか、考えてみれば、あれも時間をかけて何かを見に行くという旅だったのだ。そのためだけの旅。当時の私は旅先でお酒を飲む楽しみも知らず、十一面観音像を見て、本当にそれだけですぐ東京へ戻ったはず。我ながらストイックな旅だった。
時が経って大阪に住み、この桜井駅まで来るハードルもだいぶ下がったが、今日は今日で、桜を見るために同じ場所にやってきた。そんなことに不思議さを感じながら、バスに乗る。30分ほどの乗車時間の途中、小学生の一団が乗ってきて、山道の途中で降りていった。学校が終わって、バスに乗って家に帰っていくのだろう。バスに乗っている間も座席の上の膝に漢字ドリルを広げて黙々と勉強している子がいた。
その子どもたちがみんな降りてしまうとバスの中は静かになった。前のほうにひとりだけ座っている人がいるぐらいだ。又兵衛桜を見に行く人で満員、ということはないのだな。目的の大宇陀迫間という停留所が近づくと、運転手さんが「次で降りていただいて次の信号を右に曲がって歩いて行くと又兵衛桜です」とアナウンスしてくれる。バスを降り、その案内の通りに歩くと又兵衛桜の方向を示す立て看板があった。

私が目指す先には厚い雲があり、いつ雨が降ってきてもおかしくないような、そんな天気に見える。こういう日だからバスの客も少なかったのかもしれない。まあ、こんな日の花見もそれはそれでいいじゃないか。

歩きながら、少し緊張してくる。この道の先に、300年前から繰り返し咲いてきた桜があるのだ。自分で見に来ておいてなんだけど、少し怖い気さえする。そして、これは来てみて初めてわかったことだが、その目当ての桜以外にも、当然周囲に桜の木がちらほらとあって、もうそれがすでに綺麗なのである。お地蔵さんを祀った小さな祠の脇に見事な桜の木があって、「これが又兵衛桜です」と言われたら納得してしまいそうな姿だった。

徐々に人の姿が増えてきた。なるほど、私のようにバスで来る人は少数派かもしれず(その日は平日だったし)、奈良近郊に住んでいる人はみな車で来るようだ。駐車場が近くにあり、そのあたりから急にたくさんの人が現れる。その人たちが歩く先を見ると、遠くに、明かに他の桜とは違う雰囲気の木が見えて、「あれだ!」と思う。

又兵衛桜の周辺は地元の方が毎年整備しているようで、桜に続く道の途中にテントでゲートが作ってあり、維持管理協力金として100円を支払って入場する仕組みらしい。

ゲートをくぐるとすぐに又兵衛桜が現れ、鳥肌が立つ。なんだろう、この気持ちは。私は桜に限らず、古い木がそもそも好きなのだが、とんでもなく長生きしてきた木は、植物なのだが少し動物っぽくなってくるというか、怪物といってもいいのか、人智を超えた迫力を帯びる。

この桜の木の前で流れた300年間を一気に早回しにして見たいような気がする。
又兵衛桜の周りにもソメイヨシノらしき桜がたくさん咲いていて綺麗なのだが、又兵衛桜の花びらの色はその周囲の桜よりもくすんでいる。それこそ、私の家の近所の桜並木は満開になると真っ白に近いピンクに見えるのだが、又兵衛桜の花はグレーがかったように見える。

木の周りをぐるっと回れるように歩道が作ってあって、色々な角度から桜を眺めつつ歩く。下に立ってぼーっと見上げていると、風が吹いて花びらが飛んできた。これもやはり、ソメイヨシノの花びらとは違って、小ぶりで可愛い。

300年も咲き続けてきた桜の花びらだと思うと、とんでもなく貴重なものに思える。少しのあいだ、手のひらに乗せてありがたい気持ちを味わって、土の上に返した。入ってきたのとは反対側のゲートを通って少し歩くと売店があった。

売店の名物らしい柚子味噌こんにゃくを買う。こんにゃくも柚子味噌も手作りだそうで、箸に差して鍋で煮込んだこんにゃくに味噌をつけて渡してくれる。まさか桜の近くにこんないい売店があると思わず、念のために桜井駅前で買っておいた缶チューハイを飲みながらそれを食べる。

手作りのこんにゃくはスーパーで買うようなものとは違って、ほろほろと柔らかい食感があり、またそこに爽やかな風味を添える柚子味噌がたまらなくて(これだけで別売りしていて、買っていく人が多いらしかった)、もう一本おかわりしたくなる。少し迷ったが、またあとで何か食べるかもしれないし、とおかわりはやめにして、又兵衛桜の写真がラベルになったカップ入りの日本酒を、自分へのお土産に買うことにした。
川の向こうにさっき間近で見てきた又兵衛桜があって、こうして少し離れた場所から見るのもいいなと思う。

たくさんの人が桜の前にやってきて、何人かで記念撮影したり、自撮りしたり、大きなカメラでじっくりといいショットを狙ったりして、また去っていく。別の誰かがやってきて、また写真を撮って、木を見上げて、私もさっきまであそこにいて同じようにしていた。このような場面が、周りの景色や遊歩道の形などが時代ごとに変わりつつも、ずっと繰り返されてきたのだろう。無理だとわかっていながら、この桜の木の前で流れた300年間を一気に早回しにして見たいような気がする。
昔、それこそ仏像めぐりに夢中になっていた時期、鎌倉にあるお寺を訪ねて古い仏像を見た。その後、境内を歩いていると、最近建て替えられたらしいお堂に真新しい仏像が祀られていて、それはさっき見てきた渋い色合いの仏像とは全然違ったが、この今は新しい仏像もまた、何年も経って違った風合いになっていくのだろうと思った。自分がいなくなったあとの世界にも、この仏像は(たぶん何か大きなことがない限り)残っていて、100年後にこの仏像の前に立つ誰かも確実にいて、と、そんなことを考えると妙に心が安らいだ。
又兵衛桜をぼーっと見ている時間にも、それに近い感覚があった。自分の生死のスケールを超えて存在するものがあるという安心感。狭苦しい体に閉じ込められている自分が風に吹かれて散っていく未来を思い浮かべる。古い桜は色々なことを想像させてくれる。 東屋の下に椅子が並べられていて、きっとどこかの家から誰かがここに寄贈(?)したのだろう。座るとちょうど又兵衛桜がいい具合に遠くに見えた。ここに椅子を置いてくれた人に感謝したい気持ちで、少し座って最後の桜を見た。

歩いて10分ほどの場所に「あきののゆ」という温泉施設があると案内板で知り、行ってみる。「せっかく近くにあるらしいし、入っていくか」ぐらいの軽い気持ちで行ったのだが、ここのお湯が素晴らしかった。とろっとした肌触りの天然温泉の露天風呂もよかったが、「大和当帰」という、奈良に古くから伝わる薬草を使った薬湯がまたいい。いかにも体にありがたい効能がありそうな香りに包まれてのんびり湯につかり、また露天風呂のほうに行って、と何度も行ったり来たりした。

受付前の売店で、家庭のお風呂に入れて使う薬湯の入浴パックを買う。それをしまったリュックの中に、さっき薬湯につかって吸い込んだのと同じ香りが漂ってうれしい。施設を出て、さらに近くの「道の駅 宇陀路大宇陀」まで歩き、売店のなかの軽食コーナーで肉うどんを食べる。

道の駅の目の前の停留所からバスに乗り、帰りは桜井駅ではなく、同じぐらいの時間で着く榛原(はいばら)駅まで出て帰ることにした。バスの窓から川沿いの桜並木が見えて、それが遠目にも見事で、やはりこれはこれでいいと思う。榛原駅前の案内所で「さっきバスからすごい桜並木が見えたのですが」と聞いてみると、歩いて5分ほどの場所に宇陀川という川があり、その川沿いに延々と桜並木が続いているのだという。もう日が暮れてだいぶ肌寒くなってきたが、最後にその並木をひと目見て行こうと歩く。教えてもらった通り、宇田川に出るとずっと遠くまで桜の木が並んでいる。並木の脇を犬を散歩させながら歩いている人がいた。

このままずっと、引き返せないほど遠くまで川に沿って歩いていきたい気持ちに駆られたが、今日はもう帰ろう。一本の桜を目指して出掛ける楽しさを初めて知ることができたし、また来年も又兵衛桜を見に来られるかもしれない。そのときは宇田川沿いをゆっくり歩こう。
* * *
スズキナオ『今日までやらずに生きてきた』は毎月第2木曜日公開。次回第13回は6月12日(木)17時配信予定。
筆者について
1979年東京生まれ、大阪在住のフリーライター。WEBサイト『デイリーポータルZ』を中心に執筆中。著書に『深夜高速バスに100回ぐらい乗ってわかったこと』、『遅く起きた日曜日にいつもの自分じゃないほうを選ぶ』、『思い出せない思い出たちが僕らを家族にしてくれる』、『「それから」の大阪』など。パリッコとの共著に『ご自由にお持ちくださいを見つけるまで家に帰れない一日』、『椅子さえあればどこでも酒場 チェアリング入門』、『“よむ”お酒』、『酒の穴』などがある。