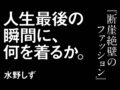「カルチャー ×アイデンティティ×社会」をテーマに執筆し、デビュー作『世界と私のA to Z』が増刷を重ね、新刊『#Z世代的価値観』も好調の、カリフォルニア出身&在住ライター・竹田ダニエルさんの新連載がついにOHTABOOKSTANDに登場。いま米国のZ世代が過酷な現代社会を生き抜く「抵抗運動」として注目され、日本にも広がりつつある新しい価値観「セルフケア・セルフラブ」について語ります。本当に「自分を愛する」とはいったいどういうことなのでしょうか? 一緒に考えていきましょう。第4回は、最近よく聞くようになった「ボディポジティブ」とセルフラブの関係について。
「ボディシェイミング」と「ボディポジティビティ」の錯綜する歴史
セルフケアとは、自分自身の「欲求・ニーズ」の輪郭を明確にし、それらを満たすために自発的に行動することである。つまり、セルフケアに伴うセルフラブを持ち合わせるには、自分自身にとっての「幸せ」を認知し、大切にする必要性があるのだ。
自分の身体を愛するということは、自分の体を大切に扱うということ。痩せたときの自分だけ愛したり、自分を愛するためには他人から愛されないといけないという理由で、自分の外見に執着したりするのは、自分を愛していることにはならない。だからこそ、体型や外見にばかり言及するエンパワメントや「セルフケア・セルフラブ」のあり方は、有害になりうる危険をはらむということに注意したい。
私は1997年生まれだが、90年代のケイト・モスを筆頭に、「ヘロイン・シック」と呼ばれるような、病的なほどに痩せ細った当時のスーパーモデルたちは、その「脆さ」が崇拝され、危うい世界観も大人気だった。今となっては不健康であり、特に成長期の若い女性にとっては精神的・身体的に大きな悪影響を与えるとして「繰り返してはいけないトレンド」という認知がされているが、それでもなお、今でもファッション好きで美意識の高い若い女性たちの「インスピレーション」として掲げられ続けている。
私の物心がついた2000年代にはブリトニー・スピアーズやリンジー・ローハンなどを筆頭に、有名女性セレブたちが常にタブロイドやメディアから体型について揶揄され続けていた。今となっては「2000年代は異常な時代だった」と反面教師の教訓として伝えられているが、今のアメリカの基準では「細い」とみなされるような体型の人たちであっても、容赦無く「細くないこと」が叩かれ、「痩せる」ことが危険なほどに美化された。
2010年代には下着ブランドVictoria’s Secretのランウェイショーを歩くモデルたち、「エンジェルズ」が一世を風靡した。過酷なトレーニングと食事制限を公言し、鍛えられた身体を武器とする彼女たちは、当時は「ストイックでかっこいい」対象として、多くの女性たちが憧れる存在だった。その頃からSNSアプリTumblrでは、摂食障害を推進するようなコンテンツ(”Thinspo” “pro ana”)や、自傷を美化するようなコンテンツも広く出回った。ティーンの女子たちの摂食障害が深刻な問題として議論され、学校ではフォトショップを用いてモデルたちの体型が写真で修正されていることを教えられたり、しっかりした食事を摂ることの重要性などが強く説かれるようになったりした。
このような「細さを美化する」広告や報道などと正反対の方針を打ち出した例として有名なのが、”Dove campaign for real beauty”だ。2004年にユニリーバが開始した世界的なマーケティング企画で、女性たちをエンパワーするように、様々な人種、体型の女性たちをキャンペーンに起用した。当時は、この「多様性」のあり方が広告で起用されること自体、大きな革新だったのだ。

さらに、2014年には下着ブランドAerieが「AerieReal」というキャンペーンを開始し、それが大きく話題となった。モデルたちの写真を一切レタッチせず、「ありのまま」を見せるという約束が、とても高く評価されたのだ。
2021年あたりから、Victoria’s Secretもボディポジティビティやインクルーシビティなどを掲げるようになったが、時すでに遅しといった具合で、あまりポジティブには受け取られなかった。すでに「ワンサイズの女性しか起用しない」ことを批判をされていた2014年に、「パーフェクトボディ」と書かれた広告でワンサイズの細身のモデルしか登場させなかったことや、長年の看板企画であった「ヴィクシーエンジェルズ」のかつてのイメージがとても強かったからだ。
デジタルな技術によってシワやニキビのない肌、脂肪のない体、艶々の髪、たるみのない顔になれたとしても、それは「リアル」ではない。このような「フェイク」に自尊心を削られてしまう人々(主に若い女性)が増えたことにより、摂食障害の増加なども懸念された。ボディポジティビティムーブメントはセレブとともに、ブランドの主導で行われた。Self esteem(自尊心)を持つことの重要性が、当時のガールボスムーブメントとともに頻繁に謳われ、「誰によってもあなたの価値は損なわれない」といった具合のエンパワメントのフレーズが多く使われた。
このようにアメリカでは、常にブランドや広告、メディアがどのような「イメージ」を社会に打ち出しているのか、そしてそれがどのような社会的影響を及ぼすのか、常に広く議論されている。議論の根底で重要となるのが、「自分たちはどのような価値観を大切にしたいのか」、そして「どのような未来を子供たちに与えたいのか」という思考だ。
モノを買わせるための「エンパワメント」
今となっては、雑誌やテレビで見ていたセレブたちの「完璧な姿」は決してリアルではなく、有名人やセレブも普通の人間である、ということは広く認知されている。それはSNS時代において、セレブや有名人たちが「自分たちも普通の人間である」ということを主張することで共感を得て支持を集めるという方針を取っていることも、一つの要因として挙げられる。
「自分を愛する」ことの大切さをテーマにしたキャンペーンや、Doveのように「目に見える多様性」もかつては革新的であったが、もはや現在ではそれは「社会的に意味のあること」だとは必ずしも受け取られにくい。結局はモノを売るために、人々のコンプレックスやトラウマに漬け込んできた業界が、その作った傷を癒すように逆の戦略を取っただけであることが、認知されるようになったからだ。
以上で触れてきた「ボディシェイミング」と「ボディポジティビティ」の錯綜する歴史は、皮肉にも、見た目や体型の「理想」のゴールを変え続けた企業の影響を強く受けている。「理想」を変え続けることで「欲望」の向く方面も変わり、そのおかげで「購買」が絶えることはない。企業によって新たに差し出されるイメージも結局、我々の本来的な自尊心を高めるためではなく、「モノを買わせるため」になっているということに、多くの人が気付き始めているのだ。
「モノを買うという形のセルフケア・セルフラブ 」については、本連載では繰り返し批判的に取り上げてきた。それと同時に、「モノを売るため」に用いられるセルフケア・セルフラブの文言も、注意する必要がある。もちろん、企業が広告やメディアを通して「エンパワメント」や「セルフラブ 」、ないしは「メンタルヘルス」が大々的に取り上げられることは、それらのテーマに対して保守的な土壌を持つ地域・時代においては、確かにポジティブな効果を社会的にもたらす可能性を持つだろう。しかし一方で、現代のアメリカのように、これらが食傷気味になっている場合においては、もはや陳腐で聞こえの良い商売文句のように見えてしまうという問題点もある。
同時に、そのようなセルフケア、エンパワメント 、多様性などの推奨が「見た目」の話で終わってしまう場合も多い。いわゆる「ボディポジティビティ」ムーブメントとは、どんな体型であっても美しい、どんな外見であっても自分を愛するべき、という「確かにそうあるべき」と思うような強いパワーを持ったフレーズが中心的だったが、現在はボディポジティビティムーブメントも商売的な側面が強いことが批判されたり、逆に体型にばかり執着しすぎているため、代替として「ボディニュートラリティ」(自分の身体をありのままで受け入れる、特に愛さなくても良い)という概念も広まりつつある。
資本主義の外側で行われるセルフケア・セルフラブの模索を
上記の記事にあるような、多様性やエンパワメントをテーマとして起用する広告を「セルフラブ革命」の担い手のように称賛する「広告賛美」は、数年前までは通用した。もちろん、この記事で書かれているように、ミレニアル世代がセルフラブや「リアル」を大切にする広告を好む傾向にあるということは重要な事実であるが、同時に、その広告が生まれるまでの背景や社会に与える影響を無視して称賛することはできないはずだ。
今では「興味深く、効果的な過去の広告」として敬意をもたれているものの、メイクや下着、スキンケアなどの「商品」を通した「多様性とエンパワメント」は、根本的には資本主義に基づいた「都合の良い価値観の表明」であり、本質的に社会を良い意味で変えるムーブメントではない、という文脈で理解されることが多い。一部の人を排除しない、インクルーシブなものであり、エシカルであり、悪いステレオタイプを助長せず、エンパワメントのメッセージを持ったブランドや広告が「必要最低条件」であるという前提の上で、セルフケア・セルフラブ、そして社会規模でのエンパワメントは、消費主義とは別のところで行われなければならないのだ。
筆者について
たけだ・だにえる 1997年生まれ、カリフォルニア州出身、在住。「カルチャー×アイデンティティ×社会」をテーマに執筆し、リアルな発言と視点が注目されるZ世代ライター・研究者。「音楽と社会」を結びつける活動を行い、日本と海外のアーティストを繋げるエージェントとしても活躍。著書に文芸誌「群像」での連載をまとめた『世界と私のA to Z』、『#Z世代的価値観』がある。現在も多くのメディアで執筆中。「Forbes」誌、「30 UNDER 30 JAPAN 2023」受賞。