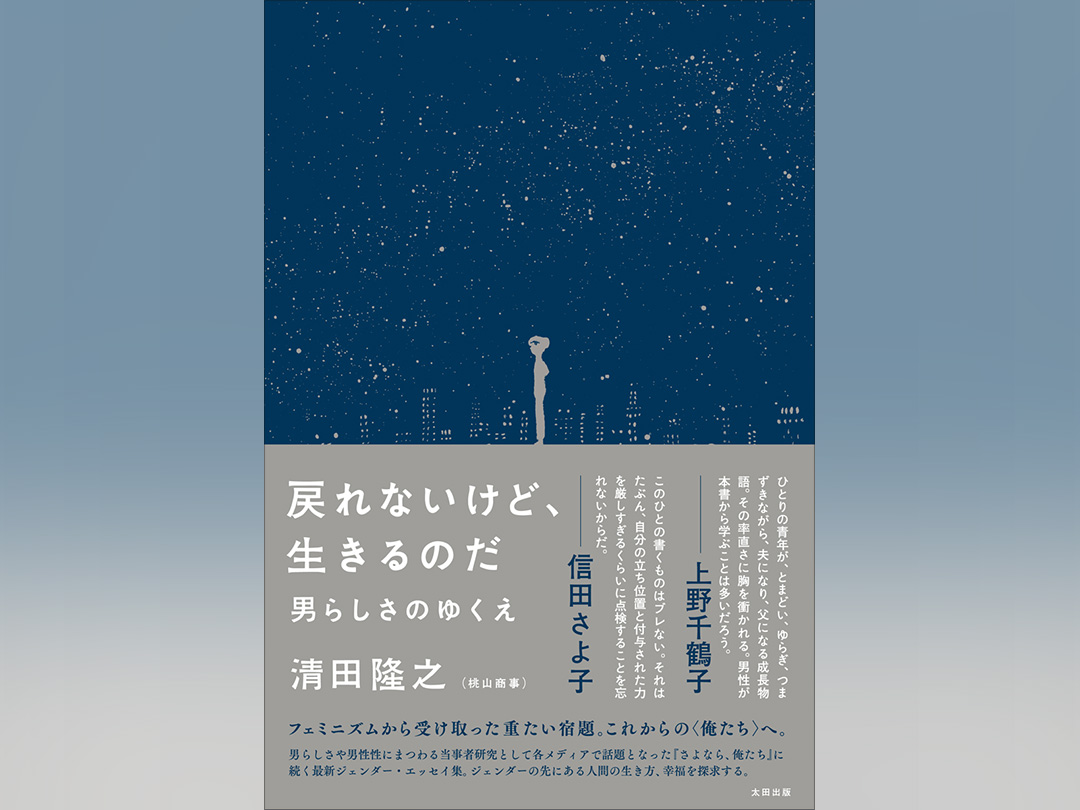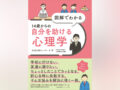男たちのなかには「お茶をする」文化が存在しないように思います。いじり合い、競い合いがメインのコミュニケーションとなっており、男同士の関係には互いへの、自身へのケアの精神が決定的に足りていないのではないでしょうか。
2024年12月24日に太田出版より刊行した、清田隆之著『戻れないけど、生きるのだ 男らしさのゆくえ』では、フェミニズムに向き合い大人の責任について考え、自分の傷や被害もまなざし、新自由主義や家父長制といった構造問題を踏まえながら男性性について探求しています。刊行を記念して、本書の一部を試し読みとして、2回に分けてOHTABOOKSTANDに公開します。
男同士の友情にまつわる疑問や不思議
ふと想像してしまう。例えば同窓会とか結婚式とか、忘年会とか久しぶりの再会とか、そういった場があったとして、彼らは一体何を話すのだろうか?かつてインターハイ制覇を目指して切磋琢磨したあの男たちも、地球を守るために最強の敵と死闘を繰り広げたあの男たちも、夢の実現に向けて同じ釡の飯を食っていたあの男たちも、仲間を救うために命がけの冒険に出たあの男たちも、最初の30分くらいは近況や思い出話なんかで盛り上がるだろうが、そこから何を話すのかいまいちイメージが湧かない。
多くを語らずとも心を通わせる男たちの姿は確かに魅力的だ。拳と拳で語り合っり不器用なハイタッチで信頼を示したり、1本のパスですべてを理解し合ったり、その連帯感はときに性愛や家族愛よりも深いものに見え、言葉に頼らないつながり方が確かに存在する……のだとは思うけれど、やっぱりなかなかイメージできない。互いの身の上話に耳を傾け合う男たちの姿が、空白の時間を想像力で埋め合う男たちの姿が、それぞれの変化に興味を示し合う男たちの姿が、どうしてもうまく想像できないのだ。それはおそらく、俺たち男の中に「お茶する」という文化が存在しないからではないか。
以前、桃山商事のPodcast番組で「男同士の友情」というテーマを取り上げた。メンバーのワッコが大学のサークル仲間で久しぶりに集まった際、男子たちの会話がさほど弾んでいないことに気づき、そこから男性間の関係性やコミュニケーションのあり方に興味を抱いたのがきっかけだった。ここで言う「男同士」とは〝マジョリティ男性〞を指しているが、そんな男同士の友情にまつわる疑問や不思議、またそのイメージについて番組リスナーに意見を募ったところ、男女あわせてたくさんの声が寄せられた。くだらない話をして笑い合う、常に若干の照れが付きまとう、太くて短い、ノリや勢いを重視る、バンバン肩を叩き合う体育会系のイメージ、構築するのに時間はかかるが簡単には壊れないもの……といった声もあれば、弱みや悩みを共有できない、個人的な話をあまりしない、ナメられたら終わり、冗談という名目でハラスメントが横行している、「会話」より「遊び」でつながっている印象、人間関係を序列化・ゲーム化しがち……というネガティブ寄りの意見も少なからずあった。
とりわけ印象的だったのは30代女性からの投稿で、そこにはこうあった。いわく、「夫には若い頃からご飯を食べたり遊びに行ったりする男友達がひとりもいません。中高一貫の男子校出身で、結婚式にはアメフト部の同期などたくさんの男性たちが出席してくれましたが、夫いわくその誰ともふたりで会うことはなく、仲間ではあっても友達ではないそうです」とのことで、これには共感しかなかった。
私自身も中高6年間を男子校で過ごし、男同士の関係に多くの時間を費やしてきたが、確かにノリ重視の空気だったし、弱みを見せづらい感じもすごくわかる。また、趣味でやっている草サッカーのチームメイトともかなり長い付き合いになるが、そこにふたりきりで会うようなメンバーはあまりいない。毎週のように集まり、おそらく家族以外では最も頻繁に顔を合わせている間柄にもかかわらず、仕事や出身地くらいの情報しか知らないケースも正直ざらだ。それで普通な気もするし、決して仲が悪いわけでもないのだが、考えてみると少し奇妙でもある。これって友達……?俺たちは一体、何を話しているのだろうか。
ふざけ合っていても常にちょっと不安
双子育児とコロナ禍が同時に始まった2020年から2022年にかけて隔週連載していたエッセイをまとめた拙著『おしゃべりから始める私たちのジェンダー入門』には、「暮らしとメディアのモヤモヤ『言語化』通信」という副題がついている。ほとんどの時間を在宅で過ごし、友達や仕事仲間ともなかなか会えなくなってしまったあの時期は、私にとって〝おしゃべり〞が圧倒的に不足していた2年間でもあった。
生活のなかで感じたモヤモヤ、仕事や育児にまつわる不安、SNSで目にした政治や芸能のニュース、心に響いた本や演劇の話など、そこには様々なテーマの文章が収録されている。エッセイとは言わば個人的な〝ひとり語り〞で、タイトルから連想されるようなおしゃべり形式の本ではないのだが、ここで取り上げた話題の数々は、本当だったら日常的な雑談のなかで友人たちと「わかるわかる」って分かち合いたかったことでもある。その最後のエッセイでテーマにしたのが「お茶する」という行為についてだった。
育った環境もあり、私は思春期の頃からいかにも〝男子っぽい〞コミュニケーション様式を内面化していた。茶化す、イジる、からかう、ふざけるが基本姿勢で、真面目な言動や感情的なリアクションは御ご法はっ度と 。遊びには何かとゲームや競い合いの要素が入り込み、盛り上がって笑いが起きればグッド・コミュニケーションとなる。各々が割り当てられた役割やキャラクターに則って振る舞い、空気を読みつつボケやツッコミを差し挟むチャンスを狙っていく。確かに楽しい瞬間も多々あるが、そこでは自分の話をしっかり聞いてもらうことも、誰かの話にじっくり耳を傾けることも、ほとんどない。
そういう感じに慣れきっていた私にとって、30歳前後で体験したコミュニケーション様式の変化は、それこそ〝革命〞と呼べるほどのインパクトがあった。それについて私は、「『お茶する』ことの醍醐味、ガールズトークの文化に学んだこと」と題したエッセイでこのように書いた。
女友達が繰り広げる会話に耳を傾けていると、とにかく話があちこちに飛ぶ。脈絡のない話題が次々飛び出してくるような印象で、それで内容がちゃんと理解できるのか、そもそも楽しいものなのか、昔はよくわからなかった。なんなら「女って人の話を聞かないよな」くらいに思っていたのだが、そうでは全然なかった。
(清田隆之『おしゃべりから始める私たちのジェンダー入門』2023年、朝日出版社)
一見カオスに思える話題は、実はシナプスが連結するようにどこかの点でつながっていて、関係ないように見えて実は関係ある話をしている。「それな」という言葉が表現しているような〝わかりみ〞のシェアと言えばいいのか、あるいはクオリア(感覚的・主観的な経験に基づく独特の質感)的つながりとでも言うのか、とにかく「その感じ、なんかわかる!」という感覚を連ねていくようにおしゃべりを続
けていく。それはむしろ相手の話をちゃんと理解していないとできないことで、そのメカニズムに気づいたときは結構な衝撃を受けた。(中略)互いの内側にあるものを共有し、理解を深めていく過程で味わう様々な感覚こそ、「お茶する」という行為の、ひいてはコミュニケーションそのものの醍醐味だと私は学んだ。
もちろんすべての男性がイジり合いや競い合いをしているわけじゃないし、おしゃべりが苦手という女性だって一定数いるだろう。だからこれはあくまで個人的な〝お茶観〞に過ぎないかもしれないが、それでもやはり、男同士の関係に必要なのはこれだと思った。ふざけ合っていても常にちょっと不安で、わちゃわちゃ騒いでいるのになんとなくさみしくて、仲良しだけどどこか信用しきれなくて、長い付き合いなのに意外とお互いのことを知らなくて__といった感覚に心当たりがあったら、それはもしかしたら「お茶する」が不足しているせいかもしれない。(本書へつづく)
* * *
清田隆之『戻れないけど、生きるのだ 男らしさのゆくえ』は、全国の書店、書籍通販サイト、電子書籍販売サイトにて販売中です。