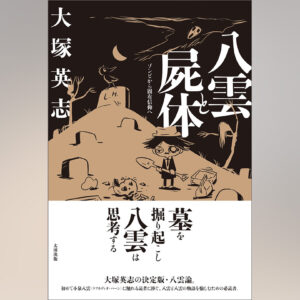ここで、旧柳田論で柄谷はいわゆる「方言周圏論」に言及する。
これは一同の対象を指す民俗語彙の分布、つまり「差異」を「時間的変遷の痕跡」と捉えるものだ。しかし柳田の方法を「方言周圏論」として捉えてしまうと、『蝸牛考』(1930)のようにたまたま上手くいった事例のイメージに引きずられてしまうのである。重要なのは同心円的な「周圏」イメージではなく、「偏差」という多様性である。
だから柄谷も引用した先の一節では、日本にこの分布図=横断面が「錯雑」化し、差異にも「種々なる変化と偶然の一致がある」と留保する。単純に、偏差の時間への変換はできないと柳田は慎重である。
無論、この時点での柄谷も同様に周圏論には慎重である。「南北の両端で一致するものがあればそれは古層として確定しうる」と周圏論を要約する。しかしこの時の「古層」とは、単に偏差として「表層」に露出しているという歴史のレイヤー性そのものへの言及であり、起源としての、あるいは後期柳田論に於いて召喚されるような無意識の領域に帰属するものを意味していない。
だから柄谷は、この空間「偏差」の時間軸への還元を歴史学の常識を踏まえ、自然村が形成された室町以前に遡行できないとその方法の限界を述べる。そして、
すると、彼のいう「固有信仰」は、歴史的にかなり近世の産物だというべきなのである。したがって、それを『海上の道』のようにはるか古代にまで確認しようとした柳田の仕事は、“非科学的”であるというほかない。
(柄谷行人「柳田國男論」『柳田国男論』2013年、インスクリプト)
このように「海上の道」の起源論としてのあり方を否定する。
さて、柳田の偏差=列島内の同一文化事象の差異を記録する方法は前回見たように、戦時下、写真論との重なりで理論的には精緻化している。「写真」は「偏差」の記録として三木茂や村治夫、あるいは土門拳らとのやりとりで再定義されていく。
しかし、「写真」という観察からなる資料を操作する方法は当初、フランシス・ゴルトンの「重ね撮り写真」に例えていた。これは写真を重ね焼きすることで差異ではなく共通点が鮮明となり、しかもそれは骨格などの形質というよりは民族や国民、あるいは何らかの属性からなるトライブの「本質」を読みとるものだ。それを国民性や民族性と言ってもいいが、柳田の場合、「固有信仰」ということばで呼ぶ。
そして柄谷の初期柳田論に於いて重要なのは、この「固有信仰」の示す範囲に慎重であることだ。柄谷は「固有信仰」を「宗教の背後に日本人のなかで生き続けている」ものと記す一方で、こう書く。
つまり、固有信仰は、個人の内面的な問題ではなく、また原始的心性でもなくて、日本人によって生きられてきた「事実」の問題であった。そして、彼はこれをいわば「経世済民」の立場から見ていたといえる。
(「柳田國男論」)
「固有信仰」という「事実」はあってもそれは「原始的心性」ではない、つまりゴルトンの重ね撮り写真によって得られるものとは一線を引く。
別のくだりでは「彼のいう『固有信仰』は歴史的にかなり近世の所産」とも言う。「固有信仰」は抽象概念ではあるが、本質論ではないということに冷静である。だから、「固有信仰」はまた「政策・制度」の問題で、社会政策論的民俗学の現在的問題であると考える。
ここでもう一度、確認しておきたいのは、柳田民俗学の思考法は理系的である、ということだ。何故ならそれは同時に近代文学の基本的態度でもあるからだ。森鷗外がヨーロッパからの新体詩の輸入者であり、まだ少年の面影が抜けなかったであろう松岡國男はその薫陶を受け、田山花袋が嫉妬するほどのロマン主義的な詩を書いた。
一方で鷗外は美術大学の講義用の解剖学の教本を書き、コロボックル論争にも参加している。そもそもが医師である。柳田がその自然科学的思考の薫陶を鷗外から受けていないはずはない。
そのような自然科学としての文学は、柳田にとって時代の気配でさえあり、だから花袋が作中で「第二の自然論」、つまり歴史や習慣としての「自然」をくどくどと説く『重右衛門の最後』を評価もしたのである。
柄谷の初期柳田論はこのような柳田の理系性に忠実である。そしてこの理系的手法として柳田を理解することがロマン主義的な起源論や固有信仰論のような本質論への柄谷の節度となっていた。
しかし、「災厄後」の柄谷の中では大きく変化する。
「実験」の語から柳田の方法を説明する手続きは同じだが、例えば「空間的な調査と比較を通して歴史的に遡行する」方法に日本列島がふさわしい理由をこう記す。
日本列島に後期旧石器時代人が渡来したのは、およそ三万年前だと考えられています。地球が寒冷化した時期で、北で宗谷海峡と津軽海峡、南で対馬海峡がほぼ陸化したので歩いてやってきたのでしょう。温暖化以後は、中国大陸、東南アジアから「海上の道」を通って、つぎつぎに渡来した。日本列島はハワイ諸島と同様、その先に進めないので、そこに人々が累積し混合していった。そしての跡がさまざまな形で残ったわけです。言語にもそれが残っている。これらの形跡には、日本人というより現生人類の歴史が刻印されているといえます。
(柄谷行人『世界史の実験』2019年、岩波書店)
初期柳田論では室町としていた遡及の限界はどこかにいってしまい、「日本人というより現生人類の歴史」がその射程に入ってしまう。人類学的ともいえる理系の記述だが、しかしそれはロマン主義に理系的記述を試みる柳田のあり方とどう違うのか。しかもその中で不用意に「海上の道」論を組み込んでしまう。
そして、もう一つの柄谷の大きな変化が「固有信仰」への強い傾斜である。
柄谷は『世界史の実験』の中で柳田は1930年代に「実験の史学」を断念した、と新たに記す。しかしこれは妥当ではない。戦時下の柳田が写真や文化映画への接近でむしろ「実験の史学」の方法を先鋭化させようとしていたことは既に見た。橋浦泰雄や、中野重治、石田英一郎ら転向マルクス主義者等をそのような先鋭化の対話場所にあたかもボディーガードの如く連れていく(しかし彼らは大抵発言はしない)姿は興味深い。『炭焼日記』も村治夫の出入りが確認できる。文化映画との交流も接続しているのだ。
そして柄谷は柳田が「実験の史学」を断念して書いたのが『先祖の話』だとする。しかし同書で柳田は民俗文化の偏差の時間軸への変換という手法は一貫して用いている。『先祖の話』に問題があるとすると「実験の史学」の手法の対象がその手法のロマン主義的な偏向をし「先祖」という起源に向かっていたからである。その結果「固有信仰」が導き出される。
柄谷は国家神道ではなく「小さな村の氏神・先祖神」に柳田の「神道」、つまり「固有信仰」を見出し「民俗学はそれを明らかにするために不可欠」なものと定義する。
そしてその「固有信仰」をこう具体的に記す。
柳田がいう固有信仰とは、簡単にいうと、つぎのようなものです。人は死ぬと御霊になりますが、死んで間もない時は、「荒みたま」である。子孫の供養や紀りをうけて浄化されて、御霊となる。それは一定の時間が経つと、一つの御霊に融けこむ。それが神(氏神)です。氏神すなわち祖霊は、故郷の村里をのぞむ山の高みに昇って、子孫の家の繁盛を見守ります。生と死の二つの世界の往来は自由です。祖霊は、盆や正月などにその家に招かれ共食し交流する存在となる。現世に生まれ変わってくることもあります。
(『世界史の実験』)
つまり文化の偏差から抽出されるある種の形式性を広く言っているとしていた柄谷の初期柳田論に於ける「固有信仰」の理解は、震災後は「先祖」の問題に収斂されてしまう。
しかし、そもそもこの国に柄谷が柳田から読みとった「先祖」に対しての「固有信仰」がどこまであったのか。ここで深入りしないが、柄谷が無批判に引用する「固有信仰」の言説の来歴には慎重さが必要だ。死者の霊は最終的には集合的祖霊に回収されるという祖霊観、そう解釈し得る仏事で年忌などがないわけではないが、このような主張は近代の西欧の日本人論によってもたらされたものでもある。東に向かうにつれて進化論的に退化し、個人の魂は集合化していくと説いたパーシヴァル・ローエルや、死者の魂の集合化と転生を説くラフカディオ・ハーンの日本人論といった明治期に成立した日本人論の俗説的な枠組と『先祖の話』の理論フレームの類似を踏まえ、もう少しこの種の「固有信仰」論は冷静であっていい。ましてハーンが『先祖の話』が書かれた十五年戦争下、いかに読まれたかは注意が必要である。
そして『先祖の話』と「震災」後の柄谷の思考が最終的に重なり合うのは「無意識」の召喚である。柳田は『先祖の話』で「無意識の伝承」を設けて「固有信仰」の所在の根拠をこう記す。
盆の祭は仏法の感化によって、明らかに変形しているのであるが、それが現在もなお盛んでありまた複雑になった御蔭に、古い習わしの若干はまだその間に保存せられている。我々が書物の通説と学者の放送をさし置いて、是非ともまず年寄や女児供の中に伝わるものを求めようとするのも、尋ねるのが痕跡であり、また無意識の伝承だからである。
(柳田國男『先祖の話』1946年、筑摩書房)
柄谷は柳田の子供論に引きずられ、その無意識に「固有信仰」がユング派の元型の如く眠っているとさえ言いた気だが、ここから「憲法九条」を「無意識」と言い出した時点まではそう遠くない。
柄谷は柳田が枢密院で新憲法の成立に関与したことに言及し、彼は「新憲法」制定で「戦争における死者を念頭においてい」た、とする。それは『先祖の話』が戦死者を思い書かれたからだと言い、つまり、ここが問題なのだが『先祖の話』の戦死者と、東日本震災の死者は柄谷の中でリンクするのである。
柄谷が理解したような、『先祖の話』に於ける死者の所在を以てそれを戦後思想としての柳田の主権者教育とも結びつけ、そこに「死者」を介した社会設計や民主主義の可能性を見る向きがある。しかし、『先祖の話』に致命的に欠けているのは言うまでもなく「死者」が「日本」限定の死者であり、しかも「国のために戦って死んだ若人」に更に限定される、ということだ。だから柄谷は柳田に感応して死者を召喚して、「歴史」を見失っているとぼくには思える。
『先祖の話』は祖霊信仰論としては「実験の史学」の範囲にあるが、しかし「死者」に関わる部分だけそこから逸脱している。『先祖の話』を書いた時期の『炭焼日記』には折口信夫が藤井春洋のことで訪ねてくる。戦死した若者を血縁でない折口が祀る、という『先祖の話』の如き光景は事実として柳田の前にあった。あるいは柳田の折口への私的な慰撫がそこにあるのかもしれない。
しかし、この国の起こした戦争での死者はアジア太平洋の諸地域に及び、外地・内地で民間人の死者も多く出した。そのような狭い「死者」への追悼からなる『先祖の話』を東日本震災の「死者」への「気持ち」を以て「九条」に繋ぐことは苦しい。論理でなく情緒で、殆ど祈りのように繋ぐ。だが、そこにあるのは、歴史でなく信仰ではないのか。そしてそれは、交換様式「X」の分かりにくさと関わってこないか。柄谷は「X」を「人間の意志を超えた」何かでそれは、原始キリスト教や原始仏教の中に萌芽がある、ともいう。この「X」に至る手だけとして「意識的に交換様式A」を追求することをあげる。「実践としてのA」の一つがアソシエーション、つまり柄谷が柳田の農政学などに見出しもした協同的な運動(取り方によっては「公民の民俗学」ではないか)であり、それによって、その「X」を待ち続けることが、できることだという。
しかし、それは殆ど偽史的な予言ではないか。ユートピアやカーゴの到来を信仰することではないか。
柄谷は『先祖の話』を九条に絡め同書を未来に向けた書とするが、それはあくまでも戦後に書かれた序文に準拠している。『先祖の話』本編では柳田は「歴史」を見失い「山人」でなく「先祖」を想像してしまっている。つまり「X」とは「先祖」であり「固有信仰」である。それは死者との交換様式でありアソシエーションである。少なくとも『先祖の話』を柄谷は、そう理解している。
「災厄」に於ける「死者」への「気持」を出発点とする思想は情緒的に人の心をうつ。だがその結果、「固有信仰」や「先祖」という不合理な領域が頭をもたげるのは気になる。それを柄谷の思考の、ヒューマニティの発露ととるのか、その文明史に存在し得ない領域を召喚するリスクを危惧するべきなのか。いずれにせよ、柄谷と柳田では「災厄後の思想」が向かう先が正反対である。柄谷の後期柳田論や「X」は、繰り返すが歴史的見通しでなく、「祈り」である。その意味で「文学」なのだろう。
最後に柳田國男に戻る。
では「実験の史学」とはそもそも何なのか。それはどのような可能性を持つのか。
指摘しておきたいのは「偏差」の比較による「実験の史学」は恐らく三つある、ということだ。
一つは起源論として「過去」へと時間を遡行するもの。
二つめはその遡行の先を無意識に見出し「固有信仰」を仮説してしまうもの。
いずれもロマン主義的なものである。
対して三つめはその「偏差」そのものを空間的にせよ時間的にせよ「実験」する「史学」である。
前回、見たように、柳田は三木茂らとのやりとりの中で「写真」や「映画」について映し出された偏差をその当事者が受けとめることを想定する。
三木さんの話はあとで願ふことにして先にプリンシブルな話をしたい。
(柳田國男、津村秀夫、三木茂、村治夫、橋浦康夫「柳田國男氏を圍んで 文化映畫と民俗學」『新映画』1941年3月号、映画出版社)
去年十二月に大阪に行つた時、偶然宝塚に行つて、実家からバスが出てゐるが、有馬に行つた。あの附近の稻の乾し方が奇拔なんです。(中略)それ一つだけ見せたのではあすこらの人でも面白がらない。ほかの人でもさうだし、それから考へると、稻を刈つて乾燥させる樣式といふのは、私の知つて居るだけでも、少くとも十以上はある。(中略)あれを全國的に種類を分けて列べて、稻の乾し方──何んといふ題名がいゝか、それは別として──それで越後はこう、京都府の山の中はこう、九州の佐賀縣の山の中はこう、海岸はこうといつたやうな形を見せる。それを一番喜ぶのは稻を掛けて居る農民です。
つまり、ここでは「起源」も「固有」も問題でなく、多様な偏差の中に自身の事例を配置することを「比較」の目的とするものだと読み取れる。そして偏差を仮に時間軸に変換して示しても、そこには「起源」でなく「変遷」の過程に位置する自身こそが見出せる。
文化映画や写真は第三者的にそれを提供するが、自身がその一葉の写真の撮影者になるという「観察」を以て「偏差」のデータベース構築に参画し、そして多様性の中の「私」の「いま」「ここ」を「実験」することが「実験の史学」の第三の方法としてある。
敗戦直前の柳田は偽史運動家を出入りさせ、『先祖の話』という死者をロマン主義的に書き「歴史」を見失いかけもするが、その「実験の史学」の方法は精緻化し、それが、戦後の仕事へと接続していく様はもう少し細かな説明が必要ではある。
そして柳田の「戦後」の仕事として、社会科の教科書づくりがある。それは自分の家から生活圏、日本、世界へと同心円的に世界を拡張していくものだ。その「偏差」とそれを越境していく世界=歴史認識をここが持つことを「史心」と柳田は読んだが、それは主権者が「実験の史学」を「実装」した姿なのである。
* * *
本連載は不定期連載です。
この続きは、次回の更新をお待ちください。
筆者について
おおつか・えいじ。国際日本文化研究センター教授。まんが原作者。
著書に『手塚治虫と戦時下メディア理論 文化工作・記録映画・機械芸術』(星海社、2018年)、『大政翼賛会のメディアミックス『翼賛一家』と参加するファシズム』(平凡社、2018年)、『大東亜共栄圏のクールジャパン「協働」する文化工作』(集英社新書、2022年)、『「暮し」のファシズム ――戦争は「新しい生活様式」の顔をしてやってきた』(筑摩選書、2021年)、『シン・論 おたくとアヴァンギャルド』(太田出版、2022年)、『木島日記 うつろ舟』『北神伝綺』『北神伝綺 妹の力』(いずれも星海社、2022年)など。
現在の研究テーマは戦時下のメディア理論と文化工作。