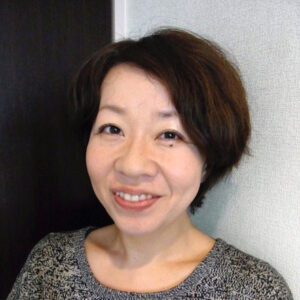日本の女性と家族、仕事と恋愛、幸せのかたちを描いてきたNHK「連続テレビ小説」(通称「朝ドラ」)。1961年度の誕生からこれまで、お茶の間の朝を彩ってきた数々の作品が、愛され、語られ、続いてきたのには理由がある。はたして「朝ドラっぽい」とは何なのか?
『大切なことはみんな朝ドラが教えてくれた』(太田出版刊)では、エンタメライターで「朝ドラコラム」の著者・田幸和歌子が、制作者のインタビューも踏まえて朝ドラの魅力に迫っています。
ここでは、その一部を特別に紹介していきます。(第3回目/全6回)
約50年もの間、数々の女性の「恋」も「愛」も「結婚」も描いてきた朝ドラ。親が決めた許嫁などを除き、その恋愛パターンには大きく分けて、以下のふたつのタイプがあると思う。
1、最初から思い合う「運命」のふたりに、障害が立ちはだかる。
2、第一印象は最悪だったふたりが、ケンカ友達から、恋に発展する。
少女マンガの恋愛パターンと非常に似通っているが、朝ドラにおいては圧倒的に多いのは2のほうだろう。
『澪つくし』などに見る、最初から思い合うふたりに障害が降りかかるパターン
1のパターンの代表作としては、朝ドラ史上最初で最高、かつおそらく最後の「恋愛ドラマ」が、最高視聴率55・3%(平均視聴率44・3%)を記録した沢口靖子主演の『澪つくし』(1985年)である。
ときは、大正末期から終戦後までの激動の時代。“陸者”と“海者”が対立する千葉の漁港・銚子を舞台に、しょう油醸造を行う旧家・坂東家(入兆)の妾の娘と、網本の長男が出会い、恋に落ちる。だが、双方の間には反目し合う「家」という大きな壁が立ちはだかる……というもの。
ストーリーは、ベタな昼メロ路線であり、和風『ロミオとジュリエット』でもある。朝ドラでここまで「恋愛」をど真ん中に据えて描いたのも珍しかったし、気恥ずかしさやテレ隠しなどなく、真正面から真剣に描いたことも新鮮だった。しかも、これを書いたのが、あのジェームス三木だということも、今思うと、興味深い。
ふたりの恋は、浜辺で絵のモデルをしていたヒロイン・かをる(沢口靖子)が、偶然通りかかった漁師の惣吉(川野太郎)に、指にささったトゲを抜いてもらい(口で!)、トキメキを覚えるというところから始まる。ふたりが恋仲になってからは、観ているこちらが恥ずかしくなるほどイチャイチャだった記憶もある。
だが、かをるが正式に実子として認知されてからが大変で、「行儀見習い」という名目で、女中頭(根岸季衣)に厳しくあたられ「女中同然」に扱われるという苦労話は、日本人好み。また、家同士の確執に対して、小細工なしにかをるの父に真正面から結婚を申し込みに行くが、大反対されて会ってもらえず、毎日毎日門の前に立つという惣吉の純朴さも、やっぱり日本人好みだろう。
後に、かをるの父の「勘当する」という計らいによって、ようやく結ばれたふたりだったが、波瀾万丈の人生が始まるのはこれから。新婚まもなく、夫・惣吉が遭難&生死不明→ショックで流産した後、父の勧めによって入兆の手代・梅木(柴田恭平)と再婚→死んだはずの先夫・惣吉が記憶喪失となって戻ってきて、夫・梅木が荒れ……と、ドロドロの展開であった。
ちなみに、『おはなはん』の高橋幸治と同様に(詳細は第5章「朝ドラのはじまり」参照)、一度死んだはずの惣吉の復活も、視聴者からの助命嘆願があったからだということが良く知られている。
『澪つくし』の場合、思い合うふたりの最大の障害は「家」「父親」であった。とはいえ、父親も、決して「悪役」ではない。結婚に反対していたものの、最終的に「娘の勘当」というかたちでふたりを結婚させるのも、父親である。
個人の小さな事情ではなく、悪役はもっと大きな「時代」や「社会」「古いしきたり」として描かれている。現代人には到底わからない感覚「女性は家長に従うのが当たり前」「親が結婚相手を決める」という「時代」が目の前に立ちはだかることで、視聴者たちはヒロインやその相手と同じく理不尽な思いになり、ふたりを応援してしまっていたのだろう。また、最初に登場した沢口靖子が、あまりにも演技が下手だったという衝撃と、ドラマ内でどんどんうまくなっていくという事実に対して、当時まだ小学6年生だった自分なりに「見守っていく」「応援してしまう」気持ちも芽生えた。私の父親がとにかくヒロイン・沢口靖子について「可愛い」「下手だ」の二言ばかりを繰り返していたのも、懐かしい。
ヒロインの再婚相手・梅木の“小物”感も、忘れられない。惣吉が戻った後、「大丈夫、あなたを愛しているから」とかをるに言われても、決してその言葉を信じることができずに、嫉妬心をむき出しにしまくる様は、子ども心にも「ドン引き」だった。当時、友人たちとの間で「梅木がいかに情けない男か」という話をした記憶もある。また、最初は「かをるさん」と呼んでいたのに、夫婦になってからの「お前」呼ばわりにもカチンときた。一方、惣吉を好きな気持ちは変わっていないが、このままではどちらも幸せになれないことから「嫌がらせはやめて、早く結婚して」と、かをるが惣吉に告げる場面には、切なさも感じた。
だが、本当はどうだったのだろう。『澪つくし』は2004年にBSで再放送されたが、大人になって改めて考えてみると、梅木は決して悪いヤツじゃない気がする。惣吉さえ戻ってこなければ、梅木は優しく良き仕事のパートナーであり続け、子どももいるし、普通の幸せな人生が送れたのではないか……と。
一方で、父親の勧めとはいえ、惣吉が遭難し、事故死とされてからほどなく「再婚」してしまった「かをる」は、実は「純愛」じゃないとも思う。純愛はむしろ、大反対を乗り越えて結ばれ、奇跡の帰還を遂げたにもかかわらず、すでに妻(かをる)があっさり再婚し、子どもまで作っていて、しかも少々自分をうっとうしがるような態度を見せ、しまいには「恋愛」よりも「しょう油醸造」のほうに夢中になってしまっていてすら、ただひたすらに「かをる」を思い続け、独身のままだった惣吉のほうではないか。また、嫉妬に苦しみながらも最終的にイイ人として死んでいく梅木もまた、純愛の人だったろう。
紆余曲折を経て、最終的には、かをると惣吉が結ばれることを匂わせるラストだったが、大人になって見てみると、「女のしたたかさ」と「男の純愛」ばかりが際立って感じられるのは不思議である。
1のパターンでは他に、初恋相手との運命的な再会の後婚約するが、彼が暴漢に襲われてしまい、帰らぬ人となってしまうという悲恋が途中で描かれた『すずらん』(1991年)もある。だが、忘れてはいけないのが、鈴木京香主演の『君の名は』(1991年)だろう。
昭和20年、東京大空襲下に出会った真知子と春樹(倉田てつを)。焼夷弾が降り注ぐ中、助け合いながら逃げ、命からがら辿り着いた数寄屋橋で、お互いの名前も知らないまま「生きていたら半年後、それがダメならまた半年後に会おう」と誓うが、運命に翻弄され、「会えそうで会えない」状態が繰り返されていく。
『君の名は』は、1952年にラジオドラマで放送された際には、あまりの人気ぶりに「番組が始まる時間になると、銭湯の女湯から人が消える」とも言われたほどの作品だ。
それなのに……1991年という時代の「朝ドラ」という枠でのこのドラマは、鳴り物入りで、1年ものとして始まったにもかかわらず、視聴率低迷、脚本家の途中降板など、大苦戦を強いられたのである。いったいなぜだったのか。
『週刊文春』(1991年4月25日号)では「視聴率上らず、NHK幹部も真っ青『君の名は』はナゼつまらないか」という記事を掲載している。以下に一部を引用したい。
元NHKチーフ・ディレクターで演出家の和田勉氏は、真知子と春樹、二人の主役にふれて、
「鈴木京香クンは、何といっても体がデカすぎる。あの大きさは、とても食うもののなかった昭和二十年なんてものじゃない。倉田てつをクンは、まったく明るすぎる。
『週刊文春』(1991年4月25日号)
このご両人が八年もスレ違うとは、まったくアタマがカラッポとしか思えない。この現代っ子の二人だったら、八日もあれば充分出会える、とつい思ってしまう。それくらい、ドラマの内容と主人公二人のイメージが合わないね。ガンバレヨーッ、と言いたいところだが、多分ムリです」(中略)
「そもそも素材が悪い」と決定的なパンチを浴びせたのは、放送評論家の佐怒賀三夫氏。
「冷静に見ると、これほどドラマの体をなしていない不出来なドラマはありません。ストーリーも何もなくて、シチュエーションを変えて、主人公の二人がただスレ違うだけ。それでも当時の日本人に受けたのは、視聴者の戦争体験とストーリーがシンクロして、ドラマを作っていたからです」
ちなみに、『ミセス』(1992年8月号)において、『いちばん太鼓』『青春家族』『君の名は』の脚本家・井沢満は次のように語っている。
テレビ小説を支えているのは、三十五歳前後の主婦をピークとして、後は老年期の男女である。「いちばん太鼓」もそうだったが、男を主役にしたテレビ小説が今ひとつ人気を得られないのは、視聴者がヒロインに感情移入して観ることができないからである。物語として良く出来ていても、観ている女性が自分を投影できない主人公では受け容れられないようである。テレビ小説は“生活の一部”として観られるのだ。
『ミセス』(1992年8月号)
「君の名は」の意外な不評も、真知子という女性像に自分を託すことが難しかったせいではなかろうか。ただ待つ、耐えるだけのヒロイン像は端的にもう旧い、のだ。
当時はまだ携帯電話などない時代。今よりはずっと「すれ違いで、会えない」という状況にリアリティがまだ存在していたはずだ。にもかかわらず、ふたりの「会えそうで会えない」繰り返しは、当時中学生だった自分にはどこかしら「志村、後ろ後ろ!(振り向くといない、の繰り返し)」のドリフのコントのように見えてしまっていた。また、真知子の「○○ですわ」「△△あそばして」といったお嬢様言葉も、ギャグのように空々しく聞こえてならなかった。
ちなみに、『君の名は』放送年の1991年というと、フジテレビでは大人気だったドラマ『東京ラブストーリー』が放送された年。奔放に見えるヒロイン・赤名リカ(鈴木保奈美)が、恋人・カンチの心の中に別の誰かがいることを感じ、「私だけを見てて!」と叫ぶ「純愛」に視聴者たちが共感し、涙した時代だ。「隣にいるのに、通じ合わない心」に共感する時代に、「名前も知らない相手を思い続ける」とか「会える手段がない」という感覚はやはりピンとこなかったのかもしれない。
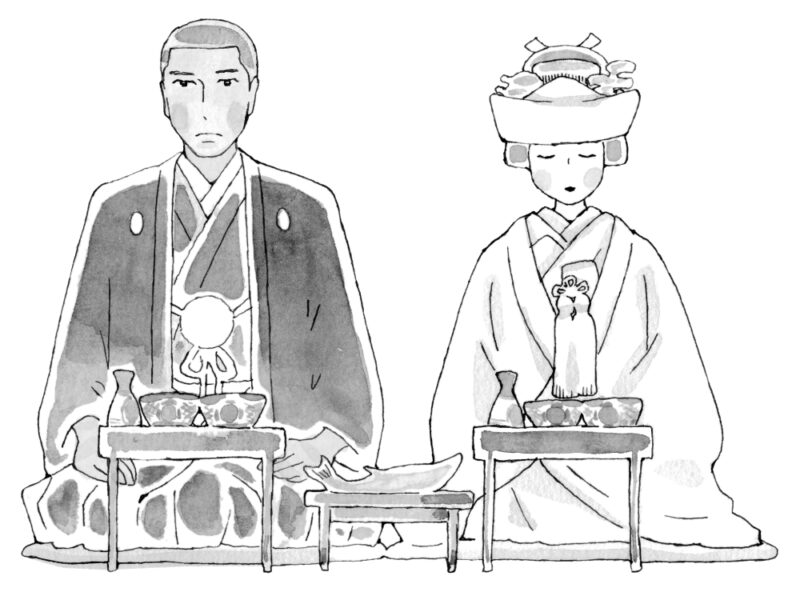
* * *
※この続きは、本書『大切なことはみんな朝ドラが教えてくれた』(田幸和歌子・著)にてお読みいただけます。
※本書では、他にも最高視聴率62.9%の”お化け番組”『おしん』の大ブームや、『ゲゲゲの女房』で挑んだ大変革、朝ドラの「職業」の変遷、新人女優の”登竜門”ヒロインオーディションについてなどを朝ドラの人気を紐解くエピソードを多数収録しています。『大切なことはみんな朝ドラが教えてくれた』(田幸和歌子・著)は、各書店・電子書籍配信先にて大好評発売中です!
筆者について
たこう・わかこ 1973年長野県生まれ。出版社、広告制作会社を経て、フリーランスのライターに。『日経XWoman ARIA』『通販生活web』でのテレビコラム連載のほか、web媒体などでのドラマコラム・レビュー執筆や、週刊誌・月刊誌での著名人インタビュー多数。エンタメ分野のYahoo!ニュース個人オーサー、公式コメンテーター。
かり・すまこ。福岡県出身。1994年に『SWAYIN' IN THE AIR』(「蘭丸」/太田出版)にてデビュー。BLから青年誌、女性誌まで幅広く活躍し、読者の熱い支持を集め続けている。2006年に『ファミリーレストラン』(太田出版)が映像化。2020年、『あした死ぬには、』が第23回文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞を受賞。『幾百星霜』(太田出版)、『どいつもこいつも』(白泉社)、『感覚・ソーダファウンテン』(講談社)、『うそつきあくま』(祥伝社)、『ロジックツリー』(新書館)など、著書多数。