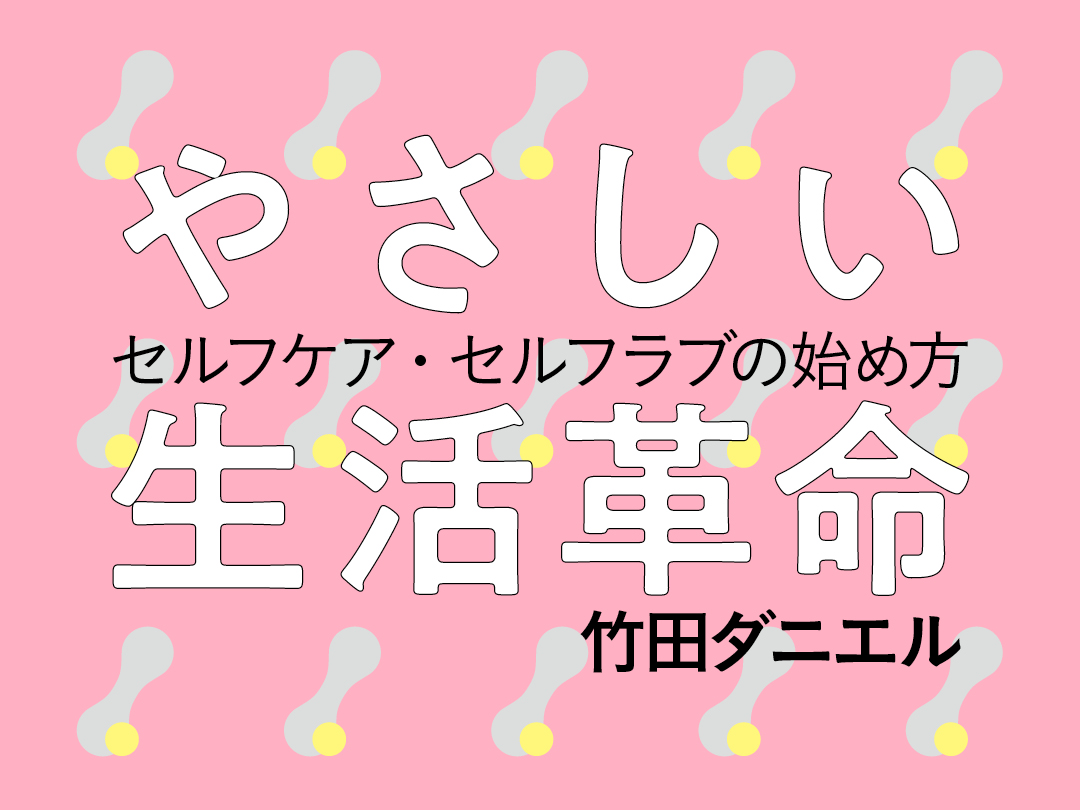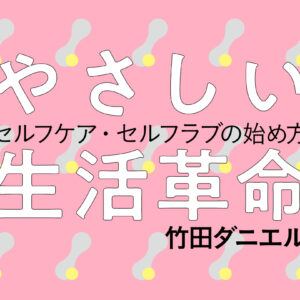「カルチャー ×アイデンティティ×社会」をテーマに執筆し、デビュー作『世界と私のA to Z』が増刷を重ね、新刊『#Z世代的価値観』も好調の、カリフォルニア出身&在住ライター・竹田ダニエルさんの新連載がついにOHTABOOKSTANDに登場。いま米国のZ世代が過酷な現代社会を生き抜く「抵抗運動」として注目され、日本にも広がりつつある新しい価値観「セルフケア・セルフラブ」について語ります。本当に「自分を愛する」とはいったいどういうことなのでしょうか?
第8回は、アメリカの学生たちが親パレスチナ運動において実践する「ラディカルなセルフケア」について。
4月17日に開始したコロンビア大学でのパレスチナ支援を表明するキャンパスプロテストを皮切りに、アメリカ全国、さらに世界中で学生らによる抗議運動が広まった。大学に対する彼らの主張は、「イスラエルのガザ戦争から利益を得ている企業からの資産売却。大学の投資に関する財務の透明性を高め、イスラエルの大学やプログラムとの学術的な関係や協力関係を断ち切る。 ガザでの完全停戦も求める」ものだ。
抗議デモに対して大学側が動員した警察官による暴力的な制圧などが、日本でも話題になった。しかし、注目されたのはネガティブなことばかりではない。ガザをはじめ世界中で起きている残忍な事実から目を背けさせられる資本主義・個人主義社会の価値観に抵抗し、間違っていると声を上げ、文字通り体を張る学生たちに勇気づけられ、未来に対してわずかにでも希望を抱いた人も多いだろう。遠い国で起きていることと自分たちが今生きている世界は確実に繋がっていて、影響を与え合っていること、そして自分たちの行動によって未来をより良い方向に変えることができるという「思いやり」の表れが、今のアメリカ社会では衝撃をもって受け止められた
実際にキャンパスで起こっていること
私は、カリフォルニア大学バークレー校とスタンフォード大学でのキャンププロテストの様子を取材した。どの現場でも特徴的だったのが、「コミュニティ意識」だ。人が道端で倒れていようが、地域の子どもがホームレスで食事に飢えていようが、「見てみぬふり」することが当たり前になってしまっているアメリカにおいて、学生たちが自らキャンプ場を設立し、みんなで「学べる場所」や「無料で食事ができる場所」、「支え合いができる場所」を作っていたことが、まさに帝国主義的なアメリカ社会のアンチテーゼのように思えた。
パレスチナの人々を抑圧するアメリカの政治システムは、アメリカ国内の弱者を抑圧するシステムと同一の問題を根底に抱えていることを指摘する抗議者たちは、そのような「排除」と「抑圧」の構造を否定し、寄付などで寄せ集めた食事やリソースを、必要な人たちに無償で提供した。これこそが「自分のため」だけではなく、「コミュニティのため」のケアなのだ。
他にも、例えばハラールやコーシャーなど、特定の宗教に配慮した食事を必要とする学生のために別途常備したり、食物アレルギーのある人のために全員が気をつけることをルールとして徹底したり、一見当たり前のように見える「ささやかな思いやり」も、あえて明言化し「大切に守るべき事項」として徹底することで、参加者の安全と安心を守ろうとした。TikTokでは、コロンビア大学をはじめとしたプロテストキャンプで、ピースフルに読書や勉強をする学生の姿を映した動画が多くの視聴回数を得た。競争社会において、学生たちが芝生で共に生活をし、ゲスト講師や「ティーチ・イン」などを通して学び合いをする様子は、イスラエルや軍事産業に投資をする「資本家」の役割が大きく浮き彫りになってしまった大学に対する「オルタナティブ」な学びの場を意味する。
学生たちが芝生で腕を組み合い、円になって座り込み、武装した多くの警察官に囲まれる映像を見かけた人も多いのではないだろうか。そこから見えるのは、「最後まで責任を持ってお互いを守る」姿である。数々の親パレスチナ運動、特に大学キャンパスで起きたものでは、多くの参加者マスクをしているというのが特徴的だった。日本にいると、コロナ以前からマスクをすることはノーマライズされており異様なことではないが、マスクの着用が一般的に定着していないアメリカ、特に南部の保守的な州では、マスクをしている人は「政治的」な意味合いを付与されてしまう。例えばノース・カロライナ州ではマスク(顔を隠すもの)を禁止する法案を提出しようという動きも出ており、まだ消えたわけではないコロナウィルス対策に対する公共衛生上の問題が懸念される。マスクをスティグマ化することによって危険に晒されるのは、免疫疾患を持つ人をはじめ、病気にかかりやすい人や気軽に病院に行けない事情がある人たちなど、社会的に弱い立場に置かれている人たちだ。そのような人たちを守るためにも、そして監視社会における個人の特定を避け、自由な言論活動を保障するためにも、多くのキャンパスでマスク着用の推奨が行われ、「可視化されるケアの形」として話題になった。学生たちの「protect eachother(お互いを守れ)」というキャッチフレーズのもと、全国で徹底されていた様々なルールには「様々な困難を抱えた人」への思いやりも含まれている。
カリフォルニア大学ロサンゼルス校やバークレー校では、お祈りするムスリム系の学生たちが撮影されないように、他の学生たちが周囲に立って壁を作り、プライバシーを守っている動画が話題になった。オハイオ州立大学では警察がお祈り中の学生たちを排除しようと取り掛かると、”Let them pray(祈らせてあげろ)”のコールが抗議者たちから上がった。警察官たちは、公共の場でお祈りしている学生たちを「不法侵入」の容疑で逮捕して連行していたのだ。他にも、逮捕者を乗せたバスを運転できないよう、プロテスト参加者たちは交通を止めたり、バスの前に居座るなどのエスカレート的なアクションも取った。この連載でも「若者の連帯と愛」を強調してきたが、これこそが宗教や人種、バックグラウンドを超えた、「ラディカルなケア」の表れの一つだ。
Z世代は甘やかされている?
今のアメリカで、若者でいることは疲れる。相次ぐ学校銃撃事件によって同世代が教室で射殺される一方、大人たちは「自衛のために」もっと銃を持てと主張し、銃規制の議論が進む気配もない。同世代が大量虐殺を止めようと訴えると、大人たちはその声を制圧するために、学生たちをさらなる警察の手による暴力に晒す。
しかしそれでも、学生たちは圧倒的多数派で銃を持った警察官たちに正面から立ち向かい、“You don’t scare us(お前らなんか怖くない)”と学生たちはコールする。彼らのキャンパスで言論の自由と抗議の自由が弾圧され、彼らが支払う学費で武器開発会社への投資に使われ続ける。国家、大学、イスラエルへの批判がこのように暴力的に抑圧され、それに対抗して最前列で戦っているのが若者たちだ。持続可能な社会を目指して「戦う」ために必要なセルフケア・セルフラブについては、この連載でも継続して触れてきたトピックだが、「自分のことに集中する」という「自分」のみに集約されるケアだけでは、コミュニティ単位での変革は起こせない。
抗議している学生たちの多くはZ世代だ。ミレニアル世代に続き、Z世代は「脆弱でワガママな世代」と上の世代の人々に頻繁に形容されてきた。人種差別や人権問題に対して敏感で、世界に蔓延する不公平・不平等を受け入れない姿勢を、「弱々しい」「文句ばかり言っている」と言う、いわゆる「マッチョ」な価値観の年長者は多い。日本でも似た現象は起きているが、今回のキャンパスでの抗議運動を見て、果たして同じことが言えるだろうか。彼らはただの理想として「戦争反対」を主張しているわけではない。自分たちが生きている間に自由なパレスチナを実現させたい、きっとできる、そんな希望にしがみついて、命懸けで抗議を続けているのだ。この姿勢は、パレスチナ問題に対してだけではなく、中絶の権利や人種差別問題に対しても共通している。要は抑圧や搾取に成り立つ世界の中では絶対に生きたくない、という強い意志の表れなのだ。
一方、レガシーメディアと呼ばれる、かつては「信頼できるメディア」だったテレビや新聞の偏向報道やイスラエル・アメリカ側にとって都合の良いプロパガンダの流布も問題になっている。コロンビア大学が警察によって制圧された際には、CNNではアンダーソン・クーパーが根拠に一切基づかない(根拠を説明しない)、「外部参加者によってホールが占拠されている」と報道をしたことなどが問題になった。しかし、コロンビア大学の学生たちによって運営されているラジオの生中継では、学生ジャーナリストたちが抗議者の声を取り上げ、どのような学生が建物の中に立てこもっているのか、どのような意図を持って抗議をしているのか、何を成し遂げたいのか、当事者の視点に立って報じた。一連の学生プロテストを最も正確に報道しているのは「共感」と「理解」を持った学生レポーターであること。そしてまさにこの「世代間」の理解の齟齬、若者たちが起こすケアの革命を「意味のない戯言」のように矮小化しようとするメディアの姿勢も浮き彫りになった。
アメリカのZ世代の絶望や価値観について当事者として書き続けている中で、「そんなの西海岸のリベラル金持ちだけだろ」と冷笑されたことは何度もあった。今回の全国での切実さや連帯感が浮き彫りになった学生運動を見てもなお、同じことが言えるだろうか。
次回の更新は、2024年7月10日(水)17時を予定しています。
筆者について
たけだ・だにえる 1997年生まれ、カリフォルニア州出身、在住。「カルチャー×アイデンティティ×社会」をテーマに執筆し、リアルな発言と視点が注目されるZ世代ライター・研究者。「音楽と社会」を結びつける活動を行い、日本と海外のアーティストを繋げるエージェントとしても活躍。著書に文芸誌「群像」での連載をまとめた『世界と私のA to Z』、『#Z世代的価値観』がある。現在も多くのメディアで執筆中。「Forbes」誌、「30 UNDER 30 JAPAN 2023」受賞。