岡本太郎にとって、縄文土器が突きつけるものこそ、現代芸術の課題であり、現代人の生の課題だった。
現代の精神の行き詰まりを突破し、日本の「繊弱な平面的な情緒主義」を突き破る根源的な力が、縄文土器にはある。
日本の伝統とは何か
岡本太郎が1952年に発表した「縄文土器論 四次元との対話」は、日本の縄文認識に大きな変容を迫った。まさに縄文観を一新した画期的な文章である。以下、この論考の内容を詳細に見ていきたい。
「縄文土器論」は、次のような文章で始まる。
縄文土器の荒々しい、不協和な形態、紋様に心構えなしにふれると、誰でもがドキッとする。なかんずく爛熱した中期の土器の凄まじさは言語に絶するのである。
激しく追いかぶさり重なり合って、隆起し、下降し、旋廻する隆線紋。これでもかこれでもかと執拗に迫る緊張感。しかも純粋に透った神経の鋭さ。常々芸術の本質として超自然的激超を主張する私でさえ、思わず叫びたくなる凄みである。
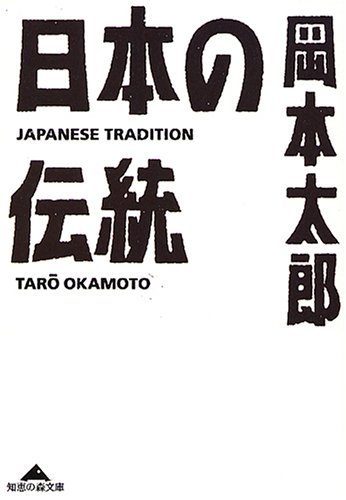
アヴァンギャルド芸術の旗手として戦後日本に衝撃を与えていた岡本は、縄文土器のなかに、「岡本太郎」を超える「凄まじさ」を見出した。土器の文様は、異様なほど隆起し、うねり、重なり合う。そこには執拗な緊張感がある一方で、透明な「神経の鋭さ」が現れている。「思わず叫びたくなる凄み」がある。
岡本は、日本の原点に強烈な「前衛」を見出し、心を湧き立たせた。そして、この地点から日本の伝統認識への再考を促す。
縄文土器の芸術性は「通常考えられている和かで優美な日本の伝統とは全く反対物である」。そのため「伝統愛好者や趣味人達」は、縄文土器を日本の伝統として受け入れることができない。伝統の異物として排除し、美術史のなかに正統な位置づけを与えようとしない。縄文人の美的感覚を自分たちの祖先のものとみなすことができなくなってしまっている。そこに「美の観念の拒絶がある」。
縄文式の重厚、複雑な、いやったらしい程逞しい美感が現代日本人の神経には到底たえられない、やりきれないという感じがする。そこで己の神経の範囲で遮断し、自動的に伝統の埒外に置いて考えるのである。
縄文式の重厚、複雑な、いやったらしい程逞しい美感が現代日本人の神経には到底たえられない、やりきれないという感じがする。そこで己の神経の範囲で遮断し、自動的に伝統の埒外に置いて考えるのである。
しかし、縄文を排斥する態度では、真の伝統への接近など叶わない。伝統は自己の外に鑑賞物として存在するのではなく、自己とのぶつかり合いの中で現れてくるものである。伝統とは「自己×過去」である。私たちは常に自己を通して過去に接触し、伝統と交わる。
伝統とは何らかの形に於てそれに己を賭すものであり、主体的にあるものである。だからこの場合自己は最も積極的な動機である。自己が先鋭化すればするほど却って断絶の相貌を呈し、そこに伝統はより激しく、豊かに弁証法的に受け継がれる。
岡本が批判するのは、「伝統という既成の観念によりかゝり、却って己を消し去る」人たちである。彼らは「不動不変の伝統という権威があるかのように振舞」い、伝統を「錦の御旗」として利用しているだけである。そして、そこから新しい動きを封じようとする反動的態度を示す。
しかし、真に伝統を推し進めるのは、伝統に対峙する人間である。「伝統というものは決して単純な過去ではなく、却って現在的なものである」。伝統は常に動いている。躍動している。「不動不変」の存在ではなく、「常に変貌し、瞬時も同一ではない」。だから伝統を掴むためには、動的に把握するしかない。今の私たちの問題として引き受け、前に進めなければならない。前衛的アプローチこそが、伝統を弁証法的に引き受け、その本質に接近する方法である。
岡本は、この観点から縄文土器との対峙を試みる。
あの原始的逞しさ、純粋さ、つまり人間に於ける根源的情熱を今日我々のものとして取り上げて、豪快、不敵な表情を持つ新しい伝統をうち建つべきである。それこそ日本に於けるアヴアンギャルドの大きな課題ではないであろうか。
岡本の眼には、日本の伝統とされてきたものが「全てがひどく卑弱であり、陰質である」ように映っていた。約10年にわたるパリ生活で触れたヨーロッパの伝統には強靭なものがあったが、日本の伝統は平板な情緒主義の現われとしか思えなかった。「我国の最大の古典と考えられている雄揮壮大な奈良の仏教美術」には「爛熱した大陸デカダンス文化の倨傲の気配」を感じ、「後味の悪さ」を覚えた。埴輪などに見られる「楽天的な美感」は、現代日本にも通じる形式主義に陥っており、「絶望した」。
ところが縄文土器にふれて、私の血の中の力がふき起こるのを覚えた。濶然と新しい伝統への視野がひらけ、我国の土壌の中にも掘り下げるべき文化の層が深みにひそんでいることを知ったのである。民族に対してのみではない。人間性への根源的な感動であり、信頼感であった。
では、縄文の精神に接近するためには、どうすればいいのか。考古学を学べばいいのか。それは「否」である。たしかに日本の考古学は「緻密さに於て世界に類例を見ない」。しかし、土器の細密な分類に終始しており、「ひろく文化的或は社会学的な見地から内容に喰い下がって行くという気構えに欠けている」。
縄文と交わるためには、「専門的な考証に捉われず、純粋に土器そのものにぶつかり、直観し、その内容を洞察しなければならない」。土器を通じて縄文の人たちの精神に触れ、そこで交わされた魂の衝突を、次の芸術に昇華しなければならない。
岡本太郎にとって縄文との対峙は、日本の伝統の再構成や日本美術史の書き直しが目的ではない。それは自己の創作上の切実な課題であり、芸術上の本質的問いそのものだった。
縄文 vs. 弥生
岡本の見るところ、縄文と弥生のあいだには決定的な断層があった。縄文は「超日本的相貌」を帯びているのに対し、弥生は平板な「『日本式』伝統」に陥っている。なぜ縄文の「激しく強靭な美感」や「逞しく漲ぎる生命感」が、唐突に絶えてしまったのか。そこに何があったのか。
岡本は、生産様式の変化に注目する。縄文は狩猟社会である。狩りは常に激しく、動的である。それは残忍な行為であり、つねに「追跡、躍進、闘争」がつきまとう。そのため「大猟」の際は「歓喜」に包まれ、祭礼が営まれる。「そこに絶えず動揺と神秘がひそ」んでいる。
それに対して、弥生は農耕社会である。人々は定住し、土着化する。すると、律義さと穏やかさが現れ、「安定と均衡、抑制と恭順、必然し依存の意識が世界観を支える」。
岡本が注目するのは、縄文人の空間認識である。そして20世紀アヴァンギャルドの姿勢と共通するものを見出す。
芸術史に於て彫刻は常に一定の空間を占める塊として扱われて来た。ところが、その外部であった空間を内に取り入れ、造型要素に転化せしめ、遂には空間そのものを彫刻化したのは20世紀のアヴァンギャルド、抽象主義彫刻家達の偉大な功績である。リプシッツ、ゴンザレス、ジャコメッティ等が見事に空間を構成して彫刻を新しい次元に飛躍させた。ところで縄文土器に於ける空間処理はこれらのアヴァンギャルド芸術に比して豪も劣らないばかりではなく、むしろ、より激しいのである。
岡本にとって、縄文土器は特異な空間認識に依拠した彫刻である。縄文人は自己の外部である空間を内側に取り込み、造形物に転化している。ジャコメッティをはじめとしたアヴァンギャルド芸術家が取り組んできた空間の彫刻化を、より鋭い感性によって成し遂げたのが縄文人であり、その結晶が縄文土器である。縄文こそが最も先鋭化した前衛である。
では、なぜ縄文人には、そのような空間把握が可能だったのか。それは、狩猟のあり方に根拠がある。
狩猟期に於ける感覚は極めて空間的に構成されている筈だ。獲物の気配を察知し、適確にその位置を掴むには極めて鋭敏な三次元的感覚を要するに違いない。更に捕らえる時は全身全霊が空間に躍動しなければならないのである。それによって生活する狩猟期の民族が、我々の想像を絶する鋭敏な空間感覚をそなえていたことは当然であり、それなしにはあのように適確、精緻な捉え方が出来る筈はない。
これに対し、弥生人たちの空間認識は「幾何学的」であり、「静的に平面化される」。これは水田耕作が広がったことによって平地の整備と区画化が進んだことに起因する。弥生人は二次元の感覚を高度に発展させていった。しかし、その一方で三次元の感覚が衰えていった。これに伴って、弥生式土器は平面的で「シンメトリカルな形式主義」に覆われることになった。この弥生以降の「伝統」が封建的農耕社会の特質と密着し、日本文化の特色とみなされてきたのである。
縄文土器——「アシンメトリー」と「不調和のバランス」
では、縄文土器の特徴はどこにあるのか。
岡本が注目したのは「隆線紋」である。紋様は、「激しく、純く、縦横に奔放に躍動し展開」しており、「もつれては解け、混沌に沈み、忽然と現れ、あらゆるアクシデントをくゞり抜けて、無限に回帰し逃れて行く」。
この「異様な衝動」は、何に起因するのか。それは、「到底信じることも出来ないようなアシンメトリー」にある。紋様は左右均整を大胆に否定し、「破調」を繰り返す。このダイナミズムが土器を躍動させ、一種異様なエネルギーを放出する。
そびえ立つような隆起がある。純く、肉太に走る隆線紋をたどりながら視線を移して行くと、それがぎりぎりっと舞上り渦巻く、突然降下し、右左にぬくぬく二度三度くねり、更に垂直に落下する。途端に、まるで思いもかけぬ角度で上向き、異様な弧を描きながら這い昇る。不均衡に高々と面をえぐり切り込んで、また平然ともとのコースに戻る。
いったい、このような反美学的な、無意味な、しかも観る者の意識を根底からすくい上げ顛動させるとてつもない美学が、世界の美術史を通じて嘗て見られたでろうか。
縄文土器は「非常なアシンメトリー、その逞しい不調和のバランス」によって特徴づけられる。この「破調」は、「力の躍動」を生み出すとともに、「強靭な均衡」を現出させている。激しくうごめきながら、全体としての平衡と均整を保っている。この矛盾的な同一性こそが、縄文土器の「美」に他ならない。
「四次元的性格」
では、なぜ縄文土器は「乱調」を帯びながら、崇高な均衡を保っているのか。
それは、この土器が「四次元的性格」を帯びていることによる。縄文土器は単なる三次元の立体として、彫刻的に鑑賞する美学的対象ではない。重要なのは「皮相な現実を超えた四次元的性格」を有していることである。「実はこゝに縄文土器の真の面目は躍如としているのである」。
岡本の見るところ、縄文土器は実用的なものであると同時に、呪術的なものである。狩猟生活と呪術は切っても切れない関係にあり、土器は儀礼で用いられたことが推察される。
全く偶然性に左右される狩猟生活は未開な心性に超自然的な意志の働きを確信させる。全てに霊があり、それが支配している。この見えない力に呼びかけるのが呪術である。
縄文土器の紋様は、単なる芸術ではない。当然のことながら、古代社会において芸術は芸術として独立していない。現代のような「芸術の為の芸術」など存在せず、「美学的意識」による制作など行われていない。土器の紋様は「強烈に宗教的、呪術的意味を帯びて居り、云いかえれば四次元を指向しているのである」。
岡本はここでフランスの哲学者レヴィ・ブリュールの「分有の法則」という概念を取り上げる。レヴィ・ブリュールは未開社会の思考様式に関心を抱き、そのあり方が近代社会と大きく異なることを論じた。レヴィ・ブリュールが重視したのは、未開社会における神秘的結合の様態で、ひとりの人間が、人間でありながら同時に他の動物(例えば鳥やカンガルー)とみなされることがある。このようなあり方を「分有の法則」と呼び、未開心性論を展開した。
岡本は、この「分有の法則」を縄文社会に投影し、「原始社会では可視の世界と不可視の世界とは、神秘的断絶なしに、端的につながっている」と論じる。縄文土器の紋様は、現代の私たちの眼には奇異なものに映る。しかし、縄文人にとって、それはとても具体的で現実的なものであったはずである。ただ、現代の私たちが、その神秘的結合の見失っているために、その具体性を理解できなくなっているのである。
だがそれらの激しい強靭な神秘的美感の根底にある精神的契機は、はっきり摘める。それは狩猟期の生き方そのものに内在する悲劇的な複合精神、アンビヴァランスである。
狩猟民族にとっては、獲物は同時に神聖な霊を持つ神である。それはまた激烈な闘争の相手であり、敵なのだ。ところが、彼らはそれを糧にして生きている。獲物の不在は直ちに生命の危機である。つまり彼らは常に、配すべからざる神を殺す。また配す故に、それは神性なのである。この矛盾律こそ彼らの生存の悲劇的な条件である。
縄文人にとって、宗教的儀礼と狩猟は切っても切れない関係にある。獣は人間を襲う「敵」でありながら、神聖な存在である。そこでは脅威の念が、そのまま神秘的な崇高と接続する。この「アンビヴァランス」こそが、宗教的儀礼につながり、縄文土器の「四次元的性格」を生み出している。
原始の逞しさ、豊かさは超自然的な世界との激しい現実的な考証の上に成立つ。自然と人間との、この生命のかねあいは動的であり、弁証法的である。あの怪奇で重厚な、苛烈極まる美観に秘められてあるものは、まさに四次元との対話なのである。
これに対して、現代人は四次元との対話を失っているように見える。超自然の世界との交流を喪失し、機械文明のなかで功利的に生きているように見える。しかし、そうではない。我々の世界にも「精霊」は存在する。人間の力を超えた現象が、現実的に我々に襲いかかり、生活のなかでの対応を迫られる。この四次元性に対して、芸術はそっぽを向いている。「芸術に無関係なように、切り離して考える処に今日の芸術の為の芸術の不幸がある」。芸術が単なる趣味や嗜好の対象となり、生の現実から乖離していることが問題である。そのような芸術は「マニファクチュア——時代の遺物」に他ならない。
今日、此ののっぴきならない現実の中で、芸術家意識を固持するあまりに精神主義に陥り、殆ど全ての芸術家たちが如何に戸迷い、それをひた隠し、非力を糊塗して過していることであろうか。この不可視であり、だが極めて現実的なるものに正面からぶつかり、己自身をひき裂かない限り、現実に対して、また芸術に於ても決定的に無力である。だが交渉を神秘化してはならない。それこそ堕落であり、退廃である。
以上、岡本太郎「縄文土器論 四次元との対話」『みづゑ』(美術出版社)1952年2月号
岡本にとって、縄文土器が突きつけるものこそ、現代芸術の課題であり、現代人の生の課題だった。
精神主義に陥らない精神のあり方とは何か。精神が観念的な功利性に回収されないためにはどうすればいいのか。精神は動的な現実性を回復することができるのか。
この現代の精神の行き詰まりを突破し、日本の「繊弱な平面的な情緒主義」を突き破る根源的な力が、縄文土器にはある。縄文土器が有する「無目的の目的、無意味の意味を我々の方法として掴み取らなければならない」。「これから芸術家は根源的生命力の叡知を以てこの袋小路をうち開き、真に現実的に世界を掴んでかからねばならない」。
掲載された写真
このような岡本太郎の論考は、これまでプリミティブな遺物として芸術的存在とみなされなかった縄文土器を、一気に日本美術史の原点へと押し上げた。この後、日本美術の全体像をとらえようとする議論は、縄文土器や土偶の存在を無視することができなくなった。
岡本の文章が大きなインパクトを与えたことは、疑いのない。しかし、この論考で見逃してはならないのが、写真の存在である。掲載された『みづゑ』は美術誌であり、誌面はヴィジュアルが重視された。そのため、縄文土器の写真が大々的に掲載され、これが大きな影響を与えたという側面がある。
この掲載写真について、岡本敏子は次のように回想している。
「縄文土器論」は一九五二年二月号の「みづゑ」に発表された。美術雑誌だから岡本太郎の素人写真というわけにはいかない。編集部は高名な写真家に依頼して、然るべき縄文土器をちゃんと撮ってもらった。ところがそれは、彼の気に入らないのである。全体のトーンがきれいでバランスのとれた、平らで安定した――それは縄文土器じゃない、と。もっと片っ方からライトを強くあてて、ディテールがとんでもいいから、ギリギリギリッと撮ってくれ。随分クレームをつけて、やっと、まだ不満ながらこの辺でという線におさまった。
岡本敏子『岡本太郎に乾杯』新潮社/1999年
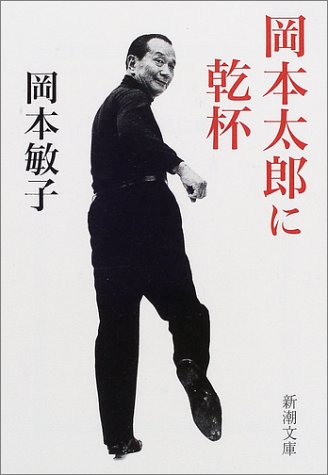
ここに映し出された縄文土器の写真は、考古学図鑑に掲載される標本的なものではない。背景は黒い画面で、強いライトによる影が、ディテールを覆い隠している。特定の細部が強調される一方で、別の細部は影の中に沈む。しかし、それによって「隆線紋」は生命を帯び、おどろおどろしく躍動する。今福龍太が的確に指摘するように、「縄文土器は、図像表現としてはじめて、岡本の論考と図版によって、モノとしての新たな形態的次元を開示した」のである。[今福2006]
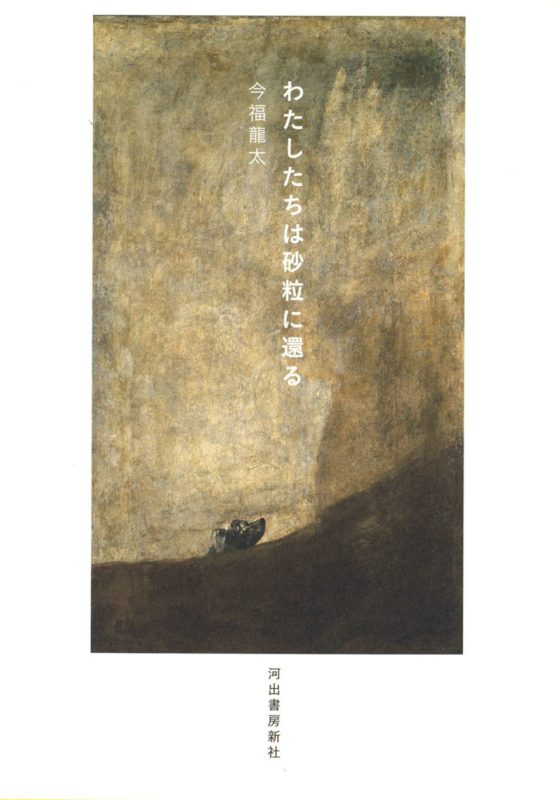
ここで当然の疑問がわく。なぜこのような縄文論が、他でもない岡本太郎によってひらかれたのか。なぜ岡本太郎は、縄文土器の「四次元性」をとらえる「眼」を有していたのか。
この疑問を説くためには、岡本太郎の思想形成期に注目する必要がある。
舞台は1930年代のパリにさかのぼる。
【引用文献】
今福龍太2006 「四次元的『日本』——『呪術』から『日常性の内部』へ」『CHIKAKU/四次元との対話 岡本太郎からはじまる日本の現代美術』川崎市岡本太郎美術館
岡本太郎1952 「縄文土器論——四次元との対話」『みづゑ』1952年2月号
岡本敏子1999 『岡本太郎に乾杯』新潮社
【お知らせ】
当連載を収録した書籍『縄文 革命とナショナリズム』が待望の書籍化! 全国書店やAmazonなどの通販サイトで、2025年6月26日(木)より発売いたします。

筆者について
1975年大阪生まれ。大阪外国語大学卒業。京都大学大学院博士課程修了。なかじま・たけし。北海道大学大学院准教授を経て、現在は東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授。専攻は南アジア地域研究、近代日本政治思想。2005年、『中村屋のボース』で大仏次郎論壇賞、アジア・太平洋賞大賞受賞。著書に『パール判事』、『秋葉原事件』、『「リベラル保守」宣言』、『血盟団事件』、『岩波茂雄』、『アジア主義』、『下中彌三郎』、『親鸞と日本主義』、『保守と立憲』、『超国家主義』、『保守と大東亜戦争』、『自民党』、『思いがけず利他』などがある。






