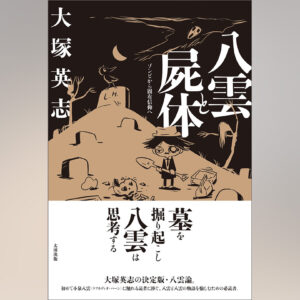5月13日(金)に公開された『シン・ウルトラマン』。庵野秀明氏による「シン・」シリーズはご存知のとおり、この後にも更に『シン・仮面ライダー』が控えていますが、ゴジラ、エヴァンゲリオン、ウルトラマン、仮面ライダーと連なる一連の「シン・」作品群には、一貫して通底する美学や方法、これまで見えにくかった文脈が確かに存在します。それを初めて可視化するのが、大塚英志新刊『シン・論 おたくとアヴァンギャルド』です。
ここでは、本書から一部をご紹介していきます。(全3回)
『シン・エヴァ』に於ける再「物語」化
『シン・エヴァ』のある種のわかり易さの原因は定型化された物語構造の援用にある。
一方ではオンライン上に「正確」を求め様々な「考察」を産む適度な「難解さ」を持ちながら、他方では、鑑賞後は多くが容易に感動しうる乖離は、例えば宮崎駿『千と千尋の神隠し』に既に見られたものだ。このアニメもまた、「油屋」や「カオナシ」なりの舞台やキャラクターの行為の持つ寓意など、細部の表象の水位では難解さに満ちあふれながら、しかしこの作品が興行収入に於いて308億円、観客動員数2350万人とジブリ作品の中でも突出していて、「わかり難さ」と「わかり易さ」の共存という点で、ある意味『シン・エヴァ』と同じ性格を持つ。
両者に共通なのは、神話あるいは民話的な物語構造の精緻な運用とそれがもたらす「わかり易さ」である。オンライン上のファンによる「考察」が細部に於いていくら多義的になされようが、それらは結局、ひとつの物語構造の中に収斂していくので、受け手は構造そのものを作品のメッセージとして理解し(と言ってもそれは「物語」のコードがただ共有されるに過ぎないが)、それが容易に「感動」を起動するのだ。こういった物語論的なシナリオの構造化による感動の創出は、断片的なイメージをビデオコンテでコラージュする手法による映像制作を常としていた新海誠が、『星を追う子ども』でのシナリオへの物語構造の意図的な実装実験を経て、『君の名は。』以降、ストーリーテラー化した例にも見てとれる質のものだ。やはりそこでも物語構造が「感動」を自動化して誘発する仕掛けが駆動している。
こういった作者の変化自体は、即ち、極端な細部への言及からなる思わせ振りな断片の羅列から受け手に物語消費論的に表象を物語構造に収斂させることによる作者のストーリーテラーへの変容を、身近な例として考えてみると、前世紀であれば、村上春樹の初期3部作の3作目『羊をめぐる冒険』に於ける村上春樹自身の言を信じるなら探偵小説的な、しかし恐らくはジョゼフ・キャンベルの単一神話論の形式の援用による「わかり易さ」=大衆性の獲得に成功した事例や、同じく中上健次の劇画原作『南回帰船』を含む末期作品に於いて、批評家によって物語の脱構築の果敢な実践と見なされた、ストーリーテリングの空転やキャラクター造形のステレオタイプ化といった事例を懐かしく思い起こせるだろう。同時に新海、庵野による物語構造の「実装」による感動装置化は実は2009年、村上春樹が『1Q84』によって先行して行っている(大塚、2009)。この作品によって村上は彼の読者の総入れ替えに成功している。
その意味で『シン・エヴァ』は、 80-90年代文学の記憶がウォッシュされ白紙化された後としての現在における、奇妙な反復としてある、とひとまず言える。こういった表現全般の再「物語」化ともいうべき現象が、2020年の現在に何故、必要とされたかは、世界史記述の再「神話」化と個人の物語の再「教養小説」化が、一方では偽史や陰謀史観の氾濫と乱反射、他方では「私」語りのカジュアルな多元化などといかに呼応しているのかをひとまとめにすれば、何かそれらしい批評が書けるのだろう。しかし、それはオンライン上にあふれ返る『シン・エヴァ』の「批評消費」とでもいうのか、データベース消費的「考察」における、刹那のマウント取り以上の意味を恐らく持ち得ない。
だから繰り返すが、本書の関心はそこ、つまり『シン・エヴァ』の意味内容にはなく、従って「成熟」も「喪失」も伏線の回収も各自、好きにやってくれ、というのが基本的な立ち位置だ。
それ故、この章で扱う、小声による困惑や物議と大きな感動を以て迎えられた「第3村問題」の映像史的背景という問題に立ち入る以前に、そもそも第3村のシークエンスが必要とされたかは、こういった神話的構造の援用が自動的にもたらした事態だとまず述べておきたい。まさに「事態」でしかないのである。
つまり「第3村」は物語論的に言えば物語構造、即ち、具体的にはエディプス神話の構造から演繹的に『シン・エヴァ』に「実装」されたものである。
『シン・エヴァ』では主人公碇シンジの目的が父碇ゲンドウ殺しに明瞭に設定される。しかし、それは第三者(つまり「母」である碇ユイ)により代行される。その結果、物語構造が「父殺し」は回避され、インセストタブー、つまりアヤナミ(仮称)という母のレプリカントや、過剰な負の母性の表象としてのアスカら未成熟な身体の持ち主との代理的結婚ではなく、作中でエィプス王の母イオカステの名を連想させもするイスカリオテの名で呼ばれる、成熟した母性としてのマリとの「結婚」が達成される。それが「感動」を起動する。とはいえ、このような劇的なシンジの父殺しの回避/代行と母子相姦の達成は、例えば戦後文学史を補助線としてサブカルチャー文学論的に論じるなら、石原慎太郎から村上春樹『海辺のカフカ』を経ての構造的な反復に他ならない。
そして繰り返すが、そのような「感動」に本書は無関心である。
重要なのは「第3村」は『シン・エヴァ』にこれら神話の構造を導き入れた結果、発生した物語要素である、ということだ。何か、「現在」の切実な反映として導入されたものではない。『シン・エヴァ』が物語構造としてエディプス神話を援用した以上、第3村のシークエンスは自動的に発現されたものである。そのことをまず、徹底して念を押しておきたい。
そもそも『シン・エヴァ』のストーリーラインが、息子シンジが忌避し続けていた父ゲンドウ殺しの決意、つまり、リピートする物語のやり直しとしてのエディプス神話のリセットにあるとすれば、主人公は神話の構造に導かれ、己の運命の発覚後、娘2人と放浪したエディプス王(アスカとレイは母/妻/娘とインセストタブーの表象として自在に置き換え可能である)の如く、まず、荒野を放浪する必要がある。事実、それが描かれる。
そして、ソポクレスがテーバイ王家を描くギリシャ悲劇3部作「エディプス王」「コロノスのエディプス」「アンティゴネー」の3作のひとつ、老いて盲目となったエディプスが娘アンティゴネーに連れられてコロノスの森に辿りつくごとく第3村に至る。そこにもうひとりの娘も合流するが、ギリシャ悲劇であればそれはエディプス王の物語の終焉のシークエンスであるが、その巻き戻しとしての『シン・エヴァ』に於いては、コロノスの森は同時にエディプス王が物語の冒頭で流離され流れ着く羊飼いの村に他ならない。物語はエディプス神話の終盤のコロノスの森を経て、そして、再び彼は物語がリセットされる場所としての流離された先の羊飼いらの許に拾われる地に至る必要がある。物語の果ての地がリセットの地に置換されるわけだ。そのようにして「第3村」は物語構造が召喚した、といっていい。
だから「第3村」はハリウッド映画に於いて文法化したキャンベルのヒーローズ・ジャーニーに従えば「父殺しのリスクから最も遠く離れた場所」であり、それ故、代理的な母性に満ちあふれていなくてはならない。『千と千尋の神隠し』でいえば銭婆のいる家である。孤児としてのエディプスはくるぶしを突き刺されて流離されるが、マックス・リュティに従えば神話や民話の外的な傷は内的な損壊の象徴であるから、第3村でのシンジ/エディプスの役割は旅立ち可能な状態への再生であり、「母胎」からの旅立ち可能な程度の成熟の達成である。
再確認すれば『シン・エヴァ』は冒頭、シンジによる父殺しという主題のミッション化、つまりその目的の再認識から始まる。TVシリーズ、旧劇場版、『シン・エヴァ』の前作に至るまで「逃げる」ことが主題化されていたのが、「戦う」というモードにリセットされる。キャンベルの単一神話論が重要視する「冒険への召命」、つまり大人への旅立ちの前の永きに渡る留保としてそれ以前の「エヴァ」は構造的にはある。その「成熟」の意志決定の場として第3村はある。その永すぎる留保は作家論的に興味深かった(と過去形で記す)が、それが物語構造の実装によりリセットされた時点で作家論は無効になる。庵野秀明に於いてはその是非は各受けとめ手の審美の問題だから何も論じないが、その「方法」はより工学化していく方向にある。物語構造の実装も工学化の一部であることは忘れるべきではない。言うまでもなく民話の構造はロシア・アヴァンギャルドと同時代にソビエトで発生した工学的文学理論であるからだ。しかし、『シン・エヴァ』はエディプス神話の王殺しの子供の予言に始まり流離へと連なる物語要素の配列の順と逆ではないかと見る向きもあるだろうが、そもそもソポクレスの戯曲「エディプス王」は王の座にあるエディプスが父殺しの犯人と名指しされ自覚していく物語構造を、倒叙法的に逆回しするものである。
従って、第3村が村外に使徒の亡霊が跋扈する神域であり、同時に母性的な「生産」をスタジオジブリ的に強調した「農村」であることも、エディプス的物語構造を実装した結果出現した「場」に他ならない。
だから、もう一度、念を押すが、このシークエンスに感動する受け手は構造から感情を起動させられたに過ぎない。
対して、「第3村」の描写にある種の全体主義的な匂い、その点ではジブリに比せば宮崎駿より高畑勲的なイデオロギーを感じる者が恐らく少なからずいたはずである。それはソビエトの集団農場的、つまり、高畑勲が『太陽の王子 ホルスの大冒険』で描いた、働かないことが悪とされる協同労働の村であり、『おもひでぽろぽろ』の故郷を持たないヒロインを「嫁」として協働の働き手として強引に回収するムラでもある。アヤナミレイ(仮称)は高畑ヒロインの如く農村に回収され、かろうじて萌芽した彼女の個は身体とともに消滅する。これを新体制下の集団農場や満州に於ける開拓村、あるいはヤマギシ会などの戦後の自然回帰的なコミューンなど、重ね合わせる全体主義的なムラの具体相は世代や政治的立場によって様々にしても、そこに共通するのはある種のファシズム性に他ならない。そして重要なのは、そのファシズム性だけはしかし物語構造が導き出したものではない、という違いだ。
だからこの時、留意すべきなのはこの第3村に感じるファシズム性が、物語構造が導く感動によって共感・肯定として結びつくことで、その結果、この映画は予期せぬ政治性を獲得する、という仕組みである。本書ではおたく表現が無自覚に帯びる政治性を作者の意図とは異なる水位で、方法や美学の産物として特定していく。それ故、第3村の感動が物語構造が自動的に起動するのに対し、同時に召喚されるファシズム性や結果的政治性は別の様式(すなわち文化映画性)によってもたらされることの違いに注意が必要だ。
そもそも本書の目的は機械や身体の機械芸術化を通じてオクタ的表現のファシズムへの脆さを指摘することにあるが、実は同じ政治的脆さが第3村という反文明的なシークエンスに於いても露呈するのである。実はそれは「第3村」シーンが採用した「映画」としての形式性に問題がある。具体的には「郷土映画」という形式であり、歴史的にいえば戦時下、漫画映画、瀬尾光世『桃太郎 海の神兵』(1945)によってアニメーションにも実装されたものだ。その点で実はこの映画は「郷土漫画映画」という限定的な意味に於いて『おもひでぽろぽろ』から『シン・エヴァ』に至る系譜の起点としてある。
* * *
本書では、『シン・エヴァ』シリーズや手塚治虫、柳田國男の映画論などからひも解く郷土映画論や、『シン・ゴジラ』でも描かれた日本映画独自の「変身」「変形」への執着論など、著者・大塚英志が戦後の「おたく」表現のフェティシズムや美学の出自について新たな切り口で論考しています。
大塚英志の最新刊、挑発的芸術論『シン・論 おたくとアヴァンギャルド』は、全国の書店・通販サイトや電子書店で大好評発売中です。
筆者について
おおつか・えいじ。国際日本文化研究センター教授。まんが原作者。
著書に『手塚治虫と戦時下メディア理論 文化工作・記録映画・機械芸術』(星海社、2018年)、『大政翼賛会のメディアミックス『翼賛一家』と参加するファシズム』(平凡社、2018年)、『大東亜共栄圏のクールジャパン「協働」する文化工作』(集英社新書、2022年)、『「暮し」のファシズム ――戦争は「新しい生活様式」の顔をしてやってきた』(筑摩選書、2021年)、『シン・論 おたくとアヴァンギャルド』(太田出版、2022年)、『木島日記 うつろ舟』『北神伝綺』『北神伝綺 妹の力』(いずれも星海社、2022年)など。
現在の研究テーマは戦時下のメディア理論と文化工作。