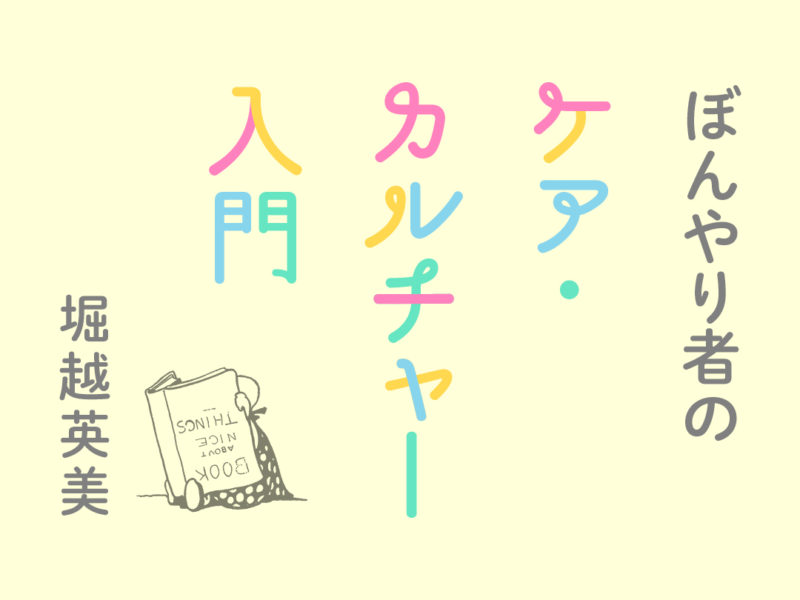『女の子は本当にピンクが好きなのか』・『不道徳お母さん講座』で話題の堀越英美さんによる新連載「ぼんやり者のケア・カルチャー入門」。最近よく目にする「ケア」ってちょっと難しそう……でも、わたしたち大人だって、人にやさしく、思いやって生きていきたい……ぼんやり者でも新時代を渡り歩ける!? 「ケアの技術」を映画・アニメ・漫画など身近なカルチャーから学びます。第16回は、なんと早くも最終回です! なぜなら、この連載を締めくくるにふさわしい大傑作が爆誕してしまったから。みんな大好き『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』です。
ここから先は会員限定コンテンツです。
ログイン、または無料の会員登録を行うと
記事の続きをお読みいただけます。