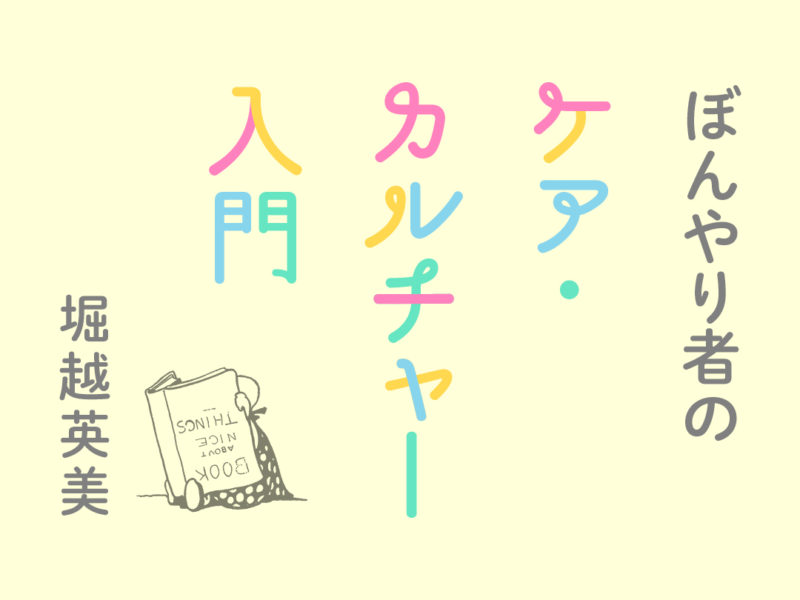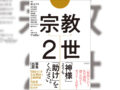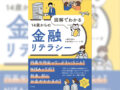『女の子は本当にピンクが好きなのか』・『不道徳お母さん講座』で話題の堀越英美さんによる新連載「ぼんやり者のケア・カルチャー入門」。最近よく目にする「ケア」ってちょっと難しそう……でも、わたしたち大人だって、人にやさしく、思いやって生きていきたい……ぼんやり者でも新時代を渡り歩ける!? 「ケアの技術」を映画・アニメ・漫画など身近なカルチャーから学びます。第13回のテーマは、話題のドラマ『エルピス』と凡庸な悪、そしてケア。
※この記事にはドラマ『エルピスー希望、あるいは災いー』の物語の核心部分に触れる記述を含みます。
「(子供と一緒にいると)うちは自分が弱なった気がします」。
ここから先は会員限定コンテンツです。
ログイン、または無料の会員登録を行うと
記事の続きをお読みいただけます。