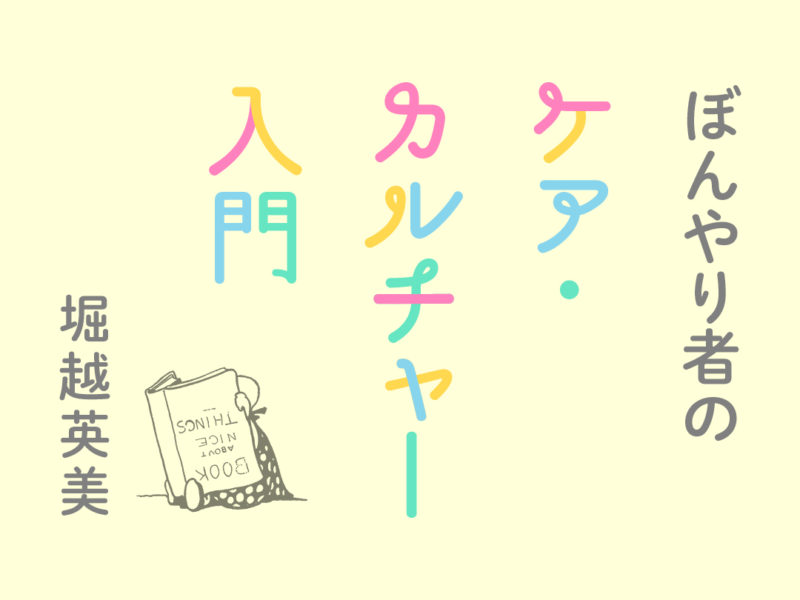『女の子は本当にピンクが好きなのか』・『不道徳お母さん講座』で話題の堀越英美さんによる新連載「ぼんやり者のケア・カルチャー入門」。最近よく目にする「ケア」ってちょっと難しそう……でも、わたしたち大人だって、人にやさしく、思いやって生きていきたい……ぼんやり者でも新時代を渡り歩ける!? 「ケアの技術」を映画・アニメ・漫画など身近なカルチャーから学びます。第14回のテーマは、ケアするヒーローとこんまり。
現代の”強い”プリンセスたち
ここから先は会員限定コンテンツです。
ログイン、または無料の会員登録を行うと
記事の続きをお読みいただけます。