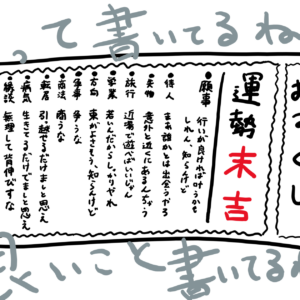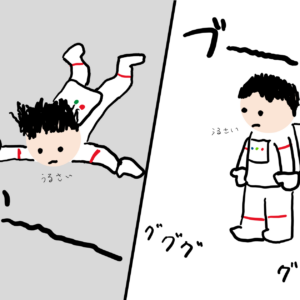宇宙機の制御工学を専門としながら、JAXAのはやぶさ2・OKEANOS・トランスフォーマーなどのさまざまな宇宙開発プロジェクトに携わる、宇宙工学研究者・久保勇貴による新感覚な宇宙連載! 久保さんはコロナ禍以降、なんと在宅研究をしながら一人暮らし用のワンルームから宇宙開発プロジェクトに参加しているそうで……!? 地べたと宇宙をダイナミックかつロマンティックに飛び回る、新時代の宇宙エッセイをお楽しみください。
名前も知らない坂道のことを覚えている。大学の裏の住宅街の、なんでもない坂道だった。
「あたし、坂道好きなんだよね」
彼女がそんなことを言ったのを覚えている。大学で待ち合わせて、二人で気の向くままに散歩をしてた時だった。よく晴れた日だったと思う。自分の好きなことを、大げさなぐらい嬉しそうに伝える人だった。
「先がどうなってるか見えないから、なんかワクワクするんだよ」
坂道が好きだなんて力説する人をタモリさん以外に初めて見たので、僕にはその意味がイマイチ分からなくて、ふーんとか適当な相槌を打ってたような気がする。彼女が指差した下り坂は、そこから見るとたしかに先が見通せなくて、そう言われてみればたしかに少し好奇心をくすぐられるような感じがした。結局あの時、その坂道の先がどうなってるかは確認しに行かなかったと思う。それから程なくして彼女にフラれたから、僕は今でもあの坂道の先にどういう景色が広がっていたのかを知らないでいる。大学三年生、専門課程が始まって宇宙工学を学び始めた頃だった。それから僕は、散歩が好きになった。
散歩は、ちょっとした冒険だ。初めて訪れる町はもちろんだけど、何年も住んでる家の近所だってそう。坂道の先、曲がり角の先がどうなってるかは実際にそこに行ってみないと分からなくて、気まぐれにひょいと路地に潜りこめば全然知らない景色、住宅街の中に描画バグみたいに埋め込まれた保全緑地、なぜか「河本」という姓だけやたらと多いお墓、ぴかぴか光るガラクタに囲まれた怪しい一軒家、家の隙間を縫って町内一帯を見渡せる小高い石階段。観光地でもフォトスポットでもないそういう景色、もしも一本隣の路地を選んでいたら出会えなかったそういう景色に、紙一重で出会ったり出会わなかったりする体験の連続が、散歩の醍醐味だと思う。
探査機ボイジャーの冒険と孤独
ボイジャーという探査機がやったのも、そういう冒険だった。数百年に一度、木星・土星・天王星・海王星がちょうど綺麗に並ぶタイミングを利用して、僕らの住む太陽系内の惑星を順番に訪問してやろうという散歩計画だった。どの惑星も、何十億年も地球と一緒に並走してきて、数百年前から望遠鏡で何度も観測されてきたお馴染みの天体だった。だけどそういう見慣れた天体でも、実際にそこがどうなってるかはやっぱり行ってみないと全然分からなくて、それまで想像していたのとは全然違う景色、木星の月イオの元気いっぱいな火山、土星の月タイタンの分厚いみかんの皮みたいなオレンジ色の大気、自転軸からなぜか60度も傾いている天王星のヘンテコな磁場、音速の猛烈な嵐が吹き荒れる海王星の濃い大気。遠くから眺めているだけでは絶対に見られなかった数々の景色、宇宙探査技術が急成長を遂げていたあの時期にちょうどあの奇跡的な天体配置が起こらなければ出会えなかった景色、そういうものをボイジャーは見た。それはやっぱり紙一重の体験だった。もしもほんの少し歴史の流れが違ってたりなんかしたら、あの歴史的な太陽系内散歩は実現できてなかったのかもしれない。
ボイジャー1号・2号は1977年に打ち上げられて今も地球と通信し続けているけれど、どちらもついに2025年ぐらいには電池の寿命が尽きてしまうらしい。電池が切れた後はもう一生地球とおしゃべりすることはできなくなってしまって、地球に戻ってくることもできなくて、ひたすら何も無い宇宙空間を飛び続けることになる。一応、万が一宇宙人たちに拾ってもらえた時のために、人類の存在を伝える金ピカのレコードを持ってたりはするけれど、今世紀中とか近い将来に見つけてもらえる可能性はまあかなり低いと思う。誰とも話せない、誰にも会えない、何百年、何千年もの長い時間が、この先もボイジャーを待ってるんだろう。なんともおそろしい孤独。
僕が散歩を好きなのは、それが少しおそろしい体験でもあるからだと思う。見慣れた景色を一歩抜け出せば、知らない誰かの知らない家、家、家、そしてその裏にある日々の生活、生活、生活、誰かにとってかけがえのない誰かとの人間関係、人間関係、人間関係、そういう無数の人生に取り囲まれると、自分という存在もこの広大な世界のなかの繰り返しの一つに過ぎない気がしてくるから、たまにそういうことを確認したくなるんだと思う。孤独で、心細くて、おそろしくて、だけどちょっぴり刺激的だから、たまに覗いてみたくなるんだと思う。
そして、なぜだか知らないけどその時決まって僕は愛のことを思ってしまう。突然思い出したように、何かを無性に愛したくなってしまう。自分の住むこの町を大切にしたいとか、この場所のこの角度から見たこの光景を自分の好きな人と共有したいとか、自分のことを好きでいてくれる人とまたこの場所をこの時間に歩きたいとか、急にそういうことを願い始めてしまう。孤独はなぜかいつも愛を連れてくる。おそろしさと温かさと、そういうものがごちゃ混ぜになるところが、散歩の良いところだと思う。
ボイジャー1号の散歩中、60億キロメートルの彼方から撮った地球を見て、同じように愛のことを思った人がいた。画素にして1ピクセルにも満たない点としてかすかに映り込んだ僕らの地球が、いかに宇宙の中でかけがえのないものかを説いた人がいた。画面上のゴミと見間違うぐらいのそのちっぽけな地球の姿は、「Pale Blue Dot(薄暗くて青い点)」と呼ばれた。ボイジャーの無限のような孤独に見合う、大きな大きな愛だった。
もう一度、あの点を見てほしい。そこに現にあり、私たちのふるさとであり、私たちそのものであるあの点を。あなたの愛する人も、あなたの知っている人も、あなたが伝え聞いたことのある人も、そして、かつてそこにいたすべての人も、みな、そこで人生を送ったのである。(中略)お互いをもっと大切に扱うこと、そして、私たちが知っている唯一のふるさとであるこの「暗い青い点」を守り育んでいくこと、それは私たちの責任であることを、この写真が強く訴えているように、私には思える。
カール・セーガン、『惑星へ〈上〉』、(pp. 26-28)、朝日新聞社

青い地球の美しさとすぐ隣にある愛
名前も知らない坂道のことを覚えている。学会参加のために一人で訪れた南フランス・トゥールーズの、なんでもない坂道だった。バスが来るまで30分以上時間が空いたので、暇つぶしにバス停の近くを散歩してたのだった。
「あたし、坂道好きなんだよね」
数年前に彼女が言ったあの言葉を、僕はぼんやり思い出していた。あの時、僕が彼女を愛しきれなかったことを思い出していた。僕が彼女にかけてしまった迷惑の一つ一つを思い出していた。よく晴れた日だったと思う。坂の中腹まで登って振り返ると、遠くの木々の中にポツポツと埋め込まれたオレンジ色の屋根が見えた。もしもバスの待ち時間が短かったら出会うことのなかった、紙一重の景色だった。観光地でもフォトスポットでもない坂道だった。彼女が好きそうな坂道だった。
孤独はなぜかいつも愛を連れてくる。だから、そのとき僕は愛のことを思っていた。坂道が好きなあの人と別れてから二年ほど経って、僕には結婚してもいいかもしれないと思える恋人ができていた。坂道じゃなくて、紅茶とパンが好きな人だった。いつか歳を取って仕事を辞めたら、フランスで紅茶とパンの店をやりたいなんて言う人だった。坂の中腹からは、なおもオレンジ色の屋根が見えていて、それは彼女が好きそうな街並だった。だから、この場所、この角度から見たこの光景を彼女と共有したくなった。またこの場所をこの時間に、こんな天気の下で彼女と歩きたいと思った。
「先がどうなってるか見えないから、なんかワクワクするんだよ」
彼女と結婚することを、僕はためらっていた。先がどうなってるか見えないことは、その時の僕にはとてもおそろしいことのように思えた。一緒に住もうよと何度も言ってくれた彼女に、僕は曖昧な言葉ばかりを返していた。坂道が好きなあの人を愛しきれなかったとか悔やんでるくせに、結局数年経っても人を愛しきる覚悟なんか全然持てていないのだった。考えるのが嫌になって忘れたふりをしているくせに、こんなところを散歩してる時だけどうしようもなく感傷的になって、思い出したように無性に何かを愛したくなるのだった。お別れしようと彼女に言われたのは、その一ヶ月後だった。だから、あの坂道から見たオレンジ色の街並を彼女と共有することは、結局できなかった。
どうして、目の前のものを愛しきれないんだろう。どうして、愛することをつい忘れてしまうんだろう。ボイジャーがあの薄暗くて青いちっぽけな地球を撮って、それに感化された後続の探査機も同じように地球を撮って、宇宙飛行士たちも何度も撮って、そういう写真がたくさん世間に出回って、その度にみんなで口を揃えてそれを美しいと言って、僕たちの地球はかけがえのないものなのだと感動して、愛を叫んで、それでもなお、僕らはそれを愛しきれないことがある。環境も、生き物も、隣の国も、友だちも、恋人も、油断してるとつい愛し忘れてしまう。だからこそ、僕たちは何度も宇宙を目指さないといけないんだろうか。僕たちは、僕は、どうやったって忘れっぽいものだから、思い出したように何度も愛し直さなきゃいけないんだろうか。宇宙開発というのは、忘れっぽい僕たちのために、僕のためにあるんだろうか。
地球は広大な宇宙にあって、ごくごく小さな場所でしかない。考えてみてほしい。あまたの将軍や皇帝たちが、勝利と栄光を求めて、このちっぽけな点のそのまた一部でほんの束の間の支配者となるために流された血の川を。また、この点の一角の居住者が、そことほとんど見分けのつかない別の一角の居住者のところに攻め入っては振るった、際限のない残虐行為を。そして、いかに頻繁に誤解が繰り返され、互いを殺し合おうとし、激しく憎悪を燃やしたかを。
カール・セーガン、『惑星へ〈上〉』、(p. 27)、朝日新聞社
自宅のワンルームに閉じこもって研究をしていたこの二年ほど、何度も散歩を繰り返してきた。でたらめな道を選んで、でたらめな角を曲がって、なるべく見たことのない景色に辿り着こうとしてきた。飽きることはなかったけれど、さすがに同じ町を数百回くまなく散歩してるともう新しい発見も無くなってきてしまったので、最近は散歩ならぬ散チャリでさらに行動範囲を拡張している。この前ついにちょっとお高い自転車を買ったので、さらに調子に乗ってチャリチャリ走りまわっている。まだまだこの町には、知らない景色がたくさんある。もっともっと知らない景色を見たいと思う。
二年ぶりに、彼女から連絡があった。出会いも別れも紙一重だけど、また僕たちは連絡を取り合うことに決めた。二年前に行けなかったたくさんの場所に、もう一度行く約束をした。彼女は相変わらず紅茶とパンが好きなようだった。だから僕はもう一度、愛を思い出す必要がある。つい忘れてしまわないように、今度こそ愛しきる必要がある。彼女と共有したい景色が、たくさんある。小学生の絵みたいに大げさに木の根が張り出した川沿いの急な斜面とか、全てに意味があるはずなのに無意味に複雑に見える工場の配管とか、チビっ子たちが恐怖などこの世に存在しないかのように爆走する団地の脇のスケボーパークとか。忘れないために、いや、多分僕はきっと忘れてしまうから、たとえ忘れても何度でも思い出すために、もっともっと知らない景色をたくさん見たいと思う。
【お知らせ】
当連載を収録した書籍『ワンルームから宇宙をのぞく』は、全国書店やAmazonなどの通販サイト、電子ブックストアにて好評発売中です。
筆者について
くぼ・ゆうき。宇宙工学研究者。宇宙機の制御工学を専門としながら、JAXAのはやぶさ2・OKEANOS・トランスフォーマーなどのさまざまな宇宙開発プロジェクトに携わっている。ガンダムが好きで、抹茶が嫌い。オンラインメディアUmeeTにて「宇宙を泳ぐひと」を連載中。