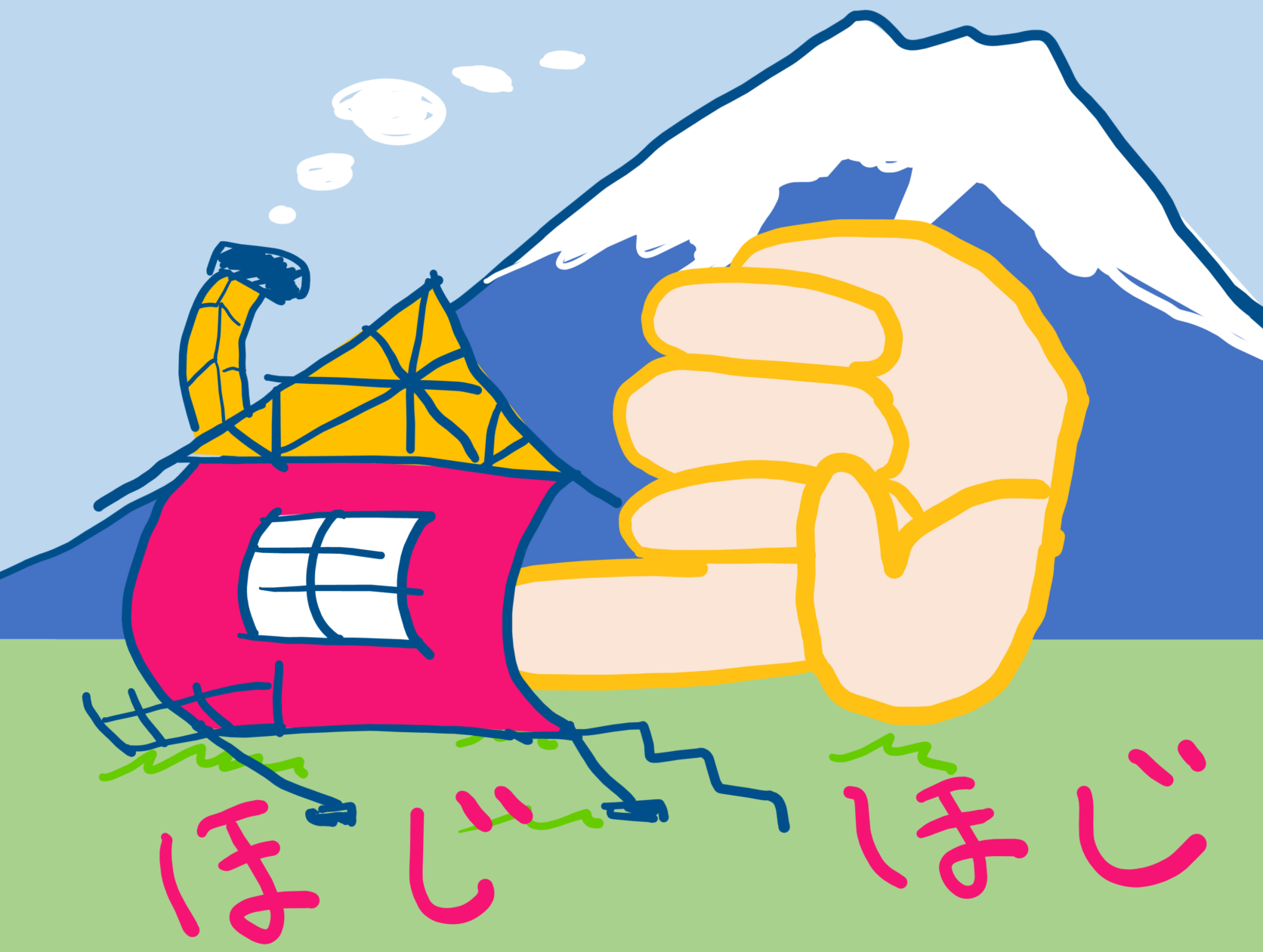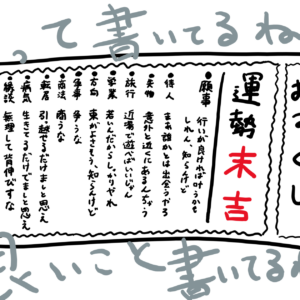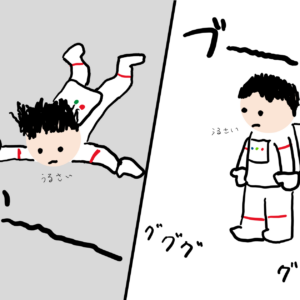うっとりとした顔で眠る女の子を腕に抱きながら、ダイナミックに鼻をほじる青年を見たことがある。夜の電車の中、それはもうダイナミックとしか言いようのないほじり方だった。第一関節までずっぽり挿しこまれた人差し指は鼻の中を縦横無尽に躍動し、それに合わせて鼻の皮膚がグイグイ伸び縮みしていた。胎児がお腹の内側を蹴ってる時の動きみたいだった。サザエさん一家がエンディングでドタバタと家に入っていく時の、家の動きみたいでもあった。
女の子は、自分の頭上でそんなダイナミック鼻ほじりが繰り広げられているとはつゆ知らず、なおもうっとりと彼氏の腕に抱かれていた。彼氏は、右手で彼女の髪をやさしく撫でたりなんかして格好をつけながらも、左手ではしっかりと鼻をほじり続けていた。車内ではサラリーマンが降りる駅を待っていて、女の子はうっとりしていて、青年は堂々と鼻をほじっていて、サラリーマン、うっとり、鼻ほじ、だから、その二人だけ別の世界のルールで生きているみたいだった。汚いのか美しいのか、面白いのか不愉快なのか分からない光景だった。
僕はその光景を、もう二度と見ることができない。

「どうも、おつかれさまです~」みたいなトーンで「どうも、トリック・オア・トリートです~」と挨拶するママさん集団を見たことがある。地元の商店街がやっていたハロウィンイベントで、仮装した子どもを連れたママさんたちが言っていたフレーズだった。「どうも、お菓子をくれないと悪戯します~」と物騒なことを言っているのに、物腰はやたらと柔らかいのが奇妙だった。本物のオバケの国の挨拶みたいだった。
僕はその光景を、もう二度と見ることができない。
夜食を買いにコンビニまで歩いていた時、「ハックション!パー!パー!パー!!」というくしゃみをするおじさんを見たことがある。どうやって文字起こししても「ハックション!パー!パー!パー!!」としか書けないぐらい、非常にはっきりと「ハックション!パー!パー!パー!!」だった。「パー!パー!パー!!」の部分は決してハックションからの惰性で出たものではなく、あくまで独立に、明確な志を持って発せられた「パー!パー!パー!!」だった。恥ずかしがることも怯むこともなく、おじさんはそのまま一人で歩き去っていった。
僕はその光景を、もう二度と見ることができない。もう二度と、同じ光景に出くわすことができない。どれだけそれを目に焼き付けようと力を込めてみても、通り過ぎた瞬間にはもう網膜の上から消えてしまって、全部全部、僕の前から無くなってしまう。
見るということは、本当はとても頼りないことだと思う。
ふと気づいたら、泣きながら母ちゃんと抱き合っていたことがある。大学の前期試験に落ちて、ダメ元で受けた後期試験の結果を見た時だった。オンラインでの結果開示で、父ちゃんは仕事に行っていて、家は静かで、「私は見たくないから一人で見なさいよ」と母ちゃんは素っ気なく言って、僕も母ちゃんも落ち着いていて、本当はそんなはずはなくて、自分の部屋で黙ってパソコンを開いて、Windows、呼吸を深くして、目を細めて、恐る恐る、自分の受験番号が、あった、何かを叫んで、それで、気づいた時にはもうリビングで泣きながら母ちゃんと抱き合っていた。リビングの電気はついていなくて、昼下がりの陽が幾度か淡く反射しながら部屋の中を満たしていて、そのように、僕も母ちゃんも細切れに、確かめるように、何度も小さく息を吐いた。
僕はその光景を、もう二度と見ることができない。もう二度と、同じ体験をすることができない。もう二度と、あの時と同じように母ちゃんと抱き合うことができない。
屈折しているのにひたむきで、けたたましいのに静謐で、破滅的なのにしあわせな演劇を観たことがある。演劇サークルの同期の作品だった。昔そういうガラスの玉を持っていた。透明なのに先が見えなくて、ひんやりしているのに人間的で、天然の顔をしながら不自然にまん丸だった。そういう演劇だった。そういう矛盾のようなものを一つずつ丁寧に拾い集めて、まとめて全部乱暴に肯定していくような演劇だった。それは時に、凄まじい光景だった。だけど、一体何がどう凄まじかったのかは、いつもよく思い出せなかった。
僕はその光景を、もう二度と見ることができない。生きるために演劇を始めた彼は、生きるためにもうすぐ演劇を辞める。だから、僕はその作品をもう二度と見ることができない。
然しながらお前たちをどんなに深く愛したものがこの世にいるか、或はいたかという事実は、永久にお前たちに必要なものだと私は思うのだ。(中略)だからこの書き物を私はお前たちにあてて書く。
有島武郎『小さき者へ』
生きているのに、生きているから僕たちは、生きなければいけないから、失うことがある、生きるように失って、ちがう、失うように生きて、作ることは苦しくて、見ることは頼りなくて、あったものは無くなって、見たものは消えて、力を入れても物理で、残らなくて、生きることだけできない、生きるには理由が必要で、美しいものだけがただあったということを認めるだけではいけなくて、存在には理由が必要で、ただそのことが悔しい、悲しい。在るということが支えなら、それは在れないということだ。人は立ち止まれない機械だ。通りすぎる少しの淀みだ。
生きるということは、この世界に在るということは、本当はとても頼りないことだと思う。
こんなにブルーライトを浴びて、僕はどこに行くのだろう。波打ち際のように県道が鳴っていて、夜。押し寄せて、遠ざかって、同じように、タイムラインがうねっている。日本中の誰もが知っている芸能人が死んだ。誰もが知っているのに、それでもやっぱり関係なく死んだ。誰かがそのことを一生懸命悲しんでいて、誰かがモスバーガーの新メニューの話をしていた。
お前たちは去年一人の、たった一人のママを永久に失ってしまった。お前たちは生れると間もなく、生命に一番大事な養分を奪われてしまったのだ。(中略)お前たちは不幸だ。恢復(かいふく)の途なく不幸だ。不幸なものたちよ。
有島武郎『小さき者へ』
人生は、勝ち目のないサバイバルゲームだ。何かを犠牲に生き延びて、勝ち残って、仲間ができて、それだけでもう十分なはずで、それなのに最後には絶対になぜかみんなゲームオーバーになる。昔そういうゲームがあった。ゲームセンターのシューティングゲームで、兄ちゃんと二人でなけなしの小遣いを投入して必死の思いで最後までクリアしても、エンディングの最後にやっぱり「GAME OVER」と表示されて終わるやつ。人生はそんな感じだ。
見/在るということは頼りなくて、僕はそのことを呪/祝いたい。怨/刻み続けたい。
母ちゃんと聖母を見たことがある。大学の前期試験の合格発表を見に、二人で上京した時だった。上野に、ラファエロの絵が来ていた。僕は生まれて初めて、本物の絵画を観た。それは、何だか分からないけれど、良いような気がした。すごく、良いような気がした。絵のこともキリスト教のことも何にも知らないけれど、すごくキラキラしていることは分かった。
前期試験の合格発表では、僕の受験番号は無かった。喜びに沸く友人たちに水を差さないように、気配を消しながら母ちゃんと一緒に発表会場を後にした。無言で後期試験の受付を済ませ、そのまましばらく街を歩いた。僕は多分、この世の終わりみたいな顔をしていた。そんな僕の顔を見た母ちゃんは、「シケた面してねえで、さっさと後期試験に備えんかいボケぇ!」みたいなことを言った。そんな言い方ではなかったけれど、僕にはそう聞こえた。聖母とはあまりにかけ離れたセリフだった。僕のシケた面はみるみる引き攣り、おかげで急激に緊張感を取り戻した。もし母ちゃんが聖母だったら、僕はあのままダメになっていたかもしれない。
後期試験の本番、正門の前で立ち止まって、母ちゃんが手のひらを僕に向けた。ビンタでもされるのかと思ったけど、母ちゃんの顔は優しかった。僕も手のひらを合わせ、ハイタッチのようなことをした。どちらともなく、うん、と喉が鳴った。はい、と小さく答えた。ルーティンでもゲン担ぎでも何でもない、その場の思いつきみたいな浮ついた行為だった。それは、何だか分からないけれど、良いような気がした。すごく、良いような気がした。
僕はその光景を、もう二度と見ることができない。もう二度と、同じ体験をすることができない。
舞台の裏で、宇宙を覗いたことがある。大学の演劇サークルの本公演だった。舞台の裏は、ステージに光が漏れないようギリギリ足元が見えるぐらいの明かりしか点いていなかった。狭い舞台裏で各々が息を殺しながら開演を待っていて、だから、近くにいるのにみんなが遠かった。独りだった。開演の曲が鳴って、頭上の灯体の陽がゆっくりと落ちた。光の粒がまばらに現れた。暗転時の目印の、蓄光テープだった。都会の夜空のようだった。それ自体が、一つの作品のようだった。地球は、宇宙の中ではあまりに孤独なのだった。
彼の作る演劇は、屈折しているのにひたむきで、けたたましいのに静謐で、破滅的なのにしあわせだった。黒塗りのモザイクみたいな変なメガネをかけながら拡声器で叫びまわったり、爆音の音楽の中で暴れまわりながら誰かを大声で祝福したりした。電脳世界のファッションショーみたいな形のステージの端に、巨大なブランコがある舞台だった。僕はシスコンのうざいお兄ちゃんの役だった。いつも妹に鬱陶しがられながら、最後の見せ場ではお兄ちゃんらしいところを見せて、なんだかんだ憎めない奴だった。
彼は、演劇が無いと死んでしまうような人だった。喩えじゃなく、本当に死んでしまいそうだった。演劇を作ることで、命を繋いでいた人だった。彼自身の内にある矛盾のようなものを一つずつ丁寧に拾い集めて、まとめて全部乱暴に肯定しているようだった。だから彼は、自分の作品を見ている時が一番楽/苦しそうな顔をしていた。
僕はその光景を、もう二度と見ることができない。生きるために演劇を始めた彼は、生きるためにもうすぐ演劇を辞める。前に進む。だから、僕は彼の作品をもう二度と見ることができない。どれだけそれを目に焼き付けようと力を込めてみても、通り過ぎた瞬間にはもう網膜の上から消えてしまって、全部全部、僕の前から無くなってしまう。
小さき者よ。不幸なそして同時に幸福なお前たちの父と母との祝福を胸にしめて人の世の旅に登れ。前途は遠い。そして暗い。然し恐れてはならぬ。恐れない者の前に道は開ける。
行け。勇んで。小さき者よ。
有島武郎『小さき者へ』
頭上の蛍光灯の陽を落とすと、光の粒がまばらに現れた。充電中を知らせる青いLED、緑のLED、玄関脇のスイッチのオレンジのパイロットランプ、テレビの赤いスタンバイランプ。就寝前のワンルームから、宇宙を覗く。地球は、宇宙の中ではあまりに孤独なのだった。僕はこの部屋で、何度もそんなことを思ったのだった。こんなに孤独で仕方ないのに、人類はまだ続いている。こんなに孤独で仕方ないから、人類はまだ続いている。
仕方ないよね、なんて割り切れなくて、おつかれさま、なんて言いたくなくて、ただしかし、生命はどうしようもなく連続的でしか成り立たない。立ち止まればそれで終わってしまうから、歩き続けていくことしか僕らには許されていない。僕が呪/祝いたいのは、きっとそういうことなんだろう。
人生は、勝ち目のないサバイバルゲームだ。何かを犠牲に生き延びて、勝ち残って、仲間ができて、それだけでもう十分なはずで、それなのに最後には絶対になぜかみんなゲームオーバーになる。汚いのか美しいのか、面白いのか不愉快なのか、全然分からないゲームだ。だからせめて生きているうちは、このゲームをせいいっぱい呪/祝いたい。なぜこんなにもどうしようもなく虚/眩しいのかと怯/震えながら、その儚/尊さに怒/浸りながら、せいいっぱい呪/祝い続けたい。
【お知らせ】
当連載を収録した書籍『ワンルームから宇宙をのぞく』は、全国書店やAmazonなどの通販サイト、電子ブックストアにて好評発売中です。
筆者について
くぼ・ゆうき。宇宙工学研究者。宇宙機の制御工学を専門としながら、JAXAのはやぶさ2・OKEANOS・トランスフォーマーなどのさまざまな宇宙開発プロジェクトに携わっている。ガンダムが好きで、抹茶が嫌い。オンラインメディアUmeeTにて「宇宙を泳ぐひと」を連載中。