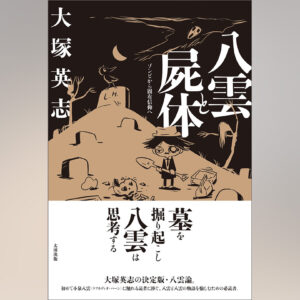さて、戦時に柳田の「カメラ・アイ」の実践を迫られるのが、東宝の文化映画のカメラマン・三木茂である。三木は亀井文夫の記録映画で求められた演出カットを「再現」してまで撮影しなかった逸話で知られる。また、カメラマンは「目隠しされた馬」でファインダーの中でしか思考できないとした亀井に反論した、いわゆる「ルーペ論争」の一方の当事者でもある。
その三木と柳田の間に、言うなればもう一つの「ルーペ論争」に似た齟齬があったことは注意していい。
戦時下、柳田に接近した文化映画グループは、藝術映画社ともう一つ、東宝の文化映画部である。東宝は三木茂が『土に生きる』(一九四一)を制作、その過程で柳田に接近し、ロケを通じて撮影されたスチール写真集をまとめ『雪国の民俗』(一九四四)が出版されるに至る。
三木は東宝文化映画部プロデューサーの村治夫に伴われ柳田の許を訪れたとされる。そして柳田と朝日新聞時代の縁故で東宝を繋いだとされる津村秀夫の司会で、柳田・三木・村に柳田の側近で転向マルクス主義者であった橋浦泰雄を加えた座談会「柳田國男を囲んで 文化映画と民俗学」(『新映画』一九四一年三月号)が残る。
この座談は『土に生きる』の試写後のことともされるが、この映画で注意しておくべきはそのクレジットである。
「村治夫 製作」とある一方で「作 監督 撮影 三木茂」ともある。当時の東宝はプロデューサーシステムであり、映画は第一義的にはプロデューサーの「作」であったが、三木はあたかも全てが自分の「作」だと主張している印象がある。それは自分が「目隠しした馬」でもなく、現地に行かぬ監督の指示リストで盲目的に撮影するわけでもない、という「ルーペ論争」を経ての自己主張ではあるのだろう。
しかし、このような三木の「自意識」こそが、柳田が最も嫌うものでもある。自然科学的文学の手法であるべきナチュラリズムを「私小説」に変えた田山花袋への批判の根拠もそこにある。
先の座談で柳田は三木に対してこうつれなく対応する。
柳田 どこを歩いたのですか。
(柳田、三木他 一九四一)
三木 男鹿半島の脇本村──吉田三郎氏の書いたものによつて‥‥
柳田 三木さんの話はあとで願うことにして先きにプリンシブルの話をしたい。そうやってゆっくりやって行けば、新しいものがちょいちょい見つかるかも知れないが、それより方法とか組織を最初に考へなければならないと思う。私共の文化映画に期待して居る所は大きい。
座談は幇間のように三木を持ち上げ、柳田に高評価を乞う津村の発言から始まるがそこはカットした。それに対して、柳田は三木の説明をスルーし、「プリンシブル」、原理原則の話をする、と言い出す。
三木への黙殺である。
柳田は先に引用した藝術映画社への談話原稿で、「現存する各地の慣行の異同を解説し、以前にあきらかに我々の間に存在していた事実が、如何なる経路を辿って改まり動いたかの歴史」を「カメラの眼」が可能にすると述べている。「文化映画」とはそのような「歴史」を可視化するものである。
「プリンシブル」とはこの一点に他ならない。
この間から私が村君なんかに話して居るのだが、題材を決めたら、旅行のついでに、あつちこつちから撮って集めていくということを心掛けていけばいい。例へば、一年の季節をやるとなって、そこへ何回となく行かなければならないということは、經濟の上から不利益だし、それも大きい問題なら十遍行つても構わないでしょうけれども、極く小さい問題で沢山集めて初めて一つの映画になるといったようなものを撮る場合には、到底出来ない。
(柳田、三木他 一九四一)
一つのムラを集中的に撮影するのではなく、「極く小さい問題」を大量に集めよと、データベースのためのデータ収集を主張する。『郷土研究』誌の主張する「小さな問題の登録」を映画でも試みられないかと考えているのである。
その具体的なイメージを柳田はこう述べる。
稲を刈って乾燥させる樣式といふものは、私の知って居るだけでも、少くとも十以上はある。例へば、關東附近のような平田地方では、直っすぐに棒を置いて、それに一列に掛けている。あれが越後に入ると、早く乾す必要があるので、家の回りなんかに高く引っ掛けて城壁のようになって家の天っぺんしか見えないようにして居る。(中略)それで越後はこう、京都府の山の中はこう、九州の佐賀縣の山の中はこう、海岸はこうといったような形を見せる。それを一番喜ぶのは稲を掛けている農民です。そうすると農村のものを撮っておきながら、農村のものに持てる。
(柳田、三木他 一九四一)
ここで示された態度は『石神問答』から重出立証法を経た方法と比して、より徹底していることがわかる。
そして、何より重要なのは、「稲の乾し型」の地域的偏差を「稲を掛けている農民」に向け見せる文化映画を計画している点である。
柳田の方法はこの地域偏差を時間的推移に変換するものだが、この引用が重要なのは、その偏差の担い手としての「農民」が自らの行為を偏差の中に位置付けるということである。ここで多様性という今ふうのことばを持ち出すのはいささか空しいが、柳田は改めてこう述べる。
これは一つの例なんですが、私はこういうような心持で、沢山の事例を早くから心掛けて、採って集めて、編集して比較して行くということにしたら、日本のまだ農民の姿で意義のあるものが非常に沢山あると思う。
(柳田、三木他 一九四一)
つまり、類似の事例を津々浦々で日頃から撮影し、撮影してそれを「集め」「編集して」様式の変遷を映像化すべきだとその「プリンシブル」を語る。
この座談会で無碍にされた三木は、しかし撮りためた写真で柳田との共著『雪国の民俗』を刊行する。しかし、その中で柳田は「写真」について駄目押しをするようにこう記した。
しかし物を視るにも兼ねての心掛けが必要である如く、話を聴くにもそれだけの容易が無くてはならぬ。斯ういう皮肉を浴びせかけるような覇気のある田舎人は、通例は必ず自分の説をもつて居て其通りに相手を思はせようとする腹がある。それを成程と聴いてしまっては、本とうは知ったことにはならい。斯ういう計畫のある意見や報告の類ならば、昔の巡検使でも今の視察員でも、皆之をきく機会をもつて居たのみならず、少し待って居れば向ふから、陳情といふものさへ遣ってくる。それが悉く的はずれだといふ気ずかいは無いが、我々はそういう多くの煩はしいものを綜合して、自分の判斷によって覚ったものを、農村の知識としなければならぬので、其爲には寧ろ写真でいうスナップのように、何の目途も無くおのずから言ひ出された言葉を、重んじなければならぬのである。そういふ中には思ひ掛けない暗示がある。それを鋭敏に把へて考へるだけの、練習も必要であり又態度ももって居なければならぬのである。
(柳田、一九四四)
柳田がここでまず危惧するのは、これまでと同様、カメラマンの作為ではなく被写体の「作為」であることはわかる。
そしてここで注意すべきは、「スナップ」なる語である。土門拳が、柳田らとの座談の中で柳田の考える写真を「スナップ」と言い換えているのは既に見た。今ではスナップ写真は日常語だが、これもこの時点では明瞭な方法意識に基づく語である。
スナップとは当時、こう定義されていた。
本來のスナップは、気付かれずに,第三者の立場で撮影することでありました。今日では、瞬間撮影をすることが凡てスナップであるように思はれてゐます。
(渡辺、一九三七)
柳田の言う「スナップ」は対象とする被写体に気づかれずに「第三者的」に撮影するという当初の意味を当然含むことは、動物の望遠レンズでの撮影への言及などで既に見た。
「スナップ撮影」の意味を変えたのは、ライカの小型・高性能で四十枚近い連続撮影ができる機能の一般化である。それは一方では、作為されない瞬間を連続写真によって偶発的に捉えるという考え方である。
しかし、他方では「スナップ」とは分節された刹那の時間のイメージであり、連続する時間の表象でもある。時間に還元しうるのが「スナップ」なのである。柳田の考えるスナップは後者である。
「スナップ」は新興写真運動の代表的技法であり、名取洋之助の得意とする手法でもあった。しかしそれはやはり「本質論」である。ライカの機能が可能にしたのは「人間の顔に瞬間的に内き出る性格」「刹那的にのみ督見された性格」(木村、一九三四)を写し撮ることで、その人物の「本質」を描くスナップショットである。これは先の土門の写真観にも近い。同様に手間は全く逆だが、重ね撮り写真が「本質」を描き出す点で重なる。
写真家たちは写真に写らぬ「本質」を写そうとしている点で変わらない。
三木もまた『雪国の春』でこう記す。
そしてそのひとつひとつの遺風習俗を觀察することによって、我々の祖先の意志といふものを知った。そこには日本の伝統の美しさ、日本の精神が宿されており、私は感動したのである。
(三木、一九四四)
「伝統」や「精神」を「写真」が写し撮ると幹は主張する。
しかし柳田にとって「スナップ」とは、第三者的な刹那の瞬間であるとともに、それが連続した時間の断片である、ということは明白だ。スナップの定義の中に時間の連続性の中の一瞬としての一ショットという概念が明確にあるのは当時の「スナップ」論で共通である。
これはヴェルトフが「あるがままのわれわれを不意に撮れ」と言ったのにも似ている。
この重出立証法やスナップが刹那の時間を前提とすることは重要である。
ここが柳田スナップ論の特異な点で、柳田はこの分断化された時間の断片としてのショットとして「偏差」を「スナップ」として捉え、それを元にして時間を再現しようとしているのである。
実は、重出立証法をめぐっては、戦後の論争の中でも「本質論」と「時間論」の二つの解釈があった。
一つは関敬吾に代表されるユングの原型の如き民俗文化のアーキタイプを抽出するもの。
つまり、本質論である。
昔話は神話をもとにしたものだと柳田先生は説いておられます。もっといえば、心理学者も原型ということをいうが、民俗学者はあまり好まないようです。その設定の方法が違っているわけです。ユンクやその学派はこの立場から神話を研究してますね。例えば、ユンクはあらゆる時代あらゆる民族の芸術や宗教のなかにあらわれる太陽、王、神の子のようなモティーフをアルケタイプ(原型)といっている。ユンクはこのモティーフを人類にとって固有の無意識のかつ生得的な理念として原古まで遡ろうとしている。
(関、一九七四)
これは歴史的な遡及で最も古い様式に至るものではなく、「本質」論に近い。
重ね撮り写真に坪井が期待したものだ。
対して、もう一つが「少しづつ違ったコマを並べていって早く回すと時間が出てくる」という谷川健一の理解だ。
座談会でも述べたように、重出立証法は映画のコマ絵の原理でもって、そこに変化する時間を求めることでもあるからだ。折口信夫は祖型の発見への志向がつよく、それで時間の観念を産み出そうとする願望は稀薄である。柳田国男はむしろ民俗事象を変化の相において捉えようとした。折口に文明批評がなく、柳田にそれが旺盛であるというのは、こうした両者の姿勢の違いによるところが大きい。
(谷川、一九七四)
重出立証法に話を戻すと、にはどうしたらよいかという課題がよこたわっている。それにはまず、方法として、民俗現象の中から即自的な時間を抜く必要がある。そうしてその民俗的な現象を地域社会の時間とかかわりない形で並べてみる。
民俗現象が個々のばあいには「即自的な時間」つまり、ただの刹那でしかないが、これを「他者と比較し得る時間に変える」という谷川は理解する。
これらは、カメラアイをただ、瞬間の切断でなく、互いにそれを繋ぐという意味を同時に持たせたヴェルトフにある意味で忠実だ。
「キノグラス」=私が映画視する(私がカメラを通して見る)+私が映画記録する(私がカメラでフィルムに記録する)+私が映画構成する(私がモンタージュする)
(ヴェルトフ、一九二九)
「見ること」と「撮影すること」が等価であるだけでなく、それをモンタージュ、構成する、という思考をヴェルトフのキノグラス概念は含む。柳田は撮影場所の異なる「スナップ」を「モンタージュ」する文化映画を構想していたのは明らかだ。それがモンタージュ論として正確なのは第一に「スナップ」という単独では意味が成立しない写真を最小単位として定義し、その「モンタージュ」によって新たな意味(柳田の場合は「歴史」を生成させようとする点である。これはエイゼンシュテインのモンタージュ論に極めて正確である。
こういった柳田の重出立証法をモンタージュと同義のコラージュという語で捉えたのが千葉徳爾である。
このような方法で本土の南北両端の状況を、つまり最も異なった土地の光景を持出して並べてみる。これがいわゆるコラージュと呼ばれる芸術的手法であって、両者の相違点と類似点とがもっとも鋭く示されるはずである。柳田の脳神経の飛躍のしかたは、まずこのような点に認められる。
(千葉、一九九八)
「コラージュ」は写真を同一視面に配置して新たな意味を生成させる手法で、千葉の理解は重出立証法の空間的変化をそう呼んでいることは明らかだ。
こうして見た時、新興芸術運動の「スナップ」は本質論であり、柳田の「スナップ」は時間的連続のない瞬間としてのショットであることは明確だ。
その三木はこう述べる。
それであるから、この本の写真ですは世に云ふ報道写真とか芸術写真とか云ふ美しい写真ではなく、云へばその方の本質とはまつたく反対な写真ばかりであると思う。
(三木、一九四四)
もつとも私自身さういう写真を作れない故もあるが、とかく初心を絶対的に美しいものにしなければ承知できない方々には失望を与えると思う。
私としては平凡でもよい、そのものがなんであるか、なんの目的を持っているか、なんで作られているか、どの位の大きさか、何時、何処でと云うことが明瞭でさえあれば、あとはそう必要ではないのである。
したがつてカメラの位置も、自分の眼の高さから上でもなく、下からでもない位置から撮影し、必要ない限り同一レンズを使ってトリミングを一切行はない方法をとつた。つまり有りのまま、そのままを見せたいと云うのが私の念願である。
三木はこのように自分の写真に作為はないという。
しかし三木の『雪国の春』に於ける写真は新興芸術運動的な「スナップ」であり、作為がないどころかそこに参与した人々が参照したドイツやソビエトのプロパガンダ写真に特有のローアングルが採用され、柳田の思考からは正反対である。
その点で、三木と柳田の方法には根本的な乖離が最後まで埋まらなかった。
以上、早足で概観したが、柳田の学問の方法は、
①参与者一人一人がデータベースづくり/アーカイヴィングの参加者であり、
②その作業の中で自身の担うミニマムな地域や、あるいは「現在」にしか見えぬものが地域的な偏差とそれが還元された時間の中に自ずと位置付けられる、
というものだとわかる。それをアカデミズム的な「研究」ではなく、社会運動として行おうとしており、このようなアーカイヴ制作の過程それ自体が「学問」であるという思考に基づく。
そこには情報論で「ローデータ」と侮蔑的に呼ばれる一つ一つのデータの固有性と、それが帰属する集合知への道筋が「本質論」でなく多様性・他者性の中で位置付けられる。
このように柳田の「学問」が情報論と人文学の接合がお題目として叫ばれる時代に、既に充全な回答を用意していることは明らかなのである。
それを柳田はこう『民間伝承論』で、結論した。
フォクロアはどこまでも常民大衆の生活より帰納せらるべき学問であって、あらかじめ煙にまかし盲従させるべき英雄的事業ではないのである。採集・分類・索引・比較・綜合の事業が、この基礎の上で行わるべきであることを自分が強調する所以である。
(柳田、一九三四)
このように情報論によって「生活」を帰納せしめる方法として、民俗学はかつて設計された。
【参考文献】
岡正雄「柳田國男との出会い」『柳田国男研究』創刊号(一九七三年)
関敬吾「日本民俗学の歴史」『日本民俗学大系 日本民俗学の歴史と課題 第2巻』(一九六二年、平凡社)
谷川健一「「重出立証法」私見 民俗学と時間」『季刊柳田國男研究 第六号』(一九七四年、白鯨社)
千葉徳爾、「柳田國男と初期民俗学研究法─自学とその成果を中心に─」『日本民俗学』215号(一九九八年)
坪井正五郎「「重ね寫眞」の術を觀相其他に應用する考案」『青年界』第三巻第十二号(一九〇四年)
松村瞭「人類学上より観たる日本民族」『人類学雑誌』第41巻第12号(一九二六年)
三木茂「あとがき」柳田國男・三木茂『雪國の民俗』(一九四四年、 養徳社)
渡辺義雄『スナップ写真の狙ひ方・写し方』(一九三七年、玄光社)
柳田國男『石神問答』(一九一〇年、聚精堂)
柳田國男「編輯者の一人より」『民族』1巻1号(一九二五年-1)
柳田國男「編輯者より」『民族』2巻2号(一九二七年-1)
柳田國男「編輯者の一人より」『民族』2巻6号(一九二七年-2)
柳田國男「編輯者より」『民族』3巻1号(一九二七年-3)
柳田國男『現代史学大系 第七巻 民間伝承論』(一九三四年、共立社)
柳田國男「小さき問題の登錄」『民間傳承』第一巻一号(一九三五年、国書刊行会)
柳田國男「文化映画と民間伝承」『文化映画研究』一九三九年五月号
柳田國男「雪国の話」柳田國男・三木茂『雪國の民俗』(一九四四年、 養徳社)
柳田國男・土門拳・濱谷浩・田中俊雄・坂本万七「座談会:民俗と写真」『写真文化』一九四三年九月号
柳田國男・橋浦泰雄・村治夫・三木茂・津村秀夫「座談会 柳田國男氏を圍んで 文化映畫と民俗學」『新映画』一九四一年三月号
関敬語他「座談会 民俗学の方法を問う」『季刊柳田國男研究 第六号』(一九七四年、白鯨社)
Dz・ヴェルトフ著/近藤昌夫役「「キノグラス」から「ラジオグラス」へ(キノキの入門書より)」、大石雅彦・田中陽編『ロシア・アヴァンギャルド③ キノ─映像言語の創造』(一九九四年、国書刊行会)
木村伊兵衛「文芸家の肖像」『アサヒカメラ』一九三四年一月号
大塚英志『殺生と戦争の民俗学 : 柳田國男と千葉徳爾』(二〇一七年、角川選書)
大塚英志『公民の民俗学』(二〇〇七年、作品社)
筆者について
おおつか・えいじ。国際日本文化研究センター教授。まんが原作者。
著書に『手塚治虫と戦時下メディア理論 文化工作・記録映画・機械芸術』(星海社、2018年)、『大政翼賛会のメディアミックス『翼賛一家』と参加するファシズム』(平凡社、2018年)、『大東亜共栄圏のクールジャパン「協働」する文化工作』(集英社新書、2022年)、『「暮し」のファシズム ――戦争は「新しい生活様式」の顔をしてやってきた』(筑摩選書、2021年)、『シン・論 おたくとアヴァンギャルド』(太田出版、2022年)、『木島日記 うつろ舟』『北神伝綺』『北神伝綺 妹の力』(いずれも星海社、2022年)など。
現在の研究テーマは戦時下のメディア理論と文化工作。