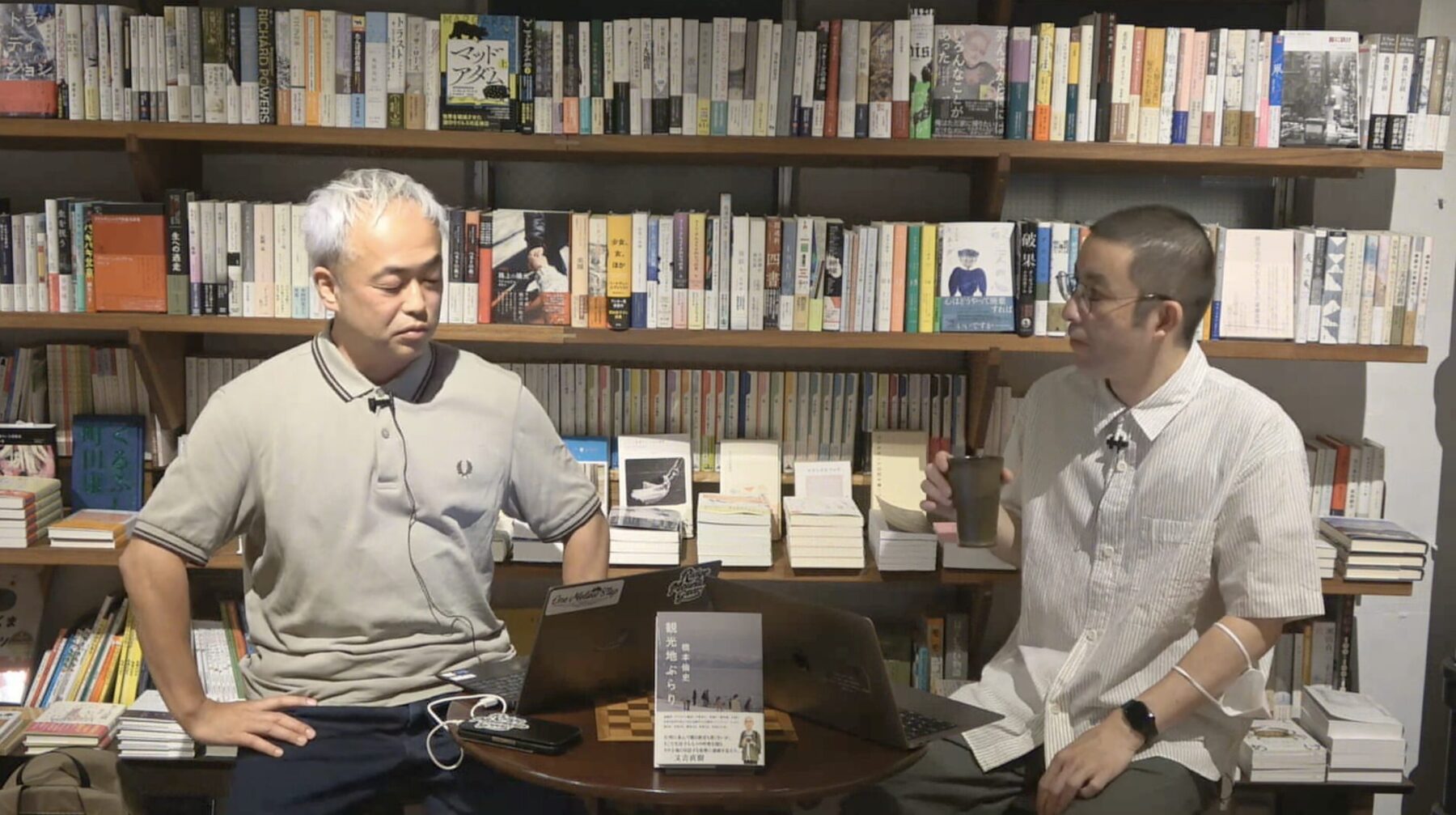橋本倫史『観光地ぶらり』(太田出版)の刊行記念として、2024年5月25日、東京・三鷹の書店UNITÉでトークイベントが行われました。「いま、ノンフィクションを書くということ」というテーマで、著者の聞き手を担当編集者が務めた対談の記録をお送りします。文学は社会を変えることができるのか。
編集者との今に至るまでの時間があって『観光地ぶらり』ができた
橋本倫史(以下、橋本) この三鷹の「UNITÉ」という書店から「うちでトークイベントを」というお話をいただいて、どんなテーマがいいかと考えていたときに、ノンフィクションが本になるまでのことを話すのがいいんじゃないかと思ったんです。今回の『観光地ぶらり』は、この企画だけがポンとあるわけじゃなくて、森山さんと知り合ってから今に至るまでの時間があるんですよね。森山さんと知り合ったのは2005年だから、もう20年近く前で。
橋本倫史(はしもと・ともふみ)1982年広島県東広島市生まれ。物書き。著書に『ドライブイン探訪』(ちくま文庫)、『市場界隈 那覇市第一牧志公設市場の人々』、『東京の古本屋』、『そして市場はつづく』(以上、本の雑誌社)、『水納島再訪』(講談社)、『観光地ぶらり』(太田出版)がある。
森山裕之(以下、森山) そんなに経ちますか?
森山裕之(もりやま・ひろゆき)1974年長野県長野市生まれ。編集者。株式会社太田出版代表取締役社長。主な担当書籍に『虹ヶ原 ホログラフ』(著=浅野いにお、太田出版)、『ばらばら』(著=星野源、写真=平野太呂、リトルモア)、『東京百景』(著=又吉直樹、ヨシモトブックス)、『青春狂走曲』(サニーデイ・サービス/北沢夏音=著、スタンド・ブックス)などがある。
橋本 当時僕は、評論家の坪内祐三さんが早稲田大学で受け持っていた授業を履修していて、それが「編集・ジャーナリズム論」という講義だったんです。授業が終わると、すぐ近くにある「金城庵(きんじょうあん)」というお蕎麦屋さんで飲み会があって、そこには坪内さんの担当編集者の方たちもいらしていて。そこに森山さんもいらっしゃっていたんですけど、森山さんは編集者の方たちのなかでも最年少くらいでしたよね?
森山 今50歳なんで、30歳前後でしたね。橋本くんはあの頃、20歳ぐらいでしたっけ?
橋本 大学4年生で、23になる年でした。それまで僕は文学が好きだったわけでもなかったところから、坪内さんの授業をたまたま履修したところから、「面白そうな世界がある」と気づかされて、そこからいつのまにか今の仕事に至っていて——。森山さんは当時、雑誌『クイック・ジャパン』の編集長でしたね。
森山 ちょうど坪内さんに、『東京』というエッセイの連載をしていただいていました。でもそれも、始めるのがなかなか大変だったんです。一度連載を引き受けていただいたんですが、いざ原稿をという段で、なかなか第1回を書いていただけなくて。当時の連絡手段は電話かファックスでしたけど、ここから先は何度もご連絡するのも申し訳ないなと思って、坪内さんが行く酒場に当てずっぽうで通って、どうにかして坪内さんに会おうとしてたんです。そういう場所のひとつが「金城庵」で、どうにか連載を始めてもらうことができたんですけど。
橋本 もちろん、森山さんはそれ以前から坪内さんと面識があったのは大きいと思うんですけど、今のお話、ちょっと面白いですね。というのも、坪内さんは当時、雑誌『ダ・カーポ』で『酒日誌』を連載されていて、どこで飲んでいるか、ある程度あたりをつけることもできたと思うんです。ただ、自分が通っている酒場に編集者が待ち構えていてることを、坪内さんはわりと嫌いそうだな、と。
森山 はい。待ち構えている感じを出さないようにしました(笑)。僕もふらっと行ったという体で、神保町とか銀座とか新宿とか、いろんな酒場に行きましたね。とにかく電話で催促するのが嫌だったんです。だからハズレも多かったですけど、最後にどこかの酒場でご一緒したときに、「森山さんもよくやるねえ」と言われて、「森山さんが編集長を務めるリニューアル1号目に原稿はもう間に合わないからゼロ回として敬ちゃん(連載の写真を撮り下ろすことが決まっていた写真家の北島敬三さん)と対談しよう」と。それでリニューアル号にゼロ回の対談を掲載し、次号から『東京』の連載が始まりました。自分の雑誌には坪内さんの言葉が必要だと思っていたので、そこから始めたいと思ったんです。
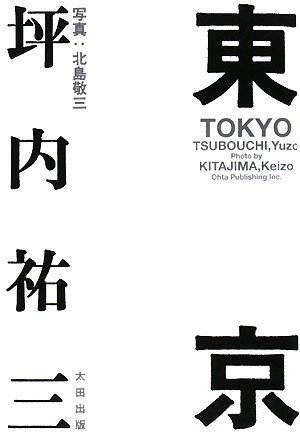
コストパフォーマンスからいちばん遠い書き手
橋本 2005年に坪内さんの授業を受けて、僕はそこで初めて編集者という存在を目の当たりにしたんですけど、その当時は「ライターになりたい」と思っていたわけでもなかったんです。だから、『クイック・ジャパン』の編集長だった時代の森山さんとは仕事でご一緒したことはなくて。しっかり仕事でご一緒したのは、森山さんがその後吉本興業に移られて、『マンスリーよしもと』という雑誌をリニューアルされたときなんですよね。最初の頃は編集会議にも呼んでもらってました。
森山 そうでしたっけ?
橋本 そうなんです。フリーの編集者やライターの方、吉本の社員の方もいて、「特集はどうするか?」って会議をやっていて。僕は当時、ほんとにひよっこみたいなライターだったので、編集会議に行っても、端っこにちょこんと座ってるだけでしたけど。
森山 そんなこと、やってましたね。そういうのが大事だと思ってたんです。もともと広報誌として30年ぐらい続いてきた『マンスリーよしもと』を、ジャーナリズムというか、同時代のお笑いを切り取るような雑誌に変えたいと思ったんですね。そういう雑誌をつくろうと思ったときに、編集者の頭の中とかアンテナなんて知れてると思ったし、自分のこと自体信用してなかったので、感度のあるライターさんや放送作家さんを集めて、今このタイミングに何を出すべきかってことを考えたいと思っていました。でも——ちゃんと会議費出してましたっけ?
橋本 どうでしたっけ。ちょっと、そこまでおぼえてなくて。
森山 充分ではなかったと思いますが、確か出してた気がします。『クイック・ジャパン』の頃は、ライターを集めての企画会議なんて考えもしなかったから、企画を出してくれたライターにはその記事の担当をお願いしていました。『マンスリーよしもと』をリニューアルしたときは、テレビ番組の企画会議の形式を持ち込んで、いろんな人の知恵を持ち寄って、その時代の記録としてのお笑いの雑誌をつくりたいと考えたんですね。それで橋本くんにも来てもらったと思います。
橋本 一緒に会議に参加してる方たちって、放送作家であれ編集者であれスペシャリストで、皆さん「こういうテーマを!」というものを持ってらしたんですよね。ただ、当時の自分としては、「私が気になっているテーマはこれです!」と打ち出せるものが何もなくて。テレビは好きでしたし、お笑いも好きでしたけど、ただ好きってだけだった。20代の頃を思い返してみると、酒場で出会った編集者の人から「へえ、ライターなんだ? 専門は何?」とかって言われることも多くて、そのたびに「いや、特に専門がどうとかってことじゃないんですけど」って、もごもご答えていたんです。そんな状態だったから、せっかく呼んでもらっていた編集会議からも、徐々にフェードアウトして。ただ、編集会議には参加しなくなっても、ライターとしては関わり続けていたんですけど、印象に残っている号のひとつが『マンスリーよしもとPLUS』(2011年2月号)で。このときの第2特集が「ピース」なんですよね。

森山 これ、ピースがキングオブコントで準優勝した直後でしたね。
橋本 そうなんです。このピース特集のなかで、僕がどういう記事を担当したのかと読み返してみると、そのひとつが「完全密着 ある日のピース」というルポ記事なんですよね。朝10時から29時半まで密着取材して書いた記事なんですけど、声をかけてもらえるのはやっぱりこういう企画だったんだな、と。
森山 橋本くんの著書『東京の古本屋』と、やってることは変わらないですね(笑)。

橋本 自分で聞くのもどうかとは思うんですけど、この当時、「こういう取材に関しては橋本に振ってみよう」というのは、どういうところで選んでくださってたんですか?
森山 あれはなんだっけ——たぶんキングオブコントの現場だったと思うんだけど、囲み取材も終わってるのに、又吉くんのところにしつこく取材してる人がいたんですよ。それが橋本くんだった(笑)。
橋本 ありましたね。キングオブコント決勝の密着取材で入っているときでした。
森山 囲み取材って、大体面白くないんですよ——それが終わったあとに、まだ粘って最後まで言葉を拾おうとしている橋本くんを見て、しつこいなあとも思ったし、信頼できるなとも思ったんです。そういう意味では全然変わってないですね。この『観光地ぶらり』もそうですけど、橋本くんってコストパフォーマンスからいちばん遠い書き手のひとりですよね(笑)。でも、橋本くんにとって切実だからこそ同じ場所に何回も通って取材するんだと思うんですよね。橋本くんがピースの又吉直樹くんと会ったのもそのときがほぼ初めてだったと思うんだけど、あのときのしつこさというか、そこで橋本くんが投げかけた言葉に切実さがあったからこそ、又吉くんも信用したし、ちゃんと応えたんだと思います。その後も橋本くんと又吉くんの関係も続いて、今回『観光地ぶらり』の帯文を又吉くんに書いていただくことにもなりました。又吉くんは言葉を大事にする人だし、相手がその言葉を必要としているのかどうかを大事にする人だと思うから。だから——ほんとにコストパフォーマンスが悪い。それに尽きるんじゃないですか。しかしそれは書き手としての橋本くん自身にとって必要なコストというか、書くための方法論なんじゃないかと思っています。書くものにもそのコストが確実に表われているから。