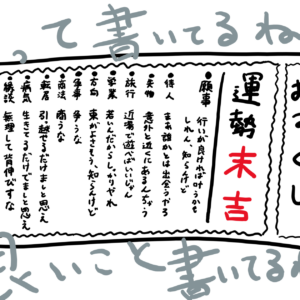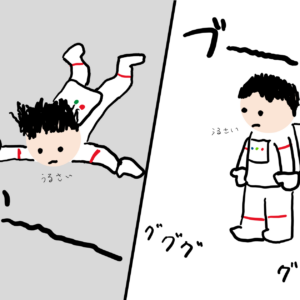宇宙機の制御工学を専門としながら、JAXAのはやぶさ2・OKEANOS・トランスフォーマーなどのさまざまな宇宙開発プロジェクトに携わる、宇宙工学研究者・久保勇貴の新連載がOHTABOOKSTANDに登場! 久保さんはコロナ禍以降、なんと在宅研究をしながら一人暮らし用のワンルームから宇宙開発プロジェクトに参加しているそうで……!? 地べたと宇宙をダイナミックかつロマンティックに飛び回る、新時代の宇宙エッセイをお楽しみください。
宇宙研の桜
国道の脇の並木道を抜けると快晴だった。吐いた息が白くなった。守衛所に朝が来ていた。
僕は、ワンルームを飛び出して久しぶりに研究所に来ていた。守衛のおじさんに在勤証を見せ、寝ぼけた自転車で正門をくぐる。守衛のおじさんはシャンと背筋を正しながらも、肩肘をほどよく脱力した敬礼で挨拶してくれる。それに、僕も脱力ぎみの会釈をとろりと返す。冬の日、2月の朝。JAXA宇宙科学研究所、通称「宇宙研」と呼ばれる研究所に、僕は今通っている。
JAXAは、実は2003年までは全く異なる三つの研究機関だった。飛行機の研究をする航空技術研究所(NAL)、宇宙の実用的な利用に主眼を置く宇宙開発事業団(NASDA)、そして宇宙の科学を探究する宇宙科学研究所(宇宙研)の3つ。2003年に統合されてJAXAという一つの組織になった後もなんだかんだそれぞれの気風は色濃く残っていて、JAXAの事業所ごとに研究の方針も雰囲気も実は結構違っている。特に、他の二機関と違って「宇宙研」の名は今でも部門名として正式に残っていて、拠点である相模原キャンパスには宇宙科学・宇宙探査の最先端を切り拓いてきた開拓者精神みたいなものが未だに根付いている。元々は東京大学の研究グループが母体だったという背景から今でも学生を受け入れていて、そのせいなのかどことなくアットホームな空気が強いのも宇宙研の特徴だ。
守衛所から真っすぐ前を向くと、突き当たりには大きな桜の木が一本立っていて、その日も静かに春を待っていた。毎年満開の季節になると、記念写真を撮る研究グループをどこからともなく呼び寄せる、大きな桜の木。そう、「科学」とか「宇宙開発」とか言うと、なんとなく冷徹なマッドサイエンティストのイメージとか無機質な宇宙船のイメージとかと結びつくことも多い気がするけれど、やっぱりそこには「人」がいるのだということを、この桜の木はいつもふんわりと思い出させてくれる。当たり前だけど研究者にも季節感があって、個人的な感情がある。宇宙開発は人の気持ちで動いている。宇宙研のアットホームな空気、そしてその背後にある人間味を支える柱として立っているようで、だから、僕はこの桜の木が好きなんだと思う。
自転車で桜の木の方に向かっていくと、その右手には実寸大の大きなロケットの模型が二つ見えてくる。1985年の国際ハレー彗星探査でも活躍したM-3SIIロケットと、初代はやぶさをはじめとして多くの挑戦的ミッションを支えてきたM-Vロケット。東から西に向かってカメラを構えれば、ちょうどそのロケットが桜の木の枝の懐にすっぽりと収まる形で配置されている。遠くから見ると巨大な白いクレヨンみたいなシルエットをしていて、その風貌がなんともかわいらしくて、だから、僕はこのロケットたちが好きなんだと思う。
春を待つ桜の木はまだ蕾を一つも付けていなくて、だから、まばらな枝の隙間から後ろの景色が透けて見えた。重ねればそれはカメラアプリの過剰なフィルターのように、背景に写るものに枝木の黒い脈を投影した。自転車で動きながら見ると、そのフィルターの底には朝景色が流れていて、つまり写るものと写すものとが、映画の二重写しのように動くのだった。

宇宙開発の父・糸川英夫の根性とペンシルロケット
宇宙研のロケットは、人の気持ちと根性で飛ばしてきたような歴史がある。なんせ、アメリカやソ連が既に数十トンサイズのデカいロケットを打ち上げていた1950年代に、ようやく200グラムのおもちゃみたいなロケットで研究開発を始めようとしていたのだ。ちょうどGHQによる航空機研究の禁止令が解かれた頃だった。そんな中で、「ロケットを使って太平洋を二十分で横断だ!」なんて構想を堂々と掲げていたんだから、恐らく理屈よりも根性で前に進んでいた感じだったんじゃないかと思う。当時研究グループを率いていた糸川英夫先生は、「1958年までに、高度100km辺りまで到達できるロケットを日本が打ち上げることができますか?」と文部省の役人に聞かれた時も、「飛ばしましょう。」と一切ためらわなかったらしい(※1)。おもちゃみたいなロケットを飛ばしていた頃に、この威勢である。敗戦後の赤字まみれの経済も、敗戦国に向けられた憐れみの目も全部ひっくり返してやろうという意志と根性でロケットを飛ばし続けたんじゃないだろうか。「ペンシルロケット」と呼ばれた糸川先生のこのおもちゃみたいなロケットが、宇宙研のロケットの歴史の全ての始まりだった。開拓者精神というとちょっぴり大げさに聞こえるけれど、この頃の技術者たちの根性は今の宇宙研の気風にしっかりと引き継がれていると思う。
桜の木を横目に見ながら自転車を漕ぐ。駐輪場へ向かう道のレンガの舗装は数年前からところどころゆるゆるになっていて、踏むとポコポコと音を立てながらレンガが揺れる。自転車でその上を走ると、ポコポコポコポコポコポコ、そして、見上げた快晴の空にはポツンと黒い機影が見えた。おっ、と声が出そうになって、しかし、渇いた声帯は思うように振動せず、口先だけが無意味にとんがった。軍用輸送機だった。宇宙研のある相模原市は横田基地と厚木基地のちょうど真ん中あたりに位置していて、軍用機がたまに空を飛んでいる。旅客機よりもガタイのいい機体は不愛想な色で塗られていて、しかし、はるか上空をゆったりと動くそれは、いつもなんだか遠い出来事のように通り過ぎていく。そういう時、僕は大体ぼーっとしている。まあそんなもんか、と思う。目の前で動いているのに、確実に見えているのに、それがとりあえず今の自分の生活には直接関係ないことに安心している。冬の日、2月の朝。軍用機はゆったりと動いているように見えても着実に目的地へ向かって飛んでいて、だから、あっという間に遠くの空に見えなくなった。
糸川先生は、元々は飛行機の設計者だった。中学生の頃にリンドバーグによる大西洋横断に感化されて航空学科に進み、中島飛行機に入社してプロの設計者になった。1935年だった。ヒトラーがベルサイユ条約を破棄した年だった。そうしてすぐに戦争に巻き込まれて、軍の命令で戦闘機を作らなければいけなくなった。糸川先生らは陸軍の隼(はやぶさ)という戦闘機を設計した。名機だった。けれども戦争に負けて、航空機の研究はアメリカに全面禁止された。夢を追いかけて、時代に振り回されて、それでもめげず、再び情熱を傾け始めたのがあのおもちゃみたいなペンシルロケットだった。
空を飛ぶ技術と戦争
空を飛ぶ技術、つまり航空と宇宙の技術は、そのまんま軍事の技術でもある。飛行機は銃を付ければ戦闘機になるし、ロケットだって人工衛星の代わりに爆弾を載せるだけでそのまんまミサイルになってしまう。ミサイルもロケットも、根本的な技術は全く同じものだ。冷戦時のアメリカ・ソ連の宇宙開発競争も、建前上は夢や希望を与えるためとか言っていても、結局は軍事的に相手より勝るためのものだった。そう考えると宇宙研の、ひいては日本のロケット開発の歴史は特殊だった。弾道ミサイルをロケットに転用するという始まり方ではなく、あくまで糸川先生が掲げる平和利用的なロケットの構想から発展していったものだった。
駐輪場に自転車を止め、レンガ舗装の道を歩いて引き返す。相変わらずゆるゆるのレンガは、一歩一歩足を踏み出す度に、ポコ、ポコ、ポコ、ポコ、ポコ、ポコ、そして、食堂の前で鳥が死んでいた。生垣の脇で仰向けになって白いお腹を見せながら、手足をお行儀よく縮めて硬直していた。何という鳥かは分からなかった。血は出ていなかった。上から覗くと顎を上げたような格好に見えるその顔は、力なく目を閉じていて、だからだろうか、どこか恍惚としたような印象だった。快晴の朝に落とされた、非現実的な世界の幻影のようだった。硬直した体が朝の空気に包まれてやわらかになり、しかし、人形じみた無抵抗さ、命の通っていない自由さで、生も死も休止したような姿だった。だから、ずっと見ていたかったのだけれど、死体を観察しているところを周りに見られるのはなんだかいけないことのような気がしてきて、それで、目を逸らした。
僕は飛んでいった飛行機は全機、無事に帰ってきてもらいたいって、ずっと願っていたよ。でも自分の飛行機は特攻に使われたり、人殺しさせたと言って非難されたりした。鉄板(防弾板)一枚を隼の座席の背中に入れたら助かったパイロットもいっぱいいたはずだよ。でも「1グラムも重くするな」と言われて、それはできなかったんだ。飛行機は僕の子供だよ。子供に人殺しさせたい親がどこにいるんだ。
『後列のひと 無名人の戦後史』 清武 英利/文藝春秋 /75ページ
糸川先生は10年ほどロケット開発の最前線に立ってから東京大学を辞め、その後は妻と子供を置いてアンさんという女性の家に居ついて暮らしていたらしい。堂々とはしていたようだけど、浮気や不倫と言ってもいいのかもしれない。
僕はアンさんと何回も別れようと思ったんだよ。でもね、もうこれっきりにしようと言って、橋の真ん中から両方に歩き出して、渡り終わったらまた振り向いて一緒になっちゃうんだよね。
後列のひと 無名人の戦後史』 清武 英利/文藝春秋 /76ページ
そう、人には個人的な感情がある。研究者にも季節感があるように、日本の宇宙開発の父である糸川先生にも個人的な感情がある。きっとそう、不愛想な色の軍用機を操縦していたパイロットにも、感情がある。きっとそうだ。
「あのね、久保さん」
ある先生との会話を思い出す。
「個人としては、今の世界の状況は、本当に涙が出ます」
「でもね、」
「僕らは、科学を淡々と伝えるしかないんです」
その先生はいつもほんわかした笑顔で気さくに話す人で、お酒を飲んだらちょっぴり陽気になりすぎてしまう人で、その先生が、少しも茶化した態度を取らずに僕に語りかけていた。真っすぐな言葉だった。優しい言葉だった。
「個人の感情はそうだけど、でも、組織としてはそういう立場は表明できないんです」
「僕らの立場としては、静観しかないんです」
優しい言葉だった。だからこそ、悲しくてたまらなかった。個人の感情はそうで、でも宇宙の技術はそのまんま軍事の技術で、宇宙開発は複雑な国際関係の中で成り立っていて、優しくないから争うのではなくて、みんな優しくて、優しいのに、それでも争いを止めることはできないのだった。
「僕ら科学者は、ニュートラルな立場で科学を語れる稀有の存在なんです」
「久保さん、そうなんだよ」
「糸川英夫だって、そうだったんだよ」
研究者には、決して感情が無いわけではない。みんな個人的な感情があって、そう、悲しい。正確に宇宙機を飛ばすための技術は、正確に人を殺すための技術にもなってしまう。誰かが大切にしているものを、正確に壊すための技術にもなってしまう。でも、だから、僕たちは淡々と科学をやる、しかないのだろう、きっと。けれど、本当はどうすればいいかなんて全然わからない。こんなことしてていいんだろうか、とか思う。我が子のように大切に研究を育てて、それで、その研究の成果が人を正確に殺すことに貢献したなら、僕は人殺しの親だろうか。ちがう。ちがうけど、どのくらいちがうんだろう。定性的に? ちがう。定量的に? ちがう! 頭がぼーっとする。だけどぼーっとしてると、遠くの国の悲しみは遠い出来事のように通り過ぎていってしまう。動いているのに、見えているのに、それがとりあえず今の自分の生活には直接関係ないことに安心してしまう。だから、どうすればいいか僕には全然わからない。わからないまま時間が過ぎる。あの日、先生との会話が終わったあとで、僕は誰もいない部屋で声を上げて泣いた。どうすればいいかわからなくて、自分の浅はかな考えが恥ずかしくて、みんな優しくて、優しいのに無力で、泣いたのだった。
鳥の死体は、週が明けると無くなっていた。血も付いていなかった。跡形もなく綺麗に無くなっていて、そうして、まあそんなもんか、と思った。また死が通り過ぎた。桜の蕾は一つも付いていなかった。軍用機は飛んでいなかった。何にもなかった。雲一つなかった。快晴だった。頬がほてって目ばかり冷たい。瞼が濡れた。よろめくように後ずさって目を上げた途端、さあと音を立てて青空が僕の眼のなかへ流れ落ちるようだった。僕にできることは、何一つなかった。
* * *
※1 日本の宇宙開発の歴史[宇宙研物語] – 『ある新聞記事』 https://www.isas.jaxa.jp/j/japan_s_history/chapter01/01/04.shtml
【お知らせ】
当連載を収録した書籍『ワンルームから宇宙をのぞく』は、全国書店やAmazonなどの通販サイト、電子ブックストアにて好評発売中です。
筆者について
くぼ・ゆうき。宇宙工学研究者。宇宙機の制御工学を専門としながら、JAXAのはやぶさ2・OKEANOS・トランスフォーマーなどのさまざまな宇宙開発プロジェクトに携わっている。ガンダムが好きで、抹茶が嫌い。オンラインメディアUmeeTにて「宇宙を泳ぐひと」を連載中。