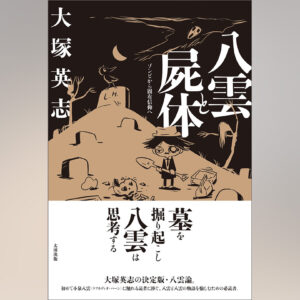5月13日(金)に公開された『シン・ウルトラマン』。庵野秀明氏による「シン・」シリーズはご存知のとおり、この後にも更に『シン・仮面ライダー』が控えていますが、ゴジラ、エヴァンゲリオン、ウルトラマン、仮面ライダーと連なる一連の「シン・」作品群には、一貫して通底する美学や方法、これまで見えにくかった文脈が確かに存在します。それを初めて可視化するのが、大塚英志新刊『シン・論 おたくとアヴァンギャルド』です。
ここでは、本書から一部をご紹介していきます。(全3回)
ログラインとしてのまえがき
本書における試みはさほど斬新なものではない。『シン・エヴァンゲリオン劇場版』(以下、『シン・エヴァ』と表記する)をありふれたアヴァンギャルドの歴史の中にただ再配置するものである。
別の言い方をすれば、本書は『エヴァンゲリオン』シリーズの背後にある凡そ近代100年の「教養」の所在についてその外郭をデッサンするものだ。
そのための立論が、例えば最初の10分程における、エッフェル塔のローアングルから戦艦の360度描写に至る美学とその無自覚な政治性の出自がどこにあるのかという問いである。それを探ることで『シン・エヴァ』が近代表現におけるありふれた事態としてある、世界表現の機械化の極東における様式化の達成であることを確かめる。その様式化は日本近代史においては、第一次世界大戦後に世界的規模で開始された世界の機械的記述という思潮を踏まえ、十五年戦争と呼ばれるこの国の戦争下で、表現全体の中で理論的仮説と実践からなる相互作用的な先鋭化が起き、それが戦後に継承された事態の結果としてあるものだ。筆者がしばしば諧謔として「おたく文化の戦時下起源」と呼ぶのはそのような現象を指摘してのことであり、『シン・エヴァ』の庵野秀明に代表されるおたく第一世代はそのことに自覚的だった再末尾に当たる。だからこれも繰り返す言い方だが『ゴジラ』や『ウルトラマン』の「特撮」の出自を自力で探れば『ハワイ・マレー沖海戦』やP.C.L.(写真化学研究所)に容易にたどり着き、しかしそれらの「教養」はポリティカルな意味は不問のまま無頓着にストックされ、殊更、その政治性について互いに語りもしなかったのである。
このような様式性は別の側面を持ち出せば「世界」を俯瞰するときにミニチュアとして把握せずにはおれない作法としても方法化される。それがいかなる世界認識に至るかは、当然だが無頓着である。何故ならそれらは「工学化」しているからである。しかも、戦後に継承されたこれらの「方法」と「美学」は近代戦争を構成主義的な意味で「構成」するもので、その様式はそれ故、イデオロギーにかかわらず、描くべきものとしての「戦争」を呼び起こし続ける。宮崎駿からガイナックスに至るおたく表現が「戦争」を描くことに寄せる方法的執念の理由はここにある。それはこの国のおたく表現が戦争機械芸術の一部に過ぎないことを意味するが、しかしそれはミリタリー表現に限定されない。
庵野秀明の鉄塔、新海誠の踏切遮断機のフェティシズムや初期『ウルトラマン』『ウルトラセブン』に於ける幾何学図形と『エヴァンゲリオン』の使徒の幾何学性の背後にはロシアアヴァンギャルド的な「構成主義」の美学を、あまりにありふれた議論とは言え、改めて見ないわけにはいかない。
同様の「ありふれた」議論はいくらでも可能だ。
プラグスーツの出自はフリッツ・ラングの映画『メトロポリス』における人造人間マリアだが、大正新興美術運動において「人造人間」は、一方ではカレル・チャペックの戯曲『R.U.R.』における万能細胞的な原形質、他方では、ユダヤ教的なゴーレム(ユダヤ教の伝承に登場する自分で動く泥人形)の双方の文脈を持っていることも殊更指摘するまでもない。綾波レイへの歴史的出自の説明が今更、必要とも思えない。
「第3村」も同様である。身体は戦争という機械化されたシステムを構成する。身体の記号的な書式と兵器あるいは身体のリアリズムの「共存」はその副産物である。戦争という機械への身体の組み込みはいうまでもなく「前線」でなく「銃後」でもおき、そして「生産」の現場でマルクス主義との共犯によって身体の定義にもなる。「労働」の戦争への組み込みもまた「機械芸術」であり画一化した喜びが求められる。
機械化、すなわち、メカニズムは「物語」の水位にも至る。文学の「メカニズム」化は横光利一「機械」や探偵小説といった機械化文学となる一方、教養小説のフォルマリズム的な「機械化」としてプロップらの「昔話の形態学」がある。この教養小説の機械化の文脈はRPGにまでは最小限、通底しうる。ストーリーテリングは「成熟」のゲーム的達成として描かれる。その先に、「成熟」のゲーム的達成を喜ぶ「批評」が待ち構えている。
こういった芸術の戦争機械化と戦時下、同時進行したのが「言説」や「身体」の発露による参加型の「協働的」とでもいうべきファシズムであり、それが「物語」や「キャラクター」の水位で行われれば物語消費(メディアミックス)になる。ゼロ年代以降は参加型による批評空間がオンライン上に整備されるが、この情報空間の受け手による自発的補完は大政翼賛会や報道技術研究会の動員技術の最終形であり、『シン・エヴァ』の「ネタバレ」や「考察」の統率のとれた管理はその援用にさえ思える。そこでおきているのは「考察」と自称する批評とテキストの補完関係、まさに相互の他者性の喪失という点でネルフの野望に近いものだ。
本書はそのような機械化的教養の戦時下における形成史をローアングルのエッフェル塔、第3村の出自、人造人間論の三つのありふれた視点からありふれた記述をすることでその所在を確認する。しかしそれは『シン・エヴァ』の是非や解を語るのではない。動機としてあるとすれば同作がそのような方法=美学の実装化を徹底したということへの「慰労」としか言いようのないものである。
実を言えば、ひとつひとつの文章は『シン・エヴァ』のために用意されたものではない。それぞれ独立して別の目的で書かれ、『シン・エヴァ』を生成したのと同じ「教養」の所在と、別形式の発露について書かれたものだ。近代、あるいは戦時下の機械的教養の所在を指摘するのに個別に書かれたが、しかし、『シン・エヴァ』の上に配置すると極めて分かりやすいものになる。それは『シン・エヴァ』が、というより『シン・ゴジラ』を出発点とし、『シン・ウルトラマン』『シン・仮面ライダー』と続く「シン」なる試みが、例えば成田亨のデザイン画に準拠しカラータイマーを消去したように、これらの「おたく」周辺の歴史的教養を踏まえたあるべき形へのある程度、自覚的な「つくり直し」であると感じるからだ。結果的に顕わになるのはおたく表現史の表現による歴史修正が「シン」の意図するものであろうという「批評」ではある。各論考はこの「ログライン」に従って読み取っていただくことで『シン・エヴァ』へと機械的に、無粋に変換されるだろう。
* * *
本書では、『シン・エヴァ』シリーズや手塚治虫、柳田國男の映画論などからひも解く郷土映画論や、『シン・ゴジラ』でも描かれた日本映画独自の「変身」「変形」への執着論など、著者・大塚英志が戦後の「おたく」表現のフェティシズムや美学の出自について新たな切り口で論考しています。
大塚英志の最新刊、挑発的芸術論『シン・論 おたくとアヴァンギャルド』は、全国の書店・通販サイトや電子書店で大好評発売中です。
筆者について
おおつか・えいじ。国際日本文化研究センター教授。まんが原作者。
著書に『手塚治虫と戦時下メディア理論 文化工作・記録映画・機械芸術』(星海社、2018年)、『大政翼賛会のメディアミックス『翼賛一家』と参加するファシズム』(平凡社、2018年)、『大東亜共栄圏のクールジャパン「協働」する文化工作』(集英社新書、2022年)、『「暮し」のファシズム ――戦争は「新しい生活様式」の顔をしてやってきた』(筑摩選書、2021年)、『シン・論 おたくとアヴァンギャルド』(太田出版、2022年)、『木島日記 うつろ舟』『北神伝綺』『北神伝綺 妹の力』(いずれも星海社、2022年)など。
現在の研究テーマは戦時下のメディア理論と文化工作。