ふやけて崩れたハンバーガー、やる気のない食堂の冷たいからあげ、サービスエリアの伸びきったうどん……。おいしくなかった食事ほど、強く記憶に残っていることはありませんか。外食の「おいしい」が当たり前となった今、口に合わなかった食事の記憶から都市生活のままならなさを描く短編小説連載。
3 愚者のためのクレープ
出勤のためにエレベーターホールからエントランスを通り抜けようとすると、たすけて。と蚊のようにか細い声が背後から聞こえてきた。ぎょっとして振り向くと壁から若い男の生首が生えている。
思わずたじろぐと、生首は焦った顔をして、待ってくださいあの僕401号室の者です、えっとですね、ちょっと閉め出されちゃってあの、と小声でまくしたててきた。一瞬驚いたがよく見れば生首ではなく、エントランスの隅にある集合ポストの壁に首から下を隠しているだけのようだった。オートロック、開けてもらえませんか。男の首は懇願する。ああ、ええと、もちろんいいですよ。別にオートロックで閉め出されるなんてありがちなことだけれど、どうしてこの男は不自然に身体を隠しているのだろう。スラックスのポケットから鍵を出して解錠すると、エントランスの内扉がうぃーんと開いた。振り向いてどうぞ、と言うと、男はぬうっと集合ポストの壁から姿を現した。
男はパンツのほかには何も身に着けていなかった。そしてなぜか、片手にはインスタントラーメンの袋を握りしめていた。
あっけにとられていると、男は心底恥ずかしそうに、あのちょっと彼女といろいろあって……と言葉を濁し、マジでありがとうございます、とへこへこ頭を下げながらエレベーターに乗り込んでいった。痩せた後ろ姿を見るに、どうやら大学生くらいだろう。どういういろいろがあってパンいちでエントランスに放り出されているのかも、それからどうするのかも知らないが、わたしはここに越してきてから初めて他の住人と言葉を交わしたなと思った。記念すべきファーストコンタクトが半裸のラーメンマンというのは極めて遺憾だが。
しかし、どのくらいの間あそこに身を隠していたのだろう。たまたま通りがかったのがわたしで良かったねと思う。相手が悪かったら普通に通報されている。というか、彼女がどうとか言ってたけど、ここは単身用マンションなんだけどな……。
まあそういうびっくりアクシデントも発生したとはいえ、単身用マンションというのは基本的には静かでいい。下期の人事異動のせいで、会社の勝手な都合で突然こちらの営業所に転勤させられたのは癪だったけれど、ここを斡旋してくれた総務部には多少感謝してもいいかもしれない。引っ越しの荷解きはまだ完全には終わっていなかったが、とりあえず必要なものは揃った。
もともと就職してから住み始めたベッドタウンの古くて巨大な集合住宅は、平日休日昼夜問わず子どもの泣き声やそれを咎める老人の怒鳴り声や深夜になってから突然掃除機をかけだす両隣の住人などなど、住宅規模の大きさに比例してさまざまな人の発するさまざまな音が四六時中響いているような場所だった。上下階も両隣もお互いの顔を知っていたし、今どきわりとしっかりした近所付き合いがあるような古典的な集合住宅だった。その明け透けのなさに助けられることも多かったし、好き好んでここに住んでいるのだから仕方ないと割り切りつつ、かといって身体がすっかり慣れてしまうかといえばそうでもないわけで。いつもうっすらとした不眠がつきまとうばかりの日々だった。
本社を離れて先月から住むことになったこのコンパクトなマンションの201号室は東向きで、カーテンから漏れる陽の光で目覚めることができるというこの上ない条件の部屋だった。スヌーズ機能が呆れるくらい繰り返しアラームを鳴らしてもいっこうに起きられなかった今までの生活とは大違いだ。昼間はその分あまり日が入らないようだけど、平日はどうせ仕事に出ているのだから関係ないことだった。
快適に起きられるようになってからは肌つやもいいし、じぶんの健康状態が良好であるとわかる。慢性的な疲労は歳を重ねたせいだと思い込んでいたけれど、どうやら清潔で静かな寝床が用意されているだけで解決できる不調というのは意外とあるらしい。ふつう、急に転勤させられてきたわたしのような人間は慣れない土地で心身のバランスを崩したりするものらしいけれど、わたしの場合は逆だった。
会社側はそんなことまで把握していないだろうが、そもそもわたしの出身はもともとこちら側なのだ。中学まで、今のマンションからそう遠くない河川敷の近くで両親と弟と4人で暮らしていた。父の転勤で移り住んだ町が今は地元と呼ぶべき場所だけれど、わたしにとってはこの町にこそ子ども時代の思い出が詰まっているし、懐かしさを覚える場所だった。実家があるわけでも、当時の友だちとも別段交流はない。でも一時的とはいえせっかく越してきたのだから懐かしい場所をたずねてみたいという気持ちに駆られていた。量販店で一番安い自転車を買い、週末のたびに河川敷や通っていた中学校や公園を見に行っては写真を撮って、この街にも当時と変わらない部分がまだいくらか残されていることを確認して安心した。
実家のある地方とは違って、こっちは多少中心部とは離れているとはいえ大都市だ。事実、子どものころに家族でよく行ったレストランやショッピングセンターはとうの昔に取り壊されていて、面影すらも残っていなかったのだから。
何度か週末を重ねるともう行く場所も目星がつかなくなってきて、そろそろこの思い出巡りも終わりかなと思いながらグーグルマップを眺めていると、画面の端に小さな遊園地の名前を見つけた。ここ、まだあったのか! 名前を見た瞬間に記憶がよみがえる。弟が生まれる直前、母が入院しているころに父が一度だけわたしを連れて行ってくれたのだ。半日もいれば園内を回りきってしまえるくらいにはこぢんまりとした、由緒正しき町の遊園地。わたしが子どもの頃は、それなりにこういう場所がどこにでもあったような気がしていたけれど、気がついたらずいぶん姿を消していたようだった。どれどれ。調べてみればホームページも古めかしい仕様のままでなんだか愛おしい。電車とバスを乗り継ぐ必要はあったけれど、ここから小一時間もかからないくらいの距離だ。次の週末は絶対にここに行こう。わたしはグーグルマップに勢いよく☆のピンを打った。

弟が生まれたのはわたしが5歳の時だった。短い入院とはいえ、母と離れるのが寂しくてしょげていたわたしを、父なりに元気づけようとしてくれたのだと思う。何に乗ったかはあまり覚えていなかったけれど、観覧車だとかローラーコースターだとか、そういう類いだったろう。
やけに覚えているのは、ベンチで食べた父作の塩辛いおにぎりと、売店のクレープである。父はそのどちらも一口食べては、ひどい味だから残してもいいぞと言ったのを、わたしはおいしいと言い張ってたいらげたのだ。まだ5歳である。別に父に気を遣うなんて芸当ができたわけもなく、ただ味覚が未発達だっただけに、味の善し悪しがわからなかっただけである。父はよほどたまげたのか、家族で食事に出かけるたびにこの話をして、食わなくていいって言ってるのにぺろっと食べちゃってさあ、と何度でも一人で笑っていた。父が数年前に食道がんの手術をしてからというもの、家族で外食をする機会はほとんどなくなったのでずっと忘れていた思い出だった。
土曜の遊園地はそれなりに混んではいたが、ちゃちな町の遊園地など今どきの子どもはきっと見向きもしないのだろう、園内の大半は赤ん坊くらいの本当に小さな子を連れた家族か、レトロ風の写真映えを狙ってやってきたらしい若いカップルのどちらかだった。あとは不倫っぽい怪しい中高年の男女。入り口のカウンターで入園券を買う。最低料金の入園券があればとりあえず中に入れて、アトラクションに乗るためにはそれぞれ個別の料金がかかるというシステムだ。一日フリーパスを買ってもよかったが、ひとりでアトラクションに乗りまくりたい気分でもなかったのでやめておく。
見るからに小規模な園内は全体的に大味なテイストで、わたしにとってはその統一されていない世界観がひどく懐かしかった。ところどころ塗装のはげた、ただ上下にはねたり回転したりするだけの乗り物、クレーンゲームやメダルゲームを雑多に並べただけの屋内スペース(BGMは浜崎あゆみやモー娘。のカラオケ音源が垂れ流し)、古めかしいデザインの着ぐるみ、誰も知らないフォークシンガーや手品師の謎のミニコンサート。わたしの思い出のレストランやショッピングモールはあっけなく取り壊されてしまったというのに、都市圏にこんな施設が30年以上もまだ残存しているだなんて拍子抜けだ。ここだけが忘れ去られた土地のように、強烈なノスタルジーを放っていた。
園内をあれこれ眺めていると、広場の端に売店を見つける。クレープ、ソフトクリーム、そば、うどん、スパゲッティ、ラーメンという手当たり次第なんでもありそうな品書きが薄汚れたガラス戸に貼り付いていた。父と来た売店はここだ。あの時に頼んだものがは何だったか具体的には思い出せなかったので、カウンターで品書きを指さして、一番上に書いてあったイチゴチョコクレープを注文する。650円。それが相場として安いのか高いのか判断はつかなかったが、クレープと言った瞬間、レジを打っていた店員の女が一瞬めんどくさそうな顔をしたのをわたしは見逃さなかった。
ひどく疲れた表情におおよそ似つかわしくないギンガムチェックのエプロンを身に着け、遊園地のロゴが刺繍されたキャップを目深に被っている。会計が終わると女はガラス張りの厨房へ移動して、平たい天板の上でだるそうにクレープを焼き始めた。甘く小麦の焼けるにおいが漂ってきて、少しだけ空腹を覚える。T字の棒きれみたいな道具を使って、砂場の整地でもするように緩慢な速度で生地が伸ばされていく。あまりに不躾に観察しすぎたのか、女がさりげなく身体の角度を変えたので、それからはクレープ作りの様子が見えなくなってしまった。
ほどなくして、どっぞ、と遊園地のくせにひどく無愛想に手渡されたイチゴチョコクレープはずっしりと重たかった。大量に詰められたホイップクリームだ。とにかく量が多ければヒトは満足するでしょうという短絡的な考えで作られた愚者のためのクレープ。あたたかくも冷たくもないただぬるくてクチャクチャした生地に、てっぺんには申し訳程度に突き刺さったぺらぺらのイチゴが数枚、さらに申し訳程度といってももう少し誠意を見せろと言いたくなるくらいには少しだけのチョコレートソースが黒光りしていた。これこれ。と、口角を歪ませながら思わず声に出してしまう。どこからどう見ても期待通りだ。添えられたプラ製のスプーンは使わず、まずはひと思いにかぶりつく。なまぬるい生地は見た目通り焼けてるんだか焼けてないんだかわからない仕上がりで、イチゴやチョコレートソースを包むどころかお互いを邪魔しあうとんでもないミスマッチぶりだった。もちゃもちゃと食べ進めてややもせず生地は破けて、ぬるり、と口の端からクリームが飛び出る。これがまたベタベタに甘ったるいうえに、植物性油脂特有の膜を張るような油っぽさが舌にはりつくのだ。これはこういうクリームの味が決め手になるようなお菓子に使うのではなく、コーヒーゼリーだとかプリンの頭に爪の先ほどちょこんとのっけるくらいの用途に使われるタイプのクリームではないだろうか。実に粗悪なホイップクリーム! これが持ち手の下までぎっちりと詰まっているのである。お約束通りイチゴが入っているのは上から数センチのところまでで、あとはこのひどいクリームが詰められているだけだ。工事現場の三角コーンにセメントを流し込んだらこんな感じだろうと、わたしは重たいクレープを持ちながら気味の悪い想像をした。
メリーゴーラウンドを前にして、白茶けたベンチでただ一人イチゴチョコクレープをむさぼる中年の姿を通りすがりの幾人かが一瞥したが、すぐさまわたしの存在など見もしなかったように去っていった。あたりを見回してみれば、写真を撮りあうカップルや親子など遊園地にふさわしそうな人々にまじって、わたしのように焦点の定まらない目でぼんやりと園内をうろついているだけのボサボサ頭の人間というのもわりと存在していることに気付く。入園料だけで一万円近くする本気のテーマパークとは違って、町の遊園地というのは確かに映画のチケットよりも安い値段で入園できるし、入ってしまえばアトラクションなど乗らずとも自由にいくらでもいていいのだから格好の暇つぶしスポットなのかもしれない。ほぼパチンコ屋のようなものである。遊園地のほうが外の空気も吸えるしパチンコ屋よりはいくぶん健康によさそうだが。
クレープは本当に持ち手の下までホイップクリームがぎっちり詰まっていた。どうせぼろい商売をするならばクリームも出し渋ったっていいものを、これだけは過剰なまでのサービスなのか、あるいはヤケクソなのか知る由もないがいじらしくて笑えてくる。途中から胸焼けがしたけれど律儀に食べきって、包み紙を売店脇のくずかごに捨てる。もう夕飯はいらないかもしれないな。父が一口で顔をしかめた理由を、わたしは数十年の時を経て理解した。当時ですら既においしいクレープは世に出回っていたはずだから、ここのはよっぽど子ども騙しである。遊園地の売店という立地に甘んじていたとはいえ、よく今の今まで淘汰されずに生き残ってくれたものだ。クレープだなんてちょっとコツをつかめば、だいたいはそれなりにおいしく作れそうなものだけれど……。
売店のカウンターをちらりと見れば、小さなリュックサックを背負った5歳くらいの男の子がぐずっていた。ミッキーいない、もっと大きい観覧車がよかった、クレープおいしくない、と泣きべそをかきながら訴えており、傍らで食べかけのクレープを持ちながらおろおろしているのは男の子の祖父母のようだった。そりゃあ今の子どもは騙されてはくれませんよなあ。困った顔で男の子をなだめすかす祖父母の姿を、じぶんの両親に重ねて少し胸が痛んだ。この調子じゃそう遠くないうちにここもやがてなくなってしまうんじゃないかという予感がして、つい先週まですっかり忘れていたくせに、そうなったら嫌だなと思った。遊園地がなくなることそれ自体ではなく、それに伴ってごく個人的な、別の何かも喪ってしまうような気がしたのだ。
ふたたびベンチに腰掛けて辺りをじっと眺めていると、じぶん以外のすべての人がメリーゴーラウンドの木馬のようにぐるぐると光を放っているような錯覚におそわれた。わたしはここに何をしに来たんだっけ。急にじぶんが老けたような気がして、顔を触る。そんなばかな。転勤してきたばかりで、少しハイになっているのかもしれない。とうの昔の思い出ばかりを蒐集して何になるのだろう。それでもカメラロールをさかのぼってみれば、集積された断片のなかに、忘れかけていたじぶんの記憶が定着しているような感覚にもなった。その場所や人や物それ自体がなくなったとしても、記憶は別の場所に宿ることだってあるんだろう。わたしはさほど頭がよくないのだから、覚えておきたいと思ったら、なんでもこうやって痕跡を残しておいたほうがいいとじぶんを納得させる。
食べる前に撮っておいた、ギンガムチェックのかわいい包み紙のクレープをじぶんの無骨な手が掴んでいる写真をスワイプして選択した。お父さんの言うとおりひどい味だったよと、短いメールを送ろうかどうか、しばらく悩む。
第4回につづく
【お知らせ】
当連載を収録した書籍『お口に合いませんでした』が待望の書籍化! 全国書店やAmazonなどの通販サイトで、2024年10月29日(火)より発売いたします。

※当サイトOHTABOOKSTANDに掲載の「関連商品」は、関連書籍および編集部おすすめのアイテムです。このほかの欄に表示される広告は自動表示につき、編集部が評価して表示するものではありません。
筆者について
イマジナリー文藝倶楽部「オルタナ旧市街」主宰。19年より、同名ネットプリントを不定期刊行中。自家本『一般』『ハーフ・フィクション』好評発売中。『代わりに読む人』『小説すばる』『文學界』等に寄稿。

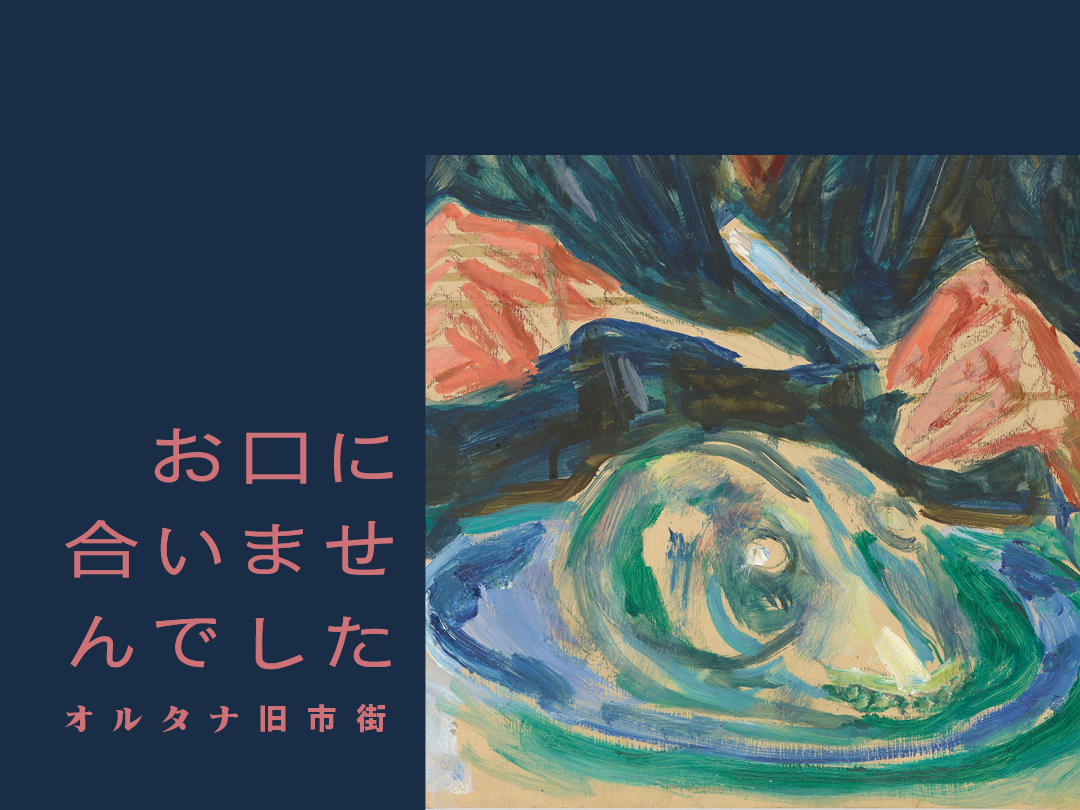
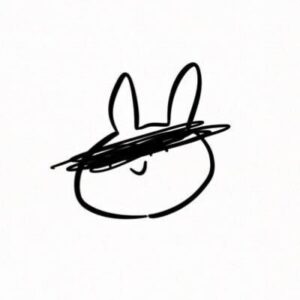



![eモンズ [当社製品保証1年!インボイス対応!] 業務用 クレープメーカー 【 クレープファクトリーワン 】 日本語マニュアル付き 食品安心検査済み 電気式 火力 1450w 温度調節 50-290℃ 直径40cm 100v トンボ スパテラ カス受け ステンレス CF-1 クレープ焼き器 クレープ機 クレープパン](https://m.media-amazon.com/images/I/41V4R-P3v8L._SL160_.jpg)

