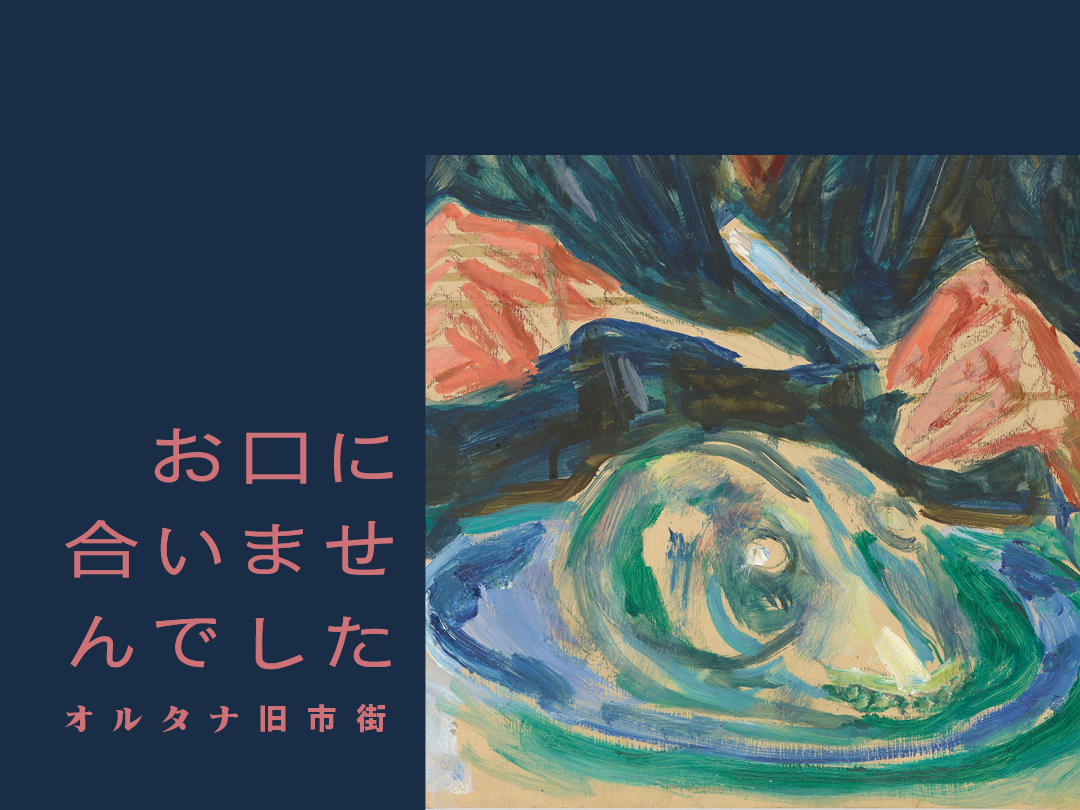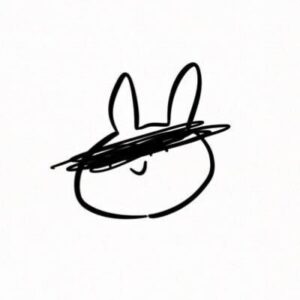ふやけて崩れたハンバーガー、やる気のない食堂の冷たいからあげ、サービスエリアの伸びきったうどん……。おいしくなかった食事ほど、強く記憶に残っていることはありませんか。外食の「おいしい」が当たり前となった今、口に合わなかった食事の記憶から都市生活のままならなさを描く短編小説連載。
むかしむかし、国じゅうのあらゆるものを見通すことのできる不思議な12の窓を持つ王女さまがいました。王女さまは美しく聡明でしたが傲慢で、じぶんひとりで国を治めたいと考えていたので、結婚のお話が持ち上がったとき、「王女から見つかることなく、うまく隠れることのできた相手でなければ結婚はしない」というお触れを出しました。これに挑戦し、もしも失敗して王女さまに見つかったらば即刻打ち首。王女さまはなんでも見通す自慢の12の窓を使って挑戦者たちを難なく見つけだし、お城の前には99のさらし首が並びました。もう王女さまに勝てる者はいないだろうと思われていたとき、ある日挑んできた心優しき青年は、森で助けた動物たちの知恵を借りて、アメフラシに化けることで王女さまの目を見事にあざむきます。青年の知性を心から尊敬した王女さまは彼を夫とし、青年は国を治める王となったのでした。
めでたし。そう話し終えると、洗面所でつやつやの髪をとかしていた冬子さんは心底興味なさそうに、ふーんと言った。「あめふらし」というグリム童話のなかでもとびきりマイナーな話である。で、結局アメフラシってなんなの?と冬子さんが言うので、スマホで画像検索したアメフラシの画像をそうっと見せる。腹足綱後鰓類、まあウミウシとナメクジとタコの中間みたいなにゅるっとしたビジュアルです。冬子さんはぎゃっと叫んで、朝から気色悪いもの見せてくんじゃねーよ死ね!と木製の重たいヘアブラシの柄でわたしの額をごつりと殴った。痛い。ごめんなさい。けっこうマジでキレている冬子さんを横目にすごすごとパーカーを羽織って、先に出かけますねぇとお声がけして逃げるように玄関をとびだす。こういう時はさっさと逃げないと罰ゲームを食らうのだ。今日は3限からだから家でゆっくりしていたかったし、冬子さんは半同棲的にだらだら遊びに来ている恋人という立場であって、追い出される筋合いはないのだが……。
乗り込んだエレベーターはひとつ下の3階で停まり、扉がひらいた先にはヘッドフォンを首からさげた、同世代くらいの女の子が立っていた。女の子はわたしの顔を見るとあからさまにゲッという顔をしたが、急いでいたらしくそのまま乗り込んでくる。ぼくは無害な人間ですというアピールをしておきたくて会釈をしたけど無視された。まあ、小さいマンションだ。ほかの住人となんてなるべく関わりたくないし、同じエレベーターに乗り合わせそうになったらいったん見送りたいし、じぶんが住んでる階すらも知られたくないよね。女の子が一人暮らしをするにあたって強いられるさまざまな防衛術のことは、以前冬子さんに教えてもらったから、こんなふうに警戒されても傷ついたりしない。いや、やっぱりちょっとは傷つくかもしれない。若干ひりひりする額にさりげなく触れてみればちょっとだけコブができていた。我慢します。男だから。
3限が始まるまではたっぷり時間があったから、別にどこかで時間をつぶしたってよかったのだが、気乗りせずまっすぐ大学に向かう。学食はまだ空いていて、おしゃべりしているサークルの集まりや、必死の形相でレポートを書き上げている人や朝練終わりの運動部などがまばらに座っているだけだった。2限が終わったらどっと混み出すから、早めにお昼を済ませてしまおう。それで来週の課題の準備でもするかな。1年生の時はコロナ禍まっただなかだったから、こんな風に学食でのんびり勉強できるのは大学生らしい感じがしてうれしい。正月に親戚の集まりで、大学生活の様子を叔父さんに話したらまじめだァねと笑われたが、学費を払って遊び呆けるという感覚の方が理解不能だった。叔父さんはわたしの肩を叩きながらモラトリアムを大事にしろよと言ってきたけど、叔父さんの時代と違って我々はそんなに暇じゃない。半年後には就活。うかうかしているとあっという間に乗り遅れる。
しょう油ラーメン340円、券売機のボタンを迷いなく押して食券を買う。醤油の「醤」だけがひらかれているのがずっと気になる。曲がりなりにもここは私大の偏差値ランキングでは中の上といったレベルだし、「醤油」くらい読めるけどな。ネーミングはともかく物価高の昨今にしてはかなり努力の感じられる値段だと思う。しょう油ラーメンは学食のメニューのなかで2番目に安いということで学生たちからは一定の信頼を置かれていた。ちなみに最も安いのは310円のカレーライス中盛り。しかしこれはかなりレトルトに近く、具もほとんど入っていないしあまりおすすめはしない。
てろりん、と警告音のようにスマホが鳴り、片手に空のトレイを持ちながら画面を確認すると冬子さんからラインが来ていた。「帰ったら罰ゲーム」。気が重い。ひとまず見なかったふりをして、かすれたインキで印字されたしょう油ラーメンの食券をカウンターに滑らせる。ほどなくするとレーンの向こうから半分濡れたどんぶりが無愛想に手渡される。メラミン製のどんぶりは内側に何らかの模様が描かれていたが塗装が剥げて、いまいち清潔感に欠けていた。この残念さを味で上回ってくるというわけもなく、我が校の学食は見た目も味もそこそこ、中の下以下といったところである。いまどき学食がおいしくないなんて大学は珍しいような気もしたが、おいしくしすぎても関係のない学外の人間が出入りするようになってきっと鬱陶しいだろうから、このくらいでいいのかもしれない。いいかい学生さん。それが、人間えら過ぎもしない貧乏過ぎもしない、ちょうどいいくらいってとこなんだ。ネットミームでつまみ食いしただけの、ほとんど読んだことのない『美味しんぼ』のワンシーンを脳内で再生する。
学食は広い。大きな長机の一番端の席に腰掛けると、じぶん一人だけが招かれた晩餐会にいるようだった。今朝のグリム童話をまだ引きずっているな。晩餐会には到底ふさわしくない激安ラーメンをすする。醤油と大量の化学調味料を湯で溶いただけであろう平たい味のスープに、着色料でも入っているんじゃないかというくらい黄色すぎるちぢれた中華麺。わたしたち学生はこのしょう油ラーメンのことを、親愛の意味も込めてケミカルラーメンと呼んでいた。スープは前述のとおり、中華麺はかんすいの入れすぎでコシがあるどころかゴムみたいな食感がするし、具材はしなびたチャーシュー(のわりに、やけに切り口が正円の形をしているので、これも何かの合成食品なのではないかと疑っている)と、理由はわからないがやたらと臭いネギとがのっかっているだけの文字通りケミカルなラーメンだったが、食べ慣れてしまうとなぜだかクセになる。有名なラーメン屋の一杯と、インスタントの袋麺と、カップラーメンのそれぞれをTPOに応じて選び取るように、学食のケミカルラーメンはこれはこれで、いちジャンルとしての地位をごく小規模な範囲で確立していたのだった。
でも冬子さんはしょう油ラーメン、というかそもそも学食のメニュー全般のことを毛嫌いしていた。付き合いはじめたばかりの頃、わたしの食べていたしょう油ラーメンを一瞥した冬子さんに、よくそんなグミみたいなラーメン食べられるねと鼻で笑われてからは一緒に学食に行くことはなくなった。わたし自身は別に笑われても構わなかったが、周りにいたほかの学生たちが冬子さんのほうをちらりと見たのが気になったからだ。冬子さんは他人からどう思われようが構わず、じぶんの思ったことを思ったタイミングで全部口にする。取り繕うことを一切しない潔さはすがすがしく、その飾らない態度が好きだった。けれども、これを無遠慮で高慢だと思う人間も少なくはない。不要な諍いから冬子さんを守るのはじぶんの役目のように感じてもいた。
しょう油ラーメンはスープの味に奥行きがないくせに結構しょっぱいのですぐ飽きる。ぬるくなったどんぶりを箸でかき回しながら、無意味に黄色いちぢれた麺をつまむ。この形状を初めて見た時から、やけに懐かしい気分にさせられる。どういうわけだか、学食のラーメンを見るたびに、春の雨上がりの海岸風景がセットで思い出されるのをずっと不思議に思っていたのだが、これが故郷の風物詩とよく似ているというのを思い出したのが今朝のことだった。アメフラシのたまご。春先の海辺には、ゆであがった中華麺をそのまま鍋から放り出したような見た目の、細長いチューブ状の物体がよく落っこちている。あれはアメフラシのたまごなのだ。磯場のある海辺以外では、この光景は珍しいのだと教えられたのは実家のある町を出てからだった。ちなみに『美味しんぼ』6巻で知った知識であるが、これをもずくのように食べる地域もあるらしい。
生ぬるい潮のにおいと、濡れた浅瀬に転がる黄色い中華麺。自転車で駆ける春の海辺のちょっとだけ浮足立つ感じ。アメフラシのたまごって学食のラーメンに似ているのよと冬子さんに教えてあげたかったんだけど、アメフラシがマイナー生物すぎてそこまでたどり着けなかった。また話したら怒るだろうか。でも、わたしにしては珍しく、冬子さんにじぶんの思い出を語って聞かせたい気分だった。冬子さんはわたしのルーツになど微塵も興味はないだろうけど。
ぼやぼやしていると2限が終わるチャイムが鳴って、学食はにわかに混み始めた。1年生らしい4人組のグループが、トレイを持ちながらうろうろと席を探している様子だったので、あ、俺もう出るんでいいですよ、と、なかよしグループに席をゆずってあげる。わたし。おれ。ぼく。じぶんにぴったりの一人称がいつまで経っても定まらない。Meを意味する言葉のどれもがじぶんを指すものであり、そうではないような気がした。
5限のゼミが終わったら帰るつもりだったが、なんとなく飲み会をやる流れになって、みんなのうしろについていく。飲み会ってまだ新鮮。帰りたくなかったからちょうどよかった。「飲み会になりました」と一言だけラインをして、あとはスマホの通知を切る。冬子さんは怒るかな。
ゼミの飲み会は盛り上がりも盛り下がりもせず、でもきっちりカラオケでオールして、解散したのは結局日もとっくにのぼったころだった。楽しいから一緒に過ごしているというわけではなく、しばらく失われていた大学生らしい生活を一通り実践してみたくてそうしているという共通の感覚があった。一晩を明かしても、それぞれのごく個人的な核心には触れることなく、誰のこともよく知らないまま時間だけが上滑りしていった。ゼミのメンバーでオールする。脳内の「大学生っぽいことスタンプラリー」にスタンプがぽんと押される。数時間ぶりにスマホを見ると、特に誰からの連絡も来ていなかった。「オールしたからこれから帰る」と冬子さんに一応送っておく。既読はすぐついて、OKサインを掲げたうさぎのスタンプがぽんと送られてきた。怒ってない。てか、起きてる。
これから動き出す街を逆走しながら帰路へつく。朝帰りの後ろめたさは、経験してみると背徳感の裏にすこしだけ優越感がある。叔父さんの言っていたモラトリアムは、こういう時間の積み重ねにあるんだろうとなんとなく思った。じぶんの部屋に帰ると、冬子さんはとっくに起きていて、キッチンで鍋にお湯を沸かしながら、なんだか珍しく機嫌がよさそうだった。「おなかすいたでしょ。きのう駅のスーパーで東北の物産展やっててさ。どうせ二日酔いでしょ。ラーメン食べたいでしょ?」食べたい食べたい。まさかの朝ラーですか。別におなかはすいていないし、なんなら昨日もラーメンを食べたけど、言わなかった。あれはあれでTPOに応じたいちジャンルであって、冬子さんが買って作ってくれるラーメンとはまったく別物である。
酒はそんなに残っていなかったけれど、一刻も早くシャワーを浴びたかった。ラーメンができるにはもう少しかかりそうだし、さっと浴びちゃおうかな。外出着を適当に脱ぎ散らかしながらキッチンをのぞくと、コンロの脇には『秘伝の味 東北名物』と書かれたラーメンの袋が置かれている。中にはスープの小袋がいくつかと、半生の中華麺がころんと入っていた。それは確かに見覚えがあった。着色料でも入っているんじゃないかというくらい黄色すぎるちぢれた中華麺。口をついて出る。「学食のラーメンに似てんじゃん」。冬子さんはえー、そうかなあ。と野菜を切りながら引き続き上機嫌で返す。なので、絶対に言わない方がいいとわかっていたのに、言ってしまった。こういう黄色くて太いラーメンが、アメフラシのたまごに似てるんだよって昨日話したかったんだよね。なんかこっちでは全然見かけないけど、実家、海の近くだからさ、そういうとこでしか見られないんだって。おもしろくない?道端にこういうラーメンそっくりの物体が落ちてて「なんでそういう余計なことばっか言うの」
冬子さんはわたしの話をさえぎって低い声で言う。嫌だって言ったよね。やばい。それから瞬時に激昂した冬子さんは、出て行けというようなことを大声でわめいて、わたしをぐいぐい外へ押しやった。ラーメンの袋を手に持ったまま、パンツ一丁のまま玄関の外に放り出される。いや、待って。せめて服を着ればよかった。冬子さんはあられもない姿のわたしをすぐそばにあるエレベーターのカゴに蹴り入れ、そのままエントランスの外に放り出した。オートロックの自動ドアがこんな時にかぎってすばやく閉じる。締め出されました。パンツ一丁で。しかも、じぶんのマンションで……。
鍋のお湯をかけられなくてよかったと最悪の想像をしつつも、こうなることは想像できないわけではなかった。わたしに冬子さんを不必要に苛立たせる素質があるのも、冬子さんがわたしに依存気味で、自他境界があいまいになっているのもわかっていた。冬子さんはきっと昨日の夜からわたしにラーメンを作ってくれるつもりで一晩待っていたであろうことも。それにわざと気が付かないふりをしたことも。半分はじぶんから締め出されにいったようなものだった。
とはいえこんな格好でうろうろしているわけにもいかないので、ひとまずエントランスの隅にある集合ポストの壁に首から下を隠す。寒いし、なにより心細くて死にそうだった。昨日エレベーターで乗り合わせた3階の女の子に見つかったらきっとその場で110番されそう。こんな時にかぎって、手に持っているのがスマホじゃなくて半生ラーメンの袋なんだから泣けてくる。
しばらく集合ポストの下で体育座りをして人が通りがかるのを待った。全然人が来ないしおしりが冷たい。今日ばかりはコンパクトマンションを選んだじぶんを呪った。おそらく体感30分くらいはそうしていると、ようやく人の気配がやってきた。たしか2階に住んでいるおじさんだ。たまに深夜にゴミを捨てているのを見かける。2階の住人はスーツ姿で、これから出勤といったところだろう。あの、たすけてください。思ったよりもじぶんの声がか細くておどろく。2階の人は一瞬肩をびくっと震わせて振り返ったので、間髪入れずにじぶんは怪しい者ではありませんということを簡潔に早口で伝える。「僕、401号室のものです」なんだか別の人間を演じているようだった。オートロック、開けてもらえませんか。ああ、ええと、もちろんいいですよ。2階の人はおっかなびっくり、でも親切にポケットから鍵を出して解錠してくれる。おじさんでよかった。エントランスの内扉がうぃーんと開き、わたしは2階の人にぺこぺこ頭を下げながらふたたび4階へあがった。
しんと冷たい玄関のドアに触れると思いのほか鍵は開いていて、そうっと部屋に入るとリビングの中心で冬子さんは背中をこちらに向けながらしくしく泣いていた。かわいい冬子さん。どうして泣いているのかわたしにははっきりとわかる。でも冬子さんは仮にわたしが泣いていたとしても、きっとその理由をわかろうともしてはくれないだろう。予感だけが胸をざわつかせる。キッチンの鍋に張られた湯はすっかり冷めていて、ひとまず無言で服を身につけているあいだ、鏡のような水面がゆらりとわずかに揺れたのが見えた。
次の週、バイトの遅番から帰ってくるとわたしの部屋に置かれていた冬子さんの荷物はいつの間にかきれいになくなっていて、まさかと思ってラインをみたら、冬子さんはわたしのことをブロックしていた。静かに血の気が引くのがわかったが、一方でさほど動じていないじぶんの存在も感じていた。要するに潮時だったというだけだと思う。何もかもちぐはぐな関係であった。冬子さんの苛烈さと向き合い、抱きしめてあげられるのはじぶんだけだと思っていたけれど、「あげられる」だなんて、それはひどく傲慢なことだったのかもしれない。気高く寂しい王女さま。わたしは優しく聡明な青年なんかじゃなく、打ち首になった99人のぼんくらと変わりはなかったのだった。
結局あのあと食べなかったラーメンを冷蔵庫から取り出してゆでてみる。賞味期限は切れていたけど。たっぷりと沸かした湯の中で、ゴムのように半透明で、不自然に黄色い中華麺が鍋の中でぐつぐつと踊る。ゆであがった麺をひとくちつまむ。やっぱり学食の麺とだいたい一緒だった。
くちゃくちゃした麺を無理やり飲み込むと、今度は目の奥が熱くなって吐きそうになった。鍋をひっくり返して、ゆでたての麺を無造作に捨てる。もうもうと湯気をたてながらシンクにへばりついた黄色い塊は、濡れた浅瀬に転がるあの光景そのものだった。ああ最悪だ。きっとこれから先ずっと、黄色い中華麺をみるたびに思い出してしまうんだろう。春の海辺、学食、アメフラシのたまご、そして冬子さんの震える背中のことを。
第6回につづく
【お知らせ】
当連載を収録した書籍『お口に合いませんでした』が待望の書籍化! 全国書店やAmazonなどの通販サイトで、2024年10月29日(火)より発売いたします。

※当サイトOHTABOOKSTANDに掲載の「関連商品」は、関連書籍および編集部おすすめのアイテムです。このほかの欄に表示される広告は自動表示につき、編集部が評価して表示するものではありません。
筆者について
イマジナリー文藝倶楽部「オルタナ旧市街」主宰。19年より、同名ネットプリントを不定期刊行中。自家本『一般』『ハーフ・フィクション』好評発売中。『代わりに読む人』『小説すばる』『文學界』等に寄稿。