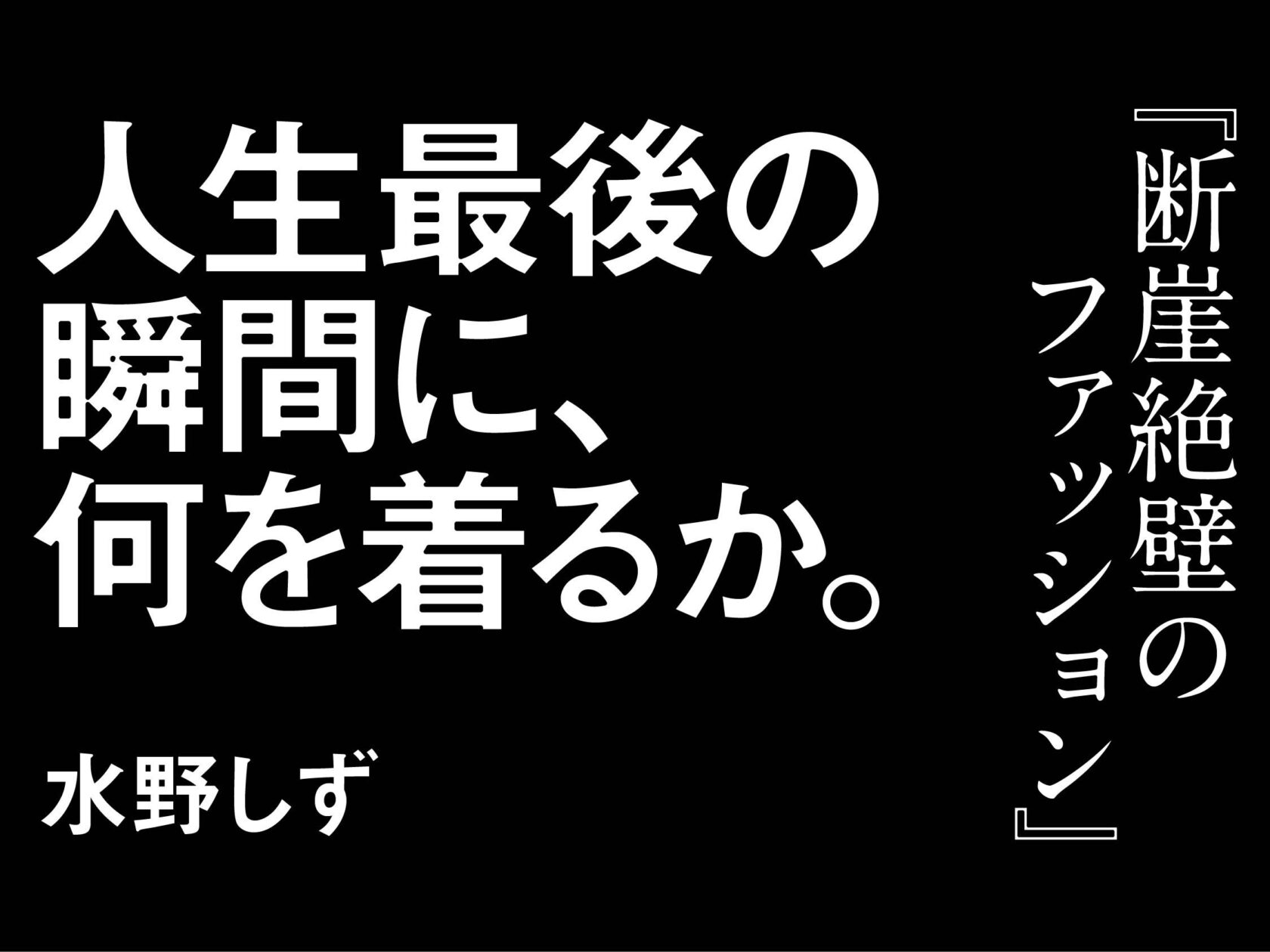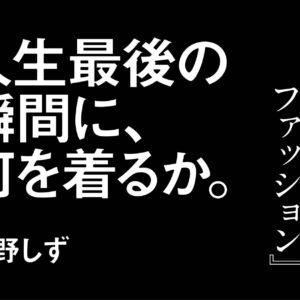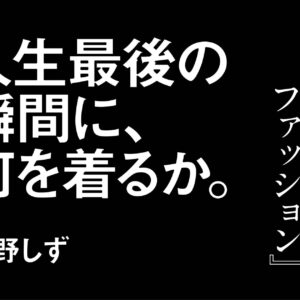「あの服も、この服も納得がいかない……私がほんとうに着たい服ってなに?」
世間は色々な問題を投げかけてくるけど、どれもこれも肝心なこと、漠然とした問いかけの先にある根本的な問題には触れていないような気もする。今のファッションが退屈でしっくりこない、悩めるすべてのみなさまへ。
こちらは、まだ誰も言葉にしていない違和感を親切に言語化する“ポップ思想家”の水野しずさんによる、トレンドを追うよりも、納得のいくスタイルを発見していくためのファッション論考の連載です。「着るという行為」について、一緒に考えていきましょう。
【なにかをギャグとして扱う前に、側から見たらギャグにしか見えないほど切迫しているものがない人の方がむしろピエロチャート】
真実だけをやっていきたい
↓
信じられないものを信じたくない
↓
信じられるものだけが信じられる
↓
信じられるものが具体的に存在するのかというと、ない
↓
ない
↓
信じるに値するものを独自に選ぶしかない
↓
《信じられる》
↓
信じられるものを信じている人はバカにされやすいが、それで構わない
↓
なにかをギャグとして扱う前に、側から見たらギャグにしか見えないほど切迫しているものがない人の方がむしろピエロ
あさはかではないものの所在
高校生になり、岡本太郎の本を読んだ影響で美術部に入りたいと思って美術部が活動していた放課後理科室の扉をガラガラとスライドしたら、巨大な絵と目があった。それは骸骨とバラと手錠に包まれた美貌の紳士の絵であった。紳士は美貌でありつつ、一般的な三十代男性の雰囲気もまたあった。小鼻の膨らみに自意識が滲んでいる感じとか、両頬が非対称に吊り上がり、平穏ではなかった暮らしを滲ませるムードにそう感じた。紳士と目があってそのまま扉を閉めた。
『今日の芸術』に描いてあった芸術観とはまるで違う、予想だにしないものがそこにあった驚き。びっくりマークを考えた人はすごい。驚きと声の対照関係は花火における光と音の関係に似ている。びっくりマークはその対照関係を正確に描写しているようにも見える(または私が関係を記号に投影している)。バカにしたい気持ちとまるでバカにできない気持ちが同時に押し寄せてわからなくなってしまい、恥ずかしさとバカバカしさとなんでここにいるのかわからない気持ちが一度に押し寄せて、どうにもならないまま抱えきれないどうにもならなさが全身の毛穴から流出してしばらくそのまま立ち尽くした。
放課後は怖い。
ついさっきまで数百人が信じ込んでいた箱庭生活の恒常性が抜け落ちてひろがっている奈落がそこらじゅうにある。チャイムの音が鳴る数秒前に走るホワイトノイズが耳に入ってくる間は、我に帰りそうになっている。「我に帰ってはいけない」ということも同時に考えている。割と必死に考えている。そうするしかなくなっている。そうやって、自我を統制する自分と統制されている自分のどちらが主体なのか判断しきれないまま、主客の序列が数秒に何百回も入れ替わって、部分的に音が割れている、いつものように音が割れているチャイムの録音再生が終わる間に膨大な数の時間の分断が発生している。もしわたしが、我に帰った場合、我はどこに帰ればいいのか。我はどこかに帰りたいっぽいというところまではわかる。それ以上のわかりには一方通行の雰囲気がある。自分に自分がバレていないふりをしなければならないように思えるからガッコーの箱庭の感じでバレを視界に入らないところまで端の方に押し寄せて、最初っからなにもなかったようなふりをして過ごさなければならないような気がする。そうやって決死で押し寄せたものを直視した場合になにがあるのかといと、この絵みたいなものではないか。じっと見る。チャイムはすでになり終わっている。残響が内耳をゆさぶっている。じっと見る。
ダサい。かなりダサい。ものすごくダサい。
もしかしたらこの絵は、今まで見た中で一番ダサいかもしれない。
特に、薄めた黒い絵の具で塗られた髑髏の影とベースに敷かれたビロードの真紅がまるで調和していないところが猛烈にダサい。あとは、紳士のまつ毛と唇だけやたら書き込みの手数が多いわりに手の甲はゴム手袋のように平板な質感でつるんとしている点もダサい。さらに、薔薇の数が三つというのも量を書く手間を惜しんだ雰囲気が露骨に出てしまっていて中途半端でダサいなと感じた。そして瞳の虹彩もまた熱心に書きこまれているのだが、細部の書き込みに適した細い絵筆がなかったのか、粘土細工で不器用にあつらえたような線の具合になっていて最高にカッコわるい。これらの画面に描かれた取り返しのつかないダサさのひとつひとつが私自身の取り返しがつかない部分と致命的に響き合っているような気がして狂おしい。恥ずかしいよりも二段階くらい取り返しがつかないことが起きている。肝心なものがすでに公開され終わっている。この、取り返しのつかなさ。さっきまでの放課後の我に帰りそうな感覚を秒で圧殺する迫力がある。こんなに取り返しがつかないのであれば、むしろ全てが大丈夫ではないか。なんなら、一刻も早く全てにおいて取り返しがつかない方が話がはやいのではないか。いったん取り返しがつかなくなってしまえば、なんにも大丈夫ではないせいでむしろ大丈夫になり、帰るとか帰らないの話ではなくなってしまうのではないか。
どうせなら、そのほうが「あさはか」ではないのではないか。
当時の私は、この世のどこに「あさはか」ではないものがあるのかひとときも休まることなく毎秒熱心に考えていた。この世の全てが香取慎吾の衣装のようなノリでよかれと思って配置された「なにかではなかったなにか」に見えてしまう。ダサくもカッコよくもなくて、おもしろくもつまらなくもない「ちょうどいい」もの。あるいは、「ちょうどわるい」もの。そのどちらでもないもの。ちょうどなんでもないもの。そんなものらについて考えはじめるといくらでも涙が出る。悲しみがストローの私をただ通り抜けている。一言でいいから、ちょうどなんでもないものではないものと会話がしたい。日本語ではなくてもいいからそうしたい。もしかしたら、そんなふうになってしまうこちらの頭に問題があるのかもしれないが、だからといって、誰かが問題を肩代わりしてくれるわけではないのだから、文句を言われた場合には「うるせーばかやろう」と言うしかない。私があなたではないから殴るものを、私は随時殴り返す心の自由を保有しているのだと宣言したい。
ちょうどなんでもないようなものを避けるために図書館から大量の本を持ってきて学校の机の上に積み上げた。クラスの人はそれを「塹壕」と呼んだが、相応しい呼び方だと思った。うれしかった。うれしさを表現する方法はわからなかった。わかりあえなかった。それでよかった。目に入るものがひとつひとつなんでも自分で疑ったり納得をする前にちょうどいい塩梅に加工されてしまい口当たりがただ、いい。そういったものは異様なほどにスルスル入ってくるだけでなんにも信用に値しない。そうしてあまりにものどごしばかりがいいために、こちらから積極的に避けに行かないとのどごし以外はなんにもよくないものが身体中に走る神経の隙間に頭からつま先までみっしりと隙なく入り込んでつまる。一旦そうなってしまうと、「わからない」部分を知覚するための亀裂を私自身に入れる余地がなくなって、おもしろくないもので全身が詰まってやむなく窒息せざるを得ない。そうならないためにはこちらから避けるしかない。避けるのは抵抗するより難しい。土のうを積んで、穴を掘り、かなりアグレッシブに退避しなければ達成できない。「信じられるかもしれなかったもの」が私に伝わってくる過程で特に信じているわけでも、また信じていないわけでもない、ちょうどよく便利で、なんとなくやり過ごせそうだったらそれでいい。そういう態度で行われるやり過ごしの伝言ゲームを無数に通過するから目に入ってくるもののほとんどがちょうどなんでもないものになってしまう。ちょうどなんでもないものが割れたチャイムの隙間の無数の空白にひとつひとつさし挟まって、大丈夫風の、正味のところではぜんぜん大丈夫ではない、安心だが安全かどうかは皆目見当がつかない中性子線のようなものになって私の身体を通過している(ように思われる)。
翌日私は、目撃した絵の作者と目される人物を目で追った。なんだか不吉にグレーがかった黒髪、ヘルメットをかぶっているような極厚・平行の前髪、各自が意思を持ってうごめきどこにも焦点があっていない両目、不満足を丸出しにしたへの字口。フリーダ・カーロ(あるいは両津勘吉)ナイズされた眉毛。赤縁眼鏡、前傾姿勢、早歩き。すごい。かなりの「実力(自分の内心で価値判断を行う能力)」の持ち主であることは明らか。
制服は校則の範囲内で律儀に着こなしていたものの、鞄が異様だった。彼女は通学用の学生鞄に無数の、おおよそ30個程度の安全ピンを付け、肩掛けの部分には血糊(もしくは赤い絵の具)で人間の体を通う血液とは全く違うベクトルに赤い、苺ジャムのような赤さで装飾した包帯をびっしりと巻き、写真を入れたキーホルダーを四つも五つもぶら下げている。後日、人からそのカバンにぶら下げられていた人物はRAG FAIRというボーカルグループの中心人物だと聞いた。
あの絵に描かれていた人物も同じだ。私は確信をした。強くした。
3月26日の更新は諸般の事情により休載とさせていただきました。
次回は、4月23日(火)17時更新予定です。
筆者について
みずの・しず バイキングでなにも食べなかったことがある。著書『親切人間論』他