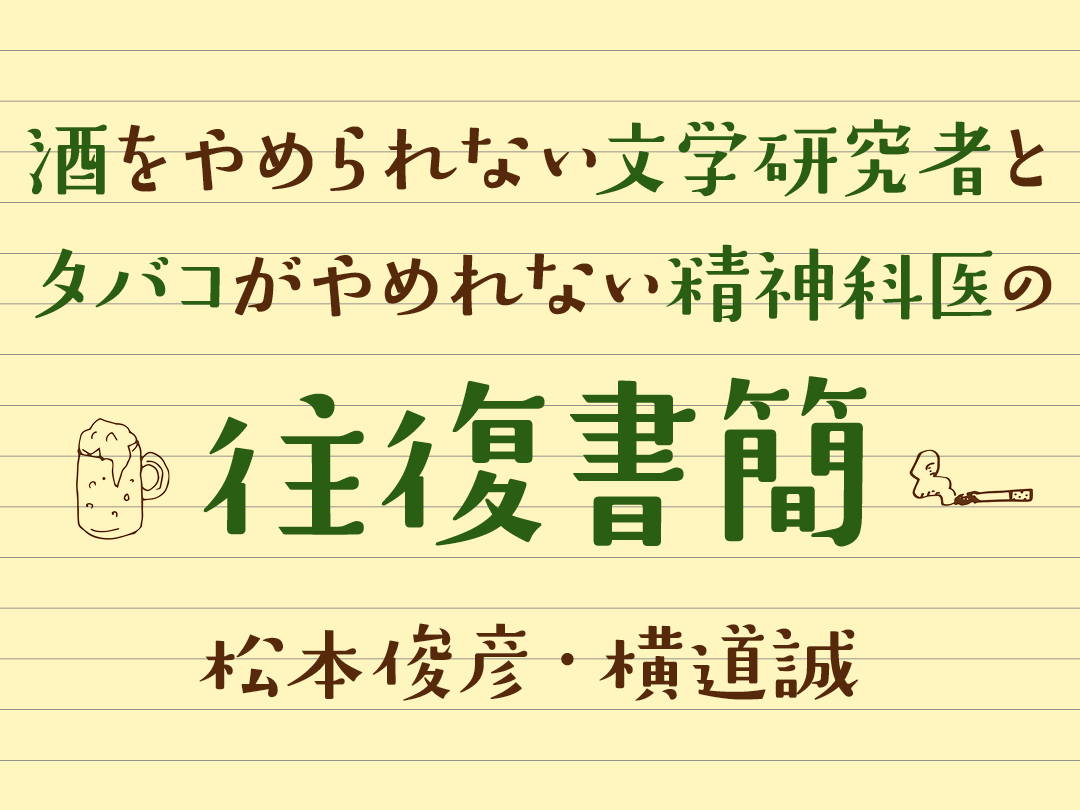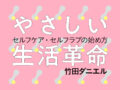依存症は、現代人にとって、とても身近な「病」です。非合法のドラッグやアルコール、ギャンブルに限らず、市販薬・処方箋薬、カフェイン、ゲーム、スマホ、セックス、買い物、はたまた仕事や勉強など、様々なものに頼って、なんとか生き延びている。そして困っている、という人はたくさんいるのではないでしょうか。
そこで、本連載では自身もアルコール依存症の治療中で、数多くの自助グループを運営する横道誠さんと、「絶対にタバコをやめるつもりはない」と豪語するニコチン依存症(!?)で、依存症治療を専門とする精神科医・松本俊彦さんの、一筋縄ではいかない往復書簡をお届けします。最小単位、たったふたりから始まる自助グループの様子をこっそり公開。
物質依存と行動嗜癖
こんにちは、トシ。
ここから先は会員限定コンテンツです。
ログイン、または無料の会員登録を行うと
記事の続きをお読みいただけます。