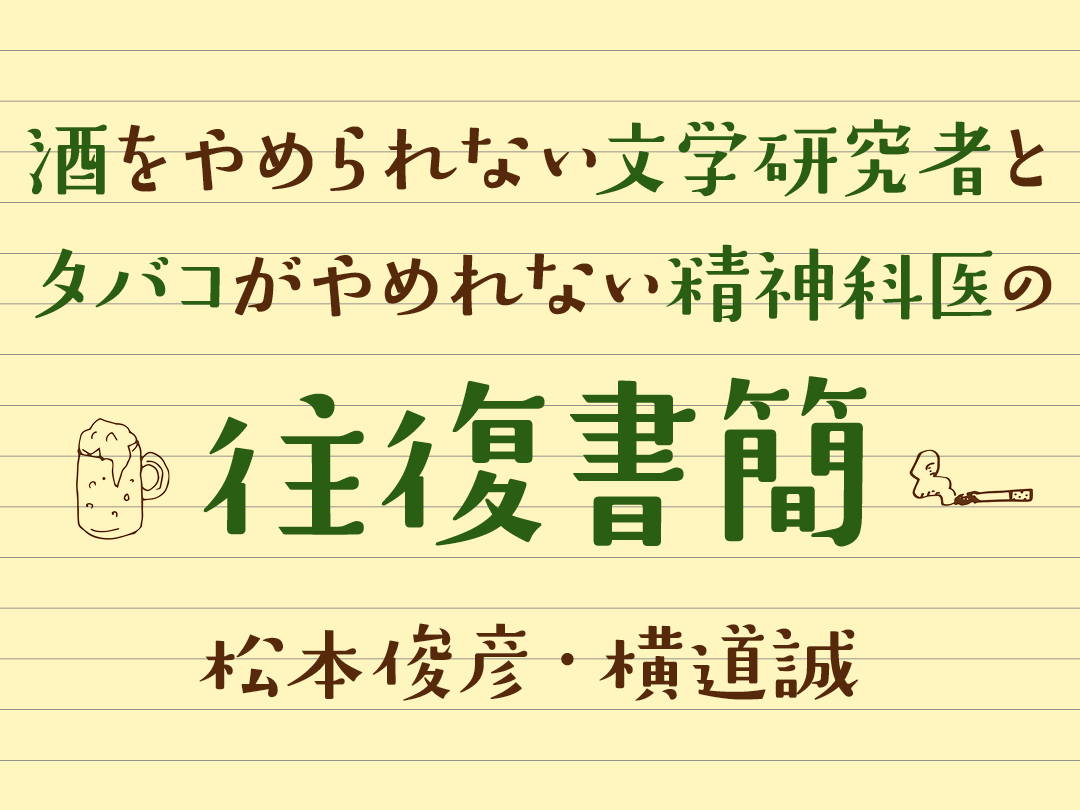依存症は、現代人にとって、とても身近な「病」です。非合法のドラッグやアルコール、ギャンブルに限らず、市販薬・処方箋薬、カフェイン、ゲーム、スマホ、セックス、買い物、はたまた仕事や勉強など、様々なものに頼って、なんとか生き延びている。そして困っている、という人はたくさんいるのではないでしょうか。
そこで、本連載では自身もアルコール依存症の治療中で、数多くの自助グループを運営する横道誠さんと、「絶対にタバコをやめるつもりはない」と豪語するニコチン依存症(!?)で、依存症治療を専門とする精神科医・松本俊彦さんの、一筋縄ではいかない往復書簡をお届けします。
今回は、連載の前半で話題になった「ひととのつながり」と依存症の回復の関係を再考します。特に最も身近な他者――家族との関係について。
はじめに
マコト、お手紙ありがとう。
ここから先は会員限定コンテンツです。
ログイン、または無料の会員登録を行うと
記事の続きをお読みいただけます。