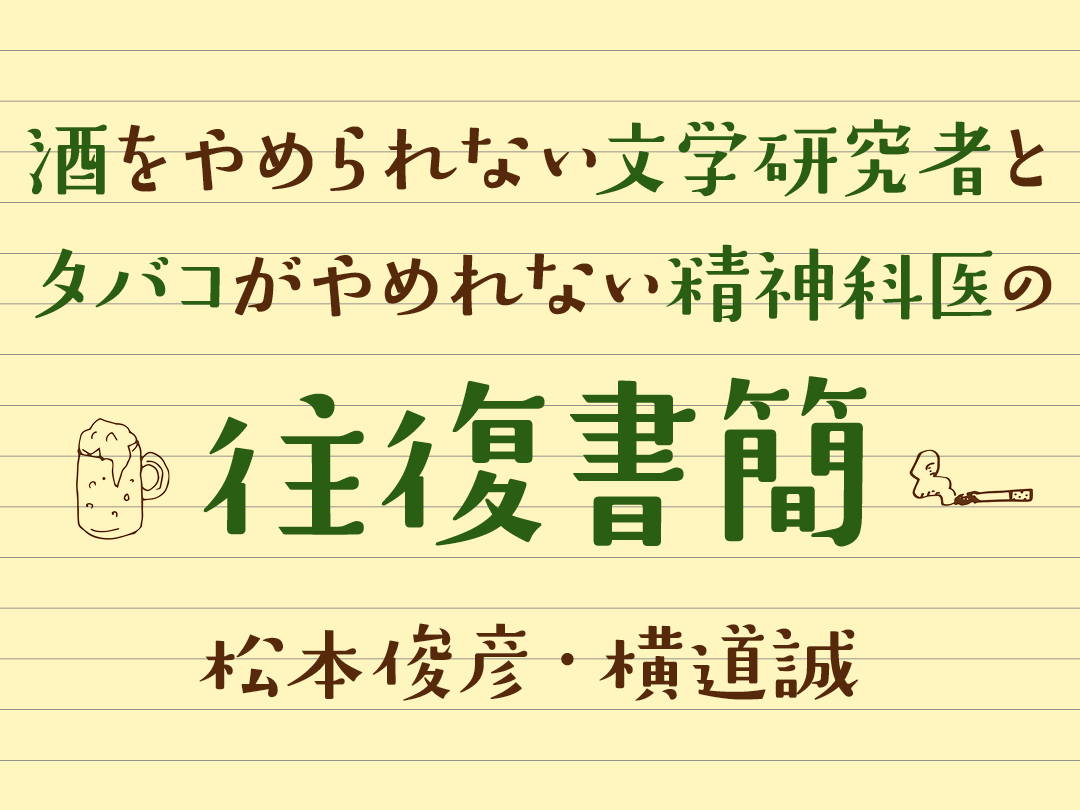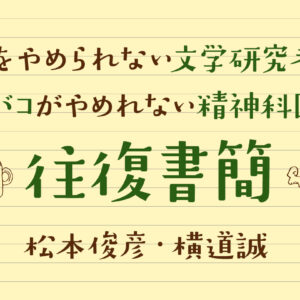依存症は、現代人にとって、とても身近な「病」です。非合法のドラッグやアルコール、ギャンブルに限らず、市販薬・処方箋薬、カフェイン、ゲーム、スマホ、セックス、買い物、はたまた仕事や勉強など、様々なものに頼って、なんとか生き延びている。そして困っている、という人はたくさんいるのではないでしょうか。
そこで、本連載では自身もアルコール依存症の治療中で、数多くの自助グループを運営する横道誠さんと、「絶対にタバコをやめるつもりはない」と豪語するニコチン依存症(!?)で、依存症治療を専門とする精神科医・松本俊彦さんの、一筋縄ではいかない往復書簡をお届けします。最小単位、たったふたりから始まる自助グループの様子をこっそり公開。
第2回は、トシさんの自己紹介と、本連載のテーマである「依存症」とは何か?について。
「ヘイ、マコト」
こんな呼びかけから始まる文章を書くなんて、本当に初めての体験です。ちょっと恥ずかしいような、くすぐったいような感覚、あるいは、「こんな自分でも『自助グループの仲間』にしてもらってもいいの?」といった戸惑いがあります。
不本意な人事、そして自助グループとの出会い
私は依存症を専門とする精神科医です。依存症という分野、実は自ら進んで選んだ道ではありません。確かに医学部入学前から、漠然と「将来は精神科医になりたいなぁ」とは考えてはいました。でも、依存症は完全に想定外だったのです。
私がこの分野を専門としたのは、単に大学医局の不本意な人事のせいでした。なにしろ、精神科領域の中で依存症は「超」がつくほどマイナーかつ不人気分野です。それだけではありません。全国の医学部を見わたせば一目瞭然ですが、依存症を専門として精神科教授になったという人は、まず見当たりません。つまり、この分野を専門にした瞬間に、エリートコースからの離脱、「セカンドクラス」精神科医決定というわけです。
ですから、依存症専門病院赴任当初、私は、大学医局からの「一年だけ泣いてくれ」という言葉をすがるように信じ、やたらと医者に挑み、絡んでくる依存症患者の対応に疲弊し、ため息をついては、「早くふつうの精神科医に戻りたい」とこぼしていました。
そんな私を大きく変えたのが、自助グループとの出会いでした。思い起こせば、25年前のとある日曜日、担当患者から「今度、スピーカーをやるから、聞きに来てくださいよ」と懇願されて、「しょうがねえか」と重い腰を上げ、郊外の教会へと足を運んだのでした。
そこでは、薬物依存症の自助グループ「ナルコティクス・アノニマス」のオープン・スピーカーズ・ミーティングが開催されていました。それが私にとって生まれて最初の自助グループ体験でした。教会の講堂では、薬物依存症の当事者が代わる代わる登壇し、薬物にまつわるずっこけ話や武勇伝を面白おかしく語っては、会場をドッカン、ドッカンと沸かせていました。
そして、新たなスピーカーが登壇し、「薬物依存症の××です」と自己紹介するたびに、聴衆たちは声を揃えて呼びかけていたのが、冒頭の「ヘイ、××」だったのです。その呼びかけは、「これまでどんな立派なこと、どんな悪事をしてこようとも、いまここにいるありのままのあなたを認めるよ」と、無条件承認の応援コールとなって、会場を不思議な一体感で包みました。
最初のうち、私はことさらにステージから距離をとり、傍観的態度を決め込んでいました。しかし、どうやら興奮の渦に巻き込まれ、我知らず人垣を掻き分けて前に進んでいたようです。ふと気がつくと、会のクロージング、あの「平安な祈り」の唱和の際に、私は当事者と一般参加者とが手をつなぎ合って作る大きな輪のなかにいました。 一方の手は、クリーン20年にもなるダルクの施設長のゴツゴツした大きな手とつながり、もう一方の手は、その日初めて自助グループにやってきた人の手――汗でベトベトに湿った掌は、直前まで覚醒剤を使っていた人のものでした――とつながっていたのを、今でも鮮明に覚えています。
神さま、与えてください。
変えられるものを変える勇気と
変えられないものを受け容れる心の落ち着きを
そして、その両者を見分ける賢さを
会場の空気が震えていたのか、それとも私自身が震えていたのか、今となって確かめようがありません。しかし確かに、私はそこで何か大きなものに包まれるような神秘的な感覚を体験したのです。
そして、依存症の人たちに羨望の念を抱きました。「仲間がいるっていいなぁ」と素直に思いました。だって、人は年をとるごとに本当の意味での仲間は少なくなり、孤独になっていくものです。かつての友人は成功を競いあい、マウンティングしあうライバル関係へと変容し、仕事を通じて知り合った人の名刺だけはやたらと増えるものの、所詮は利害関係上のつながりにすぎません。プライベートだってそうです。結婚したり子どもができたりと、私的生活でも責任が増すごとに、家族の前ですら仮面が必要となってくるでしょう。
それなのに、依存症の人たちには仲間がいるわけです。仮面なし、マスクなし、パンツを脱いだフリチン状態でつながれる仲間がいる。その羨望の念が、私をして、「1年といわず、もう少し長く今の病院にいて、その世界を覗いてみよう」と変節させた気がします。
依存症とは何か?――「依存」と「依存症」の違い
ところで、依存症とはどんな病気でしょうか?
ここで注意すべきなのは、「依存」と「依存症」は別であるということです。
断言しますが、依存は決して悪いことではありません(ここを誤解すると、マッチョな自律論や自己責任論が噴出してしまいます)。
実際、みんな何かに依存していますよね? 仕事を頑張ったご褒美として、帰宅するなり缶ビールのプルリングを開けたり、ケーキやチョコレートといった甘いものを自分にごちそうしたりなんてことは、誰だってやっていることです。 あるいは、熱いコーヒーやお茶、あるいはタバコの紫煙、なかにはパチンコやゲームでもよいでしょう。要は、「それがあるから頑張れる」、もしくは、「それがないと頑張れない」といったものがある限り、その人は何かに依存しているといえるでしょう。
人はみな何かしらに依存しています。酸素や水分、食物はいうにおよばず、仲間や家族といった親密な関係性なしに生きていける人などいません。人間は弱い動物なのです。
問題は「依存症」の方です。
一日の仕事を頑張った後のビールのおかげで翌日も元気に仕事ができるのであればよいのですが、夜に飲みすぎて、翌日体調がすぐれずに仕事のパフォーマンスが低下したり、あるいは欠勤してしまったりする。あるいは、酔った際の暴言や暴力によって、自分にとって大切な人を傷つけ、関係性を壊してしまう。これらは「健康的な依存」とはいえません。
そして、こうした事態をたびたび起こしながら、なおもお酒がやめられない、あるいは、何度もやめようと決意しては再び飲むことをくりかえしてしまう――これが依存症です。たくさんのデメリットが明らかなのに、それでもつかの間の安堵を求めてやまない「不健康な依存」、それが依存症という病気です。
けれども、この厄介な病気、「病気」といいながら、徹頭徹尾、医学的疾患ともいえず、社会のありようにもいくらか影響を受けている面があります。
たとえば、最近よく子どもを持つ親御さんから、「子どもは夜通しずっとゲームをやっている。ゲーム依存症だと思う。何とか治療してほしい」という相談されます。でも、親御さんが苛立つのは、それがゲームだからではないでしょうか? もしも自分の子どもが夜通し勉強していたとしても、親は決して精神科医に相談などしないはずです。
結局ところ、親が苛立つのは、子どもが自分の思い通りにならないからなのです。その意味では、依存症は、時代の文化や価値観、あるいは社会的通念と無関係ではありません。
それから、ひとくちに依存症といっても、依存する対象によって治療の場を訪れるタイミングや基準が異なります。
たとえば、毎日に大麻煙草をふかす人と、毎晩お酒を痛飲する人を比較してみましょう。前者は、逮捕によって「社会的に殺される」ことを危惧して治療の場に登場することがありますが、皮肉にも心身は健康そのもので、「こんな元気な人が精神科に受診してもなぁ」と複雑な心境になります。一方、後者は、すでに肝臓がボロボロになり、土気色の顔をした、半ば瀕死の状態で診察室に登場し、「ちょっと来るのが遅かったなぁ。この状態だと精神科の前にまずは内科だなぁ……」と、別の意味で複雑な心境になります。
ここに依存性薬物(あ、アルコールはれっきとした薬物ですよ)の謎があります。実は、ある薬物が違法か合法かといった区別には、明確な医学的根拠などないのです。少なくとも「健康被害や依存性が深刻だから違法」ではありません。主流派に愛されている薬物は合法で、少数派に愛されている薬物は違法と、どちらかといえば多数決で決まっています。
世界中の様々な民族や文化にはそれぞれお気に入りの薬物があります。アメリカ先住民族は幻覚サボテンを宗教的儀式に使う風習があり、成人を迎える青年たちは長老たちから「正しい幻覚サボテンの使い方」を教わる風習がありました。
大麻もそうです。大麻は、かつては中近東地域、アルコール禁止のイスラム圏おける、ささやかな娯楽に過ぎませんでした。ところが、16世紀以降、植民地された南米の砂糖プランテーションにおいて、アフリカから強制的に拉致された奴隷がアメリカ大陸に持ち込みました。そして、サトウキビ畑の脇で大麻の栽培を行って、過酷な強制労働の合間に疲れを癒す嗜好品として重用され、やがて中南米の大衆的娯楽となりました。米国の白人たちはその習慣がどうにも我慢がならなかった――というのは嘘で、本当は中南米からの移民のことが気に食わなかったのでしょう。だから、大麻を目の敵にし、法律によって規制したのです。
現在、世界の多数派は西欧的なキリスト教文圏が握っています。日本を含む、キリスト教信仰国ではないアジアの国々ですら、その文化圏――赤ワインをイエス・キリストの血と捉える、アルコールに寛容な文化圏――に包摂されて、その枠組みのなかで違法/合法が定められているにすぎないわけです。
ひとはなぜ依存症になるのか?――自己治癒仮説
そんな風にいかにも怪しい「依存症」ではありますが、それでもやはり病気としての依存症は存在します。
ただし、それは、よくいわれているように依存性のある薬物を1回でも使用すると、脳の報酬系が薬物の快感にハイジャックされてしまう、といった類いの病気ではありません。それはさすがに薬物の効果を誇張しすぎでしょう。国連が2016年に刊行した「世界薬物報告書」によれば、過去1年以内にヘロインやコカイン、覚醒剤の使用経験のある人のうち、依存症の診断基準に該当する人は1割強程度です。そもそも、世の大半の人が使用しているアルコールだって、実は相当に強力な依存性薬物ですが、依存症になる人はごく一部です。
断言しますが、人間はきわめて飽きっぽい動物です。どんな気持ちがよいもの、どんなおいしいもの、どんな面白いものでも、手を伸ばせばいつでも楽しめるものとなれば、ありがたみが減じ、あっという間に飽きてしまう――それが人間の性です。
誰でもよい、一発ギャグで一気に大ブレイクしたお笑い芸人を思い起こしてみてください。あっという間にお茶の間を席巻して一世を風靡し、テレビチャンネルのどこを覗いてもその芸人が出演しているといった状況になると、余命はせいぜい3ヶ月です。人気はたちまち凋落し、潮が引くような人々の関心が消えていきます。芸能界にはそうした一発屋の死屍が累々と積み重なっていますよね? 彼らは、私たち人間の飽きっぽさによる被害者です。
そんな人間なのに、なぜ一部の人は飽きずにある薬物をくりかえし使用し、あるいは、ギャンブルやゲームに執着し、人生のすべてを犠牲にしてしまうのでしょうか?
思うに、彼らをその薬物に駆り立てているのは快感ではありません。というのも、快感ならばすぐに飽きるはずだからです。おそらくそれは快感ではなく、苦痛の緩和なのではないでしょうか? つまり、人は、かつて体験したことのない、めくるめく快感によって薬物にハマるのではなく、かねてよりずっと悩んできた苦痛が、その薬物によって一時的消える、弱まるからハマるのです。快感ならば飽きますが、苦痛の緩和は飽きません。それどころか、自分が自分であるために手放せないものになるはずです。
ちなみに、苦痛の緩和に役立つのは、心地よい酩酊だけではありません。一般的には「苦痛」と捉えられるものですら役に立つことがあります。たとえばリストカットのような自傷行為を考えてみましょう。確かにいずれの行動も、一見すると、快感にはほど遠い行為です。しかし、それでも、それよりもはるかに大きい苦痛から一時的に意識を逸らすのに役立つ可能性があります。そうであればこそ、リストカットはしばしば習慣化するのです。
こうした観点は依存症臨床ではよく知られているものです。かつて米国の依存症専門医エドワード・カンツィアンは、「依存症の本質は快感ではなく苦痛であり、人に薬物摂取を学習させる報酬は快感ではなく、苦痛の緩和である」と指摘し、「自己治療仮説」という考え方を提示しました。この自己治療仮説は、私たちに依存症の本質を教えてくれます。それは、依存症は確かに長期的には命を危険にさらしますが、皮肉なことに、短期的には、今いるしんどい場所や状況に踏みとどまり、「死にたいくらいつらい今」を一時的に生き延びるのに役立つことがある、ということです。
人が何かにハマるとき、そこには必ずピンチが存在します。大切な関係性の喪失や破局のような一大事かもしれませんし、少々無理をしている、今いる場所が何となく居心地が悪いといった程度のこともあるでしょう。程度の差こそあれ、ピンチにはちがいありません。
そのことは、依存症の臨床現場でも日々痛感させられています。というのも、診察室で酒やクスリの話をしているのは、治療を始めてせいぜい最初の1、2年だからです。治療関係さえ続いていれば、大抵、酒やクスリの問題なんて多少ともよい方向に向かうものであり、それに伴って次第に診察室で話題になるのは、日々の生活の困りごとや、今また口を開いて流血しはじめた心の傷の話です。そうした話を聞きながら、私はこう考えるのです。「この患者さんがほんとに困っていたのは、酒やクスリのことではなくて、こっちのことだったのかも……」と。
その意味では、依存症の問題はそうした根っこにある生きづらさへの応急処置にすぎず、問題の本質は酒やクスリとは別の場所にある――経験を積めば積むほど、私はそんな思いを強めてきました。これはリストカットなどの自傷にも当てはまります。あるいは、こう言い換えてもよいでしょう。曰く、依存症や自傷は「支援につながるための入場券」にすぎない、と。
そんな思いで、様々な依存症だらけのマコトの人生へと思いを馳せるとき、そして「宗教二世」としての生い立ちを考えるとき、いろいろと思うところがたくさんあります。
この往復書簡を通じて、「やめる/やめない」といった薄っぺらな依存症論ではなく、依存症の裏側にある深い井戸に糸を垂らしていきたいです。
<担当編集より>
マコトさんと私が出会ったのは、担当書への寄稿をお願いしたことがきっかけでした。打ち合わせをセッティングしたところ、まだ日が高い時間帯にもかかわらず、マコトさんは淡麗のロング缶を片手に登場しました。その時、出席者は私ひとりだったので、「私は夢を見ているのかな?」と半信半疑でいました。あまりのことに現実を受け入れられなかったのです。
しかしその後、様々なイベントでご一緒する度に、マコトさんが時間・場所を問わずお酒を飲んでいる場面を目撃することになり、「これはただごとではない」と気が付くにいたりました。編集者として、一友人として、見過ごすことはできない、という思いに駆られました。思えば、依存症というのは現代人にとって、とても身近な「病」です。
そこで依存症といえば、松本俊彦さんであろう!とトシさんにお声がけをするにいたりました。依存症の治療では、当事者同士が自身の体験について話し合う「自助グループ」が有効といわれています。トシさんは、依存症の専門医でありながら、実は超がつくほどのヘビー・スモーカーで、「ニコチン中毒」。ある意味では当事者でもあります。そんなおふたりが対話することで、何かが起こるのではないか。そしてその対話を読んでいる人にも、きっといい影響があるのではないか。そんな期待があって、今回の往復書簡を始めるにいたりました。お楽しみください。
次回の更新は、7月6日(木)17時になります。
【お知らせ】
当連載を収録した書籍『酒をやめられない文学研究者とタバコをやめられない精神科医が本気で語り明かした依存症の話』が発売決定! 全国書店やAmazonなどの通販サイトで、2024年9月13日より発売いたします。

筆者について
まつもと・としひこ 1967年神奈川県生まれ。医師、医学博士。国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部部長。1993年佐賀医科大学医学部卒業。神奈川県立精神医療センター、横浜市立大学医学部附属病院精神科などを経て、2015年より現職。2017年より国立精神・神経医療研究センター病院薬物依存症センターセンター長併任。主著として『自傷行為の理解と援助』(日本評論社) 、『アディクションとしての自傷』(星和書店)、『自傷・自殺する子どもたち』(合同出版)、『アルコールとうつ、自殺』(岩波書店, 2014)、『自分を傷つけずにはいられない』(講談社)、『もしも『死にたい』と言われたら』(中外医学社)、『薬物依存症』(筑摩書房)、『誰がために医師はいる』(みすず書房)、『世界一やさしい依存症入門』(河出書房新社)がある。
よこみち・まこと 京都府立大学文学部准教授。1979年生まれ。大阪市出身。文学博士(京都大学)。専門は文学・当事者研究。単著に『みんな水の中──「発達障害」自助グループの文学研究者はどんな世界に棲んでいるか』(医学書院)、『唯が行く!──当事者研究とオープンダイアローグ奮闘記』(金剛出版)、『イスタンブールで青に溺れる──発達障害者の世界周航記』(文藝春秋)、『発達界隈通信──ぼくたちは障害と脳の多様性を生きてます』(教育評論社)、『ある大学教員の日常と非日常――障害者モード、コロナ禍、ウクライナ侵攻』(晶文社)、『ひとつにならない──発達障害者がセックスについて語ること』(イースト・プレス)が、編著に『みんなの宗教2世問題』(晶文社)、『信仰から解放されない子どもたち――#宗教2世に信教の自由を』(明石書店)がある。