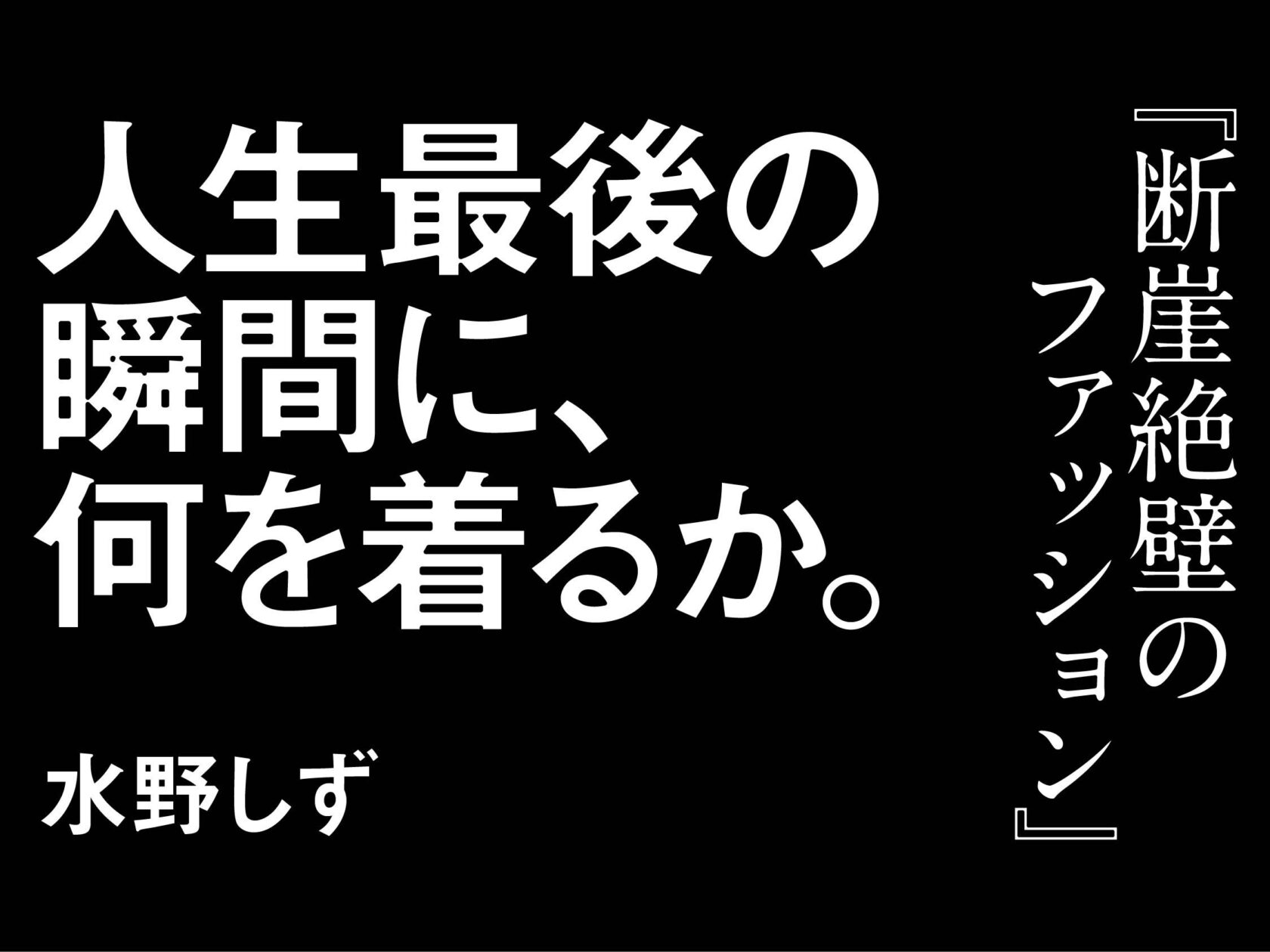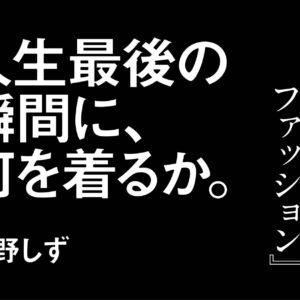「あの服も、この服も納得がいかない……私がほんとうに着たい服ってなに?」
世間は色々な問題を投げかけてくるけど、どれもこれも肝心なこと、漠然とした問いかけの先にある根本的な問題には触れていないような気もする。今のファッションが退屈でしっくりこない、悩めるすべてのみなさまへ。
こちらは、まだ誰も言葉にしていない違和感を親切に言語化する“ポップ思想家”の水野しずさんによる、トレンドを追うよりも、納得のいくスタイルを発見していくためのファッション論考の連載です。「着るという行為」について、一緒に考えていきましょう。
中学生のころ連れて行ってもらったデパートで…
「なんでも欲しい服を買ってあげる」
と、中学生になった私に母は言った。突然の高待遇に、私は内心ですこし引いた。なんでも? 突然の親切はこわい。急にそんなことを言われると、翌日はなにかの施設に連れて行かれるんじゃないか、とか、そういう、身も蓋もない想像力が働いた。断る理由はないので、言われるまま母の車に乗せてもらった。提示した高待遇に反して意外にも難色を示す娘の態度に、コメントのしようがなくなった母は、粒ガムのボトルから4つ取り出して口に放り込んだ。私がなにかを言わなければならない。そう思ったが、ガムの音が断続的に響く車内で、どのタイミングで何を言ったらいいのか、わからない。結局、目的地に着くまで変なムードは続いた。流石に申し訳なさすぎて、軽くめまいがしてきた。出だしの反応に失敗してしまった分、内容というか、ちゃんと本気で欲しいものを見つけるという「実現」の面では大成功を収めたいということを黙ったまま思った。ガムの咀嚼音を聞き続けているうちに、思いはジワジワ決心に変わった。やがて雨が降り出して、ガムの咀嚼音にワイパーの音が加わった。田畑を耕す農民のように、私はリズミカルに決意を固めた。
「絶対に渾身の、人生最高のお買い物を達成する」
車を降りると、小雨と霧の中にデパートはそびえ立っていた。名古屋市に隣接する郊外都市にある巨大なデパートの全体は、地元小学校の校舎よりもよっぽど大きい。これだけの建造物の中に、人の夢を具体的に実現する欲しさのご本尊が詰まっているのかと思うと、さっきよりもっとめまいがした。あるでしょう。これは。渾身の夢を完璧に実現してくれる、果てしなくすばらしいなにかが。デパートの建物と建物を繋ぐ連絡通路になっている部分の外観には、校庭に広げられそうなくらいのこれまた巨大なステンドグラスが嵌め込まれていた。すごい。そのとき、私の脳裏には、なぜか「豊作貧乏」という言葉が浮かんだ。言葉の印象に引っ張られて、両手に甘夏を抱え困っている感じを出しつつも「大収穫」という事態への根源的なよろこびを隠しきれない翁のイメージも浮かんだ。
デパートに入ってすぐ、目についたショップの服を手に取ったら即座に両手がさむい感じになった。満潮の海岸線から波が一斉にさーっと引いていく感じだ。なんだろう、コレは、と思って気持ちの出どころを確かめてみると「好き、欲しい、買いたい」とは真逆の方面に情緒の波が吸い寄せられていくのがわかった。この感じを平たく言うと「全然欲しくない。いらない」になるのではないか。少しずつ、判明してくる情緒の全体像が明らかになると同時に、私は手に取ったいらない布、というかワンピースの「いらなさ」をじっと見つめた。
まず色が良くない。ピンクと言っても、見ているこちらの骨や内臓にビリッとくるような引っ掛かりやスパイシーさがどこにもない。ペイントツールで塗りつぶしたような、志がどこにもない血色をしている。これを豚色と言ったら豚がかわいそうになるけど、現実問題、豚の皮膚色に近しい色味だ。ピンクと言ったらやや大げさな、白と言うにはニュアンスが強い、桜と言うにはもっと肉肉しい、ブラジル産鶏むね肉のももいろをブロック状に成型して真空ビニールパック詰にしたらなんだかこんな色になるのかもしれない。ショボいばかりか吐きそうな色だ。この最悪の色面に、心ばかりのビジューが3~4つ漠然と張り付けられている。丸みのある襟ぐりにはない方がマシなフリル、スカート部分のすそは授業参観を思わせるマーメイドラインになっていて、ここにも余計なフリルが張り付いている。全てがその場しのぎという感じ。救いがない。これ一つだけに救いがないのなら、別にいい。しかし、店内を見渡して目に入ってくるのはどれもこれも同様の精神性のものばかりで、つらかった。リボンのことを全く考えたことのない人が暇つぶしで余白にリボンを配置しているような装飾一帯のだらしなさ。私は世間知らずだったので、このときは「婦人服」とされているジャンルのものの実態を、あんまりよくわかっていなかった。極度に受け入れ難いと感じた。
どことなく、学校給食で配布された七夕のデザートに乗っていた星を思い出した。ヒトデの死体よりも活気がなく、ビート板みたいなテクスチャーの星型によろこべなかった感じと、今この瞬間のガッカリはとてもよく似ている。
それから私はデパートの1階から9階までできる限り多くの服売り場を必死になってみて回ったが、心からほしいと思えるものなんかひとつもなかった。「ない」。まさか、そんな結論になるとは。途方に暮れて、エスカレーターに運ばれながら、どの点が自分にとって最も我慢ならないのかを考えた。なにが悪いのか。悪いというか、未満というか。ここに集まっている大量の服は私の心をすこしも壊してくれない。それどころか、私を取り囲んでいる漠然としたまどろみの感じ、信用できないボヤッとした感じ、肝心な部分は最後までアヤフヤにし続けるうさんくささみたいなものに無関心でいる態度が無理だし、イヤだ。無関心というか、20メートルくらい離れたところから
「まーそーいうもんですよ」
とか言ってきている感じというか。“私そのもの”に対する他人事感がすごい。最初っから最後まで私なんかどこにもいなかったみたいにシカトを決め込むつもりなんじゃないのかコイツらは。こんな服を着たらしぬ。私の心がしぬ、身体がしぬ、言葉も魂も季節も耳もしんで全部しぬ。あり得ないこんなのありえない。
愕然とした。ボーゼンとした。もう立ち尽くすしかなかった。どれもこれも、ぜんぜん一つも好きになれない。納得ができない。つまらない。こんな建造物、真っ二つにひび割れても構わない。デパートってもっと夢のような場所じゃあなかったんですか。こう、欲しいものが一箇所に集結してどれもこれも輝いている、みたいな話では、なかったんですか。私の心を壊してくれるようなもの。痛いくらいに信じられるものなんて、世の中にあるんだろうか。
ない。なら、ないで、別にいい。「ない」って言える自分でいられるなら、別にそれで構わない。好きなものしか好きじゃない。いらないものは絶対にいらない。無料だから、とはどうしたってなれないしならない。欲しいものしか欲しくない。そういう気持ちのひとつ手前に、いらないものに対する絶対的ないらなさがものすごくある。これだけは信用ができる。誰に伝わらなくたって、構わない。
なにも買わなかった帰路、母はもうガムすら噛んでいなかった。なんにも言えなかった。言葉がわからない。強まってきた雨が、フロントガラスを叩いた。私はただひたすらガラス窓を伝う水滴のアメーバみたいに有機的なながれをじっと見た。それは表面張力に従って融合したり重みに耐えかねて落下したりの繰り返しをやっていた。ない、というか、あるとか思ってはっちゃけている方がおかしな話だったのかもしれない。むしろ、あった方がコワい。コワさを超えて、それでもあるものだけが「ある」。そういう「ある」は、コワいけどコワさの奥に痛烈なよろこびがあるのかもしれない。宝石が砕け散った瞬間を目撃したような、ショックと感動が同居したよろこびが。いらなさで、憧れはむしろ高鳴る。
「ある」より先に、「ない」という真実がある
大人になってからハッキリ「ない」と言っている人を見た。
見たというか、映画で観た。アメリカ版『VOGUE』の編集長として知られるアナ・ウィンターの仕事ぶりを描いたドキュメンタリー映画『ファッションが教えてくれること(邦題)』を一言で表すならば、やはり修羅という言葉が相応しいのでないか。『プラダを着た悪魔』のモデルになったとされる仕事の現場だ。比べて観ると、作られたフィクションの方では、困難さを物語として織り込める程度に、かなりの手心を加えられていることがわかる。
アナはファッション界の女帝だから、周りに仕えているスタイリストや下っ端アシスタントはいつなんどきもアナを失望させないために命懸けで準備の限りを尽くす。絞れる限りのアイデアを絞り、揃えられる限りのものを揃える。そこまでやっても大抵の場合、アナは諸行無常といった顔をしている。ものすごく厳しいけど、それでも全てを諦めていない人が渾身の厳しさを発揮するときの、目が座ったまま、ほうれい線周りの筋肉が奥歯の付け根に向かって引っ張られていくあの、川久保玲もよくやる表情をアナはしている。
編集部のバックルームには、アナのお目通りの瞬間を待ち望んでいる服が大量にかけられている。どれもこれも超有名なブランドの一流デザイナーによる気合が入った最新作ばかりだ。ここにある服だけでもホテルの大広間で開催されるパーティーの来客に必要なドレスが全て賄えるんじゃないかというくらいに、服が空間を埋め尽くしている。アナは、夥しい量の服を見渡し、撮り下ろした写真を一瞥しては言う。
「ない」
ないんだ。ないのかよ。副編集長はほとんど泣きながら軽口を叩いてギリギリ正気を繋ぎ止めている。スタイリストは苦悩している。アシスタントは猛然と走る。ストーリー性が破綻し切った地平で狂気とがっぷり四つの正気が悶え苦しんでいる。布まみれの地獄絵図がここに完成をしている。ああ、でもわかる。すごくわかる。「ない」。ないんだよ。「ある」より先に、より克明に「ない」という真実がすごくある。それは崖みたいに、断崖絶壁みたいに、墜落と飛翔が一体化した浮力としてあって、気絶しそうなまどろみの中に散逸してしまいそうな意識をいつだって覚醒させてくれる。
どうして忘れてしまうんだろうか。欲しいものしか欲しくない。それなのに、私の意識が断崖絶壁の淵に手をかけて、決定的な判断を下す以前に、
「あなたが欲しかったものは、きっとこれ。ですよね?」
と、穏やかな笑みを湛えて、親しげに、どっかから語りかけてくるものがある。それは親身なようでいて、よくみるとさっぱりしらけた他人事の顔をしている。あぶない。また簡単に手が届く場所になにかが「ある」ような気がしてしまった。私の知らない、遮蔽された壁の向こうの果てしないところに、なんだかすっごくいいものがきっとあるんじゃないかと。それだけが我々が生きている限りにおいて「希望」だと名乗りを上げる資格があるかのような、泥沼の日常の平衡感覚の歪みに危うく引きづり込まれそうになる。均質で夢心地のまどろみのつまらない天国っぽいなにか。その度にわたしは絶対に「なかった」あの日を思い出す。
自分で自分の心を壊すのだって、やってみればたのしい。私は覚醒をしていたい。断崖絶壁をやるために。
次回は、12月5日(火)17時更新予定。
筆者について
みずの・しず バイキングでなにも食べなかったことがある。著書『親切人間論』他