縄文と土着を結びつけた岡本太郎の「日本の伝統」論は、新しかった。「日本人とはだれか」というアイデンティティの問題に揺れていた戦後社会に、これまでにない自画像の視点を提示した。そして、岡本の批判の矛先は近代日本の民芸運動にも向けられた。
縄文土器論の加筆
1954年、岡本太郎は『今日の芸術』を出版する。彼は「芸術」に対して「うまくあってはいけない」「きれいであってはならない」「ここちよくあってはならない」と言い、対極主義を平易な言葉で語りながら、権威に対して冷水をかけた。この本はベストセラーとなり、岡本への注目はさらに大きくなった。
1955年12月には「伝統とは創造である」と題した論考を『中央公論』に発表し、亀井勝一郎の『大和古寺風物誌』や竹山道雄の『古都遍歴』を批判した。
彼は法隆寺金堂壁画の焼失を嘆く世論を批判し、次のように論じた。
今さら焼けてしまったことを嘆いたり、それをみんなが嘆かないってことをまた嘆いたりするよりも、もっと緊急で、本質的な問題があるはずです。
自分が法隆寺になればいいのです。
失われたものが大きいなら、ならばこそ、それを十分に穴埋めすることはもちろん、その悔いの空虚を逆の力に作用させて、それよりもっとすぐれたものを作る。そう決意すればなんでもない。そしてそれを伝統におしあげたらよいのです。
そのような不遜な気魄にこそ、伝統継承の直流があるのです。むかしの夢によりかかったり、くよくよすることは、現在を侮蔑し、おのれを貧困化することにしかならない。
[岡本2005:51]
岡本は、この論考を土台に、翌年(1956年)、『日本の伝統』を出版する。そして、1952年に発表した「縄文土器論 四次元との対話」を再編集し、本書の一部に組み込んだ。
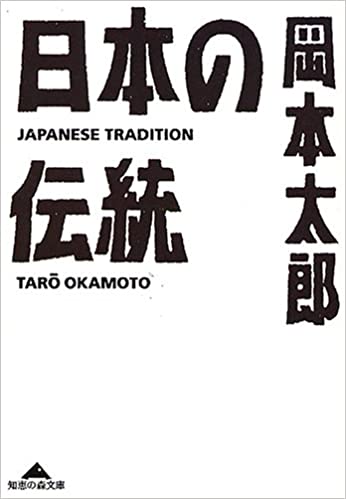
その準備のため、彼は2月から3月にかけて国立博物館、国分寺文化財保存館、東京大学人類学教室、明治大学考古学陳列館を訪問し、自らの手で縄文土器の写真撮影を行った。この写真を掲載する形で、『日本の伝統』は9月に出版された。
岡本は、縄文土器論にいくつかの加筆を行っている。重要なのは、縄文土器の四次元的性質について述べた部分の加筆である。
1952年発表の論考で、狩猟と呪術の関係について言及し、猟では、実際に獲物を捕らえる作業よりも、その前後に行われる儀礼に重要な意味があると論じていた。
加筆はこのあとである。
岡本は、おもむろに「鹿踊り」という舞踊を取り上げる。これは「シカの頭をかぶり、背には長いささら竹をつけて、それをくねらせながら腹につけた太鼓を打って部落じゅうを踊りあるく」もので[岡本2005:91]、現在でも岩手県花巻などで行われている。彼はこの民俗舞踊に、縄文を古層とする伝統を見出した。
今日でこそただのお祭りの踊り、獅子舞いとべつだん変わらないような風俗としてあつかわれていますが、鹿猟に密着した呪術から発展したものにちがいありません。
[岡本2005:91]
続いて、アイヌの「熊祭り」について加筆し、これが「古い呪術のしきたりをのこしてい」るとした上で、次のように述べた。
多くの人はこのような事がら、風俗は、ものの因果、理屈を無視した原始的で野蛮な迷信、考えかただと片づけてしまうでしょう。だが笑ってはいけない。今日だってなおさかんに、大まじめにおこなわれているのです。
[岡本2005:91]
岡本は、各地に残る民衆レベルの習俗に、「原始的な心性の残存」を見出している[岡本2005:91]。それは素朴でたくましく、時に豪快な迫力を持っている。その呪術的儀礼性は、命を懸けた狩猟と関わっており、どこまでもおどろおどろしく、生々しい。彼は、現代の生活世界に生きる「鹿踊り」や「熊祭り」のなかに、縄文の「四次元的性格」を継承するものを見出した。
岡本の加筆は、別の箇所でも見られる。
1952年の論考で、彼は縄文人の矛盾律に言及し、獣は危害を与える凶暴な「敵」でありながら、一方で、重要な食料でもあることを指摘した。そして、縄文人の「神秘的美観」の根底には、恐怖と恩恵という相反の同居があると述べていた。
この指摘のあとに、再びアイヌの「熊祭り」について加筆している。彼は、アイヌ社会における主食であるクマが、同時に「神格のなかでの主神」になることを論じ、フレーザー『金枝篇』に触れた上で、「人間の本能の深みにひそむ、愛するからこそ憎み、憎むからこそ愛するというアンビヴァランス」こそ「世界の原始社会に共通した心情」であると述べた[岡本2005:97]。
岡本は言う。
そういう人間生命のギリギリの矛盾、そして、たくましい生命力を今日とかく見うしないがちです。
[岡本2005:97]
岡本は、縄文的なるものの美が、現代でも民俗世界のなかに残っているという確信を抱き、縄文土器論を加筆した。日本の原始に存在した強靭な美は、消滅したのではない。中央では「わび・さび」の世界に追いやられながら、地方の土着世界において、堂々と息づいている。縄文人の「四次元的性格」は駆逐されず、フォークロアの生活世界のなかに根付いている。しかし、戦後日本は日本の伝統を「わび・さび」の世界に集約し、中央の知識人の権威的審美眼に従属している。土着的なものは洗練された伝統とはみなされず、その価値は正当に評価されていなかった。
これではいけない。縄文人が保有していた強靭な「矛盾律」と「たくましい生命力」を取り戻さなければならない。そうしなければ、新しい時代の美を探求することはできない。神聖なるものに肉薄することができない。
岡本は、「縄文的な美」と「わび・さびの美」の相違を、原始/中世以降という時間軸だけでなく、空間的・階級的地平に見出した。「わび・さびの美」が東京や京都のような中央で、エリート層によって担われてきたのに対し、「縄文的な美」は東北などの地方で、民衆の生活世界のなかで継承されて来た。彼は前者ではなく、後者を「日本の伝統」として再定義し、新しい芸術の方向性を見定めようとした。
そして、岡本は旅に出る。
それは、生きた「日本の伝統」と再会する旅となった。
秋田の「なまはげ」 原始宗教の現われ
岡本は1957年4月から11月にかけて『芸術新潮』で全8回の連載を行った。これは、『日本再発見 芸術風土記』と題され、翌年(1958年)、新潮社から出版された。

彼は、この連載・出版を次のように位置付けている。
私は数年前、「今日の芸術」を発表し、芸術に対し、日本人をはゞんでいる、封建的な固定観念をうち破った。そこに示した自由は新しい時代のエキスプレッションであり、その歓び、可能性だった。
次に「日本の伝統」を書いて、過去を今日的な立場からえぐり返した。勿論まだいろいろと、とり上げたい問題は残っている。だが、それよりも先に、私は今度は「現在」に体当たりしてみたいと思った。最も散文的であり、非芸術的であるときめられ、さげすまれ、ほとんどまともに顧みられていない、現代日本のありのまゝの姿から芸術の問題を掘りおこすこと。われわれの誇りと生甲斐を具体的につきつけ、この辱めをひっくり返すために。
[岡本1958:283]
まず向かった先は、秋田だった。なぜ秋田なのか。それは秋田に「原始的なもの」が残っていると考えたからだった。
私がこの芸術風土記の最初に、まず秋田をねらったのは、シーズンのせいもあったが、それよりも“なまはげ”とかその他の遺風にのこっている、極めて原始的なものに強くひかれたからであった。私の関心は、むしろ、古い、うしなわれたわれわれの文化の根源に向けられていた
[岡本1958:25]
とり残されたところに、古くから永遠にひきつがれて来た人間の生命の感動が、まだなまのまゝ生き働いているのではないかと思った。
[岡本1958:29]
彼は秋田の「なまはげ」に注目した。よく知られるように、「なまはげ」は大みそかの晩(もしくは新暦1月15日)に、鬼に仮装した若者が家々を訪れる行事である。鬼は手に木製の包丁や手桶を持ち、大きな声で子供や初嫁をおどして回る。これに対して、各家では餅や酒などを振る舞い、鬼たちをもてなす。
民俗学者の柳田国男の解釈では、「なまはげ」は「ナモミハギ」の略とされる。「ナモミ」とは、火に当たっていると皮膚にできる斑点のことで、囲炉裏のそばにいてばかりいる怠け者の皮膚をはぐ「ナモミ剥ぎ」からきていると言われる。
この解釈に、岡本は異を唱える。
怠け心や悪疫をはらうというのは「功利的なホーケン道徳の色合いをおびて」おり、後世の後付けだろうと推察する。そして「この風俗はむしろ、もっとずっと古く、アジア全般にひろく生きていた原始宗教、シャーマニズムと何らかの関係がありはしないか」と自論を展開する。[岡本1958:33]
岡本にとって「なまはげ」は、大和朝廷の神話や外来の仏教・儒教が入ってくる以前の古層と連続している。それは「原始宗教」を継承するものであり、「根源的感動」を引き起こす存在である。
そこには人間本来の生命力がある。そして自然と人間との最も緊張した対立と融合がある。
[岡本1958:34]
まず岡本が注目したのが、鬼の「お面」である。写真で見た「なまはげ」のお面は、「無邪気で、おゝらかで、神秘的」だった。そして「濃い生活の匂い」がした。彼はそこに「底抜け」で「ベラボーな魅力」を見出し、「古い民衆芸術のゆがめられない姿だ」と絶賛した[岡本1958:34]。
岡本の見るところ、「なまはげ」は「あらゆる原始的な人間社会にみられる「霊」のあらわれである」。その霊は「生命の底の深み」と連動している。生活と密着している。
しかし、それが「鬼」という言葉で呼ばれ始めると、イメージの規格化がはじまり、徐々に生活のリアリティから外れていく。本来は土地の独自の存在であったものが、記号化された「鬼」の表象へと統制され、均一化していく。これによって「ベラボーな魅力」は失われ、神秘性がそぎ落とされる。
岡本が、秋田で実際に見た「なまはげ」にも、この規格化が進行していた。お面は平板で、「鬼」の通念に沿ったものになっていた。しかし、「それをつける若い漁師の素顔の逞しさと藁の衣装とのなまなましいコントラストはすばらしかった」。そこには「なまはげ」の実感が残存しており、原始の精神が息づいていた。[岡本1958:38]
岡本曰く、「なまはげ」は「鬼なり動物なり、神なりになりきってはいない」。「人間でありながら、そのまゝ人間を超えている」。人間と霊は互いに交錯し、自由に交流する。そこに原始信仰の魂が現れている。[岡本1958:43]
岡本が「なまはげ」に見出したのは、古代人の精神であり、縄文のエートスだった。そして、このプリミティブな土着文化こそ「日本の伝統」であると見なし、根源的な生命力と神秘を見出した。
花巻の鹿踊り
その後、岡本は「日本の伝統」を探して長崎、京都、出雲などを訪れた。しかし、心の旋律に触れて来る「文化」はほとんどなかった。
そんななか、彼の心をつかんだのは、やはり東北だった。
連載の後半で、岩手を訪れた。そこで「鹿踊り」を体験し、魂を湧き立たせた。
前述のように、岡本は『日本の伝統』に収録した縄文論に、「鹿踊り」についての文章を加筆していた。旅に出る前から「縄文文化人が鹿の肉を常食にしていた時代の呪術的儀礼からの伝統だとにらんでいた」。[岡本1958:190]
生活のためにそれを殺し、肉を食う。獲物を豊かに得るための呪術であり、またその霊に対する感謝、慰撫。そしてまた食べられてくれという願いをこめての、当然の儀式である。狩猟民族の面目がこゝにある。だから中央文化や仏教の以前、山と山の間にはさまれ、狭い世界に自然と格闘しながら生きていた時代の原始宗教の名残りに違いない
[岡本1958:190]
岡本は、花巻で実際に「鹿踊り」を見学し、歓喜した。そこには「人間が動物を食い、動物が人間を食った時代」の精神が継承されていた。それは「太古の血の交歓」であり、暗い情念を秘めていた。「鹿踊り」を見ていると、「残酷で、燃えるような、宇宙的な情熱が迫って」きた。[岡本1958:193]
すっかり嬉しくなってしまった。私の今まで見た中で、そういうものが最も純粋な形で残っている。稀有な例だ。
[岡本1958:193]
「なまはげ」と「鹿踊り」―――。
岡本は、東京や京都から遠く離れた東北の生活世界に日本のエートスを見出し、その原始の躍動と対峙しながら、新たな芸術を立ち上げようと考えた。
縄文と土着を結びつけた「日本の伝統」論は、新しかった。そして、「日本人とはだれか」というアイデンティティの問題に揺れていた戦後社会に、これまでにない自画像の視点を提示した。
茶道でも華道でもない。優美でも風流でもない。「わび・さび」を愛でるアポロン的知性ではなく、魂の根源を突き動かすディオニソス的精神のなかに、岡本は庶民生活と直結する伝統を見出したのである。
民芸運動への懐疑
岡本は、この観点から近代日本の民芸運動を批判する。民芸運動は1926年に柳宗悦(やなぎ・むねよし)や河井寛次郎、浜田庄司らによって提唱された生活文化運動で、無名の職人たちによって作られた日用の道具を「民芸」と呼んで評価した。柳らは、美しいものを作ろうとする計らいこそが美を遠ざけると見なし、日常生活に即した民芸品にこそ「用の美」が宿っていると指摘した。
岡本は、出雲への旅で、出雲民芸紙の作家・安部榮四郎の自宅を訪問した。岡本は安部の作品について「和紙の特性を一だんと研究し、押し進めたその努力と成果は見上げたものだ」と率直に評価する一方で、それに付随するアクセサリーを「民芸調」でよくないと酷評した。
たとえば「出雲民芸紙」と木版調でボテッと印刷したレッテルをはったのなどを見せられると、とたんに中身のよさがすっとんでしまう。またどうして「民芸紙」なんて妙な名前をつけたんだろう。
[岡本1958:155-156]
岡本は出雲各所の窯場を見て回り、特に布志名焼の「夜づくりどっくり」や「まんじゅうむし」に感銘を受けた。そこには生活に根差した素朴さが現れており、「おゝらかで、すじがとおっている」。無駄な装飾は存在せず、「必要なだけの形」をしている。色も、土地の素材から出た自然なものが取り入れられており、冴えている。[岡本1958:156]
これらの良さは、出来上がりの結果なんか鼻もひっかけない、気にしていない凄さである。こういういわば自然に出て来たものに芸術家はいつでもほとほと感心してしまう。
[岡本1958:156]
しかし、これが「民芸」という枠にカテゴライズされ、「民芸品」を作るという意識を持ったとき、作品から純粋な魅力が消え去っていく。そこに新たな計らいが現れる。作り手たちは「民芸」という観念にとらわれることによって、「結果を目的にして」しまう。「素朴をねらえば、素朴でなくなり、生活的な、香り高い土の匂いは鼻もちならない泥臭さに変ってしまう」。そうして出来上がった作品は、「民芸らしいもの」には仕上がっているが、「豊からふくらみ」が失われている。[岡本1958:157]
岡本は民芸運動の功績を否定するわけではない。各地の職人たちが、生活世界のなかで作ってきた道具のすばらしさを自覚しないまま、捨て去って行こうとするのに対して、「待ちなさい、君たちはこういうすばらしさがある、と自覚に高めて伸ばして行くという運動は、まさに正しい」。[岡本1958:157]
しかし、そのことによって、当事者たちは「民芸」であることを意識し、「芸術」であることを意識し始める。そうすると、途端に賢しらな計らいが支配し、純粋な美が逃げ出していく。
悲劇はその指導者たちが、芸術家ではなく、“芸術主義者”、ディレッタントだったところにある。彼らの善意にかゝわらず。地方の素朴な人たちに、指導者自身が持っている芸術に対するコンプレックスを植えつけたのだ。作家、芸術家という幻影を抱きはじめ、自分の作っているものは価値のあるものだと自負しはじめたとたんに、新鮮さがひっこんでしまい、民衆芸術の素朴さを失って、彼らの指導者と同じように、ニセ芸術家になってしまうのである。
民芸運動の全面的な失敗はそこにある。それはあらゆる土地で、純粋な民衆芸術を生かしたようで、実は亡ぼしている。指導者のディレッタント的な甘さが、まだそれに気がついていないだけの話である。
[岡本1958:158]
岡本は、民芸運動の重要性を指摘しながら、その指導者たちを批判した。彼らの「芸術主義」こそが、職人たちに「芸術家」という幻影を与え、民衆芸術をゆがめてしまったと指摘した。
岡本が民芸運動の指導者を厳しく批判したちょうどこのころ、一体の土偶を手にし、生涯をかけて集めた膨大な蒐集品のすべてと交換してもよいと言った人物がいた。
最晩年の柳宗悦である。
柳は民芸運動の指導者であり、その運動を牽引してきた当人だったが、最晩年の彼は、民芸運動の潮流を追い越し、はるか先のラディカルな世界へと突入していた。
同時代の柳は、岡本の批判の先を歩んでいた。そして、縄文の美に魅入られていた。柳の心眼は、縄文の遺物に何を見出したのか。民芸運動は、どの地点で縄文と接合することになったのか。
【引用文献】
岡本太郎 1958 『日本再発見-芸術風土記』新潮社
____ 2005 『日本の伝統』光文社知恵の森文庫
【お知らせ】
当連載を収録した書籍『縄文 革命とナショナリズム』が待望の書籍化! 全国書店やAmazonなどの通販サイトで、2025年6月26日(木)より発売いたします。

筆者について
1975年大阪生まれ。大阪外国語大学卒業。京都大学大学院博士課程修了。なかじま・たけし。北海道大学大学院准教授を経て、現在は東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授。専攻は南アジア地域研究、近代日本政治思想。2005年、『中村屋のボース』で大仏次郎論壇賞、アジア・太平洋賞大賞受賞。著書に『パール判事』、『秋葉原事件』、『「リベラル保守」宣言』、『血盟団事件』、『岩波茂雄』、『アジア主義』、『下中彌三郎』、『親鸞と日本主義』、『保守と立憲』、『超国家主義』、『保守と大東亜戦争』、『自民党』、『思いがけず利他』などがある。






