岡本太郎は1930年から10年間、パリでの生活を送った。ピカソの作品を目にし、大きな衝撃を受け、自らの芸術家としての道が決まった。
世界各国の民族資料に触れ、絵を描くことから一時は離れて、人類学に没頭した。同じ時期、バタイユ、コジェーヴと出会った。
第二次世界大戦勃発により日本に戻った岡本は、日本の典型的な「伝統」を目の当たりにし、深く失望する。
闘いとしての芸術
岡本太郎がパリに向けて日本を離れたのは1929年12月。18歳のときだった。
彼はこの年の4月、東京美術学校(現在の東京芸術大学)に入学したばかりだったが、たった半年ほどで中退し、パリへと向かったのである。
このとき、彼は父母とともにパリに旅立った。父は漫画家の岡本一平。母は作家の岡本かの子。一平は朝日新聞社で漫画記者を務めていたが、ロンドン軍縮会議に際して特派員として渡欧を命じられた。これにかの子と太郎が同伴する形で、一家そろってのパリ行きが実現した。
1930年1月13日。一家はマルセイユを経由してパリに到着した。このあと、父はロンドン軍縮会議の取材のためイギリスに渡ったため、岡本はパリでのひとり暮らしを始めた。ここから約10年間のパリ生活がスタートする。
岡本の「留学」は、順風満帆ではなかった。パリの各所で名画を観て回り、ときにオランダやベルギーを訪れたが、制作は一向に進まなかった。彼はフランス社会にとけ込むため、パリ郊外にある現地の中・高等学校に入学し、寄宿舎生活を送った。そこは日本の中学1年生に相当するクラスで、12-13歳の子供たちと机を並べて歴史や数学などを学んだ。
そのようななか、大きな転機がやって来る。ピカソとの出会いだった。1932年夏、ポール・ローザンベール画廊でピカソの作品<水差しと果物鉢>と出会い、大きな衝撃を受ける。「抽象芸術こそ、国境・人種・文化圏その他、凡ゆる制約を突破する自由な表現方法であることを痛烈に悟った」[岡本1998a:106]。
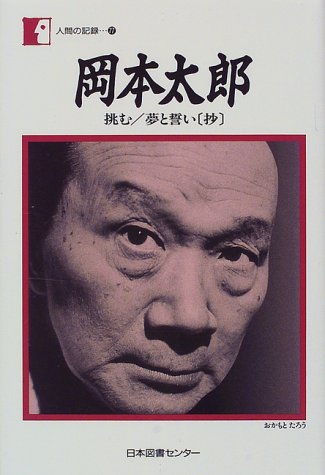
ここから彼は、抽象画の道を歩み始める。1932年10月にはサロン・デ・シュランデパンダン展に抽象絵画を初出品し、評価を受けた。さらに1933年にはアプストラクシオン・クレアシオン(抽象・創造)協会に参加し、初期を代表する作品「リボン」を発表した。
岡本にとって、抽象芸術に取り組むことは闘いに他ならなかった。
私はまず「抽象」という方法によって、直接自分をうち出し得る予感を得た。それはパリで闘う、闘える自信となった。そこにとけ込むと同時に、闘う……逆説のように思われるかもしれないが、闘わなければ真にとけ込むことは出来ないのだ。
[岡本1998a:22]
パリにとけ込むためには、パリと闘わなければならない。対決によってこそ、本質に迫ることができる。
この逆説が、岡本の信念になっていった。
彼は抽象芸術運動に身を置きながら、抽象美学に闘いを挑むようになっていく。そして、憧れのピカソに対して、立ち向かおうとしていく。彼はピカソに感動したからこそ、「アンチピカソとして自分を打ち出していった」という。「感動したものに挑むことが創造の真のスジだからだ」[岡本1998a:24]。
岡本は、抽象と具体の格闘を、キャンパスの上で表現しようとした。すると、それは最早、抽象絵画ではなくシュールレアリスムの表現ではないかと批判された。シュールレアリスムは、フロイトの深層心理学の影響を受けつつ、非合理なものや意識下の世界を表現する芸術革新運動である。現実以上の現実を追求する「超現実主義」と言われ、第一次世界大戦後のフランスで広がった。
1936年2月28日の『名古屋新聞』に、岡本の手紙が「アプストラクシオンとスユールレアリズム」と題して掲載されている。ここでは自分の作品を「ほとんどスユールレアリズムに近い」と位置付けつつ、「アオウストレートとは勿論呼び得ないしスユールレアリストとも呼び得ない状態にある」と述べている。彼のなかで、抽象絵画とシュールレアリスムがぶつかり合い、火花を散らしていた。
1936年10月、岡本は傑作を完成させる。代表作のひとつ<傷ましき腕>である。彼はこの作品をサロン・デ・シュランデパンダン展に出品し、まもなく、アプストラクシオン・クレアシオンを脱会した[岡本1998a:25]。
岡本は<傷ましき腕>について、次のように言っている。
常に私が望んでいた具象と非具象のからみあい、人間存在全体のコントンとした情感をぶつけることが出来た。だがこれはもう抽象絵画ではない。私はその時点で組織との訣別を決意したのだ。
[岡本1998a:25]
1937年6月、注目を集め始めた岡本は、初の画集『OKAMOTO』(G.L.M)刊行する。ようやく芸術家としての成功を手に入れ、飛躍の道を歩みだしたかに見えたが、「「絵描き」であることの空しさ」に直面し、新たな苦悩を抱えこんだ[岡本1998a:27]。
そんな彼の眼をくぎ付けにしたのが、人類学(民族学)の世界だった。
人類博物館とマルセル・モース
1937年、万国博の跡地にミューゼ・ド・ロンム(人類博物館)が開設された。ここで彼は世界各地の「具体的な資料」と出会う。そして、「なまなましい生活的な感動みたいなもの、そこからよびさまされて、民族学をやりたい」と思うようになった[岡本1980:315]。
何といっても、抽象論で人間存在を研究するのとはまるで違った、現実の彩りがここにはある。時空を超えた人間本来のあり方、そこからわき出てくる、むっとするほど強烈な生活感。ダイレクトにこちらにぶつかってくる。こんな具体的な資料を土台に、われわれは抽象論よりも、それを超えた人間学を学ぶべきではないか。
[岡本1998a:28]
フロイトの潜在意識を重視したシュールレアリスムは、リビドー(本能的衝動)とともに、未開社会の精神に関心を持った。そこには近代的理性が隠ぺいした「現実」が存在するとみなされ、人類学への関心が高まった。
1920年代以降、人類学は新たな時代を迎えていた。ニューギニア島東沖のトロブリアンド諸島で長期間のフィールドワークを行ったマリノフスキーは、1922年に『西太平洋の遠洋航海者』を出版し、世の中に衝撃を与えた。彼は島と島の間で腕輪や首飾りが受け渡される「クラ」という交易に注目した。これは経済的な財の交換ではなく、霊的なモノが交換されることで、社会秩序が構成される儀礼的な制度だった。第一次世界大戦によって社会秩序が崩壊状態に陥ったヨーロッパでは、資本主義の弊害と限界に対する反省的思考が高まっており、マリノフスキーのエスノグラフィーは閉塞的な近代を打破する「未開」からの視点として注目を集めた。
この流れのなかで、決定的な議論を展開したのがマルセル・モースだった。彼は1925年に『贈与論』を公刊し、古今東西の神話や慣習、儀礼を分析することで、ポスト資本主義のあり方を考察した。ここで紹介された「ハウ」や「ポトラッチ」という交換は、霊性や呪術性を含む贈与の形態である。世界は人間の理性や打算だけで動いているのではない。人間は神や精霊と共存し、恩恵と禍を受けながら生きている。世界は超越を含む四次元性によって構成されている。
岡本は、このモースの人類学に注目し、1938年ごろから、ソルボンヌ大学哲学科に在籍しながら、モースの授業を受けた。モースは「無邪気で柔い、まるで子供みたいな人だった」。そして、「講義はひどく情熱的で、引き込まれた」[岡本2000:252]。
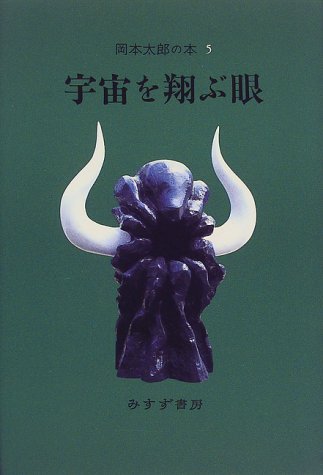
授業のほとんどは人類博物館で行われ、岡本はモースの人類学を受容しながら、具体的な民族資料に触れていった。
彼は後年、梅棹忠雄との対談で次のように回想している。
さまざまな人間の思考は、どちらかというと、演繹的なわけね。芸術などはとくにそうですよ。自分の主観からこうだ、と決めてくるエゴセントリック(自己中心的)なものだけれども、民族資料のもっている意味、ぜんぜん自分を捨てちゃって、ものから帰納的に世界を見なおす、世界観を帰納的に見なおしつくりあげるという反対の状況にぼくは感動した。ただ芸術家としていい気になっているんじゃなくて、もっと現実のものそのものから、ずっとこっちにひきよせ、こっちもひきよせられるということに情熱を感じて、民族学をやった。
[岡本1980:315-316]
岡本は「絵筆を捨てて」、人類学の研究に「ひたすら打ち込んだ」。民族資料は人間の多様性を物語るとともに、「絵とか芸術などという分化された価値観を根底から引っくり返す、宇宙的な存在感」を持っていた。心を動かされたのは、民族資料が放つ四次元性だった。そこには精霊が宿り、宇宙との交流がある。「現代先進社会の虚飾の空しさを超えた、極めて直接的な充実をつきつける」。岡本は「強烈に見かえされるような戦慄をおぼえ」、ますます人類学にのめり込んでいった。[岡本2000:251-252]
バタイユとコジェーヴ
岡本が同じ時期に交流したのがジョルジュ・バタイユだった。初めてバタイユの姿を目にしたのは1936年1月。ヒトラーやムッソリーニのファシズムに反対し、スターリンの独裁にも抗議する「コントル・アタック(反撃)」の集会に参加し、バタイユの演説を聞いた。
岡本はその時のバタイユの印象を次のように記している。
きつい表情だったが、そこに何か人間的なやわらかさが感じられた。前方をキッとにらみつけながら、畳みかけるように激しく語りだした。決してなめらかではない。どもり、つかえながら、情熱が堰にぶつかりながらあふれ出してくる、そんな感じで論理を展開して行く。ひどく純粋で、徹底的だ。筋といい、人間的雰囲気といい、私にはぴたっときた。全身がひきつけられる思いがした。
[岡本1998a:32]
岡本は、バタイユの真摯情熱的な語りに感銘を受け、友人にバタイユへの共感を語った。すると、その話がバタイユに伝わり、ふたりで会うことになった。
最初から、うちとけ、ぐっと踏み込んだ雰囲気だった。今日、すべてが精神的にいかに空しくなっているか。憤りをもって、システムに挑む同志が集結して、世界を変えて行かなければならない。二人の問題意識、情熱はまさに同じ方向を指していた。バタイユはがこの時すでにシュールレアリスムの連中と離れていることを知った。私の筋と一致しているのでうれしかった。
バタイユは、ひとりの協力者を得た、と目を輝かせた。
[岡本1998a:33]
岡本はバタイユに誘われ、コレージュ・ド・ソシオロジー・サクレ(神聖社会学研究会)に参加するようになった。この研究会はバタイユが主催したもので、聖性の理論的な探求が模索された。バタイユは神秘的主義的な実践にも乗り出し、秘密結社アセファル(無頭人)を創設した。これにも加わった岡本は、深夜にパリ郊外で行われた「誓いの秘儀」に参加し、「強烈に目ざめる思いがした」という[岡本1998a:34]。
しかし、岡本はバタイユと決別していった。それはこの運動のなかに「権力の意志」を感じたからだという。岡本は「どうしても調整できないズレを感じ」、バタイユに対して、率直な疑問と運動への決別を告げる手紙を書いた。これを読んだバタイユは逆に感動し、「その後も互いの友情は続いた」[岡本1998a:35]。
岡本は、パリの高等研究実習院で開講されていたアレクサンドル・コジェーヴのヘーゲル『精神現象学』についての講義に参加した。この講義にはバタイユやジャック・ラカン、ロジェ・カイヨワ、メルロ=ポンティなども参加し、その後のヘーゲル理解に多大な影響を与えたことで知られる。
岡本は、この講義で「強烈な弁証法論理」に触れ、「情感的なショックを覚えた」。しかし、最終的にはすべてを受け入れることができなかった。ヘーゲルの弁証法では、特定の命題(テーゼ)に対して、それを否定する反対の命題(アンチテーゼ)があり、両者がアウフヘーベン(揚棄)されることで、統合した命題(ジンテーゼ)に至るという。岡本は、最後のジンテーゼの哲学概念に、どうしても納得がいかなかった。
ジンテーゼが成立すると、世界は完成し、歴史は終わる。その「絶対感をもったロマンティスム」には惹かれるものの、歴史が終わるはずがない。世界は常に引き裂かれ、相克しながら展開する。「矛盾した両極が互いに激烈に挑みあい、反発する」。そして、人間は「この永遠の矛盾に引き裂かれて」生き続ける。[岡本1998b:135]
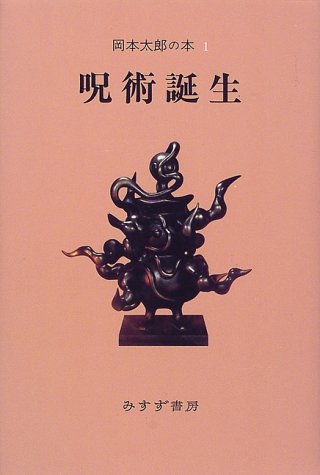
だから私は「合」を拒否する。現在の瞬間、瞬間に、血だらけになって対極のなかに引き裂かれてあることが絶対なのだ。
[岡本1998b:136]
岡本はモースとバタイユを通じて、聖性や神秘の世界に傾斜するとともに、常に闘いを挑みながら対峙する姿勢を貫いた。
第二次世界大戦が勃発し、ナチスドイツによるフランス侵攻が加速すると、岡本はマルセイユを発って日本へ引き揚げた。1940年6月のことだった。
日本の「伝統」への失望と「対極主義」
帰国した岡本は、最初に京都と奈良を訪問した。そこで彼は絶望した。京都は日本的なものの典型だと言われているが、いま残されているものは「恰好だけ」で、「現実の日本ではない」。奈良は大陸文化そのものであって、「古代の中国や朝鮮から直輸入した」ものにすぎない[岡本1998a:49]。
これがどうして日本なのか。私は見て歩きながら、しらけた気持ちになった。
[岡本1998a:49]
岡本は徴兵によって、中国の戦線に送られた。そして敗戦とともに収容所生活を送り、1946年6月に復員した。
彼は日本の展覧会を見て回った。すると、会場に入ったとたんに目に入って来るのが「暗灰色(あんかいしょく)」だった。
いわゆる“わび・さび・しぶみ”。徳川後期あたりからのゆがんだ筋をただなぞっているよう。多数の作家の作品が並んでいるのに、全部同じに見える。それぞれ個性がないのだ。洋画のスタイルは一九二〇年代、後期印象派でストップ。何十年もズレている。日本画の方はより単調な手先だけの表現だ。
[岡本1998a:47]
敗戦によって世のなかは大きく変わったはずなのに、美術界は昔のままの価値を追求している。「戦前の番付どおり。虚偽のピラミッドがふんぞりかえっていた」[岡本1998a:48]。
岡本は、このような日本の伝統に立ち向かった。それは伝統を破壊する行為ではなく、伝統に肉薄する行為に他ならなかった。伝統を掴むためには、伝統と対峙しなければならない。この逆説は、彼の信念に基づく態度だった。
1947年の秋、岡本は花田清輝『錯乱の論理』を読み、共感した。
私が本当に確かめたいこと、いままで日本のインテリや知識人が何ら発想しなかったことがそこに書いてある。「こんなヤツが日本にいたのか。奇蹟的だ」と僕は驚いたわけです。
[岡本1978:56]
このことを編集者に話すと、花田の耳に入り、花田が岡本の自宅兼アトリエを訪問した。ここでふたりは意気投合し、1948年1月19日、「夜の会」が結成された。メンバーには、岡本、花田の他、野間宏、椎名麟三、埴谷雄高、佐々木基一、梅崎春生、中野秀人、小野十三郎、安倍公房、関根弘らが加わった。
岡本は、花田が提示する「楕円」の構造に強く共鳴した。花田が1946年に出版した『復興期の精神』には「楕円幻想」という文章が収められている。岡本はこの文章に感化された。
岡本はパリでの生活から対象に対して闘いを挑むことで、逆説的に本質に迫る姿勢を身に着けていた。「人間は対極のなかに生きている」という確信を持っていた。これに対して、花田は対立するふたつの核があり、それぞれを中心に円を描くことで、楕円が生まれるという。中心は常に重なり合わず、純粋な円は生まれない。
極と極のぶつかり合いであり、にらみ合いである。僕の貫く弁証法は、「正」と「反」だけであって、永遠に「合」にならないんです。「合」を拒否する「楕円」というのはそういうものです。「正」と「反」が「合」になったらまんまるになっちゃう。だから彼があくまでも「楕円」を主張したときに、「なるほど、俺の考えと同じことを言っているな」と思って、大変うれしかったですね。
[岡本1978:58-59]
ここで「正」と言っているのはヘーゲル弁証法の「テーゼ」であり、「反」は「アンチテーゼ」、「合」は「ジンテーゼ」である。岡本は弁証法に立ちながら、「合」という絶対調和を否定した。この姿勢と花田の「楕円」は近似していた。
岡本は意を強くし、「対極主義」という概念を確立していく。1950年に彼は『アヴァンギャルド芸術』(美術出版社)を出版するが、そこで「対極主義」について次のように述べている。
私は非合理とか合理的とかの一方的な立場をとって自足するような態度は、これからの芸術家の世界観として許されないと思います。(中略)私はこれを対立する二極として一つの精神の中に捉え、しかもそれらを折衷・妥協させることなく、いよいよ引き離し、矛盾・対立を強調すべきだと思うのです。そこに真に積極的な新しい芸術精神のあり方を見出すのです
[岡本1950]
岡本は「対極主義」を打ち出す形で、<重工業>(1949年)、<森の掟>(1950年)という傑作を生みだした。彼はアヴァンギャルド芸術の旗手として注目を集め、一躍、日本を代表する芸術家としての地位を築いた。
そんなときに出会ったのが縄文土器だった。
縄文土器に見出したもの
まずは岡本が縄文土器に出会った場所が、上野の国立博物館であったことに注目する必要がある。若き日の岡本が大きな芸術的インスピレーションを受けたのは、パリの人類博物館だった。そこで目にした具体的な民族資料から「時空を超えた人間本来のあり方」を感じ、人類学にのめりこんだ。博物館に陳列されたモノと対峙し、魂をぶつけ合うことで、抽象を超えた真の「現実」をつかみ取る方法を確立していた。彼にとって博物館は、生々しい人類のエートスと出会う芸術の場だったのである。
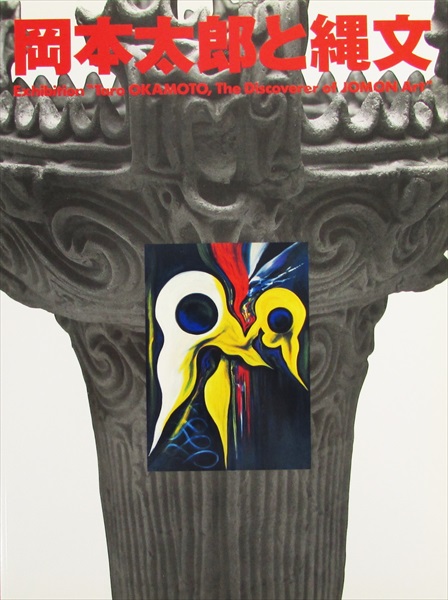
岡本が縄文土器に見出したのは、「アシンメトリー」と「不調和のバランス」だった。「隆線紋」は、もつれながら解けていき、混沌のなかに沈んでいく。しかし、再び忽然と姿を現し、無限の世界へと回帰していく。この「破調」によって生み出された「異様な衝動」こそが、縄文土器のダイナミズムであり、エネルギーそのものだった。
この読み解きは、まさに「対極主義」が基礎となって生まれたものである。縄文土器は、徹底してシンメトリカルな構造を否定する。調和を拒絶し、不均衡を強調することで、超自然的な世界へと接近する。この特質を掴んだ背景には、パリ時代から貫いた「闘い」の姿勢があり、モースやバタイユ、コジェーブらとの交流があった。「テーゼ」と「アンチテーゼ」は「ジンテーゼ」には至らない。対極のぶつかり合いによってこそ、聖性への回路が生まれ、神秘的な四次元性が現れる。
パリ時代から戦中・戦後の混乱期のなかで獲得した信念が、縄文土器との出会いによって、一気に「爆発」した。縄文土器に接した瞬間、身体中の血が熱くわき立ち、心臓がひっくり返りそうになった。次第に全身がぶるぶると震え始め、縄文土器との間に異様なぶつかり合いが起った。
この「爆発」は、そのまま「日本の伝統」の見つめ直しへとつながった。岡本は、「わびさび」の世界観に対して、縄文土器の「乱調」を対峙させた。「対極主義」によって、日本の伝統の本質に迫ろうとした。
この姿勢は、岡本ひとりの芸術的態度にとどまるものではなかった。
敗戦によって、日本人は長らく依拠してきた国体や神話を失った。占領軍によって戦前・戦中のイデオロギーは否定され、戦後民主主義が始まった。この混乱期に、自画像の崩壊に直面した日本人は、セルフイメージ獲得のために右往左往していた。そこに、岡本太郎の縄文土器論が突きつけられたのである。
岡本の問いは、「日本人とはいかなる存在なのか」「日本の伝統とは何か」という国民のアイデンティをめぐる問いと呼応していた。「日本とは何か」という根本的な問いと、その始原をめぐる探求は、戦後日本が切実に希求した実存的欲求そのものだった。
この戦後日本人の渇望に対して、意外な角度から新しい自画像を提示したのが岡本だった。
彼が提示したのは、これまでの日本人のセルフイメージとは大きく異なったディオニソス的日本だった。そこでは調和は破壊され、生命のエナジーが乱舞する。「豪快、不敵な表情を持つ新しい伝統」が顔を表し、「わび・さび」の世界を超え出ていく。
岡本は、縄文土器から得た伝統の構造を、次第に民衆世界のエートスの中に見出していった。日本各地の民衆的伝統は、時におどろおどろしく、猟奇的である。彼はフォークロア(民俗学)の世界へと接近し、日本の伝統を再定義する旅へと出ることになった。
この旅は、日本のアイデンティをめぐる問いであり、岡本の芸術活動そのものと密着していた。
【参考文献】
大谷省吾 2009 「岡本太郎の“対極主義”の成立をめぐって」『東京国立近代美術館研究紀要』13号
岡本太郎 1950 『アヴァンギャルド芸術』美術出版社
____ 1978 「「楕円」の関係」『新日本文学』33巻5号
____ 1980 「人間の根源的な生命力」(梅棹忠雄との対談)『岡本太郎著作集』第9巻、講談社
____ 1998a 『人間の記録(77) 挑む/夢と誓い(抄)』日本図書センター
____ 1998b 「対極」『岡本太郎の本① 呪術誕生』みすず書房:134-136
____ 2000 「私と人類学-パリ大学民族学科のころ」『岡本太郎の本⑤-宇宙を翔ぶ眼』みすず書房
楠本亜紀 2007 「抽象から現実へ―パリ時代の岡本太郎」『世田谷時代1946-1954の岡本太郎-戦後復興期の再出発と同時代人たちとの交流①』世田谷美術館
安井健 2011 「岡本太郎によるジョルジュ・バタイユの思想の継承と決別」『神戸大学大学院人間発達環境学研究科研究紀要』5巻1号、神戸大学大学院人間発達環境学研究科
____ 2018 「岡本太郎がパリでうけとったもの」『季刊民族学』165号、千里文化財団
【お知らせ】
当連載を収録した書籍『縄文 革命とナショナリズム』が待望の書籍化! 全国書店やAmazonなどの通販サイトで、2025年6月26日(木)より発売いたします。

筆者について
1975年大阪生まれ。大阪外国語大学卒業。京都大学大学院博士課程修了。なかじま・たけし。北海道大学大学院准教授を経て、現在は東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授。専攻は南アジア地域研究、近代日本政治思想。2005年、『中村屋のボース』で大仏次郎論壇賞、アジア・太平洋賞大賞受賞。著書に『パール判事』、『秋葉原事件』、『「リベラル保守」宣言』、『血盟団事件』、『岩波茂雄』、『アジア主義』、『下中彌三郎』、『親鸞と日本主義』、『保守と立憲』、『超国家主義』、『保守と大東亜戦争』、『自民党』、『思いがけず利他』などがある。






