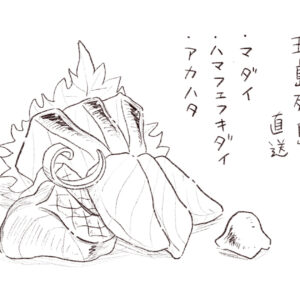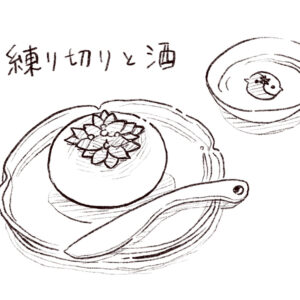時を重ねるほどに実感する。子育てとは「喜び」と「大変さ」、そしてもうひとつ、「切なさ」の3本柱から成っている。子供が寝たあとの静かになった居間で、ひとり、ウイスキーの瓶を出す。
「喜び」と「大変さ」だけじゃなかった
我が子が生まれていちばん驚いたことは、単純だけど、その我が子があまりにもかわいいということだ。
僕は自分に子供が生まれるまで、他人の子供との接し方がまったくわからず、友達家族とのピクニックやホームパーティーなどで同席しても「こんにちは。元気ですか?」なんて敬語で話しかけ、それでもう会話が途切れてしまうようなタイプだった。とはいえ人並みくらいには、小さな人間を愛らしいと思う気持ちは持ってはいたが。ところが子供が生まれるとその気持ちは突然大きくなり、街で小さな子を見かけるともうたまらず、やたらめったらと話しかけたくなるのをがまんして、抱っこしているお母さんから見えない角度からそっと微笑みかけて小さく手を振る、なんてことをやってしまう。本当はそれもまずいのか?
ただ、我が子のかわいさというのは、とてもじゃないけどその他の子供たちとは次元が違う。保育園へ送り迎えに行くと、娘と同年代の子供たちがわらわらといて元気に遊びまくっており、思わず目尻が2cmくらい下がる。が、そのなかに、かわいさ余ってもはや発光しているほどの娘を見つけると、「こんなにも尊き者がこの世に存在していいのだろうか?」と、毎度不思議に思うほどだ。親バカと言われればそれまでだけど、これはむしろ、生物に備わっている、我が子を認識するための基本機能なんだろうな。
で、そんなかわいい娘との生活は、ともに暮らせる「喜び」と、同じくらいの「大変さ」からなっている。かつてはそんなふうに想像していた。ところが、時を重ねるほどに実感することがある。それは、子育てとは「喜び」と「大変さ」、そしてもうひとつ、「切なさ」の3本柱から成っているということだ。
そう、子育ては常に切ないのだ。
お別れの切なさ
わかりやすいエピソードで言うと、「Tくんとの別れ」。
0歳児クラスから保育園で一緒だった男子に、Tくんがいた。Tくんは幼児ながらにサラサラヘアーのイケメンで、人懐っこく、娘に意地悪をしてくるようなこともなく、僕も娘の友達としてとても好ましいと思っていた。実際、娘もTくんが大好きだったようで、当時家でハマっていた「電話ごっこ」(てきとうな大きさの板をスマホに見立て、誰かと電話をしているふりをするだけ)でもよく、「もしもしTくんですか〜? けーきやさんにけーきをたのんだから、あしたいっしょにたべようね〜」などと、架空の会話を楽しんでいた。妻もよく、ニコニコしながら「これって初恋なのでは……」なんて言っていた。
ところがそんなTくんが、2歳の時、ご両親の都合で引っ越してしまうことになった。妻と娘で「もうすぐお別れだね〜。寂しいね」「そうだね〜」なんて会話をしているのを横で聞いていると、娘はむしろあっけらかんとしているのに、こっちの胸が苦しすぎて泣いてしまいそうになる。当の娘は翌日からいつもと変わらない様子で元気に過ごしていたが、僕がTくんが引っ越してしまった悲しみを消化するのには、それなりに時間がかかった。
3歳児クラスの時、娘は担当のひとりであるR先生にとても懐いていて、たまに手紙(まだ文字は書けないけれど、それらしきもの)を書いて持っていき、渡したりしていた。R先生はぱっと見、今風の若い女性なんだけど、娘が「はやくたんじょうびぷれぜんとがほしいんだ〜」と言うと「え〜、けどさ〜、待ってる時間がまた素敵なんじゃ〜ん」なんて返しているのを見たことがあり、なんて素敵な考え方なんだと大きく感銘を受けたりした。そうやって、等身大できちんと子供たちと向き合ってくれることもありがたかった。
そんなR先生だったが、娘が4歳児クラスに上がると同時に保育園自体を辞めてしまうことになった。園では、お迎え時の挨拶は通常、「さようなら、また明日(もしくはまた来週)!」と言って子供とタッチをするのが通例になっている。ところがR先生の最終登園日、僕が娘のお迎えに行くと、先生はすでに目を真っ赤にして、園児たちひとりひとりと挨拶をしていた。僕も「今までありがとうございました」と伝え、続いて娘との最後の挨拶。R先生は娘をぎゅっと抱きしめこう言った。
「さようなら、またいつか……」
こんなの、涙腺崩壊に決まってる。僕はマスクを目の下ギリギリまで持ち上げ、なんとかにこにこしている体を装いつつ、いつもより長いその挨拶の様子をじっと見ていた。
静かになった居間でしみじみと
というか実は、子育ての切なさを感じるのは、そんなにわかりやすい場面に限ったことじゃない。
僕はとっくに飽きてしまったが、自分でもよくわかっていないなんらかの素材を集めるため、なかば娘にやらされている感のあるゲーム『あつまれ どうぶつの森』で、「はい、パパはもう疲れちゃったから今日はここまで!」とセーブボタンを押した時のこと。画面内にまだとるべきアイテムが残っていたようで、娘が、「まま! いま『はにわのかけら』があったのに、ぱぱがとらないでせーぶしちゃった!」と言いだした。
いつもならこういう場合、「も〜ぱぱはしょうがないこだね〜。てんこぶ(たんこぶのこと)するよ!」とか言われ、ごく弱いげんこつを一発食らっておしまいなのだけど、この時はなんらかのスイッチが入ったのか、妻の胸に飛びこんでしがみつき、「ひんっ……ひんっ……」と、あまり聞いたことのない声で泣き始めてしまった。僕も妻もなんだかおかしくて、笑いながら「ごめんごめん」「どうしたの〜?」なんて声をかけるんだけど、同時に胸が張り裂けそうに切なく、申し訳なくもあるのだった。
欲しがったガチャガチャをやらせてやったらダブりが出てしまった時の切なさ。映画の半券でやったクレーンゲームで、何もとれなかった時の切なさ。なんなら、TVの子供番組をただまっすぐに見つめている娘の目を見るだけでも切ない。以前家族で「スシロー」に行った時、ちょっと早めに着いてしまって時間を潰した駐車場があり、その前を後日ひとりで通りすぎた時も、かなりくるものがあったな。
信じられないかもしれないけれど、こうなってくるともうなんでもよくて、ぜんぜん知らない女子中学生がコンビニの前でもくもくと「ファミチキ」を食べている。そんなシーンをふと目にするだけで、「大きくなって……」と、ジーンとしたりする。
と、長々書いてきて何が言いたかったのかというと、子育ての「喜び」や「大変さ」は、事前に想定していたこともあり、素面で受け止めたり楽しんだりすることができる。が、ふいにやってくる「切なさ」には、「酒」の力を借りて対抗するしかないのだ。
夕食も風呂も済み、妻が娘と寝室へ行って寝かしつけをしてくれ、静かになった居間の明かりを間接照明に切り替える。メインの晩酌は夕飯とともに終わっているから、あと1、2杯、夜を名残惜しんで寝るかと、ウイスキーの瓶を出してくる。と言ってもシングルモルトは贅沢品で、娘が生まれてからは国産のブレンデッド中心。たとえば、かつてはお父さんの書斎の棚にあるようなイメージだった「だるま」こと「サントリーオールド」。比較的手頃なわりに、ストレートで飲んでもしみじみうまいことに最近気がついた。
薄暗い部屋で、ついさっきまで娘が大はしゃぎしていたあたりをぼんやり眺めがら、だるまのストレートをちびちび。子育ての、あふれんばかりの切なさと、自分もずいぶんおっさんになったなぁという感慨を噛みしめる、なかなかいい時間だ。
【お知らせ】
当連載を収録した書籍『缶チューハイとベビーカー』が待望の書籍化! 全国書店やAmazonなどの通販サイトで、2024年6月26日より発売いたします。

筆者について
1978年、東京生まれ。酒場ライター、漫画家、イラストレーター。酒好きが高じ、2000年代より酒と酒場に関する記事の執筆を始める。著書に『酒場っ子』『つつまし酒』『天国酒場』など。ライター、スズキナオとのユニット「酒の穴」名義をはじめ、共著も多数。